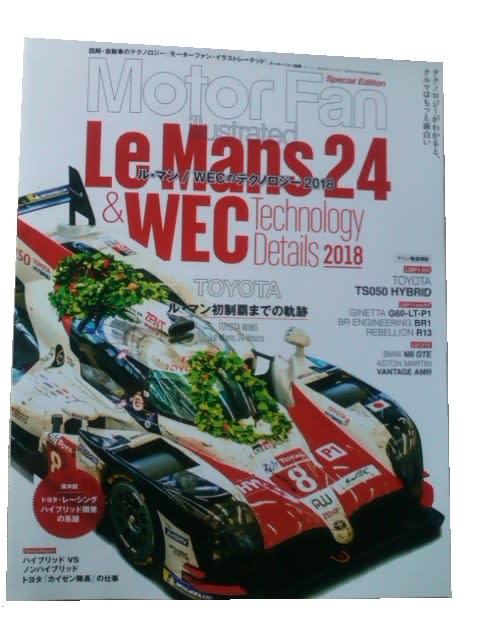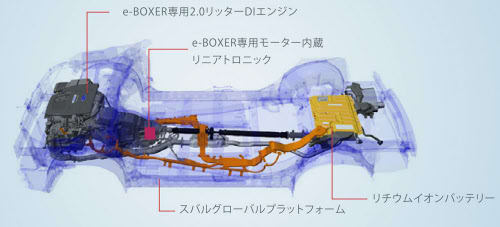どんなメーカーでも自社の技術を象徴するフラッグシップを持ちたいと思っているでつが、それを実現できるケースはまれ。
「これぞ我が社だけの唯一無二の技術!」と誇れるようなネタは…
そんななか、誰もが認める世界唯一の技術がマツダのロータリーエンジン。
1967年の初代コスモ以来、波乱の歴史を刻んできたロータリーエンジン。
市販車でその頂点に立ったエンジンとしては、1990年発売のユーノスコスモ

そのコスモに搭載された3ローター20B-REW。

こりぞ究極のロータリエンジン。
V12エンジンに匹敵するでつなぁ~
ロータリーエンジンは、そのレイアウト上2ローター以上にマルチ化しようとするとエキセントリックシャフトの分割が必要となるでつ。
そりは、レシプロエンジンのクランクシャフトを2分割でつなぐようなもの。
こりは、極めて高い工作精度と組み立て精度管理を要求される難しい仕事。
これがレース用以外で、3ローター以上のマルチローターが造られなかった最大の理由。
20B-REWは半月キーで位置決めしたテーパー継ぎ手によってエキセントリックシャフトを2分割して対応。
だけど、量産化にあたり問題になったのがその工作精度。
2ローターのエキセントリックシャフトより一桁高い1000分の1mmの加工精度が要求され、しかも組み立て後に全量チェックと場合によっては再研磨。
コスト的にはとんでもない金食い虫となりマツダを悩ませることとに…
まさに、バブル期でなければ絶対にゴーサインが出なかった空前絶後の高コストエンジン。
だけど、GT-RやNSX、レクサスLFAもだけど年に何台か出なくても、やっぱりフラグシップとして
日本の技術のすごさをアピールする上でも、コスモ3ロータは出してほしいなぁ~
「これぞ我が社だけの唯一無二の技術!」と誇れるようなネタは…
そんななか、誰もが認める世界唯一の技術がマツダのロータリーエンジン。
1967年の初代コスモ以来、波乱の歴史を刻んできたロータリーエンジン。
市販車でその頂点に立ったエンジンとしては、1990年発売のユーノスコスモ

そのコスモに搭載された3ローター20B-REW。

こりぞ究極のロータリエンジン。
V12エンジンに匹敵するでつなぁ~
ロータリーエンジンは、そのレイアウト上2ローター以上にマルチ化しようとするとエキセントリックシャフトの分割が必要となるでつ。
そりは、レシプロエンジンのクランクシャフトを2分割でつなぐようなもの。
こりは、極めて高い工作精度と組み立て精度管理を要求される難しい仕事。
これがレース用以外で、3ローター以上のマルチローターが造られなかった最大の理由。
20B-REWは半月キーで位置決めしたテーパー継ぎ手によってエキセントリックシャフトを2分割して対応。
だけど、量産化にあたり問題になったのがその工作精度。
2ローターのエキセントリックシャフトより一桁高い1000分の1mmの加工精度が要求され、しかも組み立て後に全量チェックと場合によっては再研磨。
コスト的にはとんでもない金食い虫となりマツダを悩ませることとに…
まさに、バブル期でなければ絶対にゴーサインが出なかった空前絶後の高コストエンジン。
だけど、GT-RやNSX、レクサスLFAもだけど年に何台か出なくても、やっぱりフラグシップとして
日本の技術のすごさをアピールする上でも、コスモ3ロータは出してほしいなぁ~