
本日、生命の星地球博物館にて、丹沢大山自然再生委員会報告会が開催されました。
ブリ森プロジェクトメンバーも数名が参加いたしました。
丹沢はブナ林の衰弱、シカ食圧による森林植生の劣化が起こって久しく、
官・民・学術機関、ボランティア団体が連携し、研究と対策が行われています。
<第1部>丹沢再生活動の成果と課題報告
~丹沢大山自然再生計画の取組み状況
以下は
神奈川県自然環境保全センターの報告です。
大変興味深い内容でしたので、少しパワポ画像を掲載させていただきます。




猟友会による巻刈り。個体の計測中。
この他に丹沢でのシカ捕獲は、昨年始まった5名のワイルドライフレインジャーが活躍し、猟師があまり入らない稜線部の捕獲をしています。

シカ捕獲の成果が表れるグラフ。
しかしシカ密度の高い所は、柵で植生保護をしなければ植生の回復は見られないそうです。


こちらは
サントリー「天然水の森」の取り組みです。企業による森林再生ですが、専門家の参加により、さまざまな調査研究が行われ、ハイレベルの事業は大変参考になりました。

落ち葉を貯めて土壌侵食を防ぐ実験。

昼食を挟んで、
東京農工大学農学研究院、石川芳治さんの「林床植生の回復と土壌」についての発表。土壌流出のメカニズムが大変良く分かりました。
地表の草本や落ち葉がないと、雨水による土壌浸食はどんどん進むのです。
そして、丹沢のと登山道整備をしておられる大きな山岳会、
NPO法人みろく山の会の発表。
NPO法人丹沢自然学校による丹沢エコツーリズムの発表は、
地域住民の認識を深め、地域活性化をし、最終目的は環境保全との事。ワイルドライフレインジャーの見学会も開催しています。
地域の里山再生と環境教育を活発に行っている、
NPO 法人四十八瀬川自然村、小野均さんの発表は、地域主体の楽しさが伝わってきました。キーワードは「仲間づくり」
 日本大学糸長浩司教授
日本大学糸長浩司教授による、丹沢山麓での取り組みの集約的な発表は非常に参考になりました。
「人間・地域の再生」「丹沢学会」「域学連携」「楽しければ人は来る」、これキイワードですね。
第2部はワークショップと討論で三つのテーマ ① 森林再生 ② 登山とツーリズム ③ 山里再生、に分散参加となり、私は森林再生の部に参加してきました。
10:00~16:30までしっかり勉強し、非常に有意義な一日となりました。
昨今は箱根でもシカが増え、明神ヶ岳や火打石岳では、シカが住みやすい稜線の平らな部分では下層植生が盆栽状となっています。
ブナ林も分断細分化されており、丹沢程ではありませんが、長い目で見た再生事業が必要です。
丹沢の取り組みは、将来の箱根山を見据え、先手を打てよと教えてくれました。
丹沢大山自然再生委員会の皆様、ありがとうございました!
丹沢大山再生委員会の詳細はこちらのホームページをご覧ください。
http://www.tanzawasaisei.jp/
(記者 ぶり森のらこ)
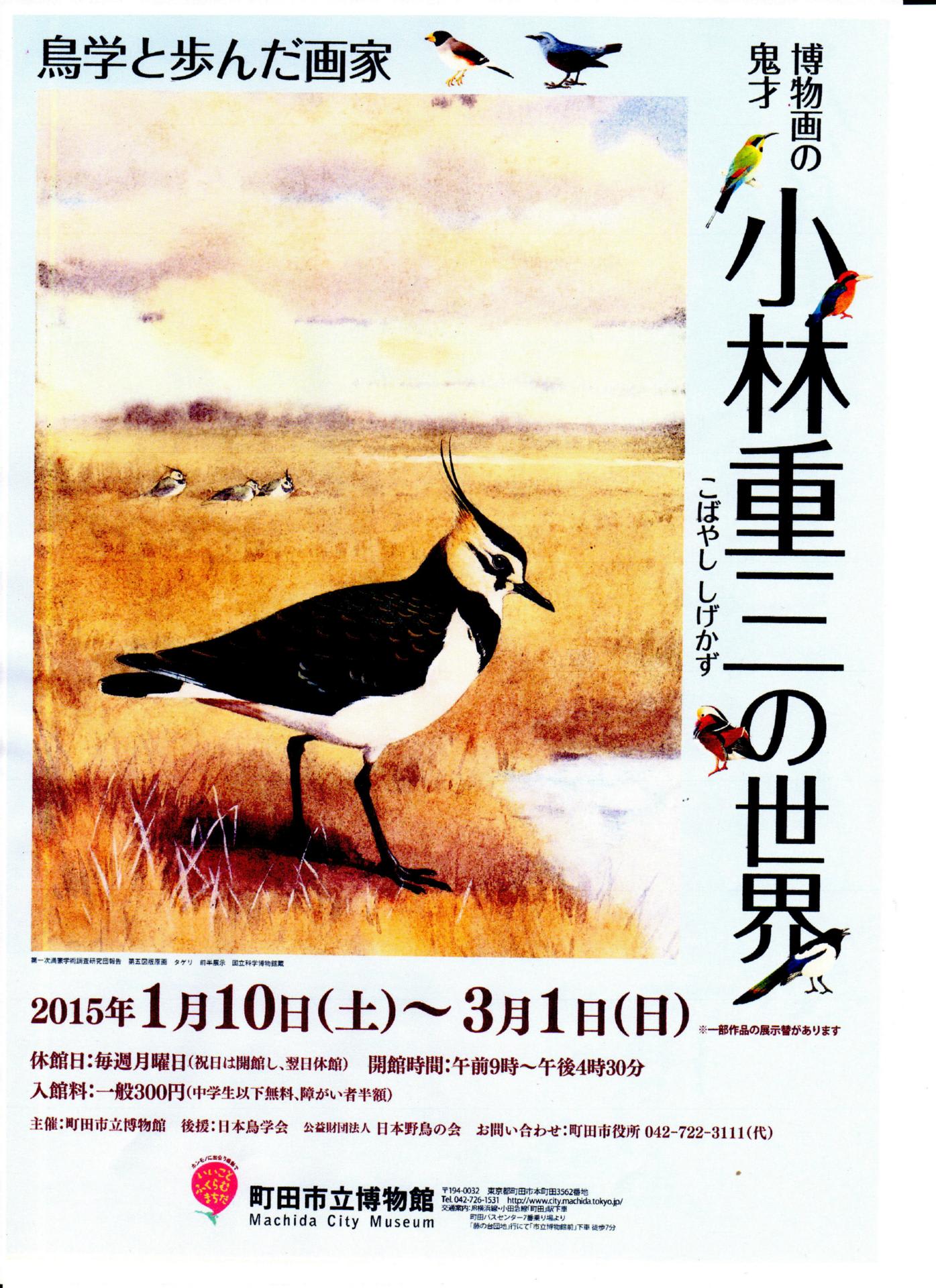




















 落ち葉を貯めて土壌侵食を防ぐ実験。
落ち葉を貯めて土壌侵食を防ぐ実験。
