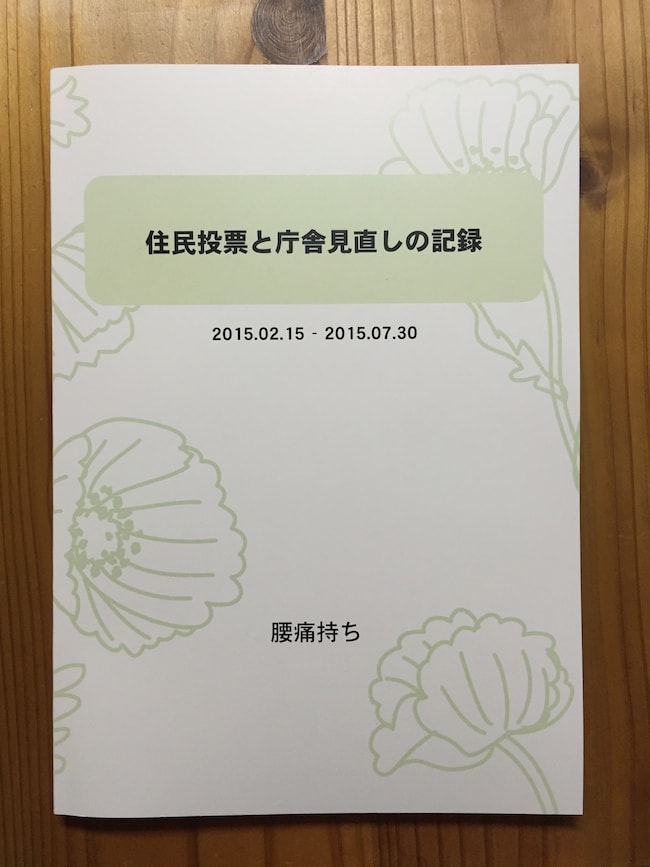昨日は久しぶりにトヨタスタジアムにサッカー観戦にいった
いろいろ気づくところもあって、本来ならばその感想がここでの投稿となるのが普通なのだろうが
ちょいと真面目な部分の(本来はぼーっとしてるほうが好き)自分の頭には別のことが占めており
まずはそちらの方を優先して
と言っても、日曜で面倒なので自分のあちらからのコピペで、以下
先日の行政訴訟の中日新聞の記事を見て
「原告は得したね!」
とつぶやいたそれなりの立場の人がいた。
裁判の解決金として穂積市長が125万円が支払うことになっているから
そのような発言になったのだろうが、原告は何も得などしていない
解決金125万円のうち100万円は市に入ることになっている
残りの25万円は、原告側の弁護士費用の一部として支払われる(4月13日東日新聞に掲載)
弁護士費用の一部の表現があるように、実際はもう少し多く費やされており
その負担は市民の自発的な募金で賄われており「得」と表現する金額には遠く及ばない
そもそもこの行政訴訟自体が、不適切な契約・判断で市が受けた損害をそれを見逃した(見過ごした)
責任者(首長)は市に損害金額を返却して欲しいという内容だ
こうした公的なお金に関することなので、原告側が勝手に(自分たちが得するために)和解をすることはできないとされており、
和解という表現はふさわしくなく、終結判決によらない解決策という少し面倒な表現が使われている
得をした人が存在するならば、明らかに得をしたのは「市」だ
これに似ているのが、例の活動交付金の取り消された件で、これも一部の議員さんと市民の活動によって最終的には130万円ほどの金額が市に返却されることになった
両者ともおせっかいな市民等が騒ぐことにより100万円台の金額が市の懐の入ることになった
得したのは誰かの話から離れるが、行政訴訟の解決の記事は中日新聞と東日新聞に掲載されていたが、よく見るとその2つの記事は微妙にニュアンスが違う
合意内容について東日新聞は肝心なところが抜けている
東日新聞がどのようなニュースソースからその記事を作成したのかは不明だが、記事には「市が発表した」との表現があるので、何らかの形(FAX?)で、肝心な部分を除いてリリースされたのではないかと思われる
更にその記事にある市長のコメントが裁判の解決案との整合性がない
裁判所からの解決案は、疑義が完全に払拭されるにいたらない、、、とあるにもかかわらず
市長のコメントは、自分たちは適法に処理し、移転補償の是非は裁判の内外で保証基準の基準を満たしている
と勝手に言いきっている
繰り返すが裁判所はこうした一連の作業に疑義が生じることを認めており、必ずしも適切ではなかったとしている
新聞記事の一番怖いところはこのところで、詳しい内容を知らない人たちは新聞記事をそのまま信じてしまう
その記事が一部しか伝えてなくても(意図的に)、間違った内容であっても一旦掲載されてしまえば
そのまま記憶されるので、実情を知っている人たちがその記事は不完全と訴えても考えを変えさせることはとても難しい
ところで、新城市は26日に臨時議会が開催される
この時期に一体何が話し合われ議決されるのか、、、
ちょいと足を運ぶと面白いことが聞ける、、、かも
引用はここまで
昨日のサッカーの対戦はグランパス対ジュビロで、グランパスが1-0で勝利
サポーターも試合に参加している感じは生でこそよく感じられる
試合自体は地味な試合に終止したが、とりあえず勝利を収めたグランパスはサポーターともども一安心といったところ
一方ツキがなかったジュビロは、、、ちょいと心配な雰囲気で
やることなすこと裏目にでるパターンにはまらないと良いのだが、、
ところで、試合前の練習はどういう意図でその練習・アップをしているか、このうち練習に使えるものはあるか
などというコーチ時代の見方をついついしてしまった