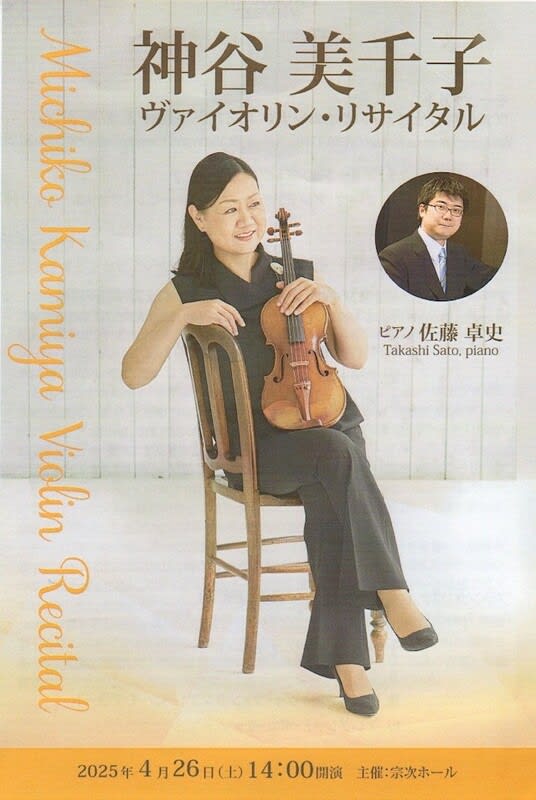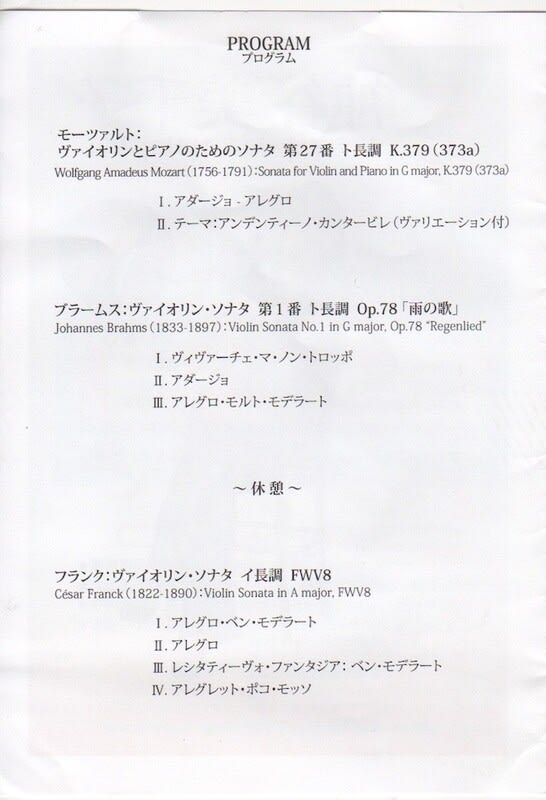時々レコードとCDの聴き比べをしてみる
昨日試みたのはこれ
風のベストアルバムから「22歳の別れ」と「海岸通り」
最近はレコード中心に聞いているが、1年くらい前に知人と聴き比べをしたのは
バッハの「音楽の贈り物」からトリオ・ソナタの部分(リヒター指揮、チェンバロ)
のCDとレコードだった
自分は熱気と言うか奏者の意気込み(チェロ奏者のフォルテする必然性とか)まで
感じ取れるレコードが心地良いと思ったが、知人はCDの音のほうがスッキリしている
との答えだった
そしてまた自己満足をするために昨日、同じ曲、同じ演奏を比べたわけだ
最初にレコードで「22歳の別れ」冒頭のギターの音がふわ~っと響く
歌の声も柔らかで、途中でハモる部分も繊細な感じで、ベースっぽい音が
でてくる時は、こんな音も入っていたのか?と思ったりした
CDに切り替えて同じ曲を聴いてみる
思いのほか悪くない!とも感じる
確かにスッキリしているような気がしないでもない
でも何かが違う、、熱っぽさとか、音の厚みとか
途中のハモリもなんか表情がない
やっぱり、自分はレコードのほうが良いなと実感する
同じ曲の聴き比べができるのはジョン・レノンの曲とか
ポール・マッカートニーの「ラム」がある
クラシック音楽ではオーケストラのクライマックスの場面では
レコードでは地響きするような感じだが、
CDは音量が大きいに過ぎないという感じ
ということで、レコードのほうが良いとした自己満足の結論で
ボケ防止のためのルーティンワークはお茶を濁すことにする
ところで、先日取り上げたピンク・フロイドのポンペイのライブ映画
109シネマズ名古屋で上映されるが、上映時刻を見ると夜になっている
田舎から電車に乗って出かけると家の戻るのは夜中になる
現在の我が家の状況ではこれは無理なので、、あっさり諦めることにした
これも大画面で音を浴びるように体験したほうが、DVDで自宅で見るより
良いだろうな、、と思う
エコーズ聴きたかったな、、と少し残念