
先週の某経済新聞の某女流作家の連載記事を読み、驚きの事実誤認、間違えを見つけました。記事のタイトルは「父が使っていたハーフカメラ」。タイトルからしてもちょっと「?」です。そもそもハーフサイズ・カメラはあっても、ハーフカメラとは言わないのでは、と私は思います。ハーフサイズ・カメラとは35ミリのフィルムを半分使用して24枚撮りのフィルムならば2倍の48枚撮影可能というカメラのことです。
某作家は、小学校とき父親から「ミノルタ16」という小型カメラを借りて遠足に行ったそうです。そのミノルタ16は「ハーフカメラ」で「12枚撮りのフィルムを入れたら24枚撮れる」と説明してました。
この作家さんは写真好きではあったが、カメラには詳しくなかったようです。ミノルタ16は16ミリフィルムを使用する小型カメラで、35ミリフィルムを使うハーフサイズ・カメラとは大違いなのです。
作家さんの記憶違い、勘違いなのでしょうが、こういう間違いを新聞社の校閲部、整理部はなぜ見逃したのか。これは大きな問題だと思いますね。作家から原稿を受け取ったらそのまま素通りなんでしょうか。
過日、NHKの番組でプロの校正者の仕事ぶりを紹介していました。私が驚いたのは最近の校正作業には「元原稿とつき合わせる」という工程が必要ないということです。著者からはデジタルデータで原稿がくるから元原稿というものが存在しない。したがって校正というのは素読みと校閲が中心となります。校正者の知識と教養、経験が問われるのです。ハーフカメラの記事も知識と教養のあるプロの校正者の目が通っていれば、そんな間違い記事は発生しなかったのだろうと思います。
私は、近頃、読書のときは鉛筆(赤鉛筆ではなく普通の黒鉛筆)を用意しています。1冊本を読むと必ず2、3カ所、誤植を見つけるものです。見つけると鉛筆で印をつけます。「彼」が「後」に、「七面鳥」が「七百鳥」に、「対潜」が「対戦」になっていたり、太平洋戦争の海戦に「戦艦愛宕」なる軍艦が登場したり、けっこう誤植、間違いを発見するものです。
ここでいう誤植も死語となりつつありますね。誤植とはそもそも植字をする人が原稿とは違う活字を拾うことをいいます。今は植字という作業がなくなったのですから、誤植は起こり得ない。文字の間違いは著者あるいは校正者のミスです。校正者が間違いを見逃すことを校正ミスといいますが、校正者の役割はますます重大です。
話をカメラに戻して、ハーフサイズ・カメラの定番、ベストセラー機は「オリンパス・ペン」でしたね。
「キヤノン・デミ」「リコー・オートハーフ」というのもありました。



オリンパス・ペンとほぼ同時期に発売された「ペトリ・ハーフ」というハーフサイズ・カメラが私の最初カメラです。小学校6年の修学旅行のときに買ってもらいました。中学にいくとクラスのK君はオリンパス・ペンを持っていました。その頃にはペトリ・ハーフは完全にマイナーな存在でした。悔しかったです。

ハーフサイズ・カメラはフィルムを2倍使えるのはいいのですが、普通にカメラを構えて撮影をするとフィルムのコマを縦に2分しているので縦位置の写真になります。普通に撮っていると縦位置の写真が多くなってしまいます。これがちょっと問題でした。今のスマホの写真のようです。
フィルムサイズが半分になるとその分解像度は下がりますが、私の場合、今もそうですが、大きくプリントすることはないので、問題なしです。
ハーフサイズ・カメラはその後、絶滅しました。16ミリカメラの後継といえる110サイズも一時的でした。それに対してフィルムのAPSサイズは今のデジタルカメラの時代にも健在ですね。










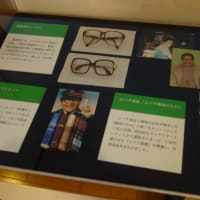






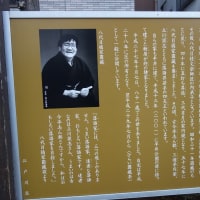


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます