図面を描く時には、柱を立てる基本的な間隔(基準寸法)を基に、間取りが決められていきます。ただ、この基準寸法は一通りではなく、地域や用途によってさまざまです。その代表が、京間と呼ばれるモジュールです。京間の1間は6尺5寸(1970㎜)で、現代風にいうと985モジュールとなります。これは、柱の芯(中心)から柱の芯の間までの距離が、985mmということです。そのほか、四国間の1間は6尺3寸(1910㎜)で955モジュールです。ただし、955では中途半端なので今では950モジュールとするのが一般的です。もっとも多く使われているのは、江戸間といわれる910モジュールです。モジュールが小さいということは、同じ広さの土地により多くの家が建てられるということです。人口が過密化していた江戸から、この910モジュールが出てきたというのは納得できることだとは思いませんか?
ちなみに家は、950モジュールで設計されています。平均身長が大きくなった現代では、910モジュールはちょっと窮屈な感じがします。だって、江戸時代の成人男子の平均身長は157㎝程度と言われていますからね。
ちなみに家は、950モジュールで設計されています。平均身長が大きくなった現代では、910モジュールはちょっと窮屈な感じがします。だって、江戸時代の成人男子の平均身長は157㎝程度と言われていますからね。


















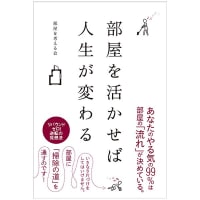

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます