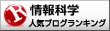光秀が謀反の直前に興行した連歌(れんが)「愛宕百韻」の解読捜査を行いました。その捜査結果をご報告します。
★ 愛宕百韻の解読捜査(捜査開始宣言)
解読を始める前にそもそも連歌とはどういうものかを知る必要があります。前編に書いたとおり和歌を詠み継いで「上の句・下の句」50組で作り上げたものが百韻です。調べてみるとかなり厳格な規則に従って詠まれるものであることがわかりました。
その規則の中から、今回の解読捜査に役立つ規則を抽出してみました。
①第二の句は脇句と称し、第一の句(発句(ほっく))と相応じて大きく離れない内容であることが必要とされる。
②脇句以下は付句(つけく)とよばれ、それぞれ前句とあいまって、一つの世界を形成する。
③第三の句は第三と称し、変化・展開が要求される。
④四句目から九十九句目までは平句と称するのに対して、発句・脇句・第三及び最後の句である挙句(あげく)は特別の重い句とされる。
⑤前句のひとつ前の句を打越(うちこし)と称し、付句(前句の次の句)は打越から離れた内容であることが要求される。前句を挟んで打越の句と付句が同趣同想の句となることは「観音開(かんのんびらき)」と称されて、特に嫌われる。
以上の規則を総合的に判断すると、愛宕百韻に込めた光秀の祈願を解読するには発句・脇句・第三・挙句の四つの句に隠された一連の意味を読み取ればよいことになります。なぜならば、これが特別の重い句であることに加えて、四句目からの平句は⑤の規則によって意味を継承することができないからです。平句の中に光秀の祈願を読み込むことは連歌の規則からみて無理なのです。
それでは問題の四つの句と詠み手をみてみましょう。
発句 「時は今 あめが下なる 五月かな」 光秀
脇句 「水上まさる 庭の夏山」 行祐(ぎょうゆう)
第三 「花落つる 池の流れを せきとめて」 紹巴(じょうは)
挙句 「国々は 猶(なお)のどかなるころ」 光慶(みつよし)
行祐は愛宕山の住職、紹巴は有名な連歌師で光秀と親交の深い人物、光慶は光秀の嫡男(ちゃくなん)です。
★ Wikipedia「愛宕山(京都市)」記事
★ Wikipedia「愛宕神社」記事
★ Wikipedia「里村紹巴」記事
この三人は光秀が土岐氏を代表する人物であることは当然認識しており、光秀の発句に詠み込んだ祈願を誰もが十分に理解したはずです。したがって、彼らの詠んだ句には光秀発句の祈願が受け継がれているはずです。
それでは解読結果は次編で!
<<続く>>
なお、連歌の規則は下記の本を参考にしました。
★ 愛宕百韻の解読捜査シリーズ
①捜査開始宣言
②標的の確定
③表の意味解釈
④土岐氏の流れ
⑤完全解読の意義
⑥遂に完全解読
★ 愛宕百韻の解読捜査(捜査開始宣言)
解読を始める前にそもそも連歌とはどういうものかを知る必要があります。前編に書いたとおり和歌を詠み継いで「上の句・下の句」50組で作り上げたものが百韻です。調べてみるとかなり厳格な規則に従って詠まれるものであることがわかりました。
その規則の中から、今回の解読捜査に役立つ規則を抽出してみました。
①第二の句は脇句と称し、第一の句(発句(ほっく))と相応じて大きく離れない内容であることが必要とされる。
②脇句以下は付句(つけく)とよばれ、それぞれ前句とあいまって、一つの世界を形成する。
③第三の句は第三と称し、変化・展開が要求される。
④四句目から九十九句目までは平句と称するのに対して、発句・脇句・第三及び最後の句である挙句(あげく)は特別の重い句とされる。
⑤前句のひとつ前の句を打越(うちこし)と称し、付句(前句の次の句)は打越から離れた内容であることが要求される。前句を挟んで打越の句と付句が同趣同想の句となることは「観音開(かんのんびらき)」と称されて、特に嫌われる。
以上の規則を総合的に判断すると、愛宕百韻に込めた光秀の祈願を解読するには発句・脇句・第三・挙句の四つの句に隠された一連の意味を読み取ればよいことになります。なぜならば、これが特別の重い句であることに加えて、四句目からの平句は⑤の規則によって意味を継承することができないからです。平句の中に光秀の祈願を読み込むことは連歌の規則からみて無理なのです。
それでは問題の四つの句と詠み手をみてみましょう。
発句 「時は今 あめが下なる 五月かな」 光秀
脇句 「水上まさる 庭の夏山」 行祐(ぎょうゆう)
第三 「花落つる 池の流れを せきとめて」 紹巴(じょうは)
挙句 「国々は 猶(なお)のどかなるころ」 光慶(みつよし)
行祐は愛宕山の住職、紹巴は有名な連歌師で光秀と親交の深い人物、光慶は光秀の嫡男(ちゃくなん)です。
★ Wikipedia「愛宕山(京都市)」記事
★ Wikipedia「愛宕神社」記事
★ Wikipedia「里村紹巴」記事
この三人は光秀が土岐氏を代表する人物であることは当然認識しており、光秀の発句に詠み込んだ祈願を誰もが十分に理解したはずです。したがって、彼らの詠んだ句には光秀発句の祈願が受け継がれているはずです。
それでは解読結果は次編で!
<<続く>>
なお、連歌の規則は下記の本を参考にしました。
| 連歌集 新潮日本古典集成 第33回島津 忠夫新潮社このアイテムの詳細を見る |
★ 愛宕百韻の解読捜査シリーズ
①捜査開始宣言
②標的の確定
③表の意味解釈
④土岐氏の流れ
⑤完全解読の意義
⑥遂に完全解読