社会主義を飲み込んでしまった資本主義経済は、今その臨界点に達しています。
今後、経済は新しいパラダイムに移行することになります。
資本主義の崩壊が起こるのですが・・・ どうなるのかは解りません。
そこでは、需要と供給、生産と消費という冷たい関係を超えたダイナミックな
経済が確かに生まれつつあります。 それは18年以上前にアルビントフラーが
『第三の波』で予測した「プロシューマ」に端を発する資本主義社会における
コミュニティー経済の可能性です。(技術の変化による価値観の変化)
(プロデューサー=生産者とコンシューマ=消費者を融合させた造語)、
トフラーはビジネスの形態は企業規模から家庭の単位に移行するとしました。
基本概念は40年ほど前に作られ、20年後に手を加えられて出版された・・・
あまりにも有名な本です。(ちなみに著者は私よりひとつ年上です)
現在書店で売られているマルチメディア本には、情報産業の未来への
過度の期待から色々と予測する時に、トフラーをお手本にしています。
インターネットを始めとし、情報革命が世の中のパラダイムを大きく変える
との未来予測、アルビントフラーの「第三の波」です。
店頭のメディア本はどれも、今の生活や価値観がいつまでも続くものと考えて
「マルチメディアの技術」のみが進んだ世界を描いている様な気がします。
旧体制の企業が無くなりトフラーの言う「家庭」単位が最終の仕事場なんて
企業や生産活動がなくなってしまえば、個人も残りませんでしょ?
核家族がもっと進んで、家族制度が崩壊すれば「家」の価値も変わるのです。
農業では(米)過剰生産と対米対策で休耕田が問題になって久しいですが・・・
職業としての農家の跡取りが居なくては・・・ その制度の役割も崩壊します。
高度消費社会とワンセットでの消費や人工は増え続ける発想でのショッピングも
少子化が進み人工そのものが減っていけば、需要は縮小して行くでしょう。
高齢化社会とは・・・ ある時期に寿命の尽きる人間がとても多いって事ですよ。
だから、この手の雑誌などの未来予測は何処か的外れな部分が含まれますよね。
アルビン・トフラーの『第三の波』に予言されている未来に対する異論は
そんな理由から来ています。 未来なんて数学的に予測は不可能だからです。
アルビン・トフラーは、その著作『第三の波』の中で次のように言っています。
過去に、人類の歴史を大きく変えた変化を波として捉える発想です。
第一の波は農業革命、狩猟から農業への転換。
第二の間には産業革命、機械的な動力を手に入れた事です。
そして第三の波が現在起こりつつある情報革命の事ですね。
農業革命の時にも、産業革命の時にも、大きな価値観の変化が起きました。
もちろん過去の事例ですから、実績も有り歴史的な事実です。
しかし、それを基にしての第三の波、情報革命の中で全ては変化する。
では・・・ どうしても無理が生じてしまうのです。
トフラーは歴史認識から、農耕や産業革命によって社会のあらゆる部分が大きく
変わった様に、「情報革命によっても社会のあらゆる部分が変化する」と
予言しています。
これは実に画期的な着眼点で、世界中の人々にインパクトを与えました。
それは、マルチメディア関係者だけで無く、一般人も思いあたる事だったのです。
しかし、残念な事に発行当初トフラーが実際に提示できた、未来の
情報社会とは結構・・・ 陳腐なものでした。
会社へ出勤せずに、それもフレックスタイムの在宅勤務。
自宅からパソコン通信で仕事をこなす様になる? 程度ですよ。
子供達は学校へ行かなくても、パソコン通信で勉強出来る。
教師はマンツーマンで、しかも全世界の教師がそれに参加してくるだろう。とか。
わざわざ買い物にいかなくても、全て通販で生活が出来、冷蔵庫の中身すら
契約先がトヨタのカンバン方式並に不足を補うイメージとか・・・
まるっきり、まんまNTTや携帯電話のCMレベルの未来です。
しかし、トフラーのこの本は、全てのマルチメディア本のお手本になりました。
だから・・・ メディアの発展予想図は、上記のイメージをしてしまうのです。
携帯電話にテレビが付き始めました。 カメラは当たり前です。
しかし、テレビにおいては殆ど意味を為さない機能でしょう。
技術の進歩とニーズには大きなズレが有り、物珍しさだけで終わります。きっと。
確かにパソコンネットが整えば、自宅で仕事も勉強も買い物も
画面に向かって済ませる事も可能になります。
しかし、「出来る」事と「やりたい」事の根本が違う事位なら・・・
少し考えれば誰にでもすぐ解ります。
確かに現実では、通勤ラッシュは嫌だと思っている人は都会には多いでしょう。
だからと言って、在宅作業の仕事に人気が集中した話は耳にしませんね。
おそらく仕事とは必要な設備が整った環境で、決められた時間だけ働いたら
後は狭いながらも自宅に帰って、仕事を忘れのんびりしたいと考えている人が
多いのでは無いでしょうか。 (アフターファイブも無くなるの?)
自宅に家族が居たら仕事の空間を隔離しなくては集中出来ない事や・・・
知的な仕事以外の生産分野はどこへ行ってしまうのでしょうね?。
漁業の漁師さんは海にも行かず、パソコンで魚を捕ったり・・・ 出来ません。
建築の大工さんが自宅のパソコンで、家が建てられる筈は有りません。
学校でも、いじめや登校拒否の問題が大きな社会現象として話題です。
それでも、家に子供が朝から晩までパソコンと向かい合ってまで居てほしい。
と考える親がそんなに大勢いるとは思われません。
治安に配慮され、安心して預けられる学校へ自ら子供が喜んで行ってくれる。
活発で目が離せない年齢の子供が家に居られたら、パートにも出られない?
子供部屋に外から鍵を掛けて教育はPC、母親はパートに出る様では本末転倒。
買い物だって、確かに雪や雨の日に買い物に出掛けるのは億劫ですよ。
だからと言って、通信販売やテレフォンショッピングに人気が集中とは別です。
デパートや専門店に誰も行かなく成る時代は来ません。
特に女性達にとってのショッピングは、娯楽の一種で楽しみなのです。
アルビントフラーの『第三の波』は、成ったら良いな的「画期的な着眼点」と
「イージーで現実離れした予測」を当時の私たちに提供してくれたんです。
なのに、日本のマルチメディア本の作者達は「画期的な着眼点」を
きちんと捉えずに「イージーで現実離れした予測」の方を膨らませているんです。
メディア代表のテレビ局のやらせ体質や、でっち上げ体質をお手本に
メディア本の制作側が、上澄みのイメージを刷り込もうとするのも
全てスポンサーの顔色優先で有って、消費者はダマされているんですね。
それでも第三の波は来るでしょう。 あのドラッカーも言ってますし・・・ 。
別に慌てる事も無い、今よりも良くなるに決まっているんだから。多分。
幕末に坂本龍馬が鉄砲を持った様に、マルチメディアを捉えるのでは無く
パソコンは戦う武器ではなく、身を守る護身用って事じゃどうだろう?











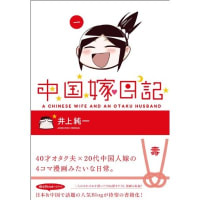


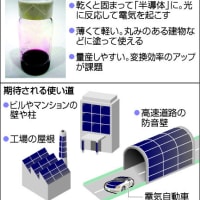

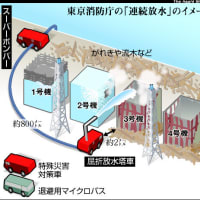



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます