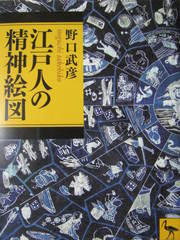
「岳台下の酒店」の主人半之助が近藤重蔵を「地境論」で代官に訴えたのは、『慊堂日暦』によると文政8年(1825年)の春のことでした。
『藤岡屋日記』によると、それ以前に近藤重蔵は隣家(半之助家)との境に大木を植え並べ、垣根を設けています。
半之助の「座敷の前へ大木を植ならべ、富士ヲ見へぬ様ニ致し候ニ付き客も来らず候」
「座敷」とは、おそらく半之助が開いた蕎麦屋の「座敷」であったでしょう。
垣根がつくられる前は、蕎麦屋の座敷から富士塚(目黒新富士)や富士山が見えたことがこの記述からわかります。
この年の盂蘭盆の頃(7月15日)、この目黒新富士を訪れたのが村尾嘉陵。
嘉陵は「東の富士」つまり目黒新富士のふもとに「そば麦をうる」家を目撃しています。
この「そば麦をうる」家とは、半之助が開いた蕎麦屋のこと。
目黒新富士のふもとに蕎麦屋があって、嘉陵はその蕎麦屋のところで「垣根」を結っている男に声を掛け、重蔵のことについて聞いています。
その男は、嘉陵の問いに「時々ここの別邸にも来ているけれども、今はとても困窮しているようだ。しかし傲放(ごうほう=おごりたかぶること)のみは以前と変わらない。とてもうるさい」と答えています。
嘉陵が5年前の文政3年(1820年)の3月4日に初めてここを訪ねた時には、目黒新富士は出来たばかりであり、元富士に較べれば「猶(なお)いまだ具足せず」という状態であり、その頂きには「祠」が「南面して」立っていました。
この「祠」とは、富士浅間社の「石祠」であったでしょう。
もちろんそのふもとには、蕎麦屋はまだ設けられてはいませんでした。
今は山からの見晴らしがよいだけで、花(桜)もやがて植えられると聞いてはいるがまだ植えられていない、とは途中で立ち寄った茶店の主人の話でした。
広重の『名所江戸百景』の「目黒新富士」を見てみると、新富士のふもとの三田用水の両側には桜が満開に咲いているものの、この文政3年当時は、植えられてはいなかったことがわかります。
「嶽台の変」が起きるのは文政9年(1826年)5月18日のことでした。
その前日の『慊堂日暦』に、気になる記事がある。
「近藤正斎、訪わる。余は為めにこれを懇規す。渡辺崋山来る。」
近藤重蔵が慊堂を訪ねて来たというのです。
「余は為めにこれを懇規す」とはどういう意味か。
「為めに」というのは、「重蔵のために」ということであるでしょう。
「懇規」とは、「規」に「ただす」という意味があることから考えると、「ねんごろにただす」という意味であると思われる。
翌日に「岳台の変」が発生していることを考えると、慊堂の「羽沢山房」にやって来た重蔵は、「明日、もし半之助が無礼を働いたならば斬り捨てることも考えている」といったことを親友である慊堂に打ち明けたのかも知れない。
それに対して慊堂は、その重蔵の軽挙妄動(な計画)をたしなめたというふうにはとらえられないだろうか。
無礼を働けば不届き者として百姓半之助を斬り捨て御免とする、という考えを重蔵が持っていたということを伺わせる慊堂の日記の内容です。
しかもその日には、崋山も慊堂を訪ねています。
おそらく重蔵とは入れ違いに、崋山が羽沢山房を訪ねたものと思われる。
慊堂は、先ほど重蔵から聞いたその企てを、崋山に洩らすようなことはなかっただろうか。
そして事件が発生するのがその翌日19日の夜。
『慊堂日暦』によると、半之助(59)は「近藤宅内」で殺されています。その妻(58)と息子夫婦は「宅内」で殺されていますが、この「宅内」とは半之助の家の中ということであるでしょう。
忠兵衛(25)が近藤家の傍らで殺害されています。
この忠兵衛とは、『藤岡屋日記』の記述から判断すると、垣根を取り払っていた日雇いの職人であったものと推測されます。
半之助と日雇い職人の忠兵衛がまず近藤家で殺され、その後、半之助の妻とその息子夫婦が半之助宅で殺されたということであると思われる。
半之助の息子(林太郎・29)が現場から逃れて自分の家に逃げ、押入れに隠れたけれども見つけられ、それをかばおうとした妻(29)が斬られ、その後に林太郎が突き殺されたということであるらしい。
そのどさくさの中で半之助の妻(58)も斬り殺されたものと思われる。
この「岳台の変」と呼ばれる事件の「評定吟味」は、5月21日に行われています。
その後の『慊堂日暦』の関連記事は以下の通り。
文政9年5月28日。
「朝、出でて紀治を訪(おとな)い、近藤の消息を以てす。治は不在。」
文政9年6月6日。
「近藤正斎父子は獄に下る。」
文政9年6月13日。
「御代官、近藤の下獄を問う。」
文政9年6月24日。
「ここに僧あり、正斎とともに半奴を殺す。」
この「僧」とは誰のことかわからないが、この事件の判決で、「一向宗駒込西善寺」の「了雄」というものが「急度(きっと)叱り」となっています。
この駒込にある「一向宗」(浄土真宗)のお寺「西善寺」とは、近藤家の菩提寺であり、近藤家がこの事件を起こしたために、「西善寺」の住職である「了雄」がその菩提寺としての責任を問われたということであるようです。
この「了雄」が、「ここに僧あり、正斎とともに半奴を殺す」という記事の「僧」に該当するとすれば、慊堂は誤伝を記したとも考えられる。
慊堂には、重蔵も殺害に加わっていたのではないかという思い込みがあったのかも知れない。
5月17日、つまり事件発生の前日、慊堂を訪問した重蔵の言や様子には、慊堂にそう思い込ませる迫力があったのではないかと、私は想像します。
文政10年(1827年)11月21日の『日暦』に、興味ある記述が出て来ます。
慊堂はそのことを11月17日に聞いたらしい。
分部家にお預けとなっていた重蔵が逃亡したというのです(実はこれは誤伝)。
近江より越前に入り、敦賀で舟を購入して越後から蝦夷地に入り、そこから清国を経由して魯西亜(ロシア)に逃げようとしたが、大坂で捕えられたということを伝聞した(これも誤伝)、という記事。
「渠(かれ)はほぼ外国の事状を知り、且つ蝦夷はその経歴するところなり」とも、そこには記されているのですが、ここに慊堂の近藤重蔵評価の一端が披瀝されています。
「ほぼ外国の事状を知り、且つ蝦夷はその経歴するところなり」
外国の事情について詳しく、さらに蝦夷地についても自ら踏査していて詳しい、ということであり、おそらく慊堂は重蔵から外国の事情や蝦夷地のことについて詳しく聞いていたのです。
この重蔵の若い妾とその間に生まれた二人の子どものその後のことについても、『慊堂日暦』には興味ある記述が多数出てくるのですが、それらについては割愛します。
また松崎慊堂について触れた本で、『江戸人の精神絵図』野口武彦(講談社学術文庫/講談社)というのも最近本屋で見つけました。
これについてはまた別の機会に触れてみたいと思います。
終わり
〇参考文献
・『慊堂日暦』(東洋文庫/平凡社)
・『江戸近郊道しるべ』村尾嘉陵(東洋文庫/平凡社)
・『江戸巷談 藤岡屋ばなし』鈴木棠三(三一書房)




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます