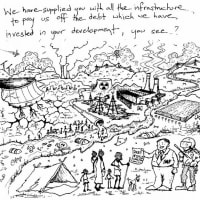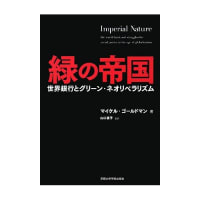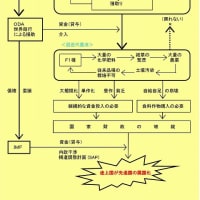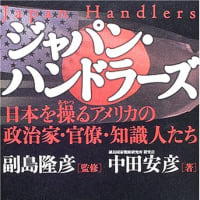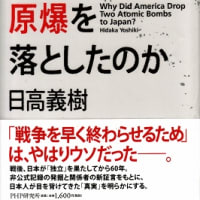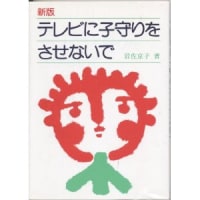何人かで同じ文章を読んで、その文章構造を図解化して、照らし合わせる作業をやっている。毎回みんなで「同じ文章を読んだ上での図解なのに、「ここまで違うか!?」と、そのすれ違いに驚くのだが、そもそも「文章を読む」とはどういうことなのだろうか?
文章を書く人は、何かを実現するために、言葉で何かを伝えようとする。
文章を読む人は、何かを実現するために、作者の意図(伝えたい何か)を汲み取ろうとする。
昔の人たち(例えば明治時代の人たち)に比べて国語力が劣っていると言われる現代人だが、まずは読者の側から考えられる壁を挙げてみた。
 クリックで応援おねがい!
クリックで応援おねがい!
↓ ↓ ↓


![]()
思い当たるのは、3つ。
①個人主義の影響。
「自分の解釈」「私の理解」といった逃げ道(妥協策)が残されているかぎり、とことん作者に同化して作者の意図を読み取ろうとする力が劣ってしまうのは必然だろう。
②優れた文章を読み、読み解く楽しさに触れる機会が減ったこと。
古文や漢文などの読解も学校で一定は行うものの、試験勉強の域を出ない。また、現代文至ってはその多くが個人主義の影響を受けた中身の薄い随筆や私小説。「読解」するようなレベルの代物でなく、その面白みを教えることができる教師も少ないように思う。
③相手の想い(心)を理解する能力が劣化していること。
集団の崩壊によって人間関係(特に母子関係、仲間関係)が希薄化したがゆえに、文字(観念)機能の習得以前の問題として、相手の想いに同化するための共認(分かり合い)機能が劣化している。だから文字を見ても、それが表している現実の生々しい息吹を感じることが苦手である。
以上3つの壁の中でも、「個人の解釈」という逃げ道が、文章の読解力を劣化させている大きな要素であるように思う。そして、おそらくこれは読者の壁であるだけでなく、作者の側も同じ壁にぶつかっている、つまり「個人の解釈」というアローワンスを前提に書いているゆるい文章が多いように思う。
この状況を突破するための答えは、「どれだけより確からしい作者(主人公or社会)の想いに近づけるか」。それには「解釈」という読者(作者)の意図や考えの介在を許さない事実追求の地平にどれだけ近づけるかが鍵であり、とことん読者(作者)の意図や考えを排除したところに立ち顕われてくるものであると思う。たとえそれがフィクションであったとしても。
そして、己の「解釈」や「考え」を排せば排するほど読者間の共認充足は高まり、当然のことながら文章の先にある作者との共認充足も高まることになる。文章を読むことの楽しさはここにあり、文章の書くことの楽しさはここにある。すべては深い共認充足のためにある。 ![]()