四国八十八ケ所霊場 ご開創1200年記念のバスツアー巡拝第15回目 平成27年3月20日から21日の
2日間 高野山お礼参り2日目 金剛峯寺のつぎに 壇上伽藍(国指定史跡地域)へ詣でました
壇上伽藍は 弘法大師御廟(ごびょう)のある奥の院とともに 高野山の二大聖地といわれ
弘法大師が 人々が厳しい修行によって悟りを開くために 真言密教の道場として
高野山で最初に開かれた場所といわれています 多くの諸堂が配され荘厳さが伝わる壇上伽藍です


金剛峯寺から通じる道 蛇腹道から壇上伽藍に入ると
最初に 東塔 があります
白川上皇の発願で1127年に建立され 当初は上皇等身大の 尊勝仏頂尊
(そんしょうぶっちょうそん)が本尊として祀られ 後に不動明王
降三世(ごうさんぜ)明王の2体が脇侍として祀られています
焼失再建を繰り返し現在の建物は昭和59年(1984)に
弘法大師御入定1150年の記念に再建されています

三昧堂 (さんまいどう)
928年頃 真然僧正(弘法大師の甥)が真言堂跡に建てていたものを
1166~1169年に 金剛峯寺六代目座主の済高上人が
この地に移したものといわれ 済高上人が
修行三昧された ことから三昧堂といわれているそうです

大会堂(だいえどう)
鳥羽法皇の皇女 五辻斎院(ごつじさいいん)内親王が
1175年に発願 度重なる火災に遭い 1848年に再建され
法会を行う 集会所的な場所になっているそうです

大会堂の左に 愛染堂
1334年後醍醐天皇の発願で 天下泰平を祈願するため
護摩をたくお堂として建立 度重なる火災に遭い1848年に再建されています
ご本尊の愛染明王は 後醍醐天皇の等身大といわれています

根本大塔の下 愛染堂の前に町石 一町石があります
奥の院御廟まで4K 36基 の町石が置かれているそうです

檜皮葺(ひわだぶき)の不動堂 は落雷から免れ
鎌倉時代の書院造り様式で 1899年に国宝に指定されいます
鳥羽院皇女の八条女院の発願で 1198年 行勝上人が建立され、
4人の建築士の発想が織り込まれているそうですが
違和感の無い建物になっていると いわれています
本尊不動明王坐像と 運慶作の八大童子像が祀られているそうです

真言密教のシンボル根本大塔
816年~887年まで 大師と 真然僧正(大師の甥)と二代を費やして完成され
多宝塔としては日本で最初に建てられもので 落雷などで焼失 現在の大塔は
昭和12年(1937年)に再建 高さ約49m 4面約24mの偉容を誇っています
 (お借り画像)
(お借り画像)
内陣は中央に 胎蔵界の大日如来が 四方に 金剛界四仏
阿閦仏、 宝生仏、阿弥陀仏、不空成就仏が祀られ
周囲16本の柱には 堂本印象画伯の 十六大菩薩が描かれ
内壁には、真言八祖像と 花鳥が描かれ 立体曼荼羅を表しているそうです

夜空に鮮やかに浮き出された ライトアップの根本大塔
夕食後散策でパチリ

大塔の鐘
巨大な銅鐘は弘法大師空海が発願し 真然僧正(大師の甥)の代に完成
焼失して 1857年に3代目の改鋳 直径2mの銅鐘が
吊るされ「高野山四郎」と呼ばれています
除夜の鐘108つ突くときは 一桁は小石 10突くごとに大き目の石で数えるそうです

再建中の中門 (前回の時パチリ)
何回も大火に見舞われ 1843年から 172年ぶりの再建です

中門 8代目 高野山開創1200年記念に完成
新たな中門は 鎌倉時代の建築様式をもとに
東西25m南北15m高さ16m 焼失していた増長天 広目天
が新たに作られ多聞天 持国天とともに 四天王がそろって安置されました
開創1200年記念大法会の初日 平成27年4月2日に
中門前の広場で 横綱 第69代白鴎関
第70代白馬富士関が 土俵入りを披露されるそうです

中門の左に納経所 お守りなども売っているお堂があります
金剛界の大日如来さまが祀られ ご馳走が供えられています
仏さまは香りがご馳走で 少しでも香りが出るよう 斜めカットしでお供えをするそうです

金堂
高野山開創当時から 1932年(昭和7年)に7度目の再建がされています
ご本尊は 明治・大正時代の 仏師 彫刻家 高村光雲作の薬師如来が祀られ
壁画は 明治から昭和初期の 日本画家 木村武山画伯の筆で描かれているそうです
また、胎蔵界 金剛界の曼荼羅の大日如来の王冠には
平清盛が額を割った血を混ぜて描いた「血の曼荼羅」が奉納されているそうです
開創1200年記念大法会の期間中 ご本尊が初めて特別公開されるそです

六角経蔵 (荒川経蔵)
1159年 鳥羽天皇の妃 美福門院が鳥羽天皇菩提を弔うために
紺紙金字一切経を浄写 3,573巻の 一切経を収めるために建立されたそうです
領地の荒川庄を寄進されことから 荒川経蔵と呼ばれ また経蔵が
六角形をしていることから六角経蔵とも呼ばれ 1934年に再建されています

一切経保存のため経蔵の下部が回転式になっており 取っ手を持って
回転さすと 空気の入れ換えができる仕組みになっていて
経蔵を一周すると 一切経を一通り読誦した 功徳があるといわれています

お坊さんの 願掛け絵馬 御社(みやしろ)の側にあります
成就が叶うと一番お世話になった方に捧げるそうです

御社の 山王院本殿 (明神社) 1522年に再建され 国の重要文化財です
向って右から一の宮に丹生明神社(山の神) 二の宮に高野明神社(狩場明神)
三の宮に総社(十二王子と百二十番神)が並んで建っており 御社の入り口左右で
白黒二匹の犬が御社を守っています
狩場明神は白黒二匹の犬を連れた猟師姿で現れ 法大師空海は二匹の犬の先導で
高野山に開山することが出来 導きの神として また 丹生明神は高野山一帯の豪族の丹生氏の
氏神であり 弘法大師空海は丹生氏の助けで高野山に開山する事が出来 山の神として 狩場明神 丹生明神を
高野山の真言密教の守り神として御社を金堂に続き建立されたと伝わっています

山王院 (さんのういん)
御社の拝殿として建立され 両側面向拝付入母屋造り
(りょうがわめんこうはいつきいりもやづくり)の建物で
藤原時代に建立され 幅21、3m 奥行7,8mあり 1594年に再建されています
国の重要文化財です

西塔 国の重要文化財です
887年に年光孝天皇の発願で建立され 現在は5代目で
高さ27,27m 1834年に再建され
金剛界大日如来と胎蔵界4仏が安置されています

鐘楼

孔雀堂
1199年後鳥羽法王の御願で 京都東寺の延杲大僧正が祈雨の修法を成就し
その賞賜として建立され 1983年に再建されています
本尊孔雀明王像は 創建時快慶の作で 重要文化財です

准胝堂 准胝観音が祀られています
准胝観音像は大師が得度剃髪の際 自ら本尊として刻んだと伝えられる像で
当初は食堂に安置され 973年に お堂を建立して安置されています
現在の堂は 883年に再建 されています

御影堂 (みえどう)
御影堂は高野山で最も尊厳を尊ぶ御堂とされています
大師の持仏堂として 仏像や古文書などを保管する場所でした
大師の弟子真如法親王(平城天皇の第三王子)が大師入定前に
描かれた 大師の御影を安置した事から御影堂と呼ばれるようになり
堂内は大師の十大弟子の肖像が大師の御影を護るように掲げられているそうです
旧3月20日には 御逮夜が行われ一般内拝ができるそうです
現在のお堂は1843年炎焼後 1847年に再建されています


檀上伽藍のほぼ中央に 三鈷の松
大師が唐の都長安の青龍寺で恵果和尚から真言密教を学び
唐から帰国される際 明州の浜から真言密教を広めるためにふさわしい
場所を求め 日本に向けて三鈷杵を投げたところ
雲に乗った三鈷杵が日本に飛んできたそうです
後に大師が二匹の犬に導かれ 高野山を訪れると 三鈷杵が引っかかった
松があり この地こそ 密教を広めるのに ふさわしいと決心されたそうです
その松は法具三鈷杵と似て 三葉の松で「三鈷の松」といわれ 参拝の方たちは
縁起物として持って帰り 特にお財布に入れておくと お金持ちになるそうです

高野山一山の玄関口にそびえる朱塗りの総門大門
高さ約26m 1705年に再建されています
両側に高さ約5mの 阿・吽の金剛力士像が
大宗教の都 高野山を訪れる方々を送迎しています バスから パチリ!
つぎは 世界遺産に登録され 女人高野と呼ばれる慈尊院へ
おしまい















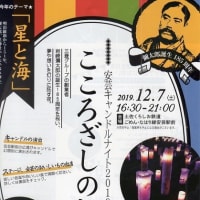




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます