ここしばらく、勤務先の会社の窮状と付き合って
こっちまで、びんぼ臭い生活になってもた。
先週は、約2回ほぼ徹夜みたいな夜を過ごした。
今年に入ってから、ずっとそんな感じ。
日銀や連銀その他の新着情報メールもいっぱい届くんだけど、
見てる暇なし。ってか、暇なときは
酒を飲むことぐらいしかする気になれない。
水泳もサボり気味。
そんな中で、昨日は久しぶりに本を読んだ。
東外大の中山智香子先生の『経済ジェノサイド』。
平凡社新書。で、今日は、その読後感想文。
と、言いつつ、
いきなり、私事から入るんだが、
その昔、「疎外論」と、言うのがあった。
城塚登先生の『若きマルクスの思想』とか、
エーリッヒ・フロムの『正気の社会』とか、
パッペンハイムの『近代人の疎外』とか、
まあ、いろいろ。よく、「人間主義マルクス」などと言われたが、
要は、近代社会では、人間は自己疎外され、人間らしく生きることができない。
だから、自己疎外状況から、自分自身の人間らしさを取り戻すことこそ、
革命あるいは社会改革の意味なのだ、と、
まあ、そこまで平板な話でもないのだが、
かいつまんで言ってしまえばそういうことになる。
おいら自身は、若いころ、この考えに大いに感銘を受け、
それなりに勉強した。城塚先生のゼミにも参加したし。
この思想を勉強したことは、その後のおいらの物事の考え方に
少なからず影響したし、今でも、勉強してよかったと思っている。
若い人にもぜひ読んでもらいたいとも。
でも、この理論は、実は、あまり評判良くない。
一つには、「人間らしさ」「本来の(疎外されていない)自分」って、
何よ? と、言う話で、そんなものは、幻想ではないか、
あるいは、現状否定として勝手に理想描いて、
それを参照系として用いることに、
どんな意味があるのか、もっと言えば、
大体、「本来の自分」として、理想の「人間」として描かれているもの自体が、
近代市民社会の中で作られた恣意的イメージにすぎないのではないか。
と、いうわけで、
おいらもひところは、感動して熱心に
書物を読み漁ったけど(と、いうのは、
いろいろ世の中に腹の立つものが多く、
そうしたものを考える際の軸となるものが欲しかった)、
いろいろ読んでいるうちに、自然と離れてゆき、
結局、多くの友人たち同様、
アルチュセールの構造主義や広松渉の物象化理論などに、
移って行った。
実はこの理論には、もう一つ問題があった。
結局のところ、こうした人間主義=ヒューマニズムは、
それ自体、キリスト教の中から生まれたすこぶる歴史的概念であり、
これは、確かに、ある意味では平等や人権、自由、民主主義に結びつく、
崇高な理想であるかのように見えながら、
その実際に果たしている機能を見れば、
植民地主義の正当化、つまり、
植民地地域の現地の人々は
いまだヒューマニズムも獲得していない低レベルの種族であり、
西欧により啓蒙され、指導されることによって
より民主的な人間にならなければならない、
と、いうイデオロギーをささえ、かつての植民地時代同様
今日のアメリカやヨーロッパによる各地域への武力介入を
正当化する役割を果たしているわけだ。
そんなこんなを勉強してゆくうちに、
簡単に「自己疎外」なんて言っている人のことを
馬鹿にしたり(もちろん、自分のことは棚に上げるさ。
弁証法だもの。)、民主主義の欺瞞性について
一席ぶったりもできるようになったが、
それでも、逆にあれから20年以上もたった今になって、
やはり、丸山真男や日高六郎や、宇井純や原田正純といった
人々の思想とともに、自分の思想的基礎となったものの
一つとして、若きマルクスの自己疎外論を大事にしたいのである。
もちろん、おいらもこの年になり、
あのころのまま、というわけにはいかない。
何らかの意味でバージョンアップした、おいらなりの「若きマルクスの思想」を
書いてみたいのである。
さて、ここまでは、前ふり。
本書で、中山先生は
「フマニステ」という言葉を使っているけれど、
要するに、ヒューマンのことである。
キリスト教の中で生まれ、
若きマルクスにより、近代社会において疎外された主体として
描かれた、
人類の進歩を支え、民主主義と人権と自由と平和を享受する
そんな人間のことである。その実、それはイデオロギーとして
多くの侵略戦争と殺戮と収奪と奴隷制を正当化し、
今日なお、収奪と不平等とを再生産する認識上の枠組みを
提供し続けている。
だから我々は、この「人間」の下に、
もう一つの層として、「人類」を描く必要がある。
単に西洋の人間概念に包摂されない
もっと歴史的にも文化的にも多様な「人類」である。
これは、要するに、ある意味では生物学的な
ホモ・サピエンスとして他の動物から区別される
一群の動物の群れ、という意味になるが、
だが、実際には、この動物の群れは
何らかの形で社会を形成し、
集団を再生産することで生存し続けている。
それは、簡単に文化とか経済とか歴史などと言えるようなものではないが、
しかしそれでも人類が生きているとき、何らかの、
我々の言葉でいえば
「社会関係」とでもしか言いようのない何ものかを
再生産し続けてしまっているのである。こうした存在のことを
中山先生は、AGフランクに従い
アントロポスと呼ぶ。
こうした多様な社会関係を
「未開」「野蛮」(それ以前には「自然」という言葉も
同じ悪いイメージで用いられていた)として
ある特定の「文化」「社会」「歴史」の在り方だけを
絶対なものとして押し付けてきたのが「人間」であった。
だが、今やその「人間」自身が、過去にない
とてつもない変容を遂げつつある。つまり
「ホモ・エコノミクス」による侵犯である。
おいらなりに考えるなら、
「ホモ・エコノミクス」は、本来、
経済学に特有の、理論的に純化するための
理論装置であったにすぎない。
確かに、「人間」は、利益を求めて行動する。
そうした人間の側面を抽象化して理論家することに
意味がないとは言えない。
また、(少なくとも入門ミクロ経済学の、
内容ではなく、序文を読む限りでは)経済学で追及される
「私的利益」とは、必ずしも金銭欲のことではない。
経済学では目的は問わない。
目的がたとえボランティアであっても、
そのボランティアという目的を効率的に遂行するため、
つまり目的に対して資源の最大限の有効活用を追求するための学問が
すなわち経済学なのである。
経済理論における「私利追求」は
けっして、ボランティアのような利他的行動を排除するものではない。
利他的行動であっても、その「他者を助けたい」という
自分自身の欲求を最大限満足させるための
資源の効率的活用を促すことこそ、ミクロ経済学の役割なのである、
と、言うわけだ。
しかし、中山先生が描き出す新自由主義者たちにとって、
少なくとも、フリードマンにとっては、
このような経済学の教科書の序章は
ゴミくずのような無意味な能書きに過ぎなかったようだ。
フリードマンにとっては、人間(フマニステ)とは、
つまり、ホモ・エコノミクスだったのである。
「いちば」ならぬ「しじょう」は
人間社会のある現象、ある側面などではなく
あるべき社会の姿そのものになってゆく。
ポランニーは、土地・人間・貨幣(資本)が交換の対象となる現代社会を
市場が社会を包摂する特殊な状況と認識していたが、
フリードマンにとっては土地や人間、貨幣が取引できない社会など
不完全な異様な社会だったようだ。
しかしながら、このような社会は
外部からの強制力という支えを抜きに維持は不可能であった。
新自由主義は、市場の機能を最大限にするべく、
国家の役割を最小限の領域に押し込めようとするが、
同時に最大限に強力なものにしようともする。
福祉や教育のための役割を最大限切り捨て、
あるいは、かかわる場合でも、
擬似的な市場を生み出すことで(例えば教育バウチャー制度)
国家の主体的な関与を否定する。
他方で、この市場社会という特異な社会の矛盾から噴き出る
アンチテーゼに対しては
最も抑圧的な役割を期待される。
このような市場と国家の役割が最大限実現されたのが
ピノチェトのチリであり、
これこそが新自由主義者たちのモデルケースになった、
と、言うのが、中山先生の位置づけである。
勿論、経済学の内部にも、
ただ、新自由主義だけがあったわけではない。
AGフランクや、JKガルブレイス、
Jロビンソン、Hミンスキー等々。
しかしフランクの一生は、
「経済学」が、その研究対象であるはずの
「私利私欲」と結びついた時、何が起こるかを
如実に示して見せた。
経済学(と、言うより、新自由主義)が、
ホモ・エコノミクスをして、フマニステばかりでなくアントロポストをも
包摂しようとしたのは、
何のことない、経済学のほうが
私利私欲に取り込まれてしまっていたからだ。
経済学において(ミクロ経済学教科書の序文を除くと)もっとも卑近な金銭欲だけが
私利として認められるのは、
結局のところ、経済学者自身の私利私欲の追及の結果に過ぎなかった、というのである。
新自由主義が推し進められる過程で、
様々なサンクションが与えられた。
それは、時限爆弾という過激な場合もあれば、
職を干される、という比較的穏便な場合もあり、
逆に、ノーベル賞というよくわからない報償による場合もある。
そして、マスメディアの存在が
学問を単なる学問以上のものにしてしまう。
ガルブレイスもフリードマンも、そのことをある意味では承知の上で、
あるいみでは無自覚に使い、使われてしまう。
学問は、象牙の塔を超え出て、「イズム」として流布されてゆく。
この過程で、実生活上においても
ホモ・サピエンスがフマニステを包摂してゆく。
もっとも、新自由主義は、その主導者であったはずの
フリードマンをも越えてゆく。
とりわけ、フリードマンが唯一の問題と呼んだ
貨幣は、結局フリードマン自身にとっても
問題になってしまった。
ひとたび貨幣が商品となってしまえば、もはや
市場の自由を遮ることはできない。
貨幣は国家を超え、
国家の抑圧体制を凌駕して、
国家と国家の利害関係の間隙を縫う形で
自己展開してゆく。
フリードマンは合理的期待形成学派とは違い
貨幣供給量についての管理を重視したが、
金利は市場で決められるべきものと考えていた、という。
だが、こんな片手落ちな話をどうして
学者さんたちが受け入れたのか、よくわからない。
いずれにせよ、フリードマンの想定を超えて
世界を股にかけて移動する貨幣に関する説明は
一方では、ストレインジの『カジノ資本主義』や
『マッド・マネー』を想起させる。
(なぜ、中山先生がストレインジの著書を取り上げなかったのか、
ちょっと気になる。)
[お休みの時間になったので、
気が向けば、
次回に続く。気が向けば。。。。ね。]
こっちまで、びんぼ臭い生活になってもた。
先週は、約2回ほぼ徹夜みたいな夜を過ごした。
今年に入ってから、ずっとそんな感じ。
日銀や連銀その他の新着情報メールもいっぱい届くんだけど、
見てる暇なし。ってか、暇なときは
酒を飲むことぐらいしかする気になれない。
水泳もサボり気味。
そんな中で、昨日は久しぶりに本を読んだ。
東外大の中山智香子先生の『経済ジェノサイド』。
平凡社新書。で、今日は、その読後感想文。
と、言いつつ、
いきなり、私事から入るんだが、
その昔、「疎外論」と、言うのがあった。
城塚登先生の『若きマルクスの思想』とか、
エーリッヒ・フロムの『正気の社会』とか、
パッペンハイムの『近代人の疎外』とか、
まあ、いろいろ。よく、「人間主義マルクス」などと言われたが、
要は、近代社会では、人間は自己疎外され、人間らしく生きることができない。
だから、自己疎外状況から、自分自身の人間らしさを取り戻すことこそ、
革命あるいは社会改革の意味なのだ、と、
まあ、そこまで平板な話でもないのだが、
かいつまんで言ってしまえばそういうことになる。
おいら自身は、若いころ、この考えに大いに感銘を受け、
それなりに勉強した。城塚先生のゼミにも参加したし。
この思想を勉強したことは、その後のおいらの物事の考え方に
少なからず影響したし、今でも、勉強してよかったと思っている。
若い人にもぜひ読んでもらいたいとも。
でも、この理論は、実は、あまり評判良くない。
一つには、「人間らしさ」「本来の(疎外されていない)自分」って、
何よ? と、言う話で、そんなものは、幻想ではないか、
あるいは、現状否定として勝手に理想描いて、
それを参照系として用いることに、
どんな意味があるのか、もっと言えば、
大体、「本来の自分」として、理想の「人間」として描かれているもの自体が、
近代市民社会の中で作られた恣意的イメージにすぎないのではないか。
と、いうわけで、
おいらもひところは、感動して熱心に
書物を読み漁ったけど(と、いうのは、
いろいろ世の中に腹の立つものが多く、
そうしたものを考える際の軸となるものが欲しかった)、
いろいろ読んでいるうちに、自然と離れてゆき、
結局、多くの友人たち同様、
アルチュセールの構造主義や広松渉の物象化理論などに、
移って行った。
実はこの理論には、もう一つ問題があった。
結局のところ、こうした人間主義=ヒューマニズムは、
それ自体、キリスト教の中から生まれたすこぶる歴史的概念であり、
これは、確かに、ある意味では平等や人権、自由、民主主義に結びつく、
崇高な理想であるかのように見えながら、
その実際に果たしている機能を見れば、
植民地主義の正当化、つまり、
植民地地域の現地の人々は
いまだヒューマニズムも獲得していない低レベルの種族であり、
西欧により啓蒙され、指導されることによって
より民主的な人間にならなければならない、
と、いうイデオロギーをささえ、かつての植民地時代同様
今日のアメリカやヨーロッパによる各地域への武力介入を
正当化する役割を果たしているわけだ。
そんなこんなを勉強してゆくうちに、
簡単に「自己疎外」なんて言っている人のことを
馬鹿にしたり(もちろん、自分のことは棚に上げるさ。
弁証法だもの。)、民主主義の欺瞞性について
一席ぶったりもできるようになったが、
それでも、逆にあれから20年以上もたった今になって、
やはり、丸山真男や日高六郎や、宇井純や原田正純といった
人々の思想とともに、自分の思想的基礎となったものの
一つとして、若きマルクスの自己疎外論を大事にしたいのである。
もちろん、おいらもこの年になり、
あのころのまま、というわけにはいかない。
何らかの意味でバージョンアップした、おいらなりの「若きマルクスの思想」を
書いてみたいのである。
さて、ここまでは、前ふり。
本書で、中山先生は
「フマニステ」という言葉を使っているけれど、
要するに、ヒューマンのことである。
キリスト教の中で生まれ、
若きマルクスにより、近代社会において疎外された主体として
描かれた、
人類の進歩を支え、民主主義と人権と自由と平和を享受する
そんな人間のことである。その実、それはイデオロギーとして
多くの侵略戦争と殺戮と収奪と奴隷制を正当化し、
今日なお、収奪と不平等とを再生産する認識上の枠組みを
提供し続けている。
だから我々は、この「人間」の下に、
もう一つの層として、「人類」を描く必要がある。
単に西洋の人間概念に包摂されない
もっと歴史的にも文化的にも多様な「人類」である。
これは、要するに、ある意味では生物学的な
ホモ・サピエンスとして他の動物から区別される
一群の動物の群れ、という意味になるが、
だが、実際には、この動物の群れは
何らかの形で社会を形成し、
集団を再生産することで生存し続けている。
それは、簡単に文化とか経済とか歴史などと言えるようなものではないが、
しかしそれでも人類が生きているとき、何らかの、
我々の言葉でいえば
「社会関係」とでもしか言いようのない何ものかを
再生産し続けてしまっているのである。こうした存在のことを
中山先生は、AGフランクに従い
アントロポスと呼ぶ。
こうした多様な社会関係を
「未開」「野蛮」(それ以前には「自然」という言葉も
同じ悪いイメージで用いられていた)として
ある特定の「文化」「社会」「歴史」の在り方だけを
絶対なものとして押し付けてきたのが「人間」であった。
だが、今やその「人間」自身が、過去にない
とてつもない変容を遂げつつある。つまり
「ホモ・エコノミクス」による侵犯である。
おいらなりに考えるなら、
「ホモ・エコノミクス」は、本来、
経済学に特有の、理論的に純化するための
理論装置であったにすぎない。
確かに、「人間」は、利益を求めて行動する。
そうした人間の側面を抽象化して理論家することに
意味がないとは言えない。
また、(少なくとも入門ミクロ経済学の、
内容ではなく、序文を読む限りでは)経済学で追及される
「私的利益」とは、必ずしも金銭欲のことではない。
経済学では目的は問わない。
目的がたとえボランティアであっても、
そのボランティアという目的を効率的に遂行するため、
つまり目的に対して資源の最大限の有効活用を追求するための学問が
すなわち経済学なのである。
経済理論における「私利追求」は
けっして、ボランティアのような利他的行動を排除するものではない。
利他的行動であっても、その「他者を助けたい」という
自分自身の欲求を最大限満足させるための
資源の効率的活用を促すことこそ、ミクロ経済学の役割なのである、
と、言うわけだ。
しかし、中山先生が描き出す新自由主義者たちにとって、
少なくとも、フリードマンにとっては、
このような経済学の教科書の序章は
ゴミくずのような無意味な能書きに過ぎなかったようだ。
フリードマンにとっては、人間(フマニステ)とは、
つまり、ホモ・エコノミクスだったのである。
「いちば」ならぬ「しじょう」は
人間社会のある現象、ある側面などではなく
あるべき社会の姿そのものになってゆく。
ポランニーは、土地・人間・貨幣(資本)が交換の対象となる現代社会を
市場が社会を包摂する特殊な状況と認識していたが、
フリードマンにとっては土地や人間、貨幣が取引できない社会など
不完全な異様な社会だったようだ。
しかしながら、このような社会は
外部からの強制力という支えを抜きに維持は不可能であった。
新自由主義は、市場の機能を最大限にするべく、
国家の役割を最小限の領域に押し込めようとするが、
同時に最大限に強力なものにしようともする。
福祉や教育のための役割を最大限切り捨て、
あるいは、かかわる場合でも、
擬似的な市場を生み出すことで(例えば教育バウチャー制度)
国家の主体的な関与を否定する。
他方で、この市場社会という特異な社会の矛盾から噴き出る
アンチテーゼに対しては
最も抑圧的な役割を期待される。
このような市場と国家の役割が最大限実現されたのが
ピノチェトのチリであり、
これこそが新自由主義者たちのモデルケースになった、
と、言うのが、中山先生の位置づけである。
勿論、経済学の内部にも、
ただ、新自由主義だけがあったわけではない。
AGフランクや、JKガルブレイス、
Jロビンソン、Hミンスキー等々。
しかしフランクの一生は、
「経済学」が、その研究対象であるはずの
「私利私欲」と結びついた時、何が起こるかを
如実に示して見せた。
経済学(と、言うより、新自由主義)が、
ホモ・エコノミクスをして、フマニステばかりでなくアントロポストをも
包摂しようとしたのは、
何のことない、経済学のほうが
私利私欲に取り込まれてしまっていたからだ。
経済学において(ミクロ経済学教科書の序文を除くと)もっとも卑近な金銭欲だけが
私利として認められるのは、
結局のところ、経済学者自身の私利私欲の追及の結果に過ぎなかった、というのである。
新自由主義が推し進められる過程で、
様々なサンクションが与えられた。
それは、時限爆弾という過激な場合もあれば、
職を干される、という比較的穏便な場合もあり、
逆に、ノーベル賞というよくわからない報償による場合もある。
そして、マスメディアの存在が
学問を単なる学問以上のものにしてしまう。
ガルブレイスもフリードマンも、そのことをある意味では承知の上で、
あるいみでは無自覚に使い、使われてしまう。
学問は、象牙の塔を超え出て、「イズム」として流布されてゆく。
この過程で、実生活上においても
ホモ・サピエンスがフマニステを包摂してゆく。
もっとも、新自由主義は、その主導者であったはずの
フリードマンをも越えてゆく。
とりわけ、フリードマンが唯一の問題と呼んだ
貨幣は、結局フリードマン自身にとっても
問題になってしまった。
ひとたび貨幣が商品となってしまえば、もはや
市場の自由を遮ることはできない。
貨幣は国家を超え、
国家の抑圧体制を凌駕して、
国家と国家の利害関係の間隙を縫う形で
自己展開してゆく。
フリードマンは合理的期待形成学派とは違い
貨幣供給量についての管理を重視したが、
金利は市場で決められるべきものと考えていた、という。
だが、こんな片手落ちな話をどうして
学者さんたちが受け入れたのか、よくわからない。
いずれにせよ、フリードマンの想定を超えて
世界を股にかけて移動する貨幣に関する説明は
一方では、ストレインジの『カジノ資本主義』や
『マッド・マネー』を想起させる。
(なぜ、中山先生がストレインジの著書を取り上げなかったのか、
ちょっと気になる。)
[お休みの時間になったので、
気が向けば、
次回に続く。気が向けば。。。。ね。]










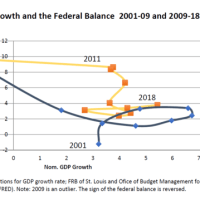
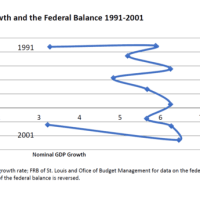
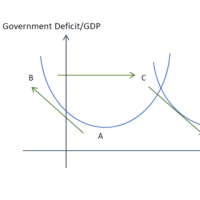
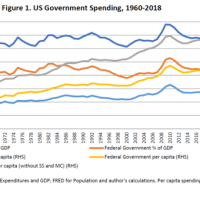
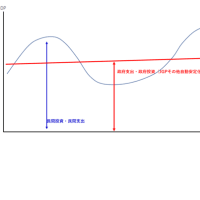
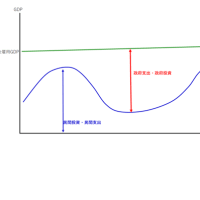
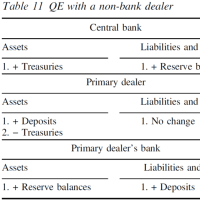
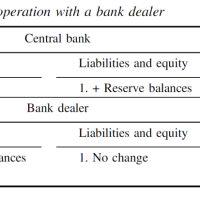
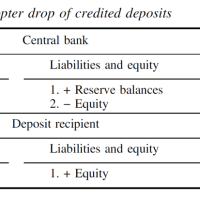
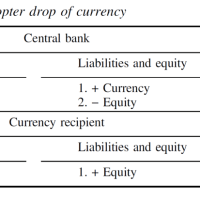
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます