レイは'Understanding Modern Money' において、冒頭、一般均衡理論を要約して、ハーンの言葉を引用し、一般均衡論体系においては貨幣が不要であることを示している。レイ自身は自分で行った要約に対して「ひびが入っている」として簡単に片づけているが、いったいMMTの立場から見て何がどう壊れているのか、十分な説明がなされているようには思えない。それはこれから本書を通じて説明します、ということなのだろうが、しかし明確に伝わっているかどうか振り返ると、何とも心もとない。これは'Modern Money Theory'のストックとフローを説明している個所と似た印象なのだが、なんか説明が中途半端なのである。ストックとフローの説明においては、事実上、フロー変数間の説明にしかなっていなかった。本書全体を通じてフローはストック変数の変化として記述されている(経済現象の記述はB/S上の残高の変化として行われ、P/Lの変化は「純資産」の増減として一括りに扱われている)のに、これでは冒頭にストックとフローの関係の説明を持ってきた意味がない。それと同じように、一般均衡論のどこがどうひび割れているのか、これはMMTにとって重要なテーマであるはずなのに、その内容が明確に記されていないのである。単に外生的貨幣供給論と内生的貨幣供給論の違い、というような個別的な話なのだろうか。そうではあるまい。
さて、MMTは主流派経済学を批判している。といっても「主流派経済学」という特定の主義主張を持ったグループがあるわけではない。現代の主要な経済学者がそれぞれの立場から議論をする際に、その議論をするうえで共通の土台となっているいくつかの前提がある。その前提を受け入れて行われている議論の全体を「主流派」と呼んでいるわけだ。必ずしも特定の主張や命題を論難しているわけではない。いわば「主流派経済学」という「ゲームのルール」を問題にしているのである。したがって主流派経済学の立場から唱えられる個別の主張についてはMMTも合意することができる場合もあるが、その根拠は全く異なったものになるだろう。
で、その主流派の前提がどんなものか。レイによれば、それが「一般均衡」論である。かつての「新古典派総合」の時代、主流派経済学の枠組みではまずはマクロ経済学があり、そしてマクロ経済政策によって完全雇用が達成されたら、そこから先はミクロ経済学(一般均衡論)の領域とされていた。この枠組みに基づく政策は60年代にはアラが見え始め70年代には完全に失敗とされるようになった。そして80年代になるとミクロ経済学に基盤を置いた保守派に対するケインズ派の抵抗として「マクロ経済学のミクロ的基礎付け」という形で論点が提起されることになる。これにより、事実上、マクロ経済学固有の枠組みは主流派経済学の中からは消えて、一般均衡論あるいは動学化された一般均衡論にとってかわられた、と言っていいように思う。ケインズの名前は、いまや古典派に対抗して政府中央銀行の介入を是とする立場総体のアイコンとなってしまい、J. M. ケインズという人間が何を語ったかについてはほとんど関心がもたれなくなった。
では、主流派経済学(ミクロ経済学)ではどのようなことが基礎的な前提とされているか。
個々の経済主体は一定の予算制約の下、市場を通じて自ら目的(通常は効用最大化・利益最大化)を実現するため主体的かつ合理的に意思決定する。こうした意思決定の総和がマクロ経済現象になっている。これが最も基礎にある前提と言っていいだろう。この主体的な目的の最適化を行う行為を集計した結果、本当に社会全体にとっても最適な条件が生まれるといえるのか、場合によってはすべての人が最低の選択をせざるを得なくなってしまうのか、様々な条件に依存するわけだが、それはここではどうでもいい。本エントリーの文脈で重要なのは「予算制約」というものの考え方である。
経済主体は予算(保有資源を売却・提供することにより得られる所得・収入)の範囲でしか、消費できない。保有資源が消費の上限になる。ただし「金融」というものもあり、これにより資源を外部から借りることで一時的には保有資源から得られる所得を超える消費ができる。また所得の一部を「貯蓄」することで将来に備えることもできる。「貯蓄」とは現在の所得と消費の差に過ぎない。現在の所得の一部を現在消費せずに銀行預金として持ち越したり、あるいは過去の借入の返済を現在の所得から行えば、いずれも「貯蓄」になる(しばしば無視されるけれど、他人に現在の所得を貸し与えるばかりでなく、過去に他人から借りた所得を返済することも、返済を受けた貸付人がそれをその期に消費するのでなければ、マクロ経済的には一種の「貯蓄」つまり現在の所得からの控除になる)。つまり金融により予算の制約を一時的に弱めることはできる。でもそれは生涯を通じて、あるいは遺産相続を認めるなら二代三代と世代を通じて、最終的にはプラスマイナスゼロになるはずだ。金融とは現在の所得(現在の貯蓄)と将来の所得(現在の借入・将来の貯蓄)の交換。ある時点で見れば、誰かの貯蓄は誰かの借入れになっている。この貯蓄と借入を一致させるのが金利。金利が高くなれば、貯蓄しようとする人は増えるし、借入をしようとする人は減る。こうしてちょうど貯蓄主体と借入主体が一致するように金利が定まる。
ある時点のすべての経済主体の「予算」を足し合わせると、その時点における世の中で利用可能な「実物資源」の総量と等しくなる。実際にはみんな所得はお金で受け取るわけだが、なぜお金を受け取るかと言えば、それで実物資源を購入できるからだ。だから実際にはお金で所得を受け取っているとはいっても、それは実物資源で受け取っていると単純化しても、第一次アプローチとしては問題ない。世の中の実物資源が限られている以上、経済主体の予算も限られている。
経済主体は、お金を媒介として市場で実物資源を取引することで、各商品の価格が決まるけれど、実際にそこで決められているのは実物資源間の相対交換比率だ。より需要が多いものの価格は上がり、需要の少ないものの価格は下がる。こうして世の中で必要とされるものの需要と供給がちょうど一致するように価格と所得(というのは、所得は、商品や労働力などの実物資源を販売することで得られるのだから)とが決定される。
つまり、この第一次アプローチの下では、お金というのは、理論的には存在しなくても構わない。お金は単に取引を滑らかにするための道具に過ぎない。人はお金で買える実物資源が必要だから、お金を稼ぐのであって、お金自体が必要なわけではない。世の中ではこうして各個人に自由に取引をさせることで、世の中で必要とされるものの価値は上がり、不要なものの価値は下がる。これがインセンティブとなって、必要なものがより多く生産され、不要なものの生産量は減る。だから誰も予算を越えて支出をすることはできないし、仮に一時的に借入をすることで予算を超えた支出ができても、それを返済できなければ、この借入をした経済主体は破綻をする。世の中で利用可能な「実物資源」が一定である以上、これは必然であり、絶対にはみ出ることがない。これがすべての主流派経済学の根底にある第一の共通了解事項だ。金融というのは、将来の所得を他の経済主体から借り入れることであって、そして返済できなければ破綻する。これは主流派経済学の枠組みにとって「前提」であって、現実の観察や理論的な検討の「結果」ではない。これが前提であることによって、世の中は市場における自由意志に任せることで効率的な資源配分が可能になる。ゴーイング・コンサーンの仮定がとられることもあるが、その場合でも、将来の債務残高が一定の額に収束しなければならない。したがって、個々の経済主体が予算制約をはみ出ることは、最終的にはできない。
予算制約をはみ出して消費することが可能になるとしたら、一つは詐欺行為が行われた場合だろう。それは経済学の対象外だとされるが、しかし誰かの詐欺的利益は他の誰かの詐欺による損害だろう。世の中全体としては、予算制約に従っていることになる。問題はそれが最適化されないことだろうが、それは本エントリーのテーマとは関係ない。
今一つは、消費を決定した時点に期待していた将来の所得の伸びが実現しなかった場合。経済主体は将来の所得を期待し、それに応じて借入をすることで、現在の消費を、現在の予算制約を上回る水準に決めることができる。しかし期待通りの所得が実現しなければ借入れた貯蓄を返済することはできず、そしてこの借入人に資源を貸し付けた(投資した)経済主体は、その回収できるはずだった資源を損失として断念するしかない。返済できなかった借入人は、それなりに社会的な懲罰を負うことになるだろうし、貸付側の損失も大きくなるだろう。ここでポイントは、確かに借入側は生涯の予算制約を超える支出をしたのだけれど、それは貸付側の損失によってあがなわれているのであって、社会全体で見れば依然として予算制約(社会全体で利用可能な実物資源の量)を越えてはいない、ということだ。t=0に借り入れによって資源を調達した主体が償還期日とされるt=xに期待通りの所得を得られなければ、この経済主体は破綻し、そして貸付人は損失を受けなければならない。これはこの主流派経済学理論の最も根底にある「ゲームのルール」であって、これが現実によって侵されるとしたら、このルールに基づくすべての命題は基礎を失うことになる。しかしそんなことはあり得ない。なんせこのルールの基礎にあるのは「現実に利用可能な実物資源は有限だ」という事実だからだ、と、いうわけだ。
もし一人でも予算の制約を受けずに消費支出できるものがいたら、それは体系全体の破綻を意味する。なぜなら、その予算の制約を受けずに消費支出できる経済主体は実際に無限に消費支出を続けるだろうし、その消費支出は誰かによって受け取られるだろうから、その支出を受け取り所得とする主体も予算の制約を受けないことになってしまうだろう。そうなればその経済主体もまた予算に制約されることなく消費支出をするようになるだろう。しかし現物資源が有限である以上、そのようなことは起こりえない。仮に無限の資源を保有する人がその資源を無制限に支出しようとすれば、その資源の価格は低下し続け、そして最終的には市場価値がゼロとなるだろう。かように予算制約に従わないで済む主体など、存在し得ないのである。
さて、これはあくまでも第一次アプローチだ。現実の世の中では誰かが「お金」を発行しているのであり、その人が「お金」を市場に適切に供給していれば、第一次アプローチで語られたとおりの状態になる。ところが「実際には」「お金」を供給量を決定しているのは中央銀行だ(「実際には」とカギカッコをつけたのは、これはあくまでも主流派経済学にとっての「実際」でありビジネスマンや実務家にとっての「実際」とは必ずしも一致しない)。主流派経済学によれば「実際に」お金の供給量を決定しているのは中央銀行なのだけれど、中央銀行はしばしばお金の供給量をうまくコントロールできないでいる。経済学にとって「価格」というのは、第一次アプローチで示した通り、まずは諸商品の交換比率、相対価格のことを言う。問題は諸商品間の交換比率なのであって、絶対的な価格水準はどうでもいいことだ。ところがそれはお金が適切に供給されており、絶対価格水準が安定している場合の話だ。もしお金が適切に供給されておらず、利用可能な資源供給の伸び率より早いペースで増えてしまったら、問題は相対価格比だけでは済まなくなる。お金の量が増えてしまえば異時点間で現物資源価格(現物資源とお金の交換比率)は変わってしまう。そして金利は、単に現在の消費をあきらめることの代償、実物リスク負担の代償としての実物報酬としてだけでなく、貨幣将来所得と貨幣現在所得の交換比率を補正する機能も担わされる。これが第二次アプローチと言っていいだろう。「お金」は、第一次アプローチにおける「欲望の二重一致」を回避するための便利な道具で、無視しても本質的には差し支えない、という地位から、マクロ経済政策論の正面に踊り出る。
この第二次アプローチの段階になるとお金の話は単純ではなくなってしまう。金融による将来所得と現在所得の交換は常に行われており、したがってお金の増え方がおかしければ、過去に行われた契約の名目金利はすべて不適切なものになってしまう。投資の実物収益率は予想外の変化をしてしまうだろう。さらには金利が下がりすぎ、すべての市場関係者が将来の金利上昇=資産価格低下を期待するようになると、金融資産には買い手がつかず、すべての人がお金だけを資産として保有しようとすることになる。したがって、第一次アプローチではお金自体を目的に集める人なんていなかったはずだが、第二次アプローチではだれもお金を手放したがらない「流動性のわな」が生じる可能性も出て来る(これとて最終的には何らかの実物資源を消費するために支出されるはずだが、当面は投資のため他人に譲渡されることはない)。いずれにしても中央銀行が適切なマネーストックのコントロールを怠れば、市場は第一次アプローチに示されたような適切な機能を果たせなくなってしまう可能性がある。あるいは何らかの理由で市場が膠着状態に陥った場合には、中央銀行が貨幣供給量を適切に調整することで、こうした膠着状態から脱することが可能かもしれない。この辺は、主流派内各派の論争事項である。しかしここで注目しておきたいのは、あくまでもお金を発行することができるのは、中央銀行だけだ、という前提である。これも「前提」であり、ゲームのルールである。実際の経済現象とは関係ない。
さて、第二次アプローチにおいても第一次アプローチと変わらないのは、最終的にすべての経済主体は実物経済資源の制約の下でしか行動できない、ということだ。これはお金の量が変動し、名目的な所得が変化するようになっても変わらない。市場は常に完全とは限らないし、情報は非対称的だし、他にもいろんな事情があるから一定の実物経済資源と技術水準のもとであっても生産量や雇用量は変化しうるし、政府が介入することによって雇用量を調整することも可能な場合もあるだろう。しかしそれにはおのずと現物資源という上限がある。政府は定義上、生産活動を行わないので、必要な資源は民間から借りてくることになる。この借入をどのようにして返済するか、というと、政府自身は固有の資源を持っていないわけだから、租税によって民間から徴収するしかない。政府の借入は将来の租税によって払い戻しされなければならない。これは「前提」から直接出てくる話であって、理論的帰結などではない。
一般均衡論からマクロ経済政策論に移っても、第一次アプローチによる前提に変化があるわけではない。すべての経済主体は、現在利用可能な実物資源の制約の下でしか選択はできない。個々の経済主体の予算制約については、金融により緩めることが可能だが、全体としてはそれは所定の資源制約の下で貯蓄と投資を一致させるということに過ぎない。この制約はいかなる経済主体であろうと逃れることはできず、政府もまた例外ではない。しかしながら政府には他の経済主体とは違う特別な性格がある。というのは、政府は中央銀行からお金を直接、裁量的に借入ることができるのである。民間銀行も中央銀行からお金を借りて、それを原資(本源的預金、ハイパワードマネー)として民間経済主体に融資を実行している(とされる)。しかし本源的なお金を供給するかしないかは、中央銀行の側の裁量である。ところが政府はそうとは限らない。政府は法律に基づき中央銀行に国債を購入させることで、極端に言えば無限にお金を発行することができる。その場合、政府は現在実物所得を民間から借入ても、将来実物所得から返済する必要はなくなる。ただし、この場合、それだけお金の量が増えてしまうから、それを相殺できるだけの中央銀行によるお金の回収が無ければ、制御不能なインフレーションに陥ることになる。なぜなら所定の時点で利用可能な実物資源の量は一定だからだ。もし中央銀行がインフレーションを回避しようとするなら最も手っ取り早い手段は金利を引き上げて過剰となったお金を回収することになるだろう。
要するにこれらは、議論の「前提」であって、何らかの理論的な結論ではない。すべての経済主体は現物資源の制約のもとで、何らかの最適化行動を行っている。すべての経済主体は現物資源の予算制約に従わなければならないが、金融市場を通じて現在所得と将来所得を交換することができる。それは政府も例外ではない。しかしもし将来所得が予想に反し、過去に借りた経済資源を返済できないとしたら、その経済主体は破綻し、そして貸付人は損失を被る。現物資源による予算制約を超えることは絶対にできない。ただし政府はこの点はやや例外で、お金を自ら発行することで破綻を免れることはできる。しかしそれはお金を中央銀行の意図に反して増やすことになる。そのため実物資源と貨幣の交換比率は貨幣に不利となり、インフレーションに陥る。それを回避するには、中央銀行は金利を引上げなくてはならない。ここには何の理論的考察もない。ただの「前提」である。しかし、すべての主流派経済理論はこの前提の上に構築されている。だから政府がお金を新たに発行して支出を賄うとしたら、インフレーションが「必ず」起こらなければならない。勿論、状況次第では、例えば「流動性のわな」に陥っている状態のもとであれば、一定期間は発行したお金がすべて民間経済主体に吸収されてしまい物価が上昇しない、ということもあり得るだろう。しかしそれはあくまでも一時的な効果に過ぎない。だから主流派経済学にとって、政府がお金を発行して支出をする、ということは必ずや歯止めの効かないインフレーションに陥ることを意味しなければならない。これはそうで「なければならない」のであって、例外は許されない。もしそうでないということがあるとしたら、それは経済理論のすべての前提に反することになってしまうからだ。「政府がお金を発行することによって赤字支出を続けても、それが原因でインフレになることはない」と主張することは、こうした主流派経済学のすべての土台を否定することなのであって、事実がどうあろうと絶対に受け入れられない話である。これは論争の余地がない。政府が無限に赤字支出を増やしていけば、必ずハイパーインフレーションに陥る、という主張は、こうした主流派経済学の「前提」を守っているのであって、何らかの意味のある命題を守っているわけではない。過去10年間、リフレ政策によってハイパワードマネーを増やし続けたが、インフレなど起こらなかったではないか。いったいいつからハイパーインフレーションが始まるのか?そんな事実など問題ではない。これは「前提」なのだ。結局、「インフレーションは非線形的に起きるのでいつ起きるかわからないし、起れば歯止めが効かない」という強弁は、これがただの前提に過ぎず、理論的に導かれた結論などではない、ということを何より雄弁に物語っている。一方において、多くの主流派は、リフレ派の主張を受け入れなかった。それは当然である。というのはハイパワードマネーが増えればインフレになる、というのは、前提でしかないのだから、いつそんなことが起こるか、論理的にわかりはしない。おそらく、都合のいいときには起こらず、そして都合が悪くなれば(たとえば「流動性の罠」がなくなれば)、突如として爆発するだろう。インフレは制御不能なのである。ともかく、いつかは起こる。それがいつかは分からない。なぜなら、前提に過ぎないから。起こってもらわなくっちゃあ困る。でもいつかは分からない。
ちょっと話がずれてしまうが、MMTと主流派の論争とされているものでかみ合っていないことの一つに、主流派側の「政府が無限に国債を発行して支出をしたらインフレになる」という批判に対して、MMT側が「何もハイパーインフレになるまで赤字支出をしなければいいではないか」とする反論というのがある。しかし主流派が言っているハイパーインフレーションというのはお金のストックと現在利用できる経済資源フロー(実物フローと、実物ストックから得られるサービス)の関係を指している。それに対してMMTが赤字支出と供給力、と言っているのは、あくまでも実物フローと実物フローの関係である。だから批判に対するMMT側の反論としては適切とは言えない。こういうずれたやり取りが起こっちゃう、という原因の一つが、まあ、例えばレイの本なんかにあるあの中途半端なストックとフローの説明なのではないか、と、そんな気もする。
さて、こうした主流派経済学の前提に対するMMTの前提とは何だろうか。これがつまりは「貨幣性生産経済」ということになるのだろう。いつも繰り返しているような話だから、適当にとどめておくが、まあ以下のような話である。
現代資本制経済の下、生産活動は利潤(より多くの明日の貨幣)を目標に組成される。「蓄積せよ蓄積せよ、それがモーゼで予言である」というわけだ。これはマルクスが古典派に対する皮肉として使った表現であるから、オリジナルとしてはむしろ古典派経済学とりわけリカードということになるのだろうが、それがマルクスによりG⇒G’=G+⊿gとして定式化され、後にマルクスの影響を強く受けたカレツキーやシュンペーター、さらにはマルクスを、価値論はじめ他の個所については拒絶していたケインズによって受け継がれることになる。MMT(CF、SFC)においては、この蓄積衝動は純資産の蓄積という形式を目指すとされる。一部のポストケインジアンが主張するのと異なり、MMTやSFCにとっては資本家が貨幣性資産、あるいは貨幣によって表象される資産(繰延された現物資産の価値も、それが将来貨幣価値を生むと期待されている限り、ここに含む)を求めるのは「将来の自分の欲求が不確実だから(将来、いつどのような実物資源を欲するようになるかわからないから)」というわけではない(それもあるだろうが、それに限らないし、中心的でもない)。なぜ貨幣利潤を求めての生産が絶えることなく継続されるか、それについてMMTやSFC、CTの文献から結論的な命題を見つけ出すことは難しいだろう。しかし一つだけ言えることがある。差し当たって貨幣利潤(より多くの儲け)を追求するためにスタートした生産は、その生産活動においてすでに負債を発行し、あるいは将来のキャッシュフローによってのみ購われる固定資産や棚卸資産を形成してしまったことにより、もはや生産活動をストップするわけにはいかないのである。その意味で、すべての経済主体はゴーイングコンサーンであり、そして純資産を獲得することによってのみ、経済活動を継続することができるのであり、そしてそのためには常に仕入れや雇用を継続し、生産活動を繰り返し、売上をたてなくてはならない。ところが現代の生産技術を前提とすれば、企業部門が十分に利益を上げるだけの売上を実現するための実物資産需要などありはしない。であれば金融資産を蓄積するしかない。そして誰かの収入は誰かの費用、誰かの債権は誰かの債務なのである。そしてさらに債権が債権であるのは、その債務者が債務内容を履行し続けることができる限りである。それはその債務の発行者が民間だろうと政府だろうと関係ない。債務者が民間だろうと政府だろうと、貨幣的生産経済主体は金融資産を蓄積せざるを得ないのだ。
つまりは民間経済主体が蓄積する金融資産・実物資産の多くは、実際には実物資源という担保を持っていない。多くの有形固定資産ですら、その実態は単に投資に際して行われた貨幣性支出の費用認識の繰り延べであり、そして将来の貨幣性収益期待が悪化すれば減損処理されざるを得ない。これらの金融債権の価値を担保しているのはただ将来の貨幣収益のみなのであり、それによって購入できる現物資源ではない。むしろ逆に、現物資源の方が貨幣収益の有無によって無価値とされ、あるいは何の有用性もないただの記号であっても、高価格で評価される。だから単に政府・中央銀行から発行された貨幣性資産の蓄積が増えたからと言って、それが直接、インフレーションを招くわけではない。一般均衡論の主張とは逆に、お金を含む貨幣性の債権債務関係の方が現物資源の利用・消費を決定している。したがって、政府が過去に行った赤字支出によって増えたお金を増税によって回収することは、一般均衡理論にとっては長期的な実物予算制約の枠内での経済活動を担保し、将来のハイパーインフレーションを避けるために必要不可欠なことになるのだけれど、貨幣性生産理論にとっては、経済主体がこれまで蓄積してきた貨幣性純資産を剥奪し、現在の生産の継続を阻害する行為に他ならないこととなる。
一般均衡論と異なり、貨幣性生産経済においては、企業は貨幣性純資産の蓄積を目標として生産活動を組織化する。一般均衡論を信じる立場からすれば、中央銀行がお金の供給量をいたずらに増やさない限り、あるいは金利が適切にコントロールされている限り、インフレは生じ得ない。あらゆる外生的ショックにより価格の変動は起こるだろうが、それはすべて相対価格比の変化である。逆に、政府による赤字支出は、それが中央銀行のハイパワードマネーの増発によって実行される限り、必ずインフレを引き起こす。これは議論の前提であって、結論ではない。貨幣性生産経済の枠組みでは、企業は貨幣性純資産を拡大しようとするため、中央銀行が政府の国債を引き受けたからと言って、それがインフレに直結するわけではない。
勿論、MMTとて、政府債務を含む金融資産の増加がインフレ要因になることはない、と言っているわけではない。とりわけ実物資源との関係は重要だ(一般均衡論の想定する実物資源制約は現在の経済システムの素描としては全く不適切なものだが、それを指摘することは実物経済資源の制約がないことを意味しているのではない)。ただし、この点について政府支出による貨幣性債権の増加ばかりを目の敵にしても意味がない。商取引自体は民間銀行の預金通貨でも手形でもでんさい、クレジットカード、バーコード決済、CPでも行われる。何も政府の発行する通貨だけが取引に使われているわけではない。そしてこれらの残高は景気が良くなれば民間経済活動の内部で――まさに「景気が良くなりインフレになった」という理由それ自体によって――増加するだろう。政府の発行する流通債務はインフレを引き起こすが、民間の発行する債務はインフレを引き起こすことがない、などと想定するのは全くばかげている。むしろ銀行預金通貨は貨幣性利益を求める企業の申し出に従って、その目論見書に記載されている貨幣性利益が見込みのあるものである限り、増やされるだろう。労賃が上昇した時、輸入原材料価格が上昇した時、企業がそうした原価上昇を確実に吸収できる水準の売上を見込む限り(そしてその場合には幾分なりとも製品販売価格の引上げが含まれるだろう)、銀行は融資を続け、拡大するだろう。中央銀行がこうした民間の活動を制限する能力は限られている。政府支出の拡大による需要増加もインフレ要因にはなり得るが、しかし製造業に関する限り、正常操業圏内に収まっている間は大きな物価上昇にはつながらないだろう。政府の活動のみをインフレの要因とすることは――一般均衡論の体系の前提ではあるが――全く不適切だろう。
むしろ問題は、政府債務に比べ、これら民間債務が非常に危なっかしいことであろう。これが資本制経済の矛盾なのだけれど、この危なっかしい資産の価値が今まさにどんどん危なっかしくなっているときにこそ、「今度こそこれまでと違う」「無限に増え続ける政府債務といった危険なものに比べ、民間債務ははるかに安全なのだ」と言わんばかりに(あるいは、実際にそう言いながら;格付け会社にそう言わせながら)、残高が増え続けてしまう。他方で、中央銀行は民間銀行の決済性の資金需要にはアコモデートせざるを得ない。勿論、アコモデートせず、破綻に任せる、という選択肢もないではないが、実を言えばそれこそまさに中央銀行の信頼を失わせることであろう。それぐらいなら、最初から金利の下支えなどやめて、中央銀行が民間債務に起因する破綻の責めを負わなければならなくなるようなアコモデートの必要性をなくしてしまう方がいい。
さて、レイは代表的な概説書で、一般均衡論にヒビが入っている、と非難した。しかし、実際にところ、一般均衡論に基礎を置く主流派経済学の問題は、論理的な整合性のなさ自体より、むしろ整合性ある部分の「前提」の方にある、と言った方がよさそうである。主流派経済学に従う人たちが、いくら事実に反しているといっても、かたくなに政府の赤字支出はインフレになる、と言い続けているのは、それが「前提」であって、議論の結論だからではないからであろう。そしていつからインフレになるのか、どのような条件でインフレになるのか語ることなく、ただ非線形に発生する、というのも、それが理論的に導き出された結論だからではなく、あらかじめ前提として決められていることに過ぎないからである。逆に言えば、主流派経済学のあらゆる命題は、こうした予算制約による実物資源とお金の結びつきを前提として成り立っているのであって、もし世の中に一人でもこの前提に反して行動できる主体の存在を認めるなら、すべてが崩壊せざるを得ない。だから主流派経済学のモデルをそのままに、ただ貨幣供給理論だけをMMTに置き換える、などということは不可能なはずである。この意味でMMTは主流派経済学の「パラダイム」に対抗しているわけで、だからレイは概説書のの冒頭でわざわざ一般均衡論を批判したのであろう。だがその批判はいかにも不徹底だったと評価せざるを得ない。要約して「ヒビが割れている」と言っただけでは全く十分ではなく、それがMMT全体の理解を中途半端なものにしてしまうことに繋がっている面があることは否めないだろう。
さて、MMTは主流派経済学を批判している。といっても「主流派経済学」という特定の主義主張を持ったグループがあるわけではない。現代の主要な経済学者がそれぞれの立場から議論をする際に、その議論をするうえで共通の土台となっているいくつかの前提がある。その前提を受け入れて行われている議論の全体を「主流派」と呼んでいるわけだ。必ずしも特定の主張や命題を論難しているわけではない。いわば「主流派経済学」という「ゲームのルール」を問題にしているのである。したがって主流派経済学の立場から唱えられる個別の主張についてはMMTも合意することができる場合もあるが、その根拠は全く異なったものになるだろう。
で、その主流派の前提がどんなものか。レイによれば、それが「一般均衡」論である。かつての「新古典派総合」の時代、主流派経済学の枠組みではまずはマクロ経済学があり、そしてマクロ経済政策によって完全雇用が達成されたら、そこから先はミクロ経済学(一般均衡論)の領域とされていた。この枠組みに基づく政策は60年代にはアラが見え始め70年代には完全に失敗とされるようになった。そして80年代になるとミクロ経済学に基盤を置いた保守派に対するケインズ派の抵抗として「マクロ経済学のミクロ的基礎付け」という形で論点が提起されることになる。これにより、事実上、マクロ経済学固有の枠組みは主流派経済学の中からは消えて、一般均衡論あるいは動学化された一般均衡論にとってかわられた、と言っていいように思う。ケインズの名前は、いまや古典派に対抗して政府中央銀行の介入を是とする立場総体のアイコンとなってしまい、J. M. ケインズという人間が何を語ったかについてはほとんど関心がもたれなくなった。
では、主流派経済学(ミクロ経済学)ではどのようなことが基礎的な前提とされているか。
個々の経済主体は一定の予算制約の下、市場を通じて自ら目的(通常は効用最大化・利益最大化)を実現するため主体的かつ合理的に意思決定する。こうした意思決定の総和がマクロ経済現象になっている。これが最も基礎にある前提と言っていいだろう。この主体的な目的の最適化を行う行為を集計した結果、本当に社会全体にとっても最適な条件が生まれるといえるのか、場合によってはすべての人が最低の選択をせざるを得なくなってしまうのか、様々な条件に依存するわけだが、それはここではどうでもいい。本エントリーの文脈で重要なのは「予算制約」というものの考え方である。
経済主体は予算(保有資源を売却・提供することにより得られる所得・収入)の範囲でしか、消費できない。保有資源が消費の上限になる。ただし「金融」というものもあり、これにより資源を外部から借りることで一時的には保有資源から得られる所得を超える消費ができる。また所得の一部を「貯蓄」することで将来に備えることもできる。「貯蓄」とは現在の所得と消費の差に過ぎない。現在の所得の一部を現在消費せずに銀行預金として持ち越したり、あるいは過去の借入の返済を現在の所得から行えば、いずれも「貯蓄」になる(しばしば無視されるけれど、他人に現在の所得を貸し与えるばかりでなく、過去に他人から借りた所得を返済することも、返済を受けた貸付人がそれをその期に消費するのでなければ、マクロ経済的には一種の「貯蓄」つまり現在の所得からの控除になる)。つまり金融により予算の制約を一時的に弱めることはできる。でもそれは生涯を通じて、あるいは遺産相続を認めるなら二代三代と世代を通じて、最終的にはプラスマイナスゼロになるはずだ。金融とは現在の所得(現在の貯蓄)と将来の所得(現在の借入・将来の貯蓄)の交換。ある時点で見れば、誰かの貯蓄は誰かの借入れになっている。この貯蓄と借入を一致させるのが金利。金利が高くなれば、貯蓄しようとする人は増えるし、借入をしようとする人は減る。こうしてちょうど貯蓄主体と借入主体が一致するように金利が定まる。
ある時点のすべての経済主体の「予算」を足し合わせると、その時点における世の中で利用可能な「実物資源」の総量と等しくなる。実際にはみんな所得はお金で受け取るわけだが、なぜお金を受け取るかと言えば、それで実物資源を購入できるからだ。だから実際にはお金で所得を受け取っているとはいっても、それは実物資源で受け取っていると単純化しても、第一次アプローチとしては問題ない。世の中の実物資源が限られている以上、経済主体の予算も限られている。
経済主体は、お金を媒介として市場で実物資源を取引することで、各商品の価格が決まるけれど、実際にそこで決められているのは実物資源間の相対交換比率だ。より需要が多いものの価格は上がり、需要の少ないものの価格は下がる。こうして世の中で必要とされるものの需要と供給がちょうど一致するように価格と所得(というのは、所得は、商品や労働力などの実物資源を販売することで得られるのだから)とが決定される。
つまり、この第一次アプローチの下では、お金というのは、理論的には存在しなくても構わない。お金は単に取引を滑らかにするための道具に過ぎない。人はお金で買える実物資源が必要だから、お金を稼ぐのであって、お金自体が必要なわけではない。世の中ではこうして各個人に自由に取引をさせることで、世の中で必要とされるものの価値は上がり、不要なものの価値は下がる。これがインセンティブとなって、必要なものがより多く生産され、不要なものの生産量は減る。だから誰も予算を越えて支出をすることはできないし、仮に一時的に借入をすることで予算を超えた支出ができても、それを返済できなければ、この借入をした経済主体は破綻をする。世の中で利用可能な「実物資源」が一定である以上、これは必然であり、絶対にはみ出ることがない。これがすべての主流派経済学の根底にある第一の共通了解事項だ。金融というのは、将来の所得を他の経済主体から借り入れることであって、そして返済できなければ破綻する。これは主流派経済学の枠組みにとって「前提」であって、現実の観察や理論的な検討の「結果」ではない。これが前提であることによって、世の中は市場における自由意志に任せることで効率的な資源配分が可能になる。ゴーイング・コンサーンの仮定がとられることもあるが、その場合でも、将来の債務残高が一定の額に収束しなければならない。したがって、個々の経済主体が予算制約をはみ出ることは、最終的にはできない。
予算制約をはみ出して消費することが可能になるとしたら、一つは詐欺行為が行われた場合だろう。それは経済学の対象外だとされるが、しかし誰かの詐欺的利益は他の誰かの詐欺による損害だろう。世の中全体としては、予算制約に従っていることになる。問題はそれが最適化されないことだろうが、それは本エントリーのテーマとは関係ない。
今一つは、消費を決定した時点に期待していた将来の所得の伸びが実現しなかった場合。経済主体は将来の所得を期待し、それに応じて借入をすることで、現在の消費を、現在の予算制約を上回る水準に決めることができる。しかし期待通りの所得が実現しなければ借入れた貯蓄を返済することはできず、そしてこの借入人に資源を貸し付けた(投資した)経済主体は、その回収できるはずだった資源を損失として断念するしかない。返済できなかった借入人は、それなりに社会的な懲罰を負うことになるだろうし、貸付側の損失も大きくなるだろう。ここでポイントは、確かに借入側は生涯の予算制約を超える支出をしたのだけれど、それは貸付側の損失によってあがなわれているのであって、社会全体で見れば依然として予算制約(社会全体で利用可能な実物資源の量)を越えてはいない、ということだ。t=0に借り入れによって資源を調達した主体が償還期日とされるt=xに期待通りの所得を得られなければ、この経済主体は破綻し、そして貸付人は損失を受けなければならない。これはこの主流派経済学理論の最も根底にある「ゲームのルール」であって、これが現実によって侵されるとしたら、このルールに基づくすべての命題は基礎を失うことになる。しかしそんなことはあり得ない。なんせこのルールの基礎にあるのは「現実に利用可能な実物資源は有限だ」という事実だからだ、と、いうわけだ。
もし一人でも予算の制約を受けずに消費支出できるものがいたら、それは体系全体の破綻を意味する。なぜなら、その予算の制約を受けずに消費支出できる経済主体は実際に無限に消費支出を続けるだろうし、その消費支出は誰かによって受け取られるだろうから、その支出を受け取り所得とする主体も予算の制約を受けないことになってしまうだろう。そうなればその経済主体もまた予算に制約されることなく消費支出をするようになるだろう。しかし現物資源が有限である以上、そのようなことは起こりえない。仮に無限の資源を保有する人がその資源を無制限に支出しようとすれば、その資源の価格は低下し続け、そして最終的には市場価値がゼロとなるだろう。かように予算制約に従わないで済む主体など、存在し得ないのである。
さて、これはあくまでも第一次アプローチだ。現実の世の中では誰かが「お金」を発行しているのであり、その人が「お金」を市場に適切に供給していれば、第一次アプローチで語られたとおりの状態になる。ところが「実際には」「お金」を供給量を決定しているのは中央銀行だ(「実際には」とカギカッコをつけたのは、これはあくまでも主流派経済学にとっての「実際」でありビジネスマンや実務家にとっての「実際」とは必ずしも一致しない)。主流派経済学によれば「実際に」お金の供給量を決定しているのは中央銀行なのだけれど、中央銀行はしばしばお金の供給量をうまくコントロールできないでいる。経済学にとって「価格」というのは、第一次アプローチで示した通り、まずは諸商品の交換比率、相対価格のことを言う。問題は諸商品間の交換比率なのであって、絶対的な価格水準はどうでもいいことだ。ところがそれはお金が適切に供給されており、絶対価格水準が安定している場合の話だ。もしお金が適切に供給されておらず、利用可能な資源供給の伸び率より早いペースで増えてしまったら、問題は相対価格比だけでは済まなくなる。お金の量が増えてしまえば異時点間で現物資源価格(現物資源とお金の交換比率)は変わってしまう。そして金利は、単に現在の消費をあきらめることの代償、実物リスク負担の代償としての実物報酬としてだけでなく、貨幣将来所得と貨幣現在所得の交換比率を補正する機能も担わされる。これが第二次アプローチと言っていいだろう。「お金」は、第一次アプローチにおける「欲望の二重一致」を回避するための便利な道具で、無視しても本質的には差し支えない、という地位から、マクロ経済政策論の正面に踊り出る。
この第二次アプローチの段階になるとお金の話は単純ではなくなってしまう。金融による将来所得と現在所得の交換は常に行われており、したがってお金の増え方がおかしければ、過去に行われた契約の名目金利はすべて不適切なものになってしまう。投資の実物収益率は予想外の変化をしてしまうだろう。さらには金利が下がりすぎ、すべての市場関係者が将来の金利上昇=資産価格低下を期待するようになると、金融資産には買い手がつかず、すべての人がお金だけを資産として保有しようとすることになる。したがって、第一次アプローチではお金自体を目的に集める人なんていなかったはずだが、第二次アプローチではだれもお金を手放したがらない「流動性のわな」が生じる可能性も出て来る(これとて最終的には何らかの実物資源を消費するために支出されるはずだが、当面は投資のため他人に譲渡されることはない)。いずれにしても中央銀行が適切なマネーストックのコントロールを怠れば、市場は第一次アプローチに示されたような適切な機能を果たせなくなってしまう可能性がある。あるいは何らかの理由で市場が膠着状態に陥った場合には、中央銀行が貨幣供給量を適切に調整することで、こうした膠着状態から脱することが可能かもしれない。この辺は、主流派内各派の論争事項である。しかしここで注目しておきたいのは、あくまでもお金を発行することができるのは、中央銀行だけだ、という前提である。これも「前提」であり、ゲームのルールである。実際の経済現象とは関係ない。
さて、第二次アプローチにおいても第一次アプローチと変わらないのは、最終的にすべての経済主体は実物経済資源の制約の下でしか行動できない、ということだ。これはお金の量が変動し、名目的な所得が変化するようになっても変わらない。市場は常に完全とは限らないし、情報は非対称的だし、他にもいろんな事情があるから一定の実物経済資源と技術水準のもとであっても生産量や雇用量は変化しうるし、政府が介入することによって雇用量を調整することも可能な場合もあるだろう。しかしそれにはおのずと現物資源という上限がある。政府は定義上、生産活動を行わないので、必要な資源は民間から借りてくることになる。この借入をどのようにして返済するか、というと、政府自身は固有の資源を持っていないわけだから、租税によって民間から徴収するしかない。政府の借入は将来の租税によって払い戻しされなければならない。これは「前提」から直接出てくる話であって、理論的帰結などではない。
一般均衡論からマクロ経済政策論に移っても、第一次アプローチによる前提に変化があるわけではない。すべての経済主体は、現在利用可能な実物資源の制約の下でしか選択はできない。個々の経済主体の予算制約については、金融により緩めることが可能だが、全体としてはそれは所定の資源制約の下で貯蓄と投資を一致させるということに過ぎない。この制約はいかなる経済主体であろうと逃れることはできず、政府もまた例外ではない。しかしながら政府には他の経済主体とは違う特別な性格がある。というのは、政府は中央銀行からお金を直接、裁量的に借入ることができるのである。民間銀行も中央銀行からお金を借りて、それを原資(本源的預金、ハイパワードマネー)として民間経済主体に融資を実行している(とされる)。しかし本源的なお金を供給するかしないかは、中央銀行の側の裁量である。ところが政府はそうとは限らない。政府は法律に基づき中央銀行に国債を購入させることで、極端に言えば無限にお金を発行することができる。その場合、政府は現在実物所得を民間から借入ても、将来実物所得から返済する必要はなくなる。ただし、この場合、それだけお金の量が増えてしまうから、それを相殺できるだけの中央銀行によるお金の回収が無ければ、制御不能なインフレーションに陥ることになる。なぜなら所定の時点で利用可能な実物資源の量は一定だからだ。もし中央銀行がインフレーションを回避しようとするなら最も手っ取り早い手段は金利を引き上げて過剰となったお金を回収することになるだろう。
要するにこれらは、議論の「前提」であって、何らかの理論的な結論ではない。すべての経済主体は現物資源の制約のもとで、何らかの最適化行動を行っている。すべての経済主体は現物資源の予算制約に従わなければならないが、金融市場を通じて現在所得と将来所得を交換することができる。それは政府も例外ではない。しかしもし将来所得が予想に反し、過去に借りた経済資源を返済できないとしたら、その経済主体は破綻し、そして貸付人は損失を被る。現物資源による予算制約を超えることは絶対にできない。ただし政府はこの点はやや例外で、お金を自ら発行することで破綻を免れることはできる。しかしそれはお金を中央銀行の意図に反して増やすことになる。そのため実物資源と貨幣の交換比率は貨幣に不利となり、インフレーションに陥る。それを回避するには、中央銀行は金利を引上げなくてはならない。ここには何の理論的考察もない。ただの「前提」である。しかし、すべての主流派経済理論はこの前提の上に構築されている。だから政府がお金を新たに発行して支出を賄うとしたら、インフレーションが「必ず」起こらなければならない。勿論、状況次第では、例えば「流動性のわな」に陥っている状態のもとであれば、一定期間は発行したお金がすべて民間経済主体に吸収されてしまい物価が上昇しない、ということもあり得るだろう。しかしそれはあくまでも一時的な効果に過ぎない。だから主流派経済学にとって、政府がお金を発行して支出をする、ということは必ずや歯止めの効かないインフレーションに陥ることを意味しなければならない。これはそうで「なければならない」のであって、例外は許されない。もしそうでないということがあるとしたら、それは経済理論のすべての前提に反することになってしまうからだ。「政府がお金を発行することによって赤字支出を続けても、それが原因でインフレになることはない」と主張することは、こうした主流派経済学のすべての土台を否定することなのであって、事実がどうあろうと絶対に受け入れられない話である。これは論争の余地がない。政府が無限に赤字支出を増やしていけば、必ずハイパーインフレーションに陥る、という主張は、こうした主流派経済学の「前提」を守っているのであって、何らかの意味のある命題を守っているわけではない。過去10年間、リフレ政策によってハイパワードマネーを増やし続けたが、インフレなど起こらなかったではないか。いったいいつからハイパーインフレーションが始まるのか?そんな事実など問題ではない。これは「前提」なのだ。結局、「インフレーションは非線形的に起きるのでいつ起きるかわからないし、起れば歯止めが効かない」という強弁は、これがただの前提に過ぎず、理論的に導かれた結論などではない、ということを何より雄弁に物語っている。一方において、多くの主流派は、リフレ派の主張を受け入れなかった。それは当然である。というのはハイパワードマネーが増えればインフレになる、というのは、前提でしかないのだから、いつそんなことが起こるか、論理的にわかりはしない。おそらく、都合のいいときには起こらず、そして都合が悪くなれば(たとえば「流動性の罠」がなくなれば)、突如として爆発するだろう。インフレは制御不能なのである。ともかく、いつかは起こる。それがいつかは分からない。なぜなら、前提に過ぎないから。起こってもらわなくっちゃあ困る。でもいつかは分からない。
ちょっと話がずれてしまうが、MMTと主流派の論争とされているものでかみ合っていないことの一つに、主流派側の「政府が無限に国債を発行して支出をしたらインフレになる」という批判に対して、MMT側が「何もハイパーインフレになるまで赤字支出をしなければいいではないか」とする反論というのがある。しかし主流派が言っているハイパーインフレーションというのはお金のストックと現在利用できる経済資源フロー(実物フローと、実物ストックから得られるサービス)の関係を指している。それに対してMMTが赤字支出と供給力、と言っているのは、あくまでも実物フローと実物フローの関係である。だから批判に対するMMT側の反論としては適切とは言えない。こういうずれたやり取りが起こっちゃう、という原因の一つが、まあ、例えばレイの本なんかにあるあの中途半端なストックとフローの説明なのではないか、と、そんな気もする。
さて、こうした主流派経済学の前提に対するMMTの前提とは何だろうか。これがつまりは「貨幣性生産経済」ということになるのだろう。いつも繰り返しているような話だから、適当にとどめておくが、まあ以下のような話である。
現代資本制経済の下、生産活動は利潤(より多くの明日の貨幣)を目標に組成される。「蓄積せよ蓄積せよ、それがモーゼで予言である」というわけだ。これはマルクスが古典派に対する皮肉として使った表現であるから、オリジナルとしてはむしろ古典派経済学とりわけリカードということになるのだろうが、それがマルクスによりG⇒G’=G+⊿gとして定式化され、後にマルクスの影響を強く受けたカレツキーやシュンペーター、さらにはマルクスを、価値論はじめ他の個所については拒絶していたケインズによって受け継がれることになる。MMT(CF、SFC)においては、この蓄積衝動は純資産の蓄積という形式を目指すとされる。一部のポストケインジアンが主張するのと異なり、MMTやSFCにとっては資本家が貨幣性資産、あるいは貨幣によって表象される資産(繰延された現物資産の価値も、それが将来貨幣価値を生むと期待されている限り、ここに含む)を求めるのは「将来の自分の欲求が不確実だから(将来、いつどのような実物資源を欲するようになるかわからないから)」というわけではない(それもあるだろうが、それに限らないし、中心的でもない)。なぜ貨幣利潤を求めての生産が絶えることなく継続されるか、それについてMMTやSFC、CTの文献から結論的な命題を見つけ出すことは難しいだろう。しかし一つだけ言えることがある。差し当たって貨幣利潤(より多くの儲け)を追求するためにスタートした生産は、その生産活動においてすでに負債を発行し、あるいは将来のキャッシュフローによってのみ購われる固定資産や棚卸資産を形成してしまったことにより、もはや生産活動をストップするわけにはいかないのである。その意味で、すべての経済主体はゴーイングコンサーンであり、そして純資産を獲得することによってのみ、経済活動を継続することができるのであり、そしてそのためには常に仕入れや雇用を継続し、生産活動を繰り返し、売上をたてなくてはならない。ところが現代の生産技術を前提とすれば、企業部門が十分に利益を上げるだけの売上を実現するための実物資産需要などありはしない。であれば金融資産を蓄積するしかない。そして誰かの収入は誰かの費用、誰かの債権は誰かの債務なのである。そしてさらに債権が債権であるのは、その債務者が債務内容を履行し続けることができる限りである。それはその債務の発行者が民間だろうと政府だろうと関係ない。債務者が民間だろうと政府だろうと、貨幣的生産経済主体は金融資産を蓄積せざるを得ないのだ。
つまりは民間経済主体が蓄積する金融資産・実物資産の多くは、実際には実物資源という担保を持っていない。多くの有形固定資産ですら、その実態は単に投資に際して行われた貨幣性支出の費用認識の繰り延べであり、そして将来の貨幣性収益期待が悪化すれば減損処理されざるを得ない。これらの金融債権の価値を担保しているのはただ将来の貨幣収益のみなのであり、それによって購入できる現物資源ではない。むしろ逆に、現物資源の方が貨幣収益の有無によって無価値とされ、あるいは何の有用性もないただの記号であっても、高価格で評価される。だから単に政府・中央銀行から発行された貨幣性資産の蓄積が増えたからと言って、それが直接、インフレーションを招くわけではない。一般均衡論の主張とは逆に、お金を含む貨幣性の債権債務関係の方が現物資源の利用・消費を決定している。したがって、政府が過去に行った赤字支出によって増えたお金を増税によって回収することは、一般均衡理論にとっては長期的な実物予算制約の枠内での経済活動を担保し、将来のハイパーインフレーションを避けるために必要不可欠なことになるのだけれど、貨幣性生産理論にとっては、経済主体がこれまで蓄積してきた貨幣性純資産を剥奪し、現在の生産の継続を阻害する行為に他ならないこととなる。
一般均衡論と異なり、貨幣性生産経済においては、企業は貨幣性純資産の蓄積を目標として生産活動を組織化する。一般均衡論を信じる立場からすれば、中央銀行がお金の供給量をいたずらに増やさない限り、あるいは金利が適切にコントロールされている限り、インフレは生じ得ない。あらゆる外生的ショックにより価格の変動は起こるだろうが、それはすべて相対価格比の変化である。逆に、政府による赤字支出は、それが中央銀行のハイパワードマネーの増発によって実行される限り、必ずインフレを引き起こす。これは議論の前提であって、結論ではない。貨幣性生産経済の枠組みでは、企業は貨幣性純資産を拡大しようとするため、中央銀行が政府の国債を引き受けたからと言って、それがインフレに直結するわけではない。
勿論、MMTとて、政府債務を含む金融資産の増加がインフレ要因になることはない、と言っているわけではない。とりわけ実物資源との関係は重要だ(一般均衡論の想定する実物資源制約は現在の経済システムの素描としては全く不適切なものだが、それを指摘することは実物経済資源の制約がないことを意味しているのではない)。ただし、この点について政府支出による貨幣性債権の増加ばかりを目の敵にしても意味がない。商取引自体は民間銀行の預金通貨でも手形でもでんさい、クレジットカード、バーコード決済、CPでも行われる。何も政府の発行する通貨だけが取引に使われているわけではない。そしてこれらの残高は景気が良くなれば民間経済活動の内部で――まさに「景気が良くなりインフレになった」という理由それ自体によって――増加するだろう。政府の発行する流通債務はインフレを引き起こすが、民間の発行する債務はインフレを引き起こすことがない、などと想定するのは全くばかげている。むしろ銀行預金通貨は貨幣性利益を求める企業の申し出に従って、その目論見書に記載されている貨幣性利益が見込みのあるものである限り、増やされるだろう。労賃が上昇した時、輸入原材料価格が上昇した時、企業がそうした原価上昇を確実に吸収できる水準の売上を見込む限り(そしてその場合には幾分なりとも製品販売価格の引上げが含まれるだろう)、銀行は融資を続け、拡大するだろう。中央銀行がこうした民間の活動を制限する能力は限られている。政府支出の拡大による需要増加もインフレ要因にはなり得るが、しかし製造業に関する限り、正常操業圏内に収まっている間は大きな物価上昇にはつながらないだろう。政府の活動のみをインフレの要因とすることは――一般均衡論の体系の前提ではあるが――全く不適切だろう。
むしろ問題は、政府債務に比べ、これら民間債務が非常に危なっかしいことであろう。これが資本制経済の矛盾なのだけれど、この危なっかしい資産の価値が今まさにどんどん危なっかしくなっているときにこそ、「今度こそこれまでと違う」「無限に増え続ける政府債務といった危険なものに比べ、民間債務ははるかに安全なのだ」と言わんばかりに(あるいは、実際にそう言いながら;格付け会社にそう言わせながら)、残高が増え続けてしまう。他方で、中央銀行は民間銀行の決済性の資金需要にはアコモデートせざるを得ない。勿論、アコモデートせず、破綻に任せる、という選択肢もないではないが、実を言えばそれこそまさに中央銀行の信頼を失わせることであろう。それぐらいなら、最初から金利の下支えなどやめて、中央銀行が民間債務に起因する破綻の責めを負わなければならなくなるようなアコモデートの必要性をなくしてしまう方がいい。
さて、レイは代表的な概説書で、一般均衡論にヒビが入っている、と非難した。しかし、実際にところ、一般均衡論に基礎を置く主流派経済学の問題は、論理的な整合性のなさ自体より、むしろ整合性ある部分の「前提」の方にある、と言った方がよさそうである。主流派経済学に従う人たちが、いくら事実に反しているといっても、かたくなに政府の赤字支出はインフレになる、と言い続けているのは、それが「前提」であって、議論の結論だからではないからであろう。そしていつからインフレになるのか、どのような条件でインフレになるのか語ることなく、ただ非線形に発生する、というのも、それが理論的に導き出された結論だからではなく、あらかじめ前提として決められていることに過ぎないからである。逆に言えば、主流派経済学のあらゆる命題は、こうした予算制約による実物資源とお金の結びつきを前提として成り立っているのであって、もし世の中に一人でもこの前提に反して行動できる主体の存在を認めるなら、すべてが崩壊せざるを得ない。だから主流派経済学のモデルをそのままに、ただ貨幣供給理論だけをMMTに置き換える、などということは不可能なはずである。この意味でMMTは主流派経済学の「パラダイム」に対抗しているわけで、だからレイは概説書のの冒頭でわざわざ一般均衡論を批判したのであろう。だがその批判はいかにも不徹底だったと評価せざるを得ない。要約して「ヒビが割れている」と言っただけでは全く十分ではなく、それがMMT全体の理解を中途半端なものにしてしまうことに繋がっている面があることは否めないだろう。










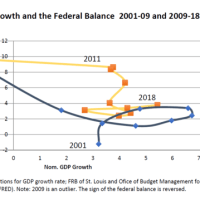
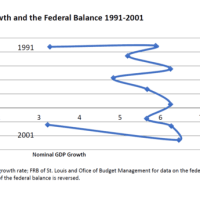
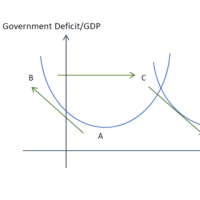
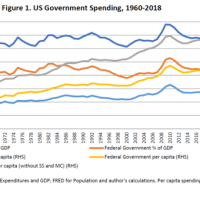
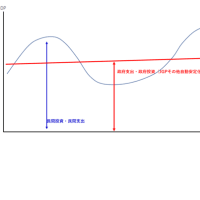
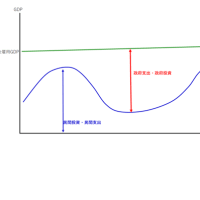
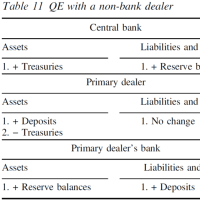
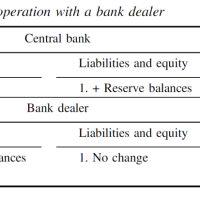
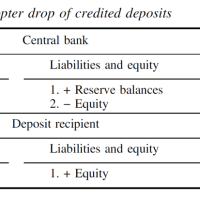
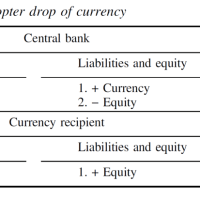
主流派経済学の前提を否定していることをMMT支持者が理解していないことで両者の議論がかみ合わないままでいると理解しました。
>一般均衡論の主張とは逆に、お金を含む貨幣性の債権債務関係の方が現物資源の利用・消費を決定している。
要点はここでしょうか。
主流派経済学では現物資源が貨幣を制約すると考えているのに対して現実にはお金が現物資源を制約することがあると。
利用されない現物資源は現物資源とみなされないが、貨幣を増やすことで現物資源とみなされるようになる可能性がある。
貨幣を減らすことでごみとみなされるようになる可能性もある。
この現物資源の中には人材も含まれていることを考えると恐ろしい話ですね。
ご指摘の点、究極的にはそもそも特定集団(この場合だと企業)が純金融資産の蓄積それ自体を純粋に目的にするのかどうかにかかっているように見えるんですよね。
プレーンな一般均衡論では、確かにそれはあり得ないと処理する(純金融資産の蓄積は、将来の実物資源獲得によってのみ正当化されるとする)んですが、最近のHagedorn Modelのように、貨幣や貨幣性資産(国債を含む)を効用関数に入れることで、含意が変わるという主張もある。
ただ、そうした改変は非常にad hocではないか、という批判は十分ありえると思います。