ランディ・レイがくだんの書物で
MMTはパラダイムの転換を促しているのだ、みたいなことを
書いてしまったせいで、
ひところMMTをパラダイムに引っ掛ける話が話題になってた。
パラダイムという言葉自体はトマス・クーンによって科学史上に
持ち込まれた概念で、この分野については
かなり難しい議論があって、おいらなんかが下手に触ると
火傷しておしまいなので、この原義についてあれこれ言うのは
やめておきたい。
と、そう思うんだったらやめときゃいいんだけれど、
レイがねえ、ああ書いちゃったからねえ、、、、、(´・ω・`)
ただ、レイがくだんの書物でああ書いているからといって
おいら自身に全く何の思い入れもなければ
「また変なこと書いてるな」とスルーすればいいわけだが、
おいら自身も、ちょっとだけ、こだわりがあるので
ちょっとだけ、考え方に触れておきたいのである。繰り返すけど、
科学史の知識なんかないからね。。。。
おいらが大学に入学して最初に「へえこんなんがあるんだ」と
感心させられた言葉の一つが「パラダイム」である。
ちょうど「現代思想ブーム」も終盤に差し掛かるころで、
フーコだのアルチュセールだの、、、、の「入門書」(別冊宝島、とか)を
一生懸命読み漁っていたころだ。まあ、あんまり理解できた覚えはないし、
ついでに言えば、だいたい内容は忘れたが。
まあフーコの「エピステーメ」とか
吉本隆明の「幻想」とか、その辺と「パラダイム」という概念は
似ている、というか、あんまり区別もつかなかった。今読めば
ちょっとは違いが判るだろうかゴールドブレンド。
このパラダイムであるが80年代半ばの
いわゆる「パラダイム再論」の文脈では、
もはやもともとの議論が科学史にかかわるものだった、なんて話は
すでにすっ飛んでいて、むしろ学知一般の分野に移っていて、
それはまあいいんだけれど、
結局、新カント派的な相対主義と同じじゃないか、というような批判もあり、
でもだとすると、
「パラダイム論」自体が時代の流行のパラダイムに載ってただけ、
というちょっと笑うに笑えない話になってしまう。
おいら自身がパラダイムという概念に接したのは
当時、学部で講義に出席していた藤原保信先生(まあ
有名どころで言えば、姜尚中先生の指導教授)が教科書に指定していた
『政治哲学のパラダイム転換』という書物、
および上原一男先生(有名どころで言えば、若田部昌澄先生および
田中先生の指導教授。ただしご本人はリフレ派からはこの世で一番
遠いような方。鬼籍に入って久しいが、もともと心臓の弱い方で
まあ誰とは言わないが、誰かさんのせいで寿命は
少なくとも10年は短くなったように思う、いや、誰とは言わないけど。
まあ草葉の陰で若田部先生のことをどのような思いで見守っているのか。。。。)が
これまた教科書に指定していた『経済学 人・時代・思想』(カンタベリー著)なんて
あたりで知ることとなる。
またおいらが大学に入学した年の何月号かの
『現代思想』誌でも「バラダイム再論」というような特集が
組まれており、それを買って、何が何だかわからないまま、
ともかく読み進めたことを覚えている。
まあ正直言うと、おいらの印象に残っているパラダイムの書物は
この3冊で終わりである。多分、他にもちょっとは
「パラダイム」という言葉が出てくる論文やらなにやらにも目を通したはずなんだが、
あんまり記憶にない。まあおいらの記憶なんてそんなもんだが。
ただ今でも覚えているのは、『現代思想』の特集及び
藤原先生の著書に書かれていることと、
上原先生の教科書(カンタベリー本)に書かれていたことのイメージの違いである。
自分の中でなんとなく一つのイメージにまとまったのは
おそらくそれから10数年後のことだろう。『現代思想』や
藤原本では、自分の現代社会の認識やその他科学的思考を根底から
捉えなおす営為の一環として位置づけられていたパラダイム概念であるが、
カンタベリー本になると、それは
経済学という特定分野の専門的学知の枠組みを変えるものではあるのだけれど、
単なる座標軸の変換という、
ごく表層的な(と、当時のおいらには思えた)問題に
集約されてしまっていたように感じられたのである。ちなみに
もともとのクーンのパラダイムという言葉は、
カンタベリー本で使われているイメージに近いようである。
レイが「パラダイムシフト」というような言葉を用いることで
何を表現したかったのか、正確にはわからないが、しかし
自分が指導している学生の言葉「MMTとは眼鏡のレンズだ」というような
表現をしばしば引用していることからも、あるいはレイ自身が学部は
心理学を専攻しており、大学院への進学も
心理学にするか経済学にするか迷った、というような述懐からも、
ある程度、イメージは見当つく。クーン自身、
「ゲシュタルト心理学」に依存している面が
あったとの話もある。なお、おいらの「ゲシュタルト」に関する知識は
木田元先生のNHKから出ていた、、、、
タイトルは忘れたけれど、何とかいう本で得たもので、
この本は入門の入門としてお勧めなんだけど、タイトル忘れた。
(ただそう考えると、
『科学革命の構造』第二版で「パラダイム」概念を放棄した
クーンの態度は、『経済発展の理論』の第二版で最終章を
消し去ったシュンペーターの態度に似たものを感じてしまう。。。
やはり「パラダイム」概念がクーンを離れて独り歩きしていったとはいっても
それはもともと、そうした内容がすでに、クーン自身は自覚していなくても
含まれていた、ということではなかったのか。いやいや
そんなことはおいらにわかりっこないねえ。。。)
突然話が変わる用で恐縮だが、「ルビンの壺」って絵のことをご存じだろうか?
「ルビンの壺」と聞いてもピンとくる人はそう多くないだろうが、
見ればほとんどの人が、ああ、これなら知っている、という代物である。
わからない人は検索してくれ。黒地に白抜きで、盃が描かれているのだが、
しかし見方によっては白い背景の前で
二人の人物が互いに向き合って見つめあっているシルエットのようにも
見える。そんな絵である。
あるいは、似たような例で、見ようによっては向こうを向いている妙齢の女性が
描かれているように見えるのだが、見方を変えると
こちらを向いている老婆のように見える絵というのがある。こちらは
Wikiによると「妻と義母」という名称らしいのだが、まあ
名前のことはどうでもいい。
こうした絵について、大概の人は、ちゃんと壺と向き合う二人、
妻と老婆、とを見分けることができる。まあおいら個人に関していうと、
子供のころ、ルビンの壺の方はすぐわかったが、妻と義母の方は
向こうを向いている妙齢の女性が描かれている、というのは
すぐわかったのだけれど、
老婆に関しては、何年かわからなかったような記憶がある。
ガキの頃からすでに頭が固いんだねえ。。。。(´・ω・`)
さて、だれでも知っている話ではあるのだが、ここには
ややめんどくさい問題がある。
「見方によって」盃か向き合う人か、妻か義母か、どちらかに見えるのだけれど、
どちらに見えるかは、「見方によって」決まってしまう、つまり、
何に見えるかは、ある程度、すでに絵を見る前に、どのような枠組みで見るかによって
決まってしまう、ということである。
絵を見るより先に何に見えるかが決まってしまう。まあ「決まってしまう」とまで言うと
ちょっと強調しすぎかもしれないが、枠組みが先に決まらないと、
どちらにも見えないのである。枠組みが決まることによって
どちらに見えるかが決まる。そして、第二の問題だが、
決して、一枚の絵の中に両方のイメージを同時にみることはできないのである。
つまり、一枚の絵を見ながら、同時に盃と向き合う人を見ることはできない。
勿論、簡単に盃から向き合う人へと、頭の中で構成されている
図柄を取り換えることはできるだろう。慣れてしまえば(ルビンの壺であれば、
慣れるまでもなく)盃から向き合う人へイメージを変えることが
瞬時にできるようになるだろう。だが、決して
同時に盃と向き合う人を、あるいは同時に妻と義母を見て取ることは
できない。瞬間的に切り替えることはできても
同時に妻と義母を見ることはできないのである。
さて、科学史上、「パラダイム転換」という言葉で知られるのは
「天動説から地動説へ」ということである。レイもこの言葉を
用いている。だが注意してほしいが、地動説と天動説の
どちらかが正しくてどちらかが誤っている、ということではない。
しかし、科学史上、ある時代はどちらかが正しいとされ、
別の時代は別の方が正しいとされた。ある時代には
どちらも正しいとされた。さてさて。。。
知っての通り、中世ヨーロッパでは地球が
世の中の中心にあり、太陽やら月やら天体の星は
地球の周囲を回っている、とされた。コペルニクスは――っつうか、
コペルニクス以前にもギリシアの時代からずっとそういう人が
いたことはいたそうなんだが(知らんわ)――、
そうじゃないよ、と、太陽が中心で、
まあ、月はたまたま地球の周りをまわってるみたいな感じだけど、
火星も金星も土星も木星もみんなして太陽の周りを
回っていることにしたほうがいいんだよ(月はちょっと違うけど)、と、唱えた。
コペルニクスが天動説を唱えた。それは事実である。
だがコペルニクス以前にも、天動説を唱える人たちは
それなりにおり、そして、なんでもWikiの情報によると
(眉に唾を付けることは必要だが)サモスのアリスタルコス(紀元前310-230頃)
はすでに「地球は自転しており、太陽が中心にあり、5つの惑星がその周りを
公転するという説を唱えた、と伝えられる。彼は、太陽を中心として、惑星の配置を
きちんと示した。これは単なる思いつきや空想を越えたものであり、ほとんど
「科学」と呼ぶ水準に達している」んだそうだ(あくまでもWiki情報だからね。まあ
この件に関してはそれほど疑う必要はないと思うけど)。
つまり、こうした言説が、世の中に受け入れられ、一般的な知識として
受け入れられるようになるには
科学的な正統性というより、
政治的あるいは宗教的、社会的な関係により、すでに
「どう見えるか」が、先に規定されることが必要なのである。
中世において、神が人を、神に似せて作った、とされている時代、
地球は神の宿る場所として、世界の中心に非ざることを得なかったであろう。
地球は宇宙の中心である。そうでなければならなかった。これに
反することは、教会に対する冒涜とされることもあった。ガリレオが
「それでも地球は動く」といわなければならなかったのは
ずっと後のことである。教会の権威が世界を支配し、世俗権力であるはずの国王さえ
宗教的権力を教会と争い、教会に相対的に有意に立つことによって
国王たる正統性を得なければならなかった時代には
当然のことであった。しかし、世俗権力(なにも政治権力に
限った話ではない)が力を得、宗教が世俗の権力関係にまで
干渉できなくなると、むしろ実務的に説得力がある方が
正しいということになる(いやまあ、そこまで簡単な話じゃないが)。
太陽を中心にしたほうが天体の動きをきれいに描くことができるようになる。
天動説から地動説へのパラダイムシフトとは
宗教的権威から世俗権力への、社会的正統性を備給するエネルギー源の
シフトと対応したものだった。一応言っておくけど
これは何も、宗教的指導者たちが科学的研究に
介入していたとか、世俗的政治・経済力が宗教的
権力を凌駕することで、学問が自由になったとか、
そんなことを言っているわけではない(そういう事実が
あったとしても)。あるいはまた
技術的な制約によって問題設定や解釈が制約される、
ということもあったろう。望遠鏡が発達しなければ、
人間は肉眼で星の動きを観測せざるを得ず、
数学を用いた表現も限られたものになる。だがここで言っているのは、
そうした権力行使の顕在化や、技術的な制約といったこととは別に、
日常的な言説の中にすでに学問の問題提起や議論の展開自体を
制限するものがあり、そうしたものによって既に
問題提起や議論の展開自体が制限を受けている、
といいうことである。それはちょうど、「ルビンの壺」や
「妻と義母」の絵において、見え方が事前に決まった枠組みに沿ってしか
見ることができない、というのと同じである。先に
認識・問題設定・議論の枠組みが、その時代の要請によって
決まってしまう。そしてそれを乗り越えるということは
決して簡単ではない。なぜなら新しい主張があったとしても
――個人のレベルで言うなら、いつの時代にもはぐれもんはいる――
社会的にそれを受け入れるだけの「枠組み」が
形成されないからである。ルビンの壺ぐらいであれば
誰にでも盃から向き合う人へと移れるだろう。
しかし妻と義母になると、そうはいかない。おいらは
これが老婆に見えるようになるまで数年かかかった。それは単に
おいらがぼんくらなだけだが、社会的な関係により
構成された認識の枠組みとなると、それだけでは済まない。
妻が老婆に見えるようになるまでには、望遠鏡の開発やら
数学の発展といった技術的要因も必要だったかもしれないが、
それさえあれば、いつでも妻が義母に見えるようになるわけではない。
天動説は、宗教的権威を中心とする支配/従属関係に
対応した表象であった。マルクス風のいい方をするなら、
地球が中心で太陽が地球を回っているものとして「あらわれてくる」。
他方で、地動説は世俗的権力が宗教的権力を凌駕して
新しい支配/従属関係を構築したことに対応した表象である。
そしてその後、地動説と天動説は、単なる
座標軸の変換として表象されることとなる。地球と太陽、
どちらを中心にしても、計算さえきちんと行われていれば
正確に天体の運動を示すことはできる。科学の脱政治化・脱権威化で
あるが、これは「脱政治化・脱権威化」という言葉に反して、
テクノクラート支配に対応した表象でもある。かつて
政治権力や経済権力が「脱宗教」の名のもとに
支配/従属関係を、日常意識に、当然のものとして
もはや問題設定に上らないものとして
表象させることができたように、
「科学」という表現は、その中に現に存在している
テクノクラート(専門家集団)を中心とした支配/従属関係を
当然のものとして、問題設定に上らないものとして
表象させる言語関係を構築している。「科学」が
政治経済宗教から独立していることを標榜するとき、
「科学」は政治からも経済からも宗教からも自律しているのであり、
それゆえに正統なのだ、と主張するとき、
それこそがまさに支配/従属関係を構築する言説の一つなのだ。
ただ、そういうことに無自覚な科学者に対して個別的な警戒が必要だというのは
当然だし簡単だ。むしろ難しいのは、自分自身の中にある
支配/従属関係をどのようにして相対化するかである。科学者が
科学の自律性を訴えるとき、そこには少なくとも一つの
真実がある。それ自体は欺瞞ではない。科学的研究を
政治経済宗教権力の支配(影響力)から守ること、そして
そうして守られた科学こそが科学として(時には
政治経済の手段として)意味を持つこと、
そういう主張することと、
「政治経済からの自律性」(すなわち中立性)という、
その言葉を発する行為自体が、すでに政治的正統化をめぐる争いに
巻き込まれているのであり、
政治経済権力を構築し、テクノクラート支配を
正統化する言説になってしまっているものだ、ということ、
両面の折り合いを何とかして、自分の中でつけていかなくてはならない。
今回のエントリーではテクノクラート支配については
これ以上、立ち入ることは避ける。
MMT自体はテクノクラートを陽表的には取り扱っていない。
しかしながらMMTの議論からすれば
それは当然の論点である。MMTがユーロを批判し、
JGPを主張するときに論じられていることは
明らかにハーバーマスにより指摘された
近代民主主義体制の下でのテクノクラート支配の必然性と
その打開であろう。(ハーバーマスがユーロの擁護者であり、
MMTがその徹底的な批判者である、ということは
ハーバーマスの両義的な議論を考えるなら
この際、大した問題ではない。)MMTが指摘しているのは
政治経済分野におけるテクノクラート支配の欺瞞性であり、
その打開策の一つ、参加型民主主義の実現のすべの一つとしての
JGPであるわけだけれど、これはまたの機会に。
今回のエントリーで言いたいのは、
要するにパラダイム論の三つの側面である。
第一に、パラダイムというのは物事を認識する際の枠組みであり
(つまり、眼鏡のレンズであり)、
それにより、問題設定が制限され、議論の展開が限定され、
しばしば結論が自動的に導かれてしまう。
こうしたパラダイムは、すでに
問題に接する前に、存在してしまう(というか、それがなければ
問題を問題として認識することができない)。
このパラダイムを相対化し、抽出することは(それ自体
また別次元の「認識の枠組み」を必要とする)簡単ではない。
第二に、パラダイムは「あれかこれか」である。盃を見るか
向き合う人を見るか、妻を見るか義母を見るか、
天動説にするか地動説にするか、
パラダイムが相対化されさえすれば、どちらも自由に選択できる。
だが、両者を同時にみることはできない。
天動説の立場に立ちながら、
木星だけは地球の周りをまわっているという説明は
成立しない。地動説なら、太陽も木星も土星も地球の周りを
回らなければならない(それがどれほど複雑な軌跡であろうと)し、
天動説なら、地球も木星も土星も太陽の周りをまわるのである。
向き合う二人の、右半分だけを人のシルエットと認識し、左半分は
盃というわけにはいかない。
そして第三に、こうしたパラダイムは支配/権力関係から
切り離すことはできない。何も支配者がパラダイムを決定しているわけでは
ない(そんなことは不可能だ)。しかしながら
議論の枠組みを決定するエネルギーは、日常的な支配/従属関係から
独立して存在することはあり得ない。それは支配者ばかりでなく被支配者が自ら
創り出すものでもある。ある被支配者は、自らが従属する必然性を
説明する理論を発見するや、それに積極的に従うことで、
自分が支配している者たちに、自分と同じようにふるまうことを
強要し、そうすることで自分の支配力を確実なものにしようとするだろう。
支配の最底辺にいる存在ですら、そうして与えられる規範を
わがものとすることを通じて、自分自身の存在の社会的意義を
確認することがしばしばである。最底辺の存在にとっては、こうした
規範を受け入れることだけが、自分自身のみじめな境遇を慰める
唯一の光であるということさえあり得るのかもしれない。
そしてこうした思考の枠組みの受け入れは、政治の現場や職場だけでなく、
家庭や学校、友人同士の間でも
再生産され、自分たちの思考を律する。あらゆる言葉、認識、
学芸、文化活動の中に入り込んでおり、それを抜きにして
社会生活が営まれることはあり得ない。そして
社会的存在である限り、このエネルギーから逃れることは
おそらく人間には不可能であろう。ただし同時に、こうしたエネルギーにも
それなりの自由度はあるのであり、それゆえこのエネルギーの結果として
生み出される「思考の枠組み」を相対化し、少しでも
ましなものにしようという試みなら無駄ではないかもしれない。
と、いうのが、当時のパラダイムにかかわる議論を
昨今のMMTと絡めて思い出したり、ひねりなおしたりして
出てきたお話。
さて、おしまいに一つ、とっても嫌なことを書いておこう。
いやだねえ。。。
パラダイムという言葉は、今日ではもはや
科学史上の論争を離れたところで使われるようになっている。
含意ももはやもともとトマス・クーンが論じようとしたことからは
はるかに隔たったところにある。レイがMMTを「パラダイム」とし、
「レンズ」になぞらえるとき、もはやクーンの問題意識とは
全く別の次元へ移っている。。。。
と、いうことは?
MMTだって、最初に言いだした人たちと違うことを言ったって
いいじゃないか?これが正しいMMT、これが間違ったMMTなんてのが
あるのか、もともとのMMTと
違う日本版MMTがあったっていいじゃないか。。。。
MMTはレンズなんかじゃないよ、オペレーションの実務的事実を記述したもんでもないよ、
国債は破綻しない、ってことで、財政支出で
景気を刺激しようってことでいいんだよ、、、
と、なってしまうと、さすがに困ってしまってわんわんわわん。
まあ、夜も更けたし、今日はここまで。
MMTはパラダイムの転換を促しているのだ、みたいなことを
書いてしまったせいで、
ひところMMTをパラダイムに引っ掛ける話が話題になってた。
パラダイムという言葉自体はトマス・クーンによって科学史上に
持ち込まれた概念で、この分野については
かなり難しい議論があって、おいらなんかが下手に触ると
火傷しておしまいなので、この原義についてあれこれ言うのは
やめておきたい。
と、そう思うんだったらやめときゃいいんだけれど、
レイがねえ、ああ書いちゃったからねえ、、、、、(´・ω・`)
ただ、レイがくだんの書物でああ書いているからといって
おいら自身に全く何の思い入れもなければ
「また変なこと書いてるな」とスルーすればいいわけだが、
おいら自身も、ちょっとだけ、こだわりがあるので
ちょっとだけ、考え方に触れておきたいのである。繰り返すけど、
科学史の知識なんかないからね。。。。
おいらが大学に入学して最初に「へえこんなんがあるんだ」と
感心させられた言葉の一つが「パラダイム」である。
ちょうど「現代思想ブーム」も終盤に差し掛かるころで、
フーコだのアルチュセールだの、、、、の「入門書」(別冊宝島、とか)を
一生懸命読み漁っていたころだ。まあ、あんまり理解できた覚えはないし、
ついでに言えば、だいたい内容は忘れたが。
まあフーコの「エピステーメ」とか
吉本隆明の「幻想」とか、その辺と「パラダイム」という概念は
似ている、というか、あんまり区別もつかなかった。今読めば
ちょっとは違いが判るだろうかゴールドブレンド。
このパラダイムであるが80年代半ばの
いわゆる「パラダイム再論」の文脈では、
もはやもともとの議論が科学史にかかわるものだった、なんて話は
すでにすっ飛んでいて、むしろ学知一般の分野に移っていて、
それはまあいいんだけれど、
結局、新カント派的な相対主義と同じじゃないか、というような批判もあり、
でもだとすると、
「パラダイム論」自体が時代の流行のパラダイムに載ってただけ、
というちょっと笑うに笑えない話になってしまう。
おいら自身がパラダイムという概念に接したのは
当時、学部で講義に出席していた藤原保信先生(まあ
有名どころで言えば、姜尚中先生の指導教授)が教科書に指定していた
『政治哲学のパラダイム転換』という書物、
および上原一男先生(有名どころで言えば、若田部昌澄先生および
田中先生の指導教授。ただしご本人はリフレ派からはこの世で一番
遠いような方。鬼籍に入って久しいが、もともと心臓の弱い方で
まあ誰とは言わないが、誰かさんのせいで寿命は
少なくとも10年は短くなったように思う、いや、誰とは言わないけど。
まあ草葉の陰で若田部先生のことをどのような思いで見守っているのか。。。。)が
これまた教科書に指定していた『経済学 人・時代・思想』(カンタベリー著)なんて
あたりで知ることとなる。
またおいらが大学に入学した年の何月号かの
『現代思想』誌でも「バラダイム再論」というような特集が
組まれており、それを買って、何が何だかわからないまま、
ともかく読み進めたことを覚えている。
まあ正直言うと、おいらの印象に残っているパラダイムの書物は
この3冊で終わりである。多分、他にもちょっとは
「パラダイム」という言葉が出てくる論文やらなにやらにも目を通したはずなんだが、
あんまり記憶にない。まあおいらの記憶なんてそんなもんだが。
ただ今でも覚えているのは、『現代思想』の特集及び
藤原先生の著書に書かれていることと、
上原先生の教科書(カンタベリー本)に書かれていたことのイメージの違いである。
自分の中でなんとなく一つのイメージにまとまったのは
おそらくそれから10数年後のことだろう。『現代思想』や
藤原本では、自分の現代社会の認識やその他科学的思考を根底から
捉えなおす営為の一環として位置づけられていたパラダイム概念であるが、
カンタベリー本になると、それは
経済学という特定分野の専門的学知の枠組みを変えるものではあるのだけれど、
単なる座標軸の変換という、
ごく表層的な(と、当時のおいらには思えた)問題に
集約されてしまっていたように感じられたのである。ちなみに
もともとのクーンのパラダイムという言葉は、
カンタベリー本で使われているイメージに近いようである。
レイが「パラダイムシフト」というような言葉を用いることで
何を表現したかったのか、正確にはわからないが、しかし
自分が指導している学生の言葉「MMTとは眼鏡のレンズだ」というような
表現をしばしば引用していることからも、あるいはレイ自身が学部は
心理学を専攻しており、大学院への進学も
心理学にするか経済学にするか迷った、というような述懐からも、
ある程度、イメージは見当つく。クーン自身、
「ゲシュタルト心理学」に依存している面が
あったとの話もある。なお、おいらの「ゲシュタルト」に関する知識は
木田元先生のNHKから出ていた、、、、
タイトルは忘れたけれど、何とかいう本で得たもので、
この本は入門の入門としてお勧めなんだけど、タイトル忘れた。
(ただそう考えると、
『科学革命の構造』第二版で「パラダイム」概念を放棄した
クーンの態度は、『経済発展の理論』の第二版で最終章を
消し去ったシュンペーターの態度に似たものを感じてしまう。。。
やはり「パラダイム」概念がクーンを離れて独り歩きしていったとはいっても
それはもともと、そうした内容がすでに、クーン自身は自覚していなくても
含まれていた、ということではなかったのか。いやいや
そんなことはおいらにわかりっこないねえ。。。)
突然話が変わる用で恐縮だが、「ルビンの壺」って絵のことをご存じだろうか?
「ルビンの壺」と聞いてもピンとくる人はそう多くないだろうが、
見ればほとんどの人が、ああ、これなら知っている、という代物である。
わからない人は検索してくれ。黒地に白抜きで、盃が描かれているのだが、
しかし見方によっては白い背景の前で
二人の人物が互いに向き合って見つめあっているシルエットのようにも
見える。そんな絵である。
あるいは、似たような例で、見ようによっては向こうを向いている妙齢の女性が
描かれているように見えるのだが、見方を変えると
こちらを向いている老婆のように見える絵というのがある。こちらは
Wikiによると「妻と義母」という名称らしいのだが、まあ
名前のことはどうでもいい。
こうした絵について、大概の人は、ちゃんと壺と向き合う二人、
妻と老婆、とを見分けることができる。まあおいら個人に関していうと、
子供のころ、ルビンの壺の方はすぐわかったが、妻と義母の方は
向こうを向いている妙齢の女性が描かれている、というのは
すぐわかったのだけれど、
老婆に関しては、何年かわからなかったような記憶がある。
ガキの頃からすでに頭が固いんだねえ。。。。(´・ω・`)
さて、だれでも知っている話ではあるのだが、ここには
ややめんどくさい問題がある。
「見方によって」盃か向き合う人か、妻か義母か、どちらかに見えるのだけれど、
どちらに見えるかは、「見方によって」決まってしまう、つまり、
何に見えるかは、ある程度、すでに絵を見る前に、どのような枠組みで見るかによって
決まってしまう、ということである。
絵を見るより先に何に見えるかが決まってしまう。まあ「決まってしまう」とまで言うと
ちょっと強調しすぎかもしれないが、枠組みが先に決まらないと、
どちらにも見えないのである。枠組みが決まることによって
どちらに見えるかが決まる。そして、第二の問題だが、
決して、一枚の絵の中に両方のイメージを同時にみることはできないのである。
つまり、一枚の絵を見ながら、同時に盃と向き合う人を見ることはできない。
勿論、簡単に盃から向き合う人へと、頭の中で構成されている
図柄を取り換えることはできるだろう。慣れてしまえば(ルビンの壺であれば、
慣れるまでもなく)盃から向き合う人へイメージを変えることが
瞬時にできるようになるだろう。だが、決して
同時に盃と向き合う人を、あるいは同時に妻と義母を見て取ることは
できない。瞬間的に切り替えることはできても
同時に妻と義母を見ることはできないのである。
さて、科学史上、「パラダイム転換」という言葉で知られるのは
「天動説から地動説へ」ということである。レイもこの言葉を
用いている。だが注意してほしいが、地動説と天動説の
どちらかが正しくてどちらかが誤っている、ということではない。
しかし、科学史上、ある時代はどちらかが正しいとされ、
別の時代は別の方が正しいとされた。ある時代には
どちらも正しいとされた。さてさて。。。
知っての通り、中世ヨーロッパでは地球が
世の中の中心にあり、太陽やら月やら天体の星は
地球の周囲を回っている、とされた。コペルニクスは――っつうか、
コペルニクス以前にもギリシアの時代からずっとそういう人が
いたことはいたそうなんだが(知らんわ)――、
そうじゃないよ、と、太陽が中心で、
まあ、月はたまたま地球の周りをまわってるみたいな感じだけど、
火星も金星も土星も木星もみんなして太陽の周りを
回っていることにしたほうがいいんだよ(月はちょっと違うけど)、と、唱えた。
コペルニクスが天動説を唱えた。それは事実である。
だがコペルニクス以前にも、天動説を唱える人たちは
それなりにおり、そして、なんでもWikiの情報によると
(眉に唾を付けることは必要だが)サモスのアリスタルコス(紀元前310-230頃)
はすでに「地球は自転しており、太陽が中心にあり、5つの惑星がその周りを
公転するという説を唱えた、と伝えられる。彼は、太陽を中心として、惑星の配置を
きちんと示した。これは単なる思いつきや空想を越えたものであり、ほとんど
「科学」と呼ぶ水準に達している」んだそうだ(あくまでもWiki情報だからね。まあ
この件に関してはそれほど疑う必要はないと思うけど)。
つまり、こうした言説が、世の中に受け入れられ、一般的な知識として
受け入れられるようになるには
科学的な正統性というより、
政治的あるいは宗教的、社会的な関係により、すでに
「どう見えるか」が、先に規定されることが必要なのである。
中世において、神が人を、神に似せて作った、とされている時代、
地球は神の宿る場所として、世界の中心に非ざることを得なかったであろう。
地球は宇宙の中心である。そうでなければならなかった。これに
反することは、教会に対する冒涜とされることもあった。ガリレオが
「それでも地球は動く」といわなければならなかったのは
ずっと後のことである。教会の権威が世界を支配し、世俗権力であるはずの国王さえ
宗教的権力を教会と争い、教会に相対的に有意に立つことによって
国王たる正統性を得なければならなかった時代には
当然のことであった。しかし、世俗権力(なにも政治権力に
限った話ではない)が力を得、宗教が世俗の権力関係にまで
干渉できなくなると、むしろ実務的に説得力がある方が
正しいということになる(いやまあ、そこまで簡単な話じゃないが)。
太陽を中心にしたほうが天体の動きをきれいに描くことができるようになる。
天動説から地動説へのパラダイムシフトとは
宗教的権威から世俗権力への、社会的正統性を備給するエネルギー源の
シフトと対応したものだった。一応言っておくけど
これは何も、宗教的指導者たちが科学的研究に
介入していたとか、世俗的政治・経済力が宗教的
権力を凌駕することで、学問が自由になったとか、
そんなことを言っているわけではない(そういう事実が
あったとしても)。あるいはまた
技術的な制約によって問題設定や解釈が制約される、
ということもあったろう。望遠鏡が発達しなければ、
人間は肉眼で星の動きを観測せざるを得ず、
数学を用いた表現も限られたものになる。だがここで言っているのは、
そうした権力行使の顕在化や、技術的な制約といったこととは別に、
日常的な言説の中にすでに学問の問題提起や議論の展開自体を
制限するものがあり、そうしたものによって既に
問題提起や議論の展開自体が制限を受けている、
といいうことである。それはちょうど、「ルビンの壺」や
「妻と義母」の絵において、見え方が事前に決まった枠組みに沿ってしか
見ることができない、というのと同じである。先に
認識・問題設定・議論の枠組みが、その時代の要請によって
決まってしまう。そしてそれを乗り越えるということは
決して簡単ではない。なぜなら新しい主張があったとしても
――個人のレベルで言うなら、いつの時代にもはぐれもんはいる――
社会的にそれを受け入れるだけの「枠組み」が
形成されないからである。ルビンの壺ぐらいであれば
誰にでも盃から向き合う人へと移れるだろう。
しかし妻と義母になると、そうはいかない。おいらは
これが老婆に見えるようになるまで数年かかかった。それは単に
おいらがぼんくらなだけだが、社会的な関係により
構成された認識の枠組みとなると、それだけでは済まない。
妻が老婆に見えるようになるまでには、望遠鏡の開発やら
数学の発展といった技術的要因も必要だったかもしれないが、
それさえあれば、いつでも妻が義母に見えるようになるわけではない。
天動説は、宗教的権威を中心とする支配/従属関係に
対応した表象であった。マルクス風のいい方をするなら、
地球が中心で太陽が地球を回っているものとして「あらわれてくる」。
他方で、地動説は世俗的権力が宗教的権力を凌駕して
新しい支配/従属関係を構築したことに対応した表象である。
そしてその後、地動説と天動説は、単なる
座標軸の変換として表象されることとなる。地球と太陽、
どちらを中心にしても、計算さえきちんと行われていれば
正確に天体の運動を示すことはできる。科学の脱政治化・脱権威化で
あるが、これは「脱政治化・脱権威化」という言葉に反して、
テクノクラート支配に対応した表象でもある。かつて
政治権力や経済権力が「脱宗教」の名のもとに
支配/従属関係を、日常意識に、当然のものとして
もはや問題設定に上らないものとして
表象させることができたように、
「科学」という表現は、その中に現に存在している
テクノクラート(専門家集団)を中心とした支配/従属関係を
当然のものとして、問題設定に上らないものとして
表象させる言語関係を構築している。「科学」が
政治経済宗教から独立していることを標榜するとき、
「科学」は政治からも経済からも宗教からも自律しているのであり、
それゆえに正統なのだ、と主張するとき、
それこそがまさに支配/従属関係を構築する言説の一つなのだ。
ただ、そういうことに無自覚な科学者に対して個別的な警戒が必要だというのは
当然だし簡単だ。むしろ難しいのは、自分自身の中にある
支配/従属関係をどのようにして相対化するかである。科学者が
科学の自律性を訴えるとき、そこには少なくとも一つの
真実がある。それ自体は欺瞞ではない。科学的研究を
政治経済宗教権力の支配(影響力)から守ること、そして
そうして守られた科学こそが科学として(時には
政治経済の手段として)意味を持つこと、
そういう主張することと、
「政治経済からの自律性」(すなわち中立性)という、
その言葉を発する行為自体が、すでに政治的正統化をめぐる争いに
巻き込まれているのであり、
政治経済権力を構築し、テクノクラート支配を
正統化する言説になってしまっているものだ、ということ、
両面の折り合いを何とかして、自分の中でつけていかなくてはならない。
今回のエントリーではテクノクラート支配については
これ以上、立ち入ることは避ける。
MMT自体はテクノクラートを陽表的には取り扱っていない。
しかしながらMMTの議論からすれば
それは当然の論点である。MMTがユーロを批判し、
JGPを主張するときに論じられていることは
明らかにハーバーマスにより指摘された
近代民主主義体制の下でのテクノクラート支配の必然性と
その打開であろう。(ハーバーマスがユーロの擁護者であり、
MMTがその徹底的な批判者である、ということは
ハーバーマスの両義的な議論を考えるなら
この際、大した問題ではない。)MMTが指摘しているのは
政治経済分野におけるテクノクラート支配の欺瞞性であり、
その打開策の一つ、参加型民主主義の実現のすべの一つとしての
JGPであるわけだけれど、これはまたの機会に。
今回のエントリーで言いたいのは、
要するにパラダイム論の三つの側面である。
第一に、パラダイムというのは物事を認識する際の枠組みであり
(つまり、眼鏡のレンズであり)、
それにより、問題設定が制限され、議論の展開が限定され、
しばしば結論が自動的に導かれてしまう。
こうしたパラダイムは、すでに
問題に接する前に、存在してしまう(というか、それがなければ
問題を問題として認識することができない)。
このパラダイムを相対化し、抽出することは(それ自体
また別次元の「認識の枠組み」を必要とする)簡単ではない。
第二に、パラダイムは「あれかこれか」である。盃を見るか
向き合う人を見るか、妻を見るか義母を見るか、
天動説にするか地動説にするか、
パラダイムが相対化されさえすれば、どちらも自由に選択できる。
だが、両者を同時にみることはできない。
天動説の立場に立ちながら、
木星だけは地球の周りをまわっているという説明は
成立しない。地動説なら、太陽も木星も土星も地球の周りを
回らなければならない(それがどれほど複雑な軌跡であろうと)し、
天動説なら、地球も木星も土星も太陽の周りをまわるのである。
向き合う二人の、右半分だけを人のシルエットと認識し、左半分は
盃というわけにはいかない。
そして第三に、こうしたパラダイムは支配/権力関係から
切り離すことはできない。何も支配者がパラダイムを決定しているわけでは
ない(そんなことは不可能だ)。しかしながら
議論の枠組みを決定するエネルギーは、日常的な支配/従属関係から
独立して存在することはあり得ない。それは支配者ばかりでなく被支配者が自ら
創り出すものでもある。ある被支配者は、自らが従属する必然性を
説明する理論を発見するや、それに積極的に従うことで、
自分が支配している者たちに、自分と同じようにふるまうことを
強要し、そうすることで自分の支配力を確実なものにしようとするだろう。
支配の最底辺にいる存在ですら、そうして与えられる規範を
わがものとすることを通じて、自分自身の存在の社会的意義を
確認することがしばしばである。最底辺の存在にとっては、こうした
規範を受け入れることだけが、自分自身のみじめな境遇を慰める
唯一の光であるということさえあり得るのかもしれない。
そしてこうした思考の枠組みの受け入れは、政治の現場や職場だけでなく、
家庭や学校、友人同士の間でも
再生産され、自分たちの思考を律する。あらゆる言葉、認識、
学芸、文化活動の中に入り込んでおり、それを抜きにして
社会生活が営まれることはあり得ない。そして
社会的存在である限り、このエネルギーから逃れることは
おそらく人間には不可能であろう。ただし同時に、こうしたエネルギーにも
それなりの自由度はあるのであり、それゆえこのエネルギーの結果として
生み出される「思考の枠組み」を相対化し、少しでも
ましなものにしようという試みなら無駄ではないかもしれない。
と、いうのが、当時のパラダイムにかかわる議論を
昨今のMMTと絡めて思い出したり、ひねりなおしたりして
出てきたお話。
さて、おしまいに一つ、とっても嫌なことを書いておこう。
いやだねえ。。。
パラダイムという言葉は、今日ではもはや
科学史上の論争を離れたところで使われるようになっている。
含意ももはやもともとトマス・クーンが論じようとしたことからは
はるかに隔たったところにある。レイがMMTを「パラダイム」とし、
「レンズ」になぞらえるとき、もはやクーンの問題意識とは
全く別の次元へ移っている。。。。
と、いうことは?
MMTだって、最初に言いだした人たちと違うことを言ったって
いいじゃないか?これが正しいMMT、これが間違ったMMTなんてのが
あるのか、もともとのMMTと
違う日本版MMTがあったっていいじゃないか。。。。
MMTはレンズなんかじゃないよ、オペレーションの実務的事実を記述したもんでもないよ、
国債は破綻しない、ってことで、財政支出で
景気を刺激しようってことでいいんだよ、、、
と、なってしまうと、さすがに困ってしまってわんわんわわん。
まあ、夜も更けたし、今日はここまで。










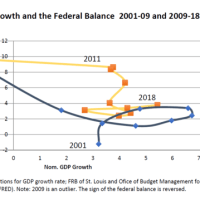
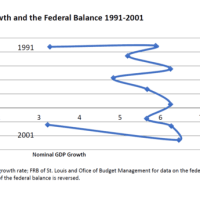
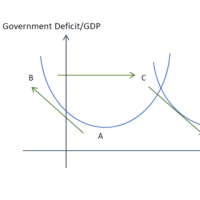
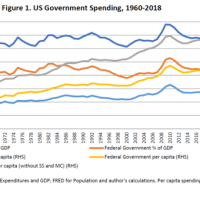
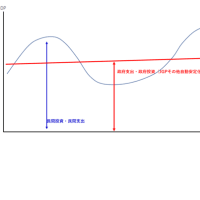
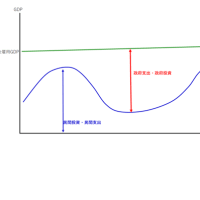
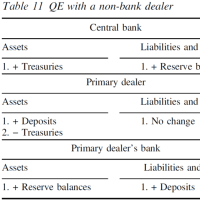
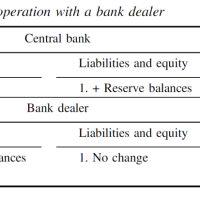
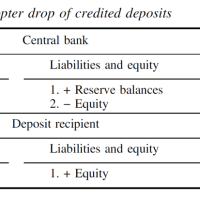
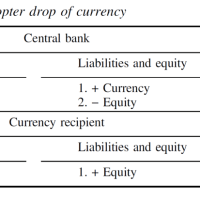
割と頻繁に天動説と地動説が逆に使われているところが目につきましたよ!
ちょっと気になったのでお知らせします。
これは悪口ではなく、「複雑さを恐れない」という意味で天動説と言っています。
MMTには「ある」の部分と「あるべき」の二つがあるとツイッターで言っていましたが、物理学と医学の違いのようなものではないでしょうか。
例えばインフレになっても原則として何もしないというのは、風邪を引いたら暖かくして寝るのが一番で薬に頼るのは良くないと言っていると考えると違和感がなくなります。
MMTが求めるのは健康の維持であり、成長は自分(民間)で勝手にすればいいのでしょう。
日本版MMTが求めるのは地動説であり物理学であり単純明快であることですから、天動説であり医学であり複雑であるMMTは切り捨てているという印象があります。
物理学としての部分は世界共通でいいとしても医学としての部分は患者(国)ごとに診断しないと役に立たないのではないでしょうか。
JGPにしても日本でそのまま適用することはできないし、本来政府がやるべきことを民間が代わりにやっているので政府が金を出すべきであるというのが本質ではないかと思います。
国ごとに、本来政府がやるべきなのに民間がやっていることをみつけて政府が金を出す仕組みを作ることでユニバーサルなJGPができるだろうということですが。
本家MMTは暗いというより地味ですが、医学だと考えれば興味を持つ人も増えるのではないでしょうか。趣味で手を出すには厳しいですけどね。
日本版MMTは解体新書を読んだ人間が、これで人間の身体について正確な知識を得たから手術ができるぞと言っているようなものでしょうか。
えと、MMTは複雑さを恐れない、とのお話ですが、むしろ逆だと思います。(レイはじめ何人かのMMT派が「複雑系経済学」学会にかかわっているらしいですが、これはバジル・ムーアという大先生の顔を立ててのことではないかと思います。。。ってか、「複雑系」というのは議論の対象の話で、議論が複雑になるかどうかは、また別だと思いますが。。)
MMTが複雑に見えるのは、従来の経済学の視点を引きずってしまっているからではないか、とおいらはそう思っています。むしろMMTの方が、現に起こっている経済現象を単純に(一貫した形で)説明できていると感じることが多い。確かに通常の経済学からは抜け落ちている論点(政府中央銀行のオペレーションの記述)など、初めて接する人には難しく、近寄りがたい内容に思われることもあるとは思いますけれど、でもそれって、あらゆる学問に共通で、他の学問分野で初めて接する人が感じる困難と比べて、特にMMTだけが難しいというほどのものでもないと思います。実際、入門レベルのミクロマクロ経済学に、数学の知識がない人が取り組むのと、MMTの入門書に財務管理(簿記会計)の知識がない人が取り組むのとでは、特に後者の方が大変だと感じることはないんじゃないかな、、。
日本版MMTと称している人たちの書いたものをちょっと読んだ限りでは(まあ、たまたまあまりよくないものを読んでしまった、とは言えるかもしれませんけれど)、ちょっと楽しようと考えすぎなんじゃないでしょうかね。「わかりやすく」と、楽をしようというのは、やっぱり違うと思います。「わかりやすく」と称して中心的な論点をすっ飛ばしてわかることだけを言っていても、やっぱり「パラダイム転換」になんてならないんじゃないか、という気がします。
「ある」と「あるべき」の区別は重要ですが、それ以上に重要なのは、どのような問題を設定するではないでしょうか。議論に際しては「ある」ことの説明をしなければなりません。しかし「ある」からという理由で、ありとあらゆることを説明しようとしても「闇夜の黒牛」になってしまいます。『単純に「ある」ことを説明する』というのは、無限に分節化・差異化して認識することが可能な「ある」ことの中から、ある特定の事象を選択し、再組織し、言語化することを意味しています。単純に「ある」ことを言えるわけではありません。この選択と再組織化(本当のことを言うと、その前段の分節化・差異化からなんですけれど)の前提となっているのが、パラダイムであり問題設定です。「ある」を論じるときにはすでに一定のパラダイムと問題設定によって枠づけられているのであり、その枠組みから必然的に「あるべき」という問題設定が出てくるはずです。「ある」ことと「あるべき」ことを機械的に切り離すことなど、できるはずないのです。無理やり切り離せば、「あるべき」ことは、「問われることのなかった問い」として意識に上ることはなくとも、ずっとまとわりつくことになるでしょう。(主流派経済学が金融危機をなぜきちんと取り扱うことができないのか、といえば、彼らの枠組みではそもそも問いを立てること自体が難しいからです。)
MMTが暴露した「ある」ことの一つは、市場には「貨幣」と「商品」の交換比率を決定するメカニズムなどなく、それこそインフレやデフレの背景にある決定的な問題だ、ということだと思います。この「ある」こと(事実の描写)に対する彼らなりの回答の一つがJGPでしょう。この「ある」ことと「あるべき」ことの組み合わせは「景気回復」によって雇用を増やし、そしてインフレになったら政府支出を減らしたり増税によって雇用を減らすことで抑制しようとするNAIRUとは正反対ですが、それはもともとNAIRUには貨幣と商品の交換価値を決める原則がない(「市場での交換によって決まる」という誤った「ある」の説明)ことに由来している、といっていい。そして「市場には貨幣と商品の交換比率を決定するメカニズムはない」というMMTの「ある」ことの描写は、実際に金融市場や労働市場の描写及びSFCの関係(いずれも「ある」こと)に由来しています。一方において、MMTがいう政府・中央銀行のオペレーションの記述を理解したといいながら、同時に貨幣と商品の交換価値が市場で決まるというのは両立しません。だから一部の日本版MMT派で「貨幣市場のオペレーション」の話を「些末なこと」として、あるいは意図的に、言及することを避け、「国債を発行して政府は財源を確保しろ」という話に転換しているのは、結局のところ、NAIRUと同じ目線で話をしている、ということに他ならないように思えるんです。おいらが日本版MMTと称する人たちに対してフラストレーションを感じるのは、こうした知的な不誠実さのせいです。勝手に「理解しにくいこと」=「些末でどうでもいいこと」と変換して、そして数多くの重要な論点をスルーしてしまう。それは確かにわかりやすさにつながり、あまり勉強したくない人たちを引き付けるのには役立つかもしれませんが、しかしそれをMMTと呼ぶのは(たとえ「日本版」としてであっても)やめてあげて欲しいと思います。