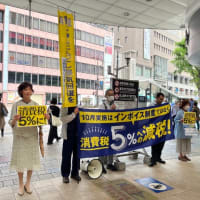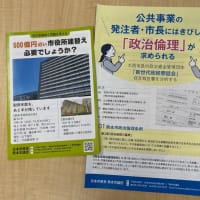1日の開催となった6月議会、質疑の時間は一人わずか10分でした。
限られた持ち時間ではありましたが、日本共産党市議団は、3人で30分の時間を目いっぱい使って、熊本地震への対応の問題点を指摘し、改善を求めました。
私は、①「災害援護資金貸付事業」、②「地震発生後の子どもたちの心のケアとしてのスクールカウンセラー設置問題」、③「学校施設の応急修理」、④「震災復興基金」の4点を質問しました。
【質問内容】は以下のとおり
まず初めに、「災害援護資金貸付事業」に21億6000万円の補正が提案されています。この制度は、そもそも被災者への制度であり、かつ所得制限もあり、生活が大変な方々がその住居や家財などの生活立て直しに利用する制度です。ところが、根拠法令となっている「災害弔慰金の支給等に関する法律」の定めによって、措置期間は無利子であるものの、返済が始まれば年3%の利息を徴収することになっています。中小企業に貸し付けられる「特別融資」は、利息補給によって、3年間は無利子の措置が取られます。そういう対応を見ましても、「災害援護資金貸付」は、最も困った方の利用するであり、利息3%の徴収について、利子補給など、市として何らかの措置を講じて、無利子の貸付けにすることはできないでしょうか。
また、「災害弔慰金の支給等に関する法律」は、昭和48年にできた法律です。その公布当初から、利率3%が定められており、超低金利の今の時代に全くそぐわないものと思われます。また、償還金が期限内に返済できなかった場合は、年利10・75%の違約金まで払わなければならない仕組みになっています。その違約金もまた、法の公布と同時公布された施行令に定められたものです。これら実態に合わない利息や違約金の徴収はやめて、無利子での貸し付け、違約金はとらないよう、被災者に大きな負担を求めるような制度の見直しを国に求めていただきたいと思いますがいかがでしょうか。
(答弁)
「災害援護資金貸付事業」は、被災によって大きなダメージを受けただけでなく、その中でも生活が厳しいであろう方々が利用する制度です。その趣旨に則り、国に対し、利息と違約金徴収の中止を強く求めていただくよう要望します。災害援護資金貸付は、措置期間の3年が経過し、実際に返済が始まった時、被災者の方々の状況によっては返済が難しいという状況も出てきます。法律の施行令第11条には「償還金の支払猶予」が定められています。償還が始まった場合には、実情に応じてこうした猶予制度も適切に運用していただくよう要望しておきます。
続けてお尋ねいたします。
第1に、スクールカウンセラー設置について伺います。
地震発生後の子どもたちの心のケアとして、市立高校では通常のカウンセラー業務で対応されました。小中学校では通常のスクールカウンセラーを拡充配置し、通常よりも手厚い相談体制が取られました。市立幼稚園では、他県の大学のボランティアによる相談体制がつくられました。要するに、市内の市立幼稚園・小中学校・市立高校については、何らかの形で手厚い相談に応えられるような体制が取られました。
今回のスクールカウンセラー配置事業の補正予算9900万円は、小中学校を対象としたスクルールカウンセラー配置の拡充にかかるもので、夏休み前・7月までの配置の分になっています。心のケアは、1学期で必要なくなるという内容のもではないので、その後も必要な相談に手厚く応えていけるような体制の確保が重要と思われます。補正予算部分の事業終了後のカウンセラー体制拡充について、考えをお聞かせください。
また、市内の小中学校同様に、県立高校でも、県の地震対応の補正で災害発生地域の県立高校に対し、スクールカウンセラーの配置拡充が行われました。もともとすべての県立高校には日常スクールカウンセラーが配置されています。ところが、今回の地震では私立高校のスクルールカウンセラー配置拡充は行われておらず、通常業務の範囲で相談業務が行われたことになりますが、昨年度の実績で言えば、市内の私立高校14校のうち2校にはスクールカウンセラーが配置されていません。この点では、今年度の私立高校への配置状況を把握することと、私立高校も含めたスクールカウンセラーの配置拡充と、未配置校への配置が行われるよう、県に対し、申し入れていただきたいと考えますがいかがでしょうか。
第2に、補正予算に「応急対応等経費」として熊本城の応急修繕経費が提案されています。熊本城の損傷は誰もが承知の通り大変な被害を受けており、放置しておけば、まわりへ危険な被害を及ぼすことも考えられるので、一定の応急修理は必要であろうと思います。
今回の熊本地震は、前震・本震という震度7レベルの地震が相次ぎ発生するという未曽有の地震災害であったと同時に、余震がすでに1700回近くも発生するという、想像できない地震災害の様相を呈しています。火山や地震の専門家も様々な形で、今後もかなり大きな余震が襲ってくるという意見を述べられています。だからこそ、応急的に手を付けるべきは、学校施設の応急修理ではないでしょうか。本震によって体育館が避難所として使えなくなったところが24カ所、教育委員会が調べた被害状況調書(5月2日現在)によれば、小学校95校、中学校42校、市立高校2校、市立幼稚園8園から被害報告があり、すべての学校施設が損傷を受けています。すべてを紹介することはできませんが、破損にとどまらず、かなりのところで「さらなる落下の恐れ」「落下しそう」「外壁に近づかないほうがいい」「生徒が入れない」あるいは「隙間があり危険である。緊急を要する」「樹木の倒壊の危険」「天井の扇風機が落ちかけている」「ガラスのヒビ割れ」「壁の亀裂」「金属部品落下の恐れ」などと書かれており、詳細に見れば見るほど、子どもたちが日常過ごす場所としての安全性の確保の問題、今後何らかの理由で避難所としての活用が必要となった場合なども考えると、一刻の放置も許されないのではないかと思います。
今回の補正予算には提案がないものの、学校施設については、復興計画による段階的な修繕・改修だけではなく、急ぎの応急修理が必要ではないかと思います。この点についてはどのようにお考えでしょうか。
第3に、今回の補正予算に「震災復興計画関係経費」が提案されています。有識者会議等も開かれ計画が策定されていくことと思います。今後、金額の面、内容の面でも多岐にわたる復興については、地域や被災者の実情に即し、自由に活用できる財源が必要となってきます。先日県で開かれた「復旧・復興有識者会議」でも「復興基金」のことが話題になっていました。東日本大震災の被害に見舞われた政令市・仙台市では、全国からの寄付金等で市独自に総額279億円の「震災復興基金」がつくられました。今後熊本市が、地域の要求に縦横に応えられるような復興を進めていこうとするとき、「復興基金」の役割は重要と思われます。国としても是非つくってほしいと考えますし、やり方はいろいろあると思います。今後検討されていくであろう「復興基金」について、市長のお考えをお聞かせください。
以上3点、市長ならびに教育長にお尋ね致します。
(答弁)
いよいよ「復興計画」の策定も始まっていきます。応急的な対応から、本格的な復興の時期へとステージが移っていきます。本日、日本共産党市議団として質疑で指摘した点は、求められる対応への改善策のごく一部です。今後は、日本共産党市議団としても設置を要望していた復旧・復興にかかる特別委員会での論議も始まっていきます。今後も様々な場で、被災者の立場に立った支援策の実施を積極的に提案していく立場を表明しまして、質疑を終わります。
限られた持ち時間ではありましたが、日本共産党市議団は、3人で30分の時間を目いっぱい使って、熊本地震への対応の問題点を指摘し、改善を求めました。
私は、①「災害援護資金貸付事業」、②「地震発生後の子どもたちの心のケアとしてのスクールカウンセラー設置問題」、③「学校施設の応急修理」、④「震災復興基金」の4点を質問しました。
【質問内容】は以下のとおり
まず初めに、「災害援護資金貸付事業」に21億6000万円の補正が提案されています。この制度は、そもそも被災者への制度であり、かつ所得制限もあり、生活が大変な方々がその住居や家財などの生活立て直しに利用する制度です。ところが、根拠法令となっている「災害弔慰金の支給等に関する法律」の定めによって、措置期間は無利子であるものの、返済が始まれば年3%の利息を徴収することになっています。中小企業に貸し付けられる「特別融資」は、利息補給によって、3年間は無利子の措置が取られます。そういう対応を見ましても、「災害援護資金貸付」は、最も困った方の利用するであり、利息3%の徴収について、利子補給など、市として何らかの措置を講じて、無利子の貸付けにすることはできないでしょうか。
また、「災害弔慰金の支給等に関する法律」は、昭和48年にできた法律です。その公布当初から、利率3%が定められており、超低金利の今の時代に全くそぐわないものと思われます。また、償還金が期限内に返済できなかった場合は、年利10・75%の違約金まで払わなければならない仕組みになっています。その違約金もまた、法の公布と同時公布された施行令に定められたものです。これら実態に合わない利息や違約金の徴収はやめて、無利子での貸し付け、違約金はとらないよう、被災者に大きな負担を求めるような制度の見直しを国に求めていただきたいと思いますがいかがでしょうか。
(答弁)
「災害援護資金貸付事業」は、被災によって大きなダメージを受けただけでなく、その中でも生活が厳しいであろう方々が利用する制度です。その趣旨に則り、国に対し、利息と違約金徴収の中止を強く求めていただくよう要望します。災害援護資金貸付は、措置期間の3年が経過し、実際に返済が始まった時、被災者の方々の状況によっては返済が難しいという状況も出てきます。法律の施行令第11条には「償還金の支払猶予」が定められています。償還が始まった場合には、実情に応じてこうした猶予制度も適切に運用していただくよう要望しておきます。
続けてお尋ねいたします。
第1に、スクールカウンセラー設置について伺います。
地震発生後の子どもたちの心のケアとして、市立高校では通常のカウンセラー業務で対応されました。小中学校では通常のスクールカウンセラーを拡充配置し、通常よりも手厚い相談体制が取られました。市立幼稚園では、他県の大学のボランティアによる相談体制がつくられました。要するに、市内の市立幼稚園・小中学校・市立高校については、何らかの形で手厚い相談に応えられるような体制が取られました。
今回のスクールカウンセラー配置事業の補正予算9900万円は、小中学校を対象としたスクルールカウンセラー配置の拡充にかかるもので、夏休み前・7月までの配置の分になっています。心のケアは、1学期で必要なくなるという内容のもではないので、その後も必要な相談に手厚く応えていけるような体制の確保が重要と思われます。補正予算部分の事業終了後のカウンセラー体制拡充について、考えをお聞かせください。
また、市内の小中学校同様に、県立高校でも、県の地震対応の補正で災害発生地域の県立高校に対し、スクールカウンセラーの配置拡充が行われました。もともとすべての県立高校には日常スクールカウンセラーが配置されています。ところが、今回の地震では私立高校のスクルールカウンセラー配置拡充は行われておらず、通常業務の範囲で相談業務が行われたことになりますが、昨年度の実績で言えば、市内の私立高校14校のうち2校にはスクールカウンセラーが配置されていません。この点では、今年度の私立高校への配置状況を把握することと、私立高校も含めたスクールカウンセラーの配置拡充と、未配置校への配置が行われるよう、県に対し、申し入れていただきたいと考えますがいかがでしょうか。
第2に、補正予算に「応急対応等経費」として熊本城の応急修繕経費が提案されています。熊本城の損傷は誰もが承知の通り大変な被害を受けており、放置しておけば、まわりへ危険な被害を及ぼすことも考えられるので、一定の応急修理は必要であろうと思います。
今回の熊本地震は、前震・本震という震度7レベルの地震が相次ぎ発生するという未曽有の地震災害であったと同時に、余震がすでに1700回近くも発生するという、想像できない地震災害の様相を呈しています。火山や地震の専門家も様々な形で、今後もかなり大きな余震が襲ってくるという意見を述べられています。だからこそ、応急的に手を付けるべきは、学校施設の応急修理ではないでしょうか。本震によって体育館が避難所として使えなくなったところが24カ所、教育委員会が調べた被害状況調書(5月2日現在)によれば、小学校95校、中学校42校、市立高校2校、市立幼稚園8園から被害報告があり、すべての学校施設が損傷を受けています。すべてを紹介することはできませんが、破損にとどまらず、かなりのところで「さらなる落下の恐れ」「落下しそう」「外壁に近づかないほうがいい」「生徒が入れない」あるいは「隙間があり危険である。緊急を要する」「樹木の倒壊の危険」「天井の扇風機が落ちかけている」「ガラスのヒビ割れ」「壁の亀裂」「金属部品落下の恐れ」などと書かれており、詳細に見れば見るほど、子どもたちが日常過ごす場所としての安全性の確保の問題、今後何らかの理由で避難所としての活用が必要となった場合なども考えると、一刻の放置も許されないのではないかと思います。
今回の補正予算には提案がないものの、学校施設については、復興計画による段階的な修繕・改修だけではなく、急ぎの応急修理が必要ではないかと思います。この点についてはどのようにお考えでしょうか。
第3に、今回の補正予算に「震災復興計画関係経費」が提案されています。有識者会議等も開かれ計画が策定されていくことと思います。今後、金額の面、内容の面でも多岐にわたる復興については、地域や被災者の実情に即し、自由に活用できる財源が必要となってきます。先日県で開かれた「復旧・復興有識者会議」でも「復興基金」のことが話題になっていました。東日本大震災の被害に見舞われた政令市・仙台市では、全国からの寄付金等で市独自に総額279億円の「震災復興基金」がつくられました。今後熊本市が、地域の要求に縦横に応えられるような復興を進めていこうとするとき、「復興基金」の役割は重要と思われます。国としても是非つくってほしいと考えますし、やり方はいろいろあると思います。今後検討されていくであろう「復興基金」について、市長のお考えをお聞かせください。
以上3点、市長ならびに教育長にお尋ね致します。
(答弁)
いよいよ「復興計画」の策定も始まっていきます。応急的な対応から、本格的な復興の時期へとステージが移っていきます。本日、日本共産党市議団として質疑で指摘した点は、求められる対応への改善策のごく一部です。今後は、日本共産党市議団としても設置を要望していた復旧・復興にかかる特別委員会での論議も始まっていきます。今後も様々な場で、被災者の立場に立った支援策の実施を積極的に提案していく立場を表明しまして、質疑を終わります。