
きみをおきてあだし心をわがもたば末の松山浪も越えなむ 古今集 東哥
いかにせん末の松山波こさばみねの初雪消えもこそすれ 匡房
ほとときす末の松山かぜ吹けば波こす暮にたちゐ鳴くなり 俊頼
うかりける昔の末の松山よ波こせとやは思ひ置きけん 俊成
浪こさむ袖とはかねておもひにきすゑの松山たづね見しより 定家
冒頭より、末の松山の歌をご紹介いたしました。
末の松山は松の歌枕。
それは理解している(と、いうか、それが知識として・・)のですが、波という言葉とワンセットになっていることにお気づきかと存じます。
この波は浪であったりするわけですが、波が浪となりますと、これで大きく意味が違ってまいります。
歌の中身を見て見ましょう。
最初にご紹介いたしました。東哥(あずまうた・詠み人知らず)ですが。もう一度。
きみをおきてあだし心をわがもたば末の松山浪も越えなむ
簡単に現代語にいたします。(酔漢風)
君の他に好きな人が出来るだろうか?いやできはしない。
そんな事があったなら、末の松山を大きな波がこえてしまう位の出来事になってしまう。
末の松山を越える浪でも来ない限り君をずっと思っているよ。
(あー照れた・・・独り言・・)
要するに、「末の松山を浪が超えるという不可能な事と同じ位に君の他に好きな人はいないのだ」となります。
この歌の後、「末の松山を越える波の存在」が大きな意味を持ってくるのです。
それを男女の誓いに見立てた求愛の歌が多く作られます。
と、普通の解説では、ここまでなのです。
後程酔漢の視点を加えてみます。
元に戻します。
そして、一番ポイントと考えられる歌がこれなのです。
契りきなかたみに袖をしぼりつゝ末の松山波こさじとは 元輔
この歌を詠みました「元輔」とは「清原元輔」です。
歌を再び現代へ。
約束しただろ!心配なんかいらないよ。互いに泣いて泣いて、着物の袖の涙を絞りながら。
末の松山を浪が超えることなんてないんだよ。僕の気持ちが変わることなんてあるわけないんだ!
(やっぱり照れる・・・・)
この歌ですが、伝承と伝説が交差しております。
多賀城に残る伝説をご紹介いたします。
昔一軒の居酒屋があり、小佐治という19歳の娘盛りの女が働いていた。ある日この店に猩々が現れ、小佐治が酒を与えると喜んで、盃に少々の鮮血をそそいで、頭を下げて出て行った。この鮮血は、唐紅で、幾世を経ても変わらないことから酒代の数倍の値で売れた。店の主人の女房である玉芝が、主人に、今度猩々が来たら刺殺して多くの血を取り黄金に替えようと話していたのを聞いた小佐治は、猩々に忠告したが、仮に命をとられても甘露の味が忘れられないと酒を要求し、もしも我が身がここで死んだら三日のうちに必ず東方から大津波が起こる。その時、あなたは西の方、末の松山に難を避けなさいと教えてくれた。
欲深い玉芝が猩々を酔いつぶれさせて、殺し、鮮血を全身から搾り取った。
死体を袋に入れて、小池に投げ入れた。その後、小佐治が猩々の話を思い出し、はっと思って東方を見ると、真っ暗になったので、津波が押し寄せて来るであろうと、一目散に末の松山目指して走り、やっと松の根に取り付いた時、天地鳴動して二千戸の市街、船舶、人畜共に天に巻き上げられ、怒涛に飲まれ、阿鼻叫喚の声ものすごく、いうべき言葉がなかった。きのうまで上千軒、下千軒と栄えた八幡の町も、とうとう一朝にして砂原と化した。猩々の屍を投げ入れた小池は「猩々ヶ池」と呼ばれている。
一体多賀城に何が起こったのか。
三大実録は貞観地震の記録を数多く残しております。
現代訳をご紹介いたします
貞観11年(869)5月26日、陸奥の国で大地震が起きた。流光が昼のように光り、暫くの間、人々は叫び、立っていることができなかった。ある者は倒れた家の下敷きとなり、ある者は地割れに呑み込まれた。牛や馬が驚いて走り出し、互いに踏みつけあった。城郭、倉、門櫓や牆壁が無数に崩れた。海は、雷鳴のような海鳴りが聞こえて潮が湧きあがり、川が逆流し津波が長く連なって押し寄せ、たちまち城下に達した。海から数十百里の先まで涯も知れず水となり、野原も道もすべて大海原となった。船に乗る暇もなく、山に登ることもできず、千人ほどが溺れ死に、後には資産も田畑も、ほとんど何もなくなった。
ここの「城郭」とは「多賀城」のことであり、逆流した川は「七北川」「砂押川」と推察出来ます。
今一度、歌です。
「波こさじとは」は「多賀城猩々伝説」にある居酒屋の娘「小佐治」ではないか。
斯様な解釈も出来ようかと。
東日本大震災での多賀城市の被害の大きさは、多く知られているところではあるけれど、写真にある現在の「末の松山」は一体どうだったのでしょうか。
国土地理院の資料をここで見てみます。
(写真小さくて申し訳ございませんが)

本当に「末の松山」直前まで津波が押し寄せてきた。これが事実なのです。
この末の松山まで、逃げた人は、先の震災でも数多くおりました。
70m手前まで津波はやって来ております。
清原元輔の歌は、「津浪の伝承」とも受け取れるわけです。
改めて、歴史の深さを思います。
芭蕉の旅に戻ります。
それより野田の玉川・沖の石を尋ぬ
末の松山は 寺を造て末松山といふ
松のあひあひ 皆墓はらにて はねをかはし枝をつらぬる契りの末も 終にはかくのごときと 悲しさも増りて 塩がまの浦に入相のかねを聞
ここでの寺は「末松山宝国寺」と言います。「青竜山円福寺」とは「松島瑞巌寺」のことですが、その末寺にあたります。
もとは「林松寺」「隣障寺」と呼ばれた時代もあるそうですが、八幡邑主天童頼澄(山形天童領主)により再興されて、後に、頼澄の諡号「宝国寺殿」を名乗ります。
松はその境内の一部であって、現在も見事な枝ぶりを見せております。
1719年の記録では「青松数十株」とありますが、芭蕉と曽良は、どのような景色を見ておったのでしょうか。
ところで「末の松山」も、歌枕により後付された名所であるから、その場所も東北地方に4か所もの説があるのです。
今井宗久(NHK黄金の日々でも登場した大阪堺の商人、茶人。丹波哲郎さんが演じておられました)の記した「都のつと」にはこうあります。
多賀国府にもなりぬ。それよりおくのほそ道といふ方を南ざまに末の松山にたづねゆきぬ
とあります。場所的にほぼ一致しております。なにより、津波伝説が、その理由には成らないかもしれませんが、指向として多賀城の現在地がしっくりくるのは当然だと考えます。
未ノ尅、塩竈ニ着、湯漬など喰。末ノ松山・興井・野田玉川・おも ハくの橋・浮嶋等ヲ見廻リ帰 。
曽良の日記にはこう記されております。
塩竈。
故郷の地名が出てまいりました。
塩がまの浦に入相のかねを聞
どこの寺の鐘なのだろうか。
千賀浦(塩竈)からの海風が多賀城まで届いてくる。
自転車で。そんな夕日の気色を走っておりました。
冒頭の写真はひーさんから頂戴いたしました。
この場ですが、改めて御礼申し上げます。
いかにせん末の松山波こさばみねの初雪消えもこそすれ 匡房
ほとときす末の松山かぜ吹けば波こす暮にたちゐ鳴くなり 俊頼
うかりける昔の末の松山よ波こせとやは思ひ置きけん 俊成
浪こさむ袖とはかねておもひにきすゑの松山たづね見しより 定家
冒頭より、末の松山の歌をご紹介いたしました。
末の松山は松の歌枕。
それは理解している(と、いうか、それが知識として・・)のですが、波という言葉とワンセットになっていることにお気づきかと存じます。
この波は浪であったりするわけですが、波が浪となりますと、これで大きく意味が違ってまいります。
歌の中身を見て見ましょう。
最初にご紹介いたしました。東哥(あずまうた・詠み人知らず)ですが。もう一度。
きみをおきてあだし心をわがもたば末の松山浪も越えなむ
簡単に現代語にいたします。(酔漢風)
君の他に好きな人が出来るだろうか?いやできはしない。
そんな事があったなら、末の松山を大きな波がこえてしまう位の出来事になってしまう。
末の松山を越える浪でも来ない限り君をずっと思っているよ。
(あー照れた・・・独り言・・)
要するに、「末の松山を浪が超えるという不可能な事と同じ位に君の他に好きな人はいないのだ」となります。
この歌の後、「末の松山を越える波の存在」が大きな意味を持ってくるのです。
それを男女の誓いに見立てた求愛の歌が多く作られます。
と、普通の解説では、ここまでなのです。
後程酔漢の視点を加えてみます。
元に戻します。
そして、一番ポイントと考えられる歌がこれなのです。
契りきなかたみに袖をしぼりつゝ末の松山波こさじとは 元輔
この歌を詠みました「元輔」とは「清原元輔」です。
歌を再び現代へ。
約束しただろ!心配なんかいらないよ。互いに泣いて泣いて、着物の袖の涙を絞りながら。
末の松山を浪が超えることなんてないんだよ。僕の気持ちが変わることなんてあるわけないんだ!
(やっぱり照れる・・・・)
この歌ですが、伝承と伝説が交差しております。
多賀城に残る伝説をご紹介いたします。
昔一軒の居酒屋があり、小佐治という19歳の娘盛りの女が働いていた。ある日この店に猩々が現れ、小佐治が酒を与えると喜んで、盃に少々の鮮血をそそいで、頭を下げて出て行った。この鮮血は、唐紅で、幾世を経ても変わらないことから酒代の数倍の値で売れた。店の主人の女房である玉芝が、主人に、今度猩々が来たら刺殺して多くの血を取り黄金に替えようと話していたのを聞いた小佐治は、猩々に忠告したが、仮に命をとられても甘露の味が忘れられないと酒を要求し、もしも我が身がここで死んだら三日のうちに必ず東方から大津波が起こる。その時、あなたは西の方、末の松山に難を避けなさいと教えてくれた。
欲深い玉芝が猩々を酔いつぶれさせて、殺し、鮮血を全身から搾り取った。
死体を袋に入れて、小池に投げ入れた。その後、小佐治が猩々の話を思い出し、はっと思って東方を見ると、真っ暗になったので、津波が押し寄せて来るであろうと、一目散に末の松山目指して走り、やっと松の根に取り付いた時、天地鳴動して二千戸の市街、船舶、人畜共に天に巻き上げられ、怒涛に飲まれ、阿鼻叫喚の声ものすごく、いうべき言葉がなかった。きのうまで上千軒、下千軒と栄えた八幡の町も、とうとう一朝にして砂原と化した。猩々の屍を投げ入れた小池は「猩々ヶ池」と呼ばれている。
一体多賀城に何が起こったのか。
三大実録は貞観地震の記録を数多く残しております。
現代訳をご紹介いたします
貞観11年(869)5月26日、陸奥の国で大地震が起きた。流光が昼のように光り、暫くの間、人々は叫び、立っていることができなかった。ある者は倒れた家の下敷きとなり、ある者は地割れに呑み込まれた。牛や馬が驚いて走り出し、互いに踏みつけあった。城郭、倉、門櫓や牆壁が無数に崩れた。海は、雷鳴のような海鳴りが聞こえて潮が湧きあがり、川が逆流し津波が長く連なって押し寄せ、たちまち城下に達した。海から数十百里の先まで涯も知れず水となり、野原も道もすべて大海原となった。船に乗る暇もなく、山に登ることもできず、千人ほどが溺れ死に、後には資産も田畑も、ほとんど何もなくなった。
ここの「城郭」とは「多賀城」のことであり、逆流した川は「七北川」「砂押川」と推察出来ます。
今一度、歌です。
「波こさじとは」は「多賀城猩々伝説」にある居酒屋の娘「小佐治」ではないか。
斯様な解釈も出来ようかと。
東日本大震災での多賀城市の被害の大きさは、多く知られているところではあるけれど、写真にある現在の「末の松山」は一体どうだったのでしょうか。
国土地理院の資料をここで見てみます。
(写真小さくて申し訳ございませんが)

本当に「末の松山」直前まで津波が押し寄せてきた。これが事実なのです。
この末の松山まで、逃げた人は、先の震災でも数多くおりました。
70m手前まで津波はやって来ております。
清原元輔の歌は、「津浪の伝承」とも受け取れるわけです。
改めて、歴史の深さを思います。
芭蕉の旅に戻ります。
それより野田の玉川・沖の石を尋ぬ
末の松山は 寺を造て末松山といふ
松のあひあひ 皆墓はらにて はねをかはし枝をつらぬる契りの末も 終にはかくのごときと 悲しさも増りて 塩がまの浦に入相のかねを聞
ここでの寺は「末松山宝国寺」と言います。「青竜山円福寺」とは「松島瑞巌寺」のことですが、その末寺にあたります。
もとは「林松寺」「隣障寺」と呼ばれた時代もあるそうですが、八幡邑主天童頼澄(山形天童領主)により再興されて、後に、頼澄の諡号「宝国寺殿」を名乗ります。
松はその境内の一部であって、現在も見事な枝ぶりを見せております。
1719年の記録では「青松数十株」とありますが、芭蕉と曽良は、どのような景色を見ておったのでしょうか。
ところで「末の松山」も、歌枕により後付された名所であるから、その場所も東北地方に4か所もの説があるのです。
今井宗久(NHK黄金の日々でも登場した大阪堺の商人、茶人。丹波哲郎さんが演じておられました)の記した「都のつと」にはこうあります。
多賀国府にもなりぬ。それよりおくのほそ道といふ方を南ざまに末の松山にたづねゆきぬ
とあります。場所的にほぼ一致しております。なにより、津波伝説が、その理由には成らないかもしれませんが、指向として多賀城の現在地がしっくりくるのは当然だと考えます。
未ノ尅、塩竈ニ着、湯漬など喰。末ノ松山・興井・野田玉川・おも ハくの橋・浮嶋等ヲ見廻リ帰 。
曽良の日記にはこう記されております。
塩竈。
故郷の地名が出てまいりました。
塩がまの浦に入相のかねを聞
どこの寺の鐘なのだろうか。
千賀浦(塩竈)からの海風が多賀城まで届いてくる。
自転車で。そんな夕日の気色を走っておりました。
冒頭の写真はひーさんから頂戴いたしました。
この場ですが、改めて御礼申し上げます。















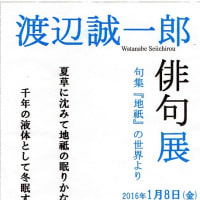










さて猩々ヶ池の説話ですが、民俗学的にみれば、この話は異種による恩返し譚です。類例は蘇民将来のような異人や貴人の場合もあります。とにかくまれびとに親切にする事によって、厄災から逃れるというパターンですね。
それだけじゃ味も素っ気もないので、酔漢さんからのお許しも出ているし、私見ですがちょっとばかり推察してみましょう。
まず出典は「多賀城市史」にある明治生まれの方の口伝のようです。
八幡の戸数が二千戸とあるのですが、明治二十二年に多賀城村が出来た時、戸数は590戸で人口4543人です。白髪三千丈というか相当な誇張ですね。古代や中世の村落について知識がなかった事もあるのでしょうし、かつてはそれほど繁栄していたんだという自負も感じます。つまり説話が作られた時、すでに多賀城の繁栄は終わっていた。口伝にはわざわざ八幡が「沖の井の里」と呼ばれていた頃とあるし、沖の井、末の松山と有名な歌枕をふたつも織り込んでいる事から、歌枕が名所として整備された後、まさに酔漢さんが今書かれている時代を過ぎた辺りに語られた印象を受けます。
また猩々ですが、そもそも中国の怪であり、日本霊異記にも今昔物語にも出てこないようです。あの鳥山石燕も描いていません。和漢三才図絵にはありますが、これは博物誌のようなものですから、図を見る限りオランウータンでしょう。ともかく猩々を漢籍に通じていない庶民が知るのは、能の「猩々」など芸能(庶民は能そのものより謡ですね)の世界からです。説話にある猩々が酒好きというのは、明らかに能の影響でしょう。そんな芸能を庶民が楽しむようになるのは江戸期からです。
更に酒ですが、中世期、良い酒は寺社が造っていました。寺社の財力は酒の専売や高利貸しなど、俗世の欲にどっぷりとつかっていた時代です。ですから近世以前に猩々が好むほどの名酒を庶民が手に入れるのは難しい。江戸期ですら名酒は上方の下り酒で庶民が常飲できるものではない。手作りの名酒があったという考えもあるでしょう。各地方にそういう名人話はあります。ただ普通に考えれば、貴重な米をわざわざ酒にする贅沢は貨幣経済が安定する江戸期以降の発想であり、それ以前の庶民は屑米を酒にし、名酒など生まれようもない筈です。
これらから考えると、比較的新しい時代、おそらくは江戸期に成立した説話だと推測します。
なので津波に関して元となるものがあるとしても、慶長の大津波でしょう。
その時代となると「猩々」は「少将」の言い換えかも知れません。慶長の頃、伊達政宗の官位は少将だと思います。説話にある八幡は天童氏が領有し、広大な下屋敷を作ったのはその頃ですね。
もしかすると政宗による急激な変革(築城や運河などいろいろやりました)と相次ぐ天変地異(この頃に計三度も仙台藩は津波の被害を受けていますし、全国的にも大地震や大噴火と大変な時期です)を、保守的な庶民たちは何らかの天罰であると揶揄し、その一端がこの説話に反映されているのかもしれません。
問題は「小佐治」です。女性の名にしては妙ですね。
名取市には京から来た公家の「小佐治」(男ですが)と幾世という女性との悲恋話が残っています。性の違いはありますが、名前が完全に一致しています。しかし限られた時間と資料では残念ながらつながりは見えてきませんでした。
もちろん貞観の地震や津波の話が原型にあり、後世の人が変化させたと考えられなくもないのですが、大事なのは口伝だという事でしょう。だからこそ時代感が反映されやすい。その時代感が色濃く出ているのは上記の通り、江戸期です。
いずれにしても、知的遊びですから、どうせ正解はないので。あしからず。
なるほど!ですね。
最初の「違和感」はそのまま表現した方が良いのかと。
これは、いつもの癖で、「自分が引いてしまう」悪癖だと自覚しているところなのですが。
多賀城だけを今後フィーチャーして行こうかと思ってます。
これも膨大な資料と時間がかかることなのですが。
ぼちぼちやって行こうかと思ってますよ。
コメントの内容には、また別途本編で語りたいと思ってます。
寒くなるし、忙しくもなりますね。
御身お大事にね。