呉での牧野茂を前回末に登場させております。この牧野さんをはじめ大和建造に関わった中心的な人物は戦後からそしてこの20数年前まで御生存でございましたので、超極秘資料であった大和設計資料ですが、多くを語る機会に恵まれるのでした。
それを、ここで少し整理してみようと思います。
以前、「友鶴事件」を語りました。海軍を揺るがした事件としてあまりにも有名な事件です。この事件後「藤本喜久雄」が艦政部から追われ、翌年亡くなった話を致しましたが、これにも、深い事実があるのです。
牧野さんは自身の回顧録でこう述べておられます
「藤本さんの設計は固定観念にとらわれない自由な観点から構造強度設計を試み、理論的に慎重に検討を加えて、思い切ってぎりぎりの線まで持っていく・・・そんなかんじでした」(前間孝則著 戦艦大和 誕生 より抜粋)と。そして自ら著した「牧野茂艦船ノート」では「計画方針は、用兵家の要求は万難を排して、これを実現するのが造船かの任務であり、不用意に拒否してはならないということであった。そのためにはあらゆる努力工夫をして、当時には奇策の類することも考案された。だからこのような難局に処して、内外の信望を集めて独力で活路を開き、闊達に腕を振うことができたが、事志と違って賽の目は裏目裏目ところがり続けたわけであった(中略)しかし、藤本設計画主任において、最も惜しまれ、また大いに責められるべきことは、復原性能についても、船体構造強度についても、新境地を開拓して、これを掛替えのない実験に適用するに際しては、その行き過ぎを規制する歯止めの要素についての見当が適切を欠いたがため、怒涛の如く押し寄せる個艦の戦力向上の要求の前に、ついに超えてはならぬ限度を超え、多数の欠陥計画を生むに至り」と著しておられます。
何故酔漢が平賀譲、藤本喜久雄との確執を最初に語ったかと申しますと、20数年前の「ヤングジャンプ 『栄光無き天才たち 平賀譲編』」を読んでからでした。
この劇画での藤本は「ちょび髭で小太り」(実際はそうなのですが・・)の軍の言いなりになって、自ら墓穴を掘った悪者否馬鹿者のような描き方をされておりました。平賀が天才であり、平賀が全てであるようなニュアンスもあります。確かに、平賀は天才であり努力家であり平賀なくしては、日本の艦艇はこれほど進化しなかったのも事実です。ですが、藤本喜久雄の評価があまりにも低く見られ、それに対するアンチテーゼをしたくなったのです。
調べてみますと、藤本の斬新なアイデイアは評価に値する価値が多く残されております。
牧野語録を紐解きます。二人の仲をこう表現しております。
「互いに胸襟を開いて論議を尽くし、研究を重ねるには余りにも自尊心が強く、独創性と性格の相違のために、相反発するものがあり」とあります。
明治44年東大造船科をを主席で卒業した藤本です。平賀の期待も大きかったのでしょうが、天才肌(藤本)と努力型(平賀)ではやはり大きな違いがあったのかと察します。
平賀先生のエピソードです。東大造船科謝恩会会場。場が大いに盛り上がっております。遅れて到着の平賀。
「先生、何か一言をお願いします。さっきから失敗談とかで盛り上がっております」
「俺が失敗などするか」でした。
この自尊心の強さが「平賀不譲」と呼ばれる所以だったのです。
牧野は平賀を尊敬していたことは事実です。が艦政では藤本の部下。
「藤本設計には常人とは思ひもつかないひらめきがあった」と評しております。
そして、この確執が「大和建造紆余曲折」の原点でもあると酔漢は考えるのです。
「第四艦隊事件の要因」に「電気溶接」も上げられます。これは船の軽量化には必要な技術です。簡単に申し上げますれば(技術に疎いので申し訳ございません)鋲で鉄板を固定するには鉄板を重ね合わせる事が必要です。例えば紙を糊付けする際には「のりしろ」が必要なのと同じです。その分紙は厚くなります。鉄板を鋲で接続すればそれだけ重量がかさみます。
今後、大和建造の主人公となる「西島亮二」です。(彼がいなかったら大和は出来ておりません)
(友鶴事件の後艦体破壊事件「第四艦隊事件」が発生します⇒詳細は割愛いたします)その査問委員会の席上、西島は平賀から「艦体が折れたのは電気溶接を無闇に使用したからだ」と指摘されています。
「電気溶接を濫用し著大な欠陥を見るに至る理由は、実に遺憾なりと言えども、おそらくは簡単にテストピースの結果良好なるに惑溺して、ストラクチャの性質に留意せざりしに基づくものならん」(軍艦総長平賀譲より)としております。
この平賀の思想が日本の建艦が世界に大きく遅れを取ることにもなったのでした。
先に紹介した西島ですが、やはり電気溶接を必要と考えており、横須賀工匠では福田烈をはじめ電気溶接の研究を日々行っていたのでした。
「電気溶接を船体構造に使える時機はもう来ませんか」と福田。
「そんなことはない。使える時機は必要である」とぶっきらぼうに平賀。
「いつごろでしょう」
「冷たい溶接が出来ればの話だが・・・」
会議場は爆笑。
平賀の溶接嫌いは後に解決しているのだが、「溶接まかりならん」という「船体構造電気溶接使用方針」が制定されたのが昭和11年1月の事でした。
前回「A140F5」が大和最終決定とお話いたしました。そしてディーゼルからタービンエンジンに変更になったことも。この決定の過程を福田啓二設計主任と江崎直吉という技術者。そして平賀で決定のように語りました。が、この史実にも大きな裏がございます。
渋谷隆太郎技術中将は最後までディーゼルにこだわります。
「平賀造船中将が突如として、おそれ多き方に進言したことがもととなり、設計責任者に一言の挨拶もなく、ディーゼルをタービンに置き換える動機を造ったのである」と証言されております。
「畏れ多き方」とは「伏見宮博恭王」を指します。
これが史実かどうか定かではありません。が、ディーゼル機関推進者からすれば、併用として決定していた事を直前で覆されたとの思いが強かったのでしょう。
ですが、修理不能は事実だったのは確かです。
このような話が出ることが「友鶴事件」後の平賀の力を物語るものだと思います。
日本のディーゼル技術はドイツに大きく遅れを取るのでした。
技術的な建艦の話は詳しくもなく、祖父を中心に海軍を語ろうと「祖父・海軍そして大和」と致しました。ですが、器として兵器としての大和を語らなければ、そしてそれを知らなければ「大和の話」が「片手落ち」となるような気が致しました。
ですが、多くを調べております内に技術者達の葛藤たるや物凄いものがあると気づきました。
「洋食好きな牧野」として登場させておりますが。実は呉においても艦政部とは繫がっておりますし、設計主任福田啓二、艦政部の「生ける計算尺」と称された「松本喜太郎」とも旧知の仲です。知らないわけはございません。
ですが、呉への転勤の際の本人の弁がこうでした
「平賀さんの信望が厚かったからかもしれませんが、村上造船大佐の采配だったでしょう。私の後呉海軍工廠造船部長として着任されてますから」
「その五」からは呉が舞台です。
「設計の牧野、現場の西島」この話を語ります。
最後に酔漢が大和建造を語る動機となりました「牧野茂」の言葉です。
「戦艦大和は、沈んでしまって今日でも不沈艦と呼ばれ、国民から親しまれている。大変嬉しい呼び名であるが、複雑な心境に私は陥る。
大和の建造の途中から用兵側から、不沈艦と言われ出したようである。私には苦々しく聞こえたが、大和基本計画主任の福田啓二さんまでが、いつのまにか時々、不沈艦という言葉を使われたのには驚きを禁じえなかった。
私は大和設計の初めから、不沈艦ではあり得ないと信じていたが、大和も武蔵も沈没してしまった今、大和をもう少し不沈艦に近づける手段があったのではないかと思う。前後部の無防御部の構造に、思い切って重量を与えて、重厚な構造にしたならば、少なくても武蔵の場合は、シブヤン海の海戦では、海底の藻屑と消えずに済んだのではなかったか。建造当時の私の主宰した設計を顧みての話である」
祖父を初め3000名近く戦死した「坊の崎海戦」
大和の構造を知ることも、「その原因の手がかりになるのでは」と考えた牧野茂先生の言葉だったのです。
もしかしたら祖父は死なずに済んだのかとも・・正直そうした思いもございます。
最後に
「平賀先生を神様扱いする向きもあるようだが、神様といっちゃ困るよね」とも。
(牧野茂艦船ノート⇒前間孝則著戦艦大和誕生より)
昭和56年冬。塩竈港。
「酔漢、明日っしゃ宗谷来るのっしゃ」と突然丹治氏から電話。
「明日すか、んで一緒にみさぁいくべ」
となります。
「砕氷艦宗谷」の現役引退で、各地の港で一般公開されるのでした。
丹治さんと宗谷内を一周。
最後に向いの岩壁から
仙台一高と仙台向山応援スタイルでエールを送りました。(だれ「おしょすい」どこでねぇべさぁ。)
「宗谷って確か・・・」
「牧野茂の造った船だったすぺ」
本日語りました事は
「前間孝則著 戦艦大和誕生 上 西島技術大佐の大仕事 1997年9月5日 第一刷発行 発行者 野間佐知子 発行所 講談社」より抜粋参考とさせていただいております。
それを、ここで少し整理してみようと思います。
以前、「友鶴事件」を語りました。海軍を揺るがした事件としてあまりにも有名な事件です。この事件後「藤本喜久雄」が艦政部から追われ、翌年亡くなった話を致しましたが、これにも、深い事実があるのです。
牧野さんは自身の回顧録でこう述べておられます
「藤本さんの設計は固定観念にとらわれない自由な観点から構造強度設計を試み、理論的に慎重に検討を加えて、思い切ってぎりぎりの線まで持っていく・・・そんなかんじでした」(前間孝則著 戦艦大和 誕生 より抜粋)と。そして自ら著した「牧野茂艦船ノート」では「計画方針は、用兵家の要求は万難を排して、これを実現するのが造船かの任務であり、不用意に拒否してはならないということであった。そのためにはあらゆる努力工夫をして、当時には奇策の類することも考案された。だからこのような難局に処して、内外の信望を集めて独力で活路を開き、闊達に腕を振うことができたが、事志と違って賽の目は裏目裏目ところがり続けたわけであった(中略)しかし、藤本設計画主任において、最も惜しまれ、また大いに責められるべきことは、復原性能についても、船体構造強度についても、新境地を開拓して、これを掛替えのない実験に適用するに際しては、その行き過ぎを規制する歯止めの要素についての見当が適切を欠いたがため、怒涛の如く押し寄せる個艦の戦力向上の要求の前に、ついに超えてはならぬ限度を超え、多数の欠陥計画を生むに至り」と著しておられます。
何故酔漢が平賀譲、藤本喜久雄との確執を最初に語ったかと申しますと、20数年前の「ヤングジャンプ 『栄光無き天才たち 平賀譲編』」を読んでからでした。
この劇画での藤本は「ちょび髭で小太り」(実際はそうなのですが・・)の軍の言いなりになって、自ら墓穴を掘った悪者否馬鹿者のような描き方をされておりました。平賀が天才であり、平賀が全てであるようなニュアンスもあります。確かに、平賀は天才であり努力家であり平賀なくしては、日本の艦艇はこれほど進化しなかったのも事実です。ですが、藤本喜久雄の評価があまりにも低く見られ、それに対するアンチテーゼをしたくなったのです。
調べてみますと、藤本の斬新なアイデイアは評価に値する価値が多く残されております。
牧野語録を紐解きます。二人の仲をこう表現しております。
「互いに胸襟を開いて論議を尽くし、研究を重ねるには余りにも自尊心が強く、独創性と性格の相違のために、相反発するものがあり」とあります。
明治44年東大造船科をを主席で卒業した藤本です。平賀の期待も大きかったのでしょうが、天才肌(藤本)と努力型(平賀)ではやはり大きな違いがあったのかと察します。
平賀先生のエピソードです。東大造船科謝恩会会場。場が大いに盛り上がっております。遅れて到着の平賀。
「先生、何か一言をお願いします。さっきから失敗談とかで盛り上がっております」
「俺が失敗などするか」でした。
この自尊心の強さが「平賀不譲」と呼ばれる所以だったのです。
牧野は平賀を尊敬していたことは事実です。が艦政では藤本の部下。
「藤本設計には常人とは思ひもつかないひらめきがあった」と評しております。
そして、この確執が「大和建造紆余曲折」の原点でもあると酔漢は考えるのです。
「第四艦隊事件の要因」に「電気溶接」も上げられます。これは船の軽量化には必要な技術です。簡単に申し上げますれば(技術に疎いので申し訳ございません)鋲で鉄板を固定するには鉄板を重ね合わせる事が必要です。例えば紙を糊付けする際には「のりしろ」が必要なのと同じです。その分紙は厚くなります。鉄板を鋲で接続すればそれだけ重量がかさみます。
今後、大和建造の主人公となる「西島亮二」です。(彼がいなかったら大和は出来ておりません)
(友鶴事件の後艦体破壊事件「第四艦隊事件」が発生します⇒詳細は割愛いたします)その査問委員会の席上、西島は平賀から「艦体が折れたのは電気溶接を無闇に使用したからだ」と指摘されています。
「電気溶接を濫用し著大な欠陥を見るに至る理由は、実に遺憾なりと言えども、おそらくは簡単にテストピースの結果良好なるに惑溺して、ストラクチャの性質に留意せざりしに基づくものならん」(軍艦総長平賀譲より)としております。
この平賀の思想が日本の建艦が世界に大きく遅れを取ることにもなったのでした。
先に紹介した西島ですが、やはり電気溶接を必要と考えており、横須賀工匠では福田烈をはじめ電気溶接の研究を日々行っていたのでした。
「電気溶接を船体構造に使える時機はもう来ませんか」と福田。
「そんなことはない。使える時機は必要である」とぶっきらぼうに平賀。
「いつごろでしょう」
「冷たい溶接が出来ればの話だが・・・」
会議場は爆笑。
平賀の溶接嫌いは後に解決しているのだが、「溶接まかりならん」という「船体構造電気溶接使用方針」が制定されたのが昭和11年1月の事でした。
前回「A140F5」が大和最終決定とお話いたしました。そしてディーゼルからタービンエンジンに変更になったことも。この決定の過程を福田啓二設計主任と江崎直吉という技術者。そして平賀で決定のように語りました。が、この史実にも大きな裏がございます。
渋谷隆太郎技術中将は最後までディーゼルにこだわります。
「平賀造船中将が突如として、おそれ多き方に進言したことがもととなり、設計責任者に一言の挨拶もなく、ディーゼルをタービンに置き換える動機を造ったのである」と証言されております。
「畏れ多き方」とは「伏見宮博恭王」を指します。
これが史実かどうか定かではありません。が、ディーゼル機関推進者からすれば、併用として決定していた事を直前で覆されたとの思いが強かったのでしょう。
ですが、修理不能は事実だったのは確かです。
このような話が出ることが「友鶴事件」後の平賀の力を物語るものだと思います。
日本のディーゼル技術はドイツに大きく遅れを取るのでした。
技術的な建艦の話は詳しくもなく、祖父を中心に海軍を語ろうと「祖父・海軍そして大和」と致しました。ですが、器として兵器としての大和を語らなければ、そしてそれを知らなければ「大和の話」が「片手落ち」となるような気が致しました。
ですが、多くを調べております内に技術者達の葛藤たるや物凄いものがあると気づきました。
「洋食好きな牧野」として登場させておりますが。実は呉においても艦政部とは繫がっておりますし、設計主任福田啓二、艦政部の「生ける計算尺」と称された「松本喜太郎」とも旧知の仲です。知らないわけはございません。
ですが、呉への転勤の際の本人の弁がこうでした
「平賀さんの信望が厚かったからかもしれませんが、村上造船大佐の采配だったでしょう。私の後呉海軍工廠造船部長として着任されてますから」
「その五」からは呉が舞台です。
「設計の牧野、現場の西島」この話を語ります。
最後に酔漢が大和建造を語る動機となりました「牧野茂」の言葉です。
「戦艦大和は、沈んでしまって今日でも不沈艦と呼ばれ、国民から親しまれている。大変嬉しい呼び名であるが、複雑な心境に私は陥る。
大和の建造の途中から用兵側から、不沈艦と言われ出したようである。私には苦々しく聞こえたが、大和基本計画主任の福田啓二さんまでが、いつのまにか時々、不沈艦という言葉を使われたのには驚きを禁じえなかった。
私は大和設計の初めから、不沈艦ではあり得ないと信じていたが、大和も武蔵も沈没してしまった今、大和をもう少し不沈艦に近づける手段があったのではないかと思う。前後部の無防御部の構造に、思い切って重量を与えて、重厚な構造にしたならば、少なくても武蔵の場合は、シブヤン海の海戦では、海底の藻屑と消えずに済んだのではなかったか。建造当時の私の主宰した設計を顧みての話である」
祖父を初め3000名近く戦死した「坊の崎海戦」
大和の構造を知ることも、「その原因の手がかりになるのでは」と考えた牧野茂先生の言葉だったのです。
もしかしたら祖父は死なずに済んだのかとも・・正直そうした思いもございます。
最後に
「平賀先生を神様扱いする向きもあるようだが、神様といっちゃ困るよね」とも。
(牧野茂艦船ノート⇒前間孝則著戦艦大和誕生より)
昭和56年冬。塩竈港。
「酔漢、明日っしゃ宗谷来るのっしゃ」と突然丹治氏から電話。
「明日すか、んで一緒にみさぁいくべ」
となります。
「砕氷艦宗谷」の現役引退で、各地の港で一般公開されるのでした。
丹治さんと宗谷内を一周。
最後に向いの岩壁から
仙台一高と仙台向山応援スタイルでエールを送りました。(だれ「おしょすい」どこでねぇべさぁ。)
「宗谷って確か・・・」
「牧野茂の造った船だったすぺ」
本日語りました事は
「前間孝則著 戦艦大和誕生 上 西島技術大佐の大仕事 1997年9月5日 第一刷発行 発行者 野間佐知子 発行所 講談社」より抜粋参考とさせていただいております。















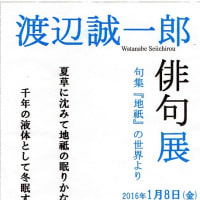

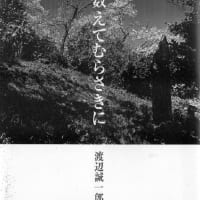







酔漢さんのお話からして、小生が高校二年の時でしょうか。
大和の主機がタービンになったのが伏見宮の承認で決ったという話は、初めて知りました。
ある時期、海軍人事の意思決定に際しては殿下と元帥の承認を得ることが慣例になっていたそうです。
この場合の殿下とは、もちろんのこと「伏見宮殿下」。元帥は同じく「東郷元帥」です。
人事だけではなかったのですね。
酔漢さんのお話に登場する造船武官のうち、一番最近まで御健在でいらしたのは、牧野さんだったでしょうか。
坊之岬沖に眠る大和の映像が撮られたのは、そう遠い昔の話ではありませんでしたね。
その映像を牧野茂さんだったか福井静雄さんだったかが見た時の話を新聞か週刊誌で読んだことがあります。
「なるほど、ここがこう壊れたか・・・」と、飽くまでも技術者の視点であったとか。
「愛着がある艦(ふね)への愛惜が聞けなかったのが意外」と言わんばかりの記者の筆でした。
実を言うと、小生もいささか意外だったのです。
しかし「どのように作ったものが、どのように壊れたか」・・・
技術者にしてみれば、しごく当然の問題意識ですね。
不沈化対策については、黛治夫氏が一家言持っていたそうです。
黛さんには大和副長の経歴もあり、レイテ海戦の際は重巡洋艦「利根」の艦長でした。
スカゲラック海戦の折、ドイツの巡洋戦艦「ザイトリッツ」は21発の大口径砲弾と魚雷一発の命中を受けながらも、帰投しました。
写真を見ると、喫水が西條甲板すれすれになっています。
シブヤン海で落伍した「武蔵」の護衛を命じられた「利根」艦長・黛大佐は「ザイドリッツ」の戦訓に鑑み、浮力保全に務められたしと信号を送っています。
また何の折だったか忘れましたが、「水密区画に桐材を詰め込んで浮力保持を図れ」と提言したことがあったかと思います。
あまりにも突飛な発想だったので無視されたそうですが・・・
パイセスⅡでの捜索映像をご覧になった時の福井さんの感想だったと思います。雑誌「丸」にも掲載されておりました。学研歴史群像でも同様な技術的視点から解説されておいででした。
「信濃」設計に大きく携わった方です。
不幸極まりない空母でしたが3番艦として横須賀の岩壁に踊る姿を見たかったというのは本当に野次馬的発想ですね。⇒このコメントでは、くだまき大和編の趣旨とは離れてしまいます。
しかして、建造過程は酔漢の勉強不足のところ多々でございます。
今後も訂正、補足よろしくお願いいたします。
小生がドイツにいた折、阿川弘之さんと海軍予備学生で同期だったという方と知合いました。
この方は横須賀軍港に浮ぶ信濃を見たことがあったそうです(呉に向けて出港する時だったかもしれません)。
そういえば「信濃」の護衛についていた駆逐艦は「雪風」と「浜風」と「磯風」だったでしょうか。
天一号作戦で「大和」に随伴した駆逐艦と同じだということに、因縁めいたものを感じます。
「信濃」については、確か豊田穣さんが書いていましたね。
朝日ソノラマ文庫(絶版)か光人社NF文庫に入っていたような気がします。
アメリカの潜水艦の名前で唯一酔漢が知っている名前です。
魚雷二発。大和型がこれで沈むわけは無いのです。大きな理由が隠されているようにしか見えませんが、誰も言う人はおりません。
責任問題も友鶴より甘かったのは軍としても言い逃れができなかった状況がございます。
最も沈没の原因究明が必要だった艦ではなかったかと思います。
ですが、あまりにも文献が少ないのも事実です。
少し、勉強してみます。
水密区画の試験が終了していなかったと思います。
それと米潜が発射した魚雷の深度調整が何らかの理由で浅く、バルジよりも上に命中したことによると、物の本で読んだ覚えがあります。
そうでもなければ、魚雷二発ごときで沈むはずがありません。
魚雷一発の命中に対し、反対舷に駆逐艦一杯分の海水を入れてバランスを取り、トラックに入稿した・・・
あの「大和」の姉妹艦です。
それと護衛の駆逐艦長たちが潜水艦に細くされにくい陸岸に沿った航路を提案したのに、
「信濃」の阿部艦長が呉入港の期日にこだわって沖に出る航路を採用した・・・
これも原因といえば原因ですね。
もっとも造船や応急の技術問題からははずれますが。
それは、塩竃で船を見たから湧いた興味でしょうか?
宗谷は知っていても設計者はわかりませんね。
また、新たな人物が登場ですね。
信濃が呉に向った理由。
西島が「最終工程を呉で」と話したからでした。牧野もそうです。
この一言がなかったら「呉へ向う信濃はなかった」とは本人の回顧録にありました。
今しがた確認いたしました。
船を底から見上げる迫力と物凄い轟音は忘れません。
しかして、漁船であっても、子供心に「かつお船」はかっこよく、「まぐろ船」は大きくて広く、「北洋船」はずんぐりむっくり。
そんな感覚があったかもしれません。
船は身近なものでした。
貨物船を見たり、客船の入港には必ず自転車で埠頭へ出かけておりました。
「誰がつくったのっしゃ?」
子供の頃、東北ドック設計課へ連れていってもらったときの質問でした。
「ここにいるみんなして作ってんのっしゃ」
当時の課長さんの言葉でした。
資材不足、熟練工不足で、艦の完成度は最低でした。
防水区画用のハッチも密閉できない状態での出航だったようです。
おまけに艦に精通している人間がおらず、雷撃を受けた後の対応も出来なかったようです。
米潜水艦の雷撃能力が上がり、大型艦に対してはより浅い位置へ命中するよう調整しておりました。
たぶん浸水海水量をより多くするためでしょうかね。
スクリュー音などもより小さくなり、雪風を始めとする護衛駆逐艦は事前に発見できなかったようです。
信濃の飛行甲板から沈没前に飛び立った唯一の艦載機は「紫電改」だったそうです。
「紫電改のタカ」のラストシーン、おはぎのエピソードは何度も読み返しました。
豊田穣さんの『空母信濃の生涯』ですが、光人社NF文庫に入っています。
絶版にはなっていないと思います。
小生も読み返し始めました。
マリアナ沖海戦で「大鳳」「翔鶴」「飛鷹」の三隻を失った結果、
昭和20年2月完成予定だった「信濃」を昭和19年11月だかまでに完成させろということになったようです。
呉での完工、水密試験の未了・・・すべては工期の繰上げに起因するような気がします。