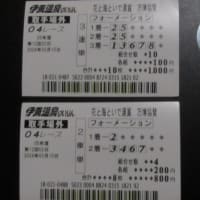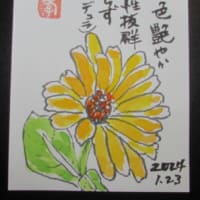村松 聡 (著)
著者について
●村松 聡:1958年、東京都生まれ。上智大学哲学科、同大学院修了後、ドイツ・ミュンヘン大学留学。
横浜市立大学国際総合科学部応用倫理学担当准教授を経て、現代早稲田大学文学学術院文化構想学部教授。
専門は近現代哲学、倫理学、生命倫理などの応用倫理学。主に徳倫理の観点から、人間とは何かについて研究を続けている。他の著書として、『ヒトはいつ人になるのか 生命倫理から人格へ』(日本評論社)、『教養としての生命倫理』(共編著、丸善出版)などがある。
〈正しさ〉が空洞化する世界で「筋を通す」ための哲学!
分断が深まる世界。複数の〈正しさ〉が衝突するなかで、人は難題を前に「何でもあり」の相対主義に陥りがちだ。人生の切実な「問い」に直面して "筋を通す" ための倫理とは?
カントに代表される義務倫理、ミルやベンサムが提唱した功利主義に対し、アリストテレスを始祖とする徳倫理はこれまで充分に注目されてこなかった。
近代が置き去りにした人間本性の考察と、「思慮」の力に立ち戻る新たな倫理学の潮流が、現代の究極の課題に立ち向かう!
◆積極的安楽死は認められるか?
◆妊娠中絶の自由か胎児の生存権か?
◆テロリストの逮捕か人質の命か?
◆安全基準か雇用の最大化か?
【徳倫理とは】
アリストテレスを始祖とし、人間本性の考察に基づいて思慮の力と「どうしたいか」を重視する倫理学。カントに代表され「すべき(でない)」と人を縛る義務倫理、ミルやベンサムが提唱し、経済学と結びついた功利主義と異なる第三の潮流である。
「つまわたりの倫理学道心」というフレーズは、私の知識ベースには直接的には存在しないようです。ただし、一般的な「倫理観」と「道徳心」についてお話しできます。