「難民キャンプ」をめぐって――小泉康一『「難民」とは誰か』より

個人は、移住を通じて自らの望みを追求する自由をもつ。一方、人口流入に対して国家が懸念を抱くことも避けがたい。では、両者の葛藤は克服しえないものなのか? 国際的視野から難民研究を牽引してきた第一人者が、人間経験の根幹をめぐる課題として考える。
◆目次
はしがき
第1章 前提として何を押さえるべきか
論点① 難民は子どもの顔で描かれる
論点② 難民は戦士、反攻勢力にもなる
論点③ 難民の本当の数は誰にもわからない
論点④ 発表数の魔術、人数の政治的操作
論点⑤ 難民は難民キャンプにはいない
論点⑥ 帰ることくらい良いことはない、という神話
論点⑦ 拷問、ジェンダー、人身売買とのつながり
論点⑧ 「家族」という理想化された概念
論点⑨ メディア報道と政治の背景にあるイデオロギー
第2章 難民はどう定義・分類されてきたか
論点⑩ 現代は紛争の性質に変化がある
論点⑪ 逃亡の原因と結果、影響は複雑化し多様化している
論点⑫ 逃亡の根本原因から、きっかけまで
論点⑬ 避難する人と避難せず残る人、事前に予測して避難する人
論点⑭ 先進国内の庇護経費は、UNHCRへの拠出額を圧倒
論点⑮ 移民と難民、カテゴリーで分ける危うさ
論点⑯ 「迫害された難民」とは呼べない避難民の人々
論点⑰ 政策的に定められた定義がかかえる問題
論点⑱ 難民条約は不要か?
第3章 難民はいかに支援されてきたか
論点⑲ 人道主義は、現代資本主義の補完物?
論点⑳ UNHCR、栄光というよりは苦闘の歴史
論点㉑ UNHCRの構造とグローバル難民政策
論点㉒ 難民キャンプで「ただ待つ」ことは人を病気にする
論点㉓ 虚偽の申告は生きるための戦略であることも
論点㉔ 歪んだ戦略を強いられる難民もいる
論点㉕ 難民全員が弱者か? その後のケアは?
第4章 当事者視点を軸に、いかに視野を広げて考えるか
論点㉖ 難民は安全保障上の脅威なのか?
論点㉗ 移住を阻止するための開発援助の是非
論点㉘ 「難民問題」ではなく、難民の問題を考える
論点㉙ 難民キャンプは、技能オリンピックにして争いの場
論点㉚ 援助活動と研究の違いと補完性
論点㉛ 多くの難民調査に欠けているもの
論点㉜ 研究者と難民の関係はどうあるべきか
論点㉝ 国際制度における新たな分担のルールを求めて
論点㉞ 難民の問題は、他のグローバルな諸課題とつながる
参考文献
あとがき
索引
キャンプの実情を知るために、歴史をやや遡って、悪名高かった香港政庁の1980年代のキャンプの様子を例として取り上げてみたい。
香港に流入したすべてのベトナム難民は、1982年7月以降、外部との接触を一切禁じられ、監獄のような「閉鎖キャンプ」に収容された。
この政策は、香港の資源が難民により圧迫されることへの危惧と、放置すれば将来ますます難民が流入してくるだろうという香港政庁の怖れを表していた。事実、狭い香港で難民のために土地が使われることは、本来なら地元住民のものである資源が他に回されることを意味していた。
香港政庁は、東南アジアから来た難民の受け入れを、地域の他の国々よりも不当に多く負担していると感じていた。政庁の目的はだから、これ以上の負担を拒み、キャンプの滞在者にはベトナムに帰ってもらい、新たな流入を阻止することにあった。
そのためにとられた方策は、香港での難民の生活状態、つまりはキャンプの生活環境を著しく劣悪にすることだった。高いフェンスとコンクリートの壁、四六時中の監視、食べること・寝ること以外に何も許されない生活、プライバシーのない蚕棚のベッド……。そうすれば難民は、香港が良い目的地ではないと考えて、流入数は止まり、すでに滞在中の難民はベトナムへ戻るだろう、というのが当局の政策における「意図」だった。
政庁は、キャンプが「一時の滞在場所」と公に認知されることを望んでいたので、キャンプ内の施設の処遇を改善して居心地を良くする試みには断固として反対した。娯楽室を一つつくるのでも、キャンプ内の居住者と政庁の役人の間で、際限のない話し合いが続けられた。
待って、待って、ただ待つだけ
キャンプ生活ではあらゆることが不確かであり、将来を決める力も難民の掌中にはない。難民には、これから先の自らの運命の選択に関与することがまったくできない。運命を決めるのは、ときおりキャンプを訪れて難民を面接する、受け入れ国の係官である。
難民は、彼らの窮状を救うべくつくられたキャンプの中で、国際機関UNHCRの関心の対象となり、彼らの多くはただ「被収容者」として、何ヵ月いや何年もの間、「どっちつかずの曖昧な状況」のなかに置かれる。祖国からは離れて存在しているが、しかしまだどこにも受け入れられていないという中途半端な状態である。
難民は多くの場合、現政権の下では未来がまったくないと考えて国を脱出する。彼らは、自分たち自身が社会の「主流」からはじき出され、「行動の自由」を否定されたと考えている。現政権から陰に日向に妨害され、職を失い、新しい職にもつけず、財産を切り売りする毎日である。失うものはもはや何一つない。彼らはより良い生活を見つけるために国外へ逃げ出す。
難民はキャンプを、新しい生活へと移るための「代償」と考え、逃亡過程の「一部」として受け止めている。彼らは出国の際、どこか特定の場所に落ちつくという積極的な動機を初めからもつわけでは必ずしもない。
自分の意思に反して祖国を離れねばならなくなったという点で、移民とは異なっている。
しかし、キャンプから出発できる時期は、予想することができない。
キャンプにいる人々がもつのは、「待つ時間」だけである。大人にとってキャンプは、自分たちが逃亡し、国際難民制度に組み込まれる前に祖国で経験した「疎外」という長いプロセスの延長線上にある。
難民にとってキャンプ生活での目標とは、ただ一つ、「出発の日」である。
毎日の生活は、待つことを中心に営まれる。インタビューを待ち、祖国に残した家族についてのニュースを待ち、他国へすでに定住した親戚の便りを待ち、キャンプに新たに到着した難民のなかに縁者・知人はいないかとリストを見ながら、入国管理当局の役人が定住許可が下りたと知らせてくる日を待っている。
彼らはかすかな期待のもとに、仮の地位に留まることに甘んじ、現在を耐えている。
彼らの状況に最も近いのは、「戦争捕虜」かもしれない。捕虜には、自分では将来を選べない不確かな現在と、行動の制約、他者への依存がある。
しかし難民が戦争捕虜と違うのは、捕虜が祖国で再び家族たちと一緒になることを期待するのに対し、難民は代わりに外国での「受け入れ」を希望することである。
祖国で彼らが営んでいた以前の生活と、不確かな未来との間にポッカリとあいた難民キャンプというエアー・ポケット。そのなかで難民が滞在を引き延ばされ、孤立させられると、難民の感情には難民であること特有の性格と立場による影響が避け難く生じる。すなわち、難民の間に「故郷を失った」という絶望が広がり、強さを増していく。
難民の多くは家族と引き裂かれ、時には一生会うことがない。深い悲しみと悲劇は、共通のものである。
しかし何より注目すべきことは、「中途半端で、どこへも行けない」という難民たちの状況が彼らの主体性を損ね、無力感を与えることである。
倦怠、退屈、疲労、無力、希望の欠如……。難民は日々の生活のなかで、自分自身や家族に起こっていることに関心を失い、難民キャンプの中の自分たちのコミュニティについて、ほとんど意識を向けなくなる。
「ただ待つ」ことは人を病気にする
難民が耐え忍ばねばならないことは、どこかへ行くために待つことである。ただ待つことは、彼らの健康を損なう。心理的には、憂鬱、不安、不満、ホームシック、あるいはこれらすべてが混合する。
選択肢が現実にないことは、当人の物理的、社会的な脆弱さを増す。ストレスや鬱の感情は、便秘や嘔吐を引き起こす。女性の多くが訴える痒みは、食物アレルギーと考えられるが、空気の汚染かストレスのような他の要因により引き起こされているのかもしれない。
移動中の人々は、食べ慣れた食料を入手できず、あまりなじみのない他の食料の摂取を増やすことになる。また避難中に食料消費の質と量が変化することは、難民の健康にとって深刻な意味をもっている
。たとえばカイロのスーダン難民は、難民キャンプには収容されていなかった。だがビタミンAと鉄分の不足が広く認められ、栄養失調の割合が非常に高かった。彼らはスーダン南部から首都ハルツームへ、それからカイロにやってきた人々である。
アフリカの難民は国境を越えて文化的類似性をもち疎外感を覚えないという考えに誤りがあることは、1980年代にすでに、アフリカ人研究者のカラダウィによって明らかにされている。
前述の香港のキャンプで支援に従事した援助団体のスタッフは、私に「難民にはキャンプの生活状況を改善する活動に参加する気持ちが欠けており、彼らは自分たちに必要なものを、責任ある大人として我々スタッフに依頼したりはしない。まるで〝何でも依存する子ども〟のようだ」と嘆いてみせた。
このように無気力となった難民の「依存症候群」のケースについては、もっと注意がはらわれてしかるべきであろう。
また、子どもの問題も深刻である。親が子どもだけを先に祖国から脱出させた場合や、移動中に親と離れた場合には、多くの子どもが亡命の意味を理解できない。
祖国の親元に帰りたいという願望と、「親が子どもに託した」先進国へ行くという使命感と興奮の間で、小さな胸は張り裂かれる。
そうした子どもは、彼らを見守る親も親類縁者も近くにいないことから、わずか7、8歳で一人前の大人のように振る舞うことを周囲から期待される。監督する親がいないので、まったく「独立的」に行動するようになる。
あまりに独立的になると、第三国に定住後、受け入れてくれた里親の家族内で、問題を起こすかもしれない。
キャンプ内で形成された新しい人間関係は、とくに重要な影響をもつ。
友人は、キャンプ内で自分の身に何か問題が起きたとき、頼りになる特別な家族となる。
友人の第三国への出発は、後に残された大人にも子どもにも、少なからぬ懸念をもたらすことになる。
しかし、大人の場合も子どもの場合も、たとえそうした友人関係が今や、祖国に残してきた親族や友達以上に重要なものとなっても、しょせん一時的なものとみなされてしまうのがつねである。個人がキャンプ内で友達との間に築き上げた絆は、つかの間のものとみなされるのだ。
香港のキャンプでは、ある年、はっきりした原因がわからないまま、一年間に五人の若者が死亡した。彼らは眠ったまま、翌朝、目を覚まさなかった。医者は、キャンプの生活状況が与えた「心理的ストレス」が原因だと診断した。
以上をまとめれば、多くの難民キャンプは、絶対的権威をもつ当局によって厳重に管理されており、難民が独裁、専制といった権力による迫害から逃亡してきたにもかかわらず、まさにそれらの権力を「再生産」し、乱用さえする。
キャンプでは多くの場合、庇護、安全、自己管理の回復といった難民の希望がともすれば損なわれ、他者への依存、無力感という新しい問題を生み出している。
囚人のように自由が制約され、そのために難民は過去を生き、将来を夢見るようになる。収容中の人々の間には、自分は「無視され、忘れ去られた」という感覚が共有される。彼らは「我々にはまったく権利がないし、まったく地位もない。我々は望まれざる者だ」という。
これは祖国を逃れはしたものの、どこにも永続的な庇護を見出せず、代わりに難民キャンプに何ヵ月、いや何年と滞在し「異常な現在」と「不確かな未来」に直面し続ける大多数の難民に「共通する経験」である。以前の社会的地位の違いはもはや、これらの人々の間では何の意味もない。
キャンプに長期滞在したことの否定的な影響は明らかである。人々が大きなストレスの下に生活していることは、疑いえない。キャンプそれ自体は、いかなる意味においても、自分自身で決定する未来へ向かって活発に能動的に生きるための動機を育むところではない。
キャンプ滞在によって、新しい国へ入国しようとする難民が何かを準備したり、前もって利益を得られたりすることはほとんどない。「監禁状態」にある難民に対する「責任をもつ組織」の間の気づきと改善が、重要性を増している。












![忘れられた皇軍 浪漫堂シナリオ文庫 by [大島渚]](https://m.media-amazon.com/images/I/41MEw1FLWHL.jpg)





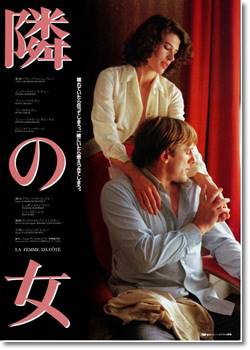
![Amazon.co.jp | 情痴 アヴァンチュール [レンタル落ち] DVD ...](https://msp.c.yimg.jp/images/v2/FUTi93tXq405grZVGgDqG2E-Sg2-7FDTZANwvnBP0L8fCu8JH5BxSVL3lAhv-slsS-EmyFrW5hmmQWF74QFO0yDxRcGs53AIQgq0BiwBbQhGe5IGcTlymF28CR_i2FODhrs0YeouB2xwyPZlb_NO3KdmNacP79d9yVBd04zf_S5tl8P9D0EpH8yLiChU7ALjwYOyKaLFVJCgsIl4CsiZRWniqkHdCpI6NZmpmZbdCKDrfCMujRfPZogHQzGPJFXw/71YsZKuAZML._AC_UF10001000_QL80_.jpg?errorImage=false)


