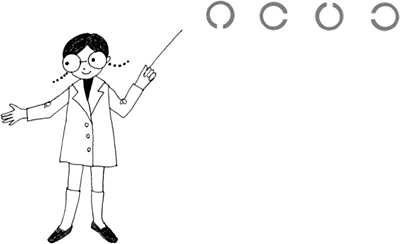東京文化会館前は花見客で混雑していた。
帰る人と花に見物に向かう人たちの人波が交雑していたのだ。
社長秘書の伊藤亜里沙と川口雄介は、同僚のたちが上野駅公園口から改札口へ向かったのに、東京国立博物館方面へ向かう。
「私とても酔ってしまったの。酔い冷ましに歩きたい。川口さん付き合ってね」亜里沙は雄介に身を寄せる。
「仕方ない。鴬谷駅まで歩きましょう」雄介は応じた。
東京芸大の前を通る時、雄介は音楽療法を日本に伝えようとしたイギリスのロブソン夫人のことを思い出したのだ。
雄介はまるで語学がダメであったの、ロブソン夫人に取材する際に芸大の大学院生の女性に通訳を依頼した。
それは、雄介が25歳の思い出である。
なお、ロブソン夫人の夫のロンドン大学名誉教授ウィリアム・A・ロブソン博士は、東京都の当面する諸問題について意見を求めるために、東京都と東京市政調査会は 1967年 4 月に招聘されている。
再度、来日したロブソン博士に伴ったロブソン夫人は芸大に招れ、音楽療法の効果を日本に伝えた。
雄介は記憶の不思議さを改めて感じた。
東京芸大の前を通らなければ、蘇ることのない思い出であったのだ。
「あなたを慕っているの」アルコールが言わせた本気、亜里沙の思わぬ告白であった。
雄介はこれまで何度も女性を好きになったが、その恋慕が成就することはなかった。
「愛するより、愛されたい」それが雄介の究極の願望であった。
「雄介さん、何時かあなたを心から好きになる人が現れるわよ。じっと待っているの」神田駅カード下のバー「藤」のママ藤子の助言であった。
42歳の藤子は娘時代、進駐軍兵士たち3人から性的暴行を受けてた被害者だった。
雄介の米国嫌いは増すばかりとなる。
雄介が幼いころのことであるが、ジープに乗った進駐軍兵士が近隣の若い娘を奪い去る光景を目撃した。
駐在所の警官がジープの前に立ちはだかり、両手を広げ行く手の制止を試みたが、跳ね飛ばされ呆気なく即死したが、この事件はどこにも報道されなかった。
雄介が中学からの英語学習をボイコットする契機となる。
「私は汚れた女だけど、私の願いを聞いてね。あなたに抱かれたい」
鴬谷ホテル街のネオンが亜里沙の本気を言わせた。
29歳になるのに、雄介にはそれまで、女性との肉体関係は皆無であったが、彼はすでに亜里沙の誘いに応じる気持ちとなっていた。
だが、思わぬ結果が待っていたのだ。
二人で風呂に入る。
「あら、あなたは包茎ではないの?」亜里沙は勃起した雄介の陰茎の異常に気付く。
「包茎?」雄介は自身の陰茎に目を落とす。
「セックス出来るかしら?」亜里沙は陰茎に手を添えながら入念に点検するのだ。
それは、<性体験なし>の雄介の気持を萎えさせた。
参考
“音楽療法”の歴史は古来までさかのぼります。音楽の力が人間の身体(しんたい)に大きな影響があることは、かなり昔から意識されていたようです。しかし、日本の“音楽療法士”の歴史はまだ浅く、誕生から20年ほどしか経っていません。
参考
包茎症状について
勃起時や平常時に皮が被って 亀頭が露出していない状態である。
包茎とは、陰茎の先端の“包皮口”が狭いことによって陰茎を包む包皮が十分にむけず、亀頭を露出することができない病気のことです。
多くは生まれつきによるものだ。
包茎でもセックスはできるのか?
挿入をするとき(包皮が邪魔をして)スムースに挿入できない時がある。
また無理に挿入しようとして包皮が突然剥けてしまい嵌頓包茎になる可能性もある。
包茎のデメリットについては以下のことが挙げられます。
1 性交時にうまく挿入できない
2 包皮と亀頭の間に恥垢(あか)が溜まり臭いの原因になる。
3 恥垢に細菌が潜み、亀頭包皮炎の原因になる。
4 長期の炎症は亀頭癌の原因となります。
5 亀頭の成長期に包皮で覆われていると、成長が阻害され、先細りの亀頭になります。
6 亀頭がいつも包皮に守られており、刺激に敏感になりやすく、包茎性早漏の原因になります。
7 尿が飛び散る原因になります。
8 真性包茎の場合は、勃起障害や射精障害の原因になります。
9 仮性包茎でも重度の場合は、カントン包茎になりやすくなります。
10 特に真性包茎では、陰茎癌のリスクが上昇します。
仮性包茎は早漏の原因の1つとして考えられます。なぜならば、亀頭は、仮性包茎の場合には平常時は包皮に保護され、刺激に慣れていません。そのために、セックスの際の刺激に敏感になるからです。
包茎のままでのメリットは特にないのが現状です。