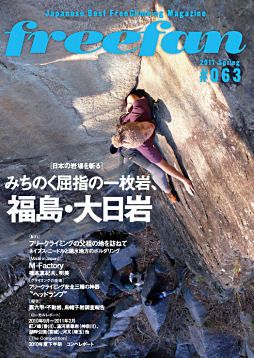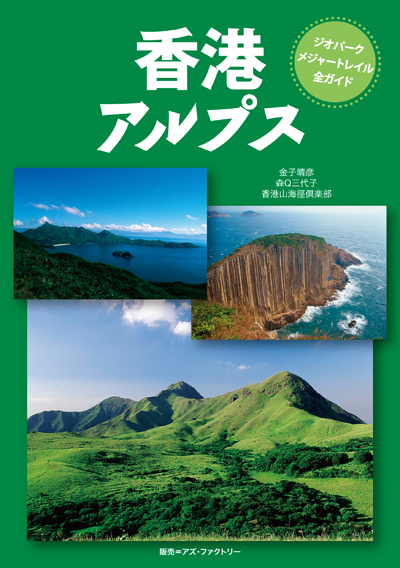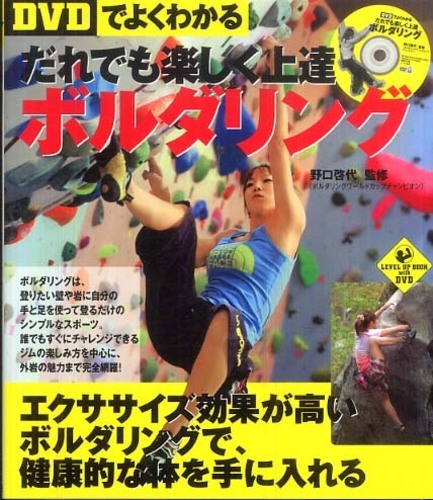「山と渓谷」2011年7月号
P195-201
小型軽量ガスストーブの特集が気になるので読んだ。
比較されているのは次の5つ。
①SOTO(SOD-300)8400円
②EPI(REVO-3700)9975円
③PRIMUS(P-114)7140円
④PRIMUS(P-153)8925円
⑤SNOWPEAK(Chi)5980円
私が良いと思ったのたのは、②と③で、出力はそれぞれ3700kcal/h, 2300kcal/hで、EPIの出力が高い。
しかし、ガス消費量と燃焼時間は、308g/h 約60分,150g/h 約90分で、PRIMUSの方が効率がよい。
沸騰時間も9℃と25℃で、比較されている。
PRIMUSはEPIに出力で負けているのに、EPIと同等か、それ以上の結果が出ている。(5製品の中でもトップクラス)
さらに、深鍋と広口鍋の沸騰時間比較が興味深い。
次のように書かれている。
広口型では、深底方に比べ、時間にして40秒から1分ほど速く沸騰し、被検体E(SNOWPEAKのこと)では2分近くも短縮したのだ。考えてみれば、熱を受ける面積が広くなるので当然の結果ではあるのだが、これまで「深底鍋のほうが利便性が高い」という習わしに従い、疑問を抱かずにクッカーを使用してきたことを反省しなくてはならない。(詳しくは実際の「山と渓谷」を読んでみて)
さて、以上の結果どうでしょうか?
「ジェットボイルについて書いていない・・・どうなってんだ?」、と思われることでしょうね。
この特集が『本体重量100g以下の小型ガスストーブ』、ってことになってるので、『オールインワンタイプ』は、どうしてもモレてしまう。そこで、2010年11月「山と渓谷」を見てみよう。
この号でもストーブ特集を企画している。
私が『オールインワン・タイプ』で気になったのは、JETBOILとPRIMUS・イータパックライト。
2-3人で行くならPRIMUS・イータパックライト、1人ならJETBOILのコンパクトタイプがよい、と思う。(どちらも、風に強く、かなり熱効率が良い)
イータパックライト15,000円(税込¥15,750)
→http://www.iwatani-primus.co.jp/products/primus/37.html
【本体重量】572g(本体、1.2ℓ専用ポット、フタ)
【収納サイズ】21.5×19×13cm
【出力】2.2kW/1,800kcal/h(Gガス使用時)
【ガス消費量】140g/h
【燃焼時間】約100分(IP-250ガス使用時)約45分(PG-110ガス使用時)
【セット内容】バーナーベース部、1.2ℓ専用ポット(鍋)、フタ、風防、ポット用ハンドル、
専用インシュレーションバッグ、ボウル、ヒートエクスチェンジャープロテクター
JETBOILはZIP、PCS FLASH、SOLと種類が多いし、同じ型でもチタン軽量タイプもある。→http://webshop.montbell.jp/goods/list.php?category=328000
好みに応じて、検討したらよい。例えばZIPの仕様は次のとおり。
JETBOIL(ZIP)8900円
【総重量】407g(ゴトク、スタビライザーを含む)
【サイズ】φ104mm×高さ165mm(収納時)
【容量】0.8L(調理容量は0.5L)
【出力】1134kcal/h
【ガス消費量】100g/h
【沸騰到達時間】0.5Lで約2分30秒(ジェットパワー1缶で約12Lの水を沸騰可能)
以上、ストーブ特集の感想は、こんな感じ。
ところで、「お前は何を使ってんだ?」と言われそう。
山岳会時代はホエーブスを使用。(プレヒート+ポンピングが手間だった)個人山行では、EPIヘッド、2種類を使用してきた。(それぞれ30年くらい前と、20年くらい前に購入)
ちなみに、普通のキャンプでは一般家庭用カセットコンロを使用・・・車で行けるキャンプ場、例えば小川山なら、これで十分、と思う。(また、韓国製ジョイントを使って一般ガスカートリッジ+EPIヘッドの組合せも利用した。これはスーパーでカートリッジ購入できて便利)
そのうち、EPIヘッドもだいぶ古くなって、火力が落ちてきたので、今はIwataniジュニアバーナーを使っている。
湯もわりと早く沸くし、そんなに悪くない。登山用品店に行かなくてもカートリッジ購入できて便利だし、ランニングコストも安い。
欠点は少し重くて、かさばること・・・かな。
 |
カセットガス |