2章 日々のこと
3章 本のことなど
4章 自作について
5章 羊と鋼と本屋大賞
6章 緑の庭の子どもたち 2015‐2017

「なるべく働きたくない人のためのお金の話」大原扁理
趣味を仕事にするとしんどいが、
仕事が趣味だという方は幸いだ。
高度経済成長を支えたモーレツ社員は団塊の世代。
よくも悪しくも現在の日本を形作った。
過剰に働き、必要以上に貯めるのは、日本人の体質なのだろうか?
それとも明治以降の傾向なのだろうか?
著者は、「必要以上に働かない」と決める。
それはそれで、大変な決意だと思う。
週休5日で、2日だけ働き、必要以上に買わない、使わない。
意外とそれで生きていける。
収入が少ないと、税金も少ないし、保険代も安くなる。
文章を読むと、けっこうまっとうな人物だと分かる。
変人かと思ったら、そうじゃなかった。
我々の方が、働き過ぎでおかしいのかも、と思ってしまう。
もちろん、一部の過剰に働く方々と、それに引っ張られて働く人のおかげで、
日本経済が成り立っているのかも知れないが。
しかし、それを一度全員で「やーめたっ」って降りるとどうなんだろう?
案外、なんとかなるかも…?
海外に行くと2か月の休暇でクライミングをしているドイツ人に出会う。
うらやましく思う。
日本人はどこで間違ってしまったのだろう?
【ネット上の紹介】
弱い私たちの、生存戦略。将来に不安や心配を感じている人へ、もっと楽に生きられる思考法。
序章 隠居生活のアウトライン
第1章 まずはつらい場所から抜け出す
第2章 落ち着いた生活をつくりあげる
第3章 手にしたお金で、自分はどう生きたいのか?
第4章 お金に対する見方・考え方の変化
第5章 お金と話す、お金と遊ぶ
対談 鶴見済×大原扁理―豊かさって何だろう?

「大河の一滴」五木寛之
引き揚げ体験を次のように書かれている。
(引き揚げについて)あまり積極的に書かれないので、貴重な資料だ。
P40
敗戦の引き揚げの極限状態のなかで、子供たちにとって大人はおそろしい存在だった。子供たちに同情して朝鮮人や旧ソ連兵がくれた餅や、黒パンや、芋などを、大人たちにいきなり強い力で奪いとられることがしばしばあったからだ。「飢えた大人ほど怖いものはない」と、当時の子供たちは骨身にしみて思い知ったのである。
P49
南北をへだてる三十八度線の境界を十三の私は、妹を背負い、弟の手を引いて走りに走った。弟が力つきて倒れれば、迷わずに置いて走りつづけるつもりだった。
P86
最初は七人の家族がいて、いま生き残っている家族は、ぼくと妹の二人だけになりました。
P261
いじめの問題を、子供は本来、残酷だからとか、いじめによって淘汰されていくんだとか言う人がいるけれど、そうではない。あれは大人の社会の反映です。大人の社会が、元気な人間、明るい人間しか認めないという立場をとるから、そうでない人間を子供たちは攻撃するのではないか。
「昭和二十年夏、子供たちが見た戦争」では、五木寛之さんは次のように話されている。
P310-311
引き揚げてきて内地に上陸すると、女の人たちは「婦人調査部」というところで身体検査をうけなければなりませんでした。レイプされて性病にかかっていないか、妊娠してしないかなどを調べるんです。
敗戦後の混乱の中で暴行を受け、妊娠してしまった人は――これを「不法妊娠」と言ったんですが――トラックで福岡の郊外にある施設に連れて行かれ、堕胎手術を受けさせられたそうです。
当時その仕事にたずさわった日赤の婦長さんという人に話を聞いたことがあります。麻酔なしの手術だったそうですが、泣き声をあげる人は1人もいなかったとおっしゃっていました。それを聞いて、何ともいえない気持ちになりましたね。
当時、人工中絶手術は法律で認められていませんでした。医師法違反に問われる危険を承知で、引き揚げ者のために献身的に働いた医師たちがいたんです。
P312
引き揚げのことを題材に作品を書くことを僕はしてこなかったんですが、おそらくこれからもしないと思います。
【ネット上の紹介】
どんなに前向きに生きようとも、誰しもふとした折に、心が萎えることがある。だが本来、人間の一生とは、苦しみと絶望の連続である。そう“覚悟”するところからすべては開けるのだ―。究極のマイナス思考から出発したブッダや親鸞の教え、平壌で敗戦を迎えた自身の経験からたどりついた究極の人生論。不安と混迷の時代を予言した恐るべき名著が、今あざやかに蘇る。“心の内戦”に疲れたすべての現代人へ贈る、強く生き抜くためのメッセージ。
人はみな大河の一滴(なぜかふと心が萎える日に
人生は苦しみと絶望の連続である ほか)
滄浪の水が濁るとき(「善キ者ハ逝ク」という短い言葉
屈原の怒りと漁師の歌声 ほか)
反常識のすすめ(内なる声を聴くということ
科学は常に両刃の剣である ほか)
ラジオ深夜一夜物語(私たちは“心の内戦”の時代に生きている
自分を憎む者は他人を憎む ほか)
応仁の乱からのメッセージ(“インナー・ウォー”の時代に
命の重さが実感されなくなった ほか)
朝日新聞で、谷川俊太郎さんへのインタビュー記事が連載されている。
ずっと気にしていた。
谷川俊太郎さんの3番目の奥さんが佐野洋子さんだから。
彼はどう語るのだろうか、と。
(佐野洋子さんは)散文作家だったけど魂は散文に収まりきらないものがあった。言葉を信用していなくて詩のことを「スープのうわずみ」と言ってましたね。
佐野さんとの関係を通じて老いとか男女の問題とか全部絡んで、新しい深い経験をしたことは確かですね。
(谷川俊太郎さんは)デタッチメント(他人に対して距離を置くこと)の人。佐野さんはそういうところが気に障ったんだと思う。しょっちゅう、けんかしていました。彼女はけんかが好きだった。けんかした後の仲直りが好きだったんだと思う。







「西遊妖猿伝」(11)~(16)諸星大二郎
16巻目で第2部『河西回廊篇』が終了する。
財産分けをしてちょうだいな
ロバとラクダが喧嘩を始めたぞ!
な…なんて性格の悪いロバだ
この続きは『西域編』へ
【あとがき】
西域を舞台にして沙悟浄や火焔山や牛魔王の登場する物語をいずれはやりたいと思います。
【参考】
潮出版社の希望コミックスは、これにて完結。
この続きはモーニングKCで①から⑥まで出ている。

「先生と私」佐藤優
7月に、「十五歳の夏」を読んだ。→「十五の夏」佐藤優(上・下)
本作品は、その姉妹編、前段階に相当する。
1960年から1975年の少年時代が描かれる。
P164-165
「佐藤君は、パリサイ派についてどう思うか」
「聖書に出てくるパリサイ派ですか」
「そうだ」
「律法を遵守するけれど、神の意志に忠実でない偽善者のことですね」
「結果として、パリサイ派は偽善者になってしまう。しかし、本人たちは律法を忠実に守っている。神の意志に最も忠実な者と信じている。マルクス主義者にはパリサイ派が多すぎる。佐藤君が見せてくれたこの本も、パリサイ派の文書だ。著者たちはマルクス主義の文献に通暁している。確かにそれなりの論理整合性もある。しかし、人間の心を打たない。(後略)」
【おまけ】
佐藤優さんの母は沖縄・久米島出身。
あの沖縄戦を生き抜いた方だ。
とてつもない幸運の持ち主と思う。
【ネット上の紹介】
誕生から高校入学までの15年間、両親・伯父・副塾長・牧師…多大な影響を与えた先生たち。知の“巨星”の思想と行動の原点を描いた自伝ノンフィクション。
僕の両親
あさま山荘
山田義塾
哲学と神様
スカウト
数学の先生
革命
進路相談
高校受験
春休み
塩狩峠
稚内
帯広
立席特急券
父の背中
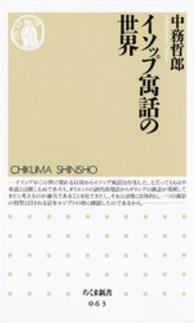
「イソップ寓話の世界」中務哲郎
P119
ごましお頭の男が、若い娘と年たけた婆さんと、二人の愛人をもっていた。婆さんは、自分より若い男と語らうのが恥ずかしくて、男が通ってくるたびに、髪の毛の黒いのを抜き続けた。若い方は、年寄りを愛人にしていることをごまかそうとして、白髪を抜いた。こうして、両方から代わる代わる毛を抜かれた男は、禿になってしまった。(子供用「イソップ童話」には、この話は掲載されない、と思う。「愛人」「禿」「男が通う」など、モラルコードやポリティカルコレクトネスに抵触するワードが、短い中に満載で教育上不適切と思われるから)
P89
共同体を襲う災いやそこにある一切の罪穢れを担わせ、全員で境界の外に追い出し、あるいは殺害することによって集団が浄められたとする。このようなスケープゴートの儀礼の全世界からの例については、フレイザー『金枝篇』の記述に詳しいが、これは未開社会や古代社会に限られた現象ではないし、制度化された儀礼としてのみ現れるものでもない。疫病や大地震のような不時の災厄に際して、人間はどれほどのスケープゴートを作り出してきたことであろう。
【ネット上の紹介】
イソップの動物寓話は、子ども向けの人生訓話としてなじみ深いものである。けれども、ほぼ同時代のソクラテスやアリストパネス、ヘロドトスなどによってすでに真剣な考察の対象とされたように、そこには読み手の立場によって多様な解釈を許容する、奥行きをもった世界が展開されている。では、イソップとは誰なのか。それはいかなる経緯によって成立し、流布されていったのだろうか。先行文明としてのメソポタミアやエジプトをも視野に入れながら、イソップ寓話をとりまく謎に迫る。
第1章 イソップ寓話とは
第2章 寓話の起源
第3章 イソップの生涯
第4章 寓話の歴史の三区分
第5章 イソップ以前―ギリシアの場合
第6章 ギリシア作家とイソップ寓話
第7章 イソップ以前―日本の場合

「「絶筆」で人間を読む」中野京子
「画家は最後に何を描いたか」という副題がついている。
代表作と晩年の作品を比較している。
また、通して読むと、西洋絵画の歴史としても楽しめる趣向だ。
P83
『フランダースの犬』のネロ少年が、死ぬ前に一度でいいから見たいと切望した絵こそ、ルーベンスの宗教画『キリスト昇架』だった。
『キリスト昇架』(1610年 - 1611年)聖母マリア大聖堂(アントウェルペン)
P200
一見、北国の雪景色を描いた風俗画にしか見えない画面に、ロバに乗った聖母マリアと綱を引くヨセフがさりげなく挿入されているのだ。
P240
パリから50キロほど南に、広大なフォンテーヌブローの森が拡がっている。(中略)
この森の北西端に隣接するのがバルビゾン村だ。 『箕をふるう人』ジャン=フランソワ・ミレー
『箕をふるう人』ジャン=フランソワ・ミレー
パリにコレラが流行し、一家はルソーの勧めでバルビゾン村へ一時避難。やがてそこがすっかり気に入り、以降、死ぬまで定住することになる。
【ネット上の紹介】
ルネサンス、バロック、印象派…もう、そんな西洋絵画の解説は聞き飽きた。知りたいのは「画家は、何を描いてきたか」、そして「最後に何を描いたか」。彼らにとって、絵を描くことは目的だったのか、それとも手段だったのか―。ボッティチェリ、ルーベンスからゴヤ、ゴッホまで、15人の画家「絶筆」の謎に迫る。
第1部 画家と神―宗教・神話を描く(ボッティチェリ『誹謗』―官能を呼び起こせし者は、消し去り方も知る
ラファエロ『キリストの変容』―バロックを先取りして向かった先
ティツィアーノ『ピエタ』―「幸せな画家」は老衰を知らず
エル・グレコ『ラオコーン』―新しすぎた「あのギリシャ人」
ルーベンス『無題』―「画家の王」が到達した世界)
第2部 画家と王―宮廷を描く(ベラスケス『青いドレスのマルガリータ』―運命を映し出すリアリズム
ヴァン・ダイク『ウィレム二世とメアリ・ヘンリエッタ』―実物よりも美しく
ゴヤ『俺はまだ学ぶぞ』―俗欲を求め、心の闇を見る
ダヴィッド『ヴィーナスに武器を解かれた軍神マルス』―英雄なくして絵は描けず
ヴィジェ=ルブラン『婦人の肖像』―天寿を全うした「アントワネットの画家」)
第3部 画家と民―市民社会を描く(ブリューゲル『処刑台の上のかささぎ』―描かれたもの以上の真実
フェルメール『ヴァージナルの前に座る女』―その画家、最後までミステリアス
ホガース『ホガース家の六人の使用人』―諷刺画家の心根はあたたかい
ミレー『鳥の巣狩り』―農民の現実を描いた革新者
ゴッホ『カラスのむれとぶ麦畑』―誰にも見えない世界を描く)