つい音楽雑誌の記事などを読むと嫌でも目に付く「愛聴盤」という文字。僕も無意識のうちに好きなアルバムについてこういった表現をしてしまうけれど、実のところ、「愛聴盤」というものが本当にあるかと問われれば甚だ疑問なところもある。
たとえば「愛読書」といわれるものなんかもそうだ。愛読というくらいだからおそらく毎日とは言わなくとも週1回は読んでいるとして、果たしてそんな本があるのかということなのだ。
おそらく小説というレベルならば一度読み終わった本をまた最初から読み返すなどそんなに多くはなかろうし、第一結末がわかっているものをそうやすやすと読めないはずだ。たとえ、それが比較的に苦ではないと思われる漫画本や写真集であったとしてもである。
そういう意味でいけば「愛聴盤」が「愛読書」よりも可能性としてはありそうなのだが、その手軽さからいうと「愛聴盤」が「愛読書」と同じ壇上で議論されるべきでないことは明白である。つまり、「愛聴盤」になると、少なくとも週3回くらいが妥当だと思われる。これは統計をとった上での数字ではなく、あくまで僕個人の考えに基づいている。
ちなみに僕が好きなのはベスト盤かコンセプト・アルバムといわれるものだ。でも、一概にコンセプト・アルバムといってもその定義はむずかしく、なんとなく同じ曲調の、あるいは同じアレンジの曲が収録されているものをそう呼ぶのだというくらいしか判らないのだが。
そんなこんなで僕がローリング・ストーンズを聴く場合は、専らベスト盤が多くなっている。ちなみによく聴くのは『ホット・ロックス』と『フォーティー・リックス』だ。けれど、これも僕が掲げる「愛聴盤」の定義からいくと愛聴盤ではなり得ないのだ。
村上龍氏の『限りなく透明に近いブルー』でこの小説のイメージにもなっているローリング・ストーンズは1973年、メンバーの麻薬所持などにより来日公演が中止になった。ちょうど同じ頃リリースされたのが『山羊の頭のスープ』。「悲しみのアンジー」を聴きたい時にはよくこのアルバムを引っ張り出して聴いていたもんだが、ベスト盤を買ってからはさっぱり聴かなくなってしまったアルバムなのである。全体的に曲のトーンが暗いということもあるけれど、どうも聴く前からワクワクしないのはなぜなんだろう。「アンジー」とはデビッド・ボウイの奥さんの名前で、ミックが彼女との不倫のことを歌っているという噂があった。ことの真相は良くわからないけれど、作曲したのはミックではなく、キースの方だと聞いた覚えがある。曲自体はいいのだが、アルバムとして順位をつけるなら下から数えたほうが良さそうだ。あれ?今日のテーマはなんだっけ。いつものようにまた脱線してしまったようだ。
The Rolling Stones - Angie (1973 -)











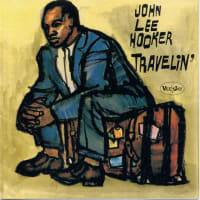









レコードの音が飛ぶくらい聴くーでしょうか^^;
CDになってから余り繰り返し聴かなくなりました
ものぐさです・笑