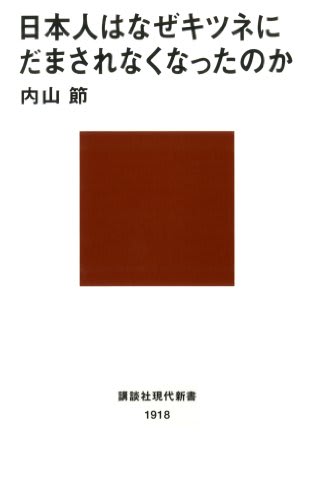
前に紹介したのが2019年の書籍で現在とこれからの日本の話だったので、今回は2007年と少し前の本である『日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか』を取り上げることにしたい。
題名はなかなかにキャッチーだが、端的に言えば「人がキツネに騙されることにリアリティを感じる世界観(コスモロジー)から感じない世界観への変化はどのようにして起こったのか」について述べた本である。アプローチとしては著者自身の聞き取りによるフィールドワークの中で、キツネに化かされる話が生まれなくなる契機が1965年にあり、それはなぜなのかと相手に問うてその答えを収拾する部分と、「正史」からはみ出す(明確なデータや文献資料に基づかない)オーラルヒストリーや一般人の世界理解をどのように取り扱うべきなのかを問う部分の大きく二つに分かれている。
以下、本書の良い点と悪い点についてそれぞれ分けて評価を述べていきたい。
【良い点】
「キツネに騙される=非合理的=否定されるべきこと」という発想からスタートするのではなく、「人がそれをどのように認識しているか」・「なぜそのように認識しているのか」という分析のスタンスを取ることによって、(進歩史観に基づいた)善悪から距離をとった形で世界観の変化を叙述することができているように思える(これは反面問題点ともつながるが、それは後述する)。
筆者も繰り返し言及しているように、今の私たちの世界観や歴史観は無色透明のものでは当然なく、様々なものから影響を受けて成立している(著者が取り上げてない例で言えば、カントの「物自体」や、カール・マンハイムの知識社会学を連想すれば十分だろう)。それを踏まえ客観的な歴史(世界像)は成立しえないという理解の元、「ではキツネにだまされることにリアリティを感じる世界観とはどのようなものか?」・「それはなぜ変化したと考えるか?」を分析することによって、(主に農村部の)日本人のコスモロジーを間主観的にあぶり出そうとしているわけである。
自分がブログで再三書いてきた具体例で言えば、偽史や都市伝説、陰謀論とその取り扱い方を例に挙げることができる(なお、「大衆的歴史観」をあたかも「正史」のように誤認する危険性としては、呉座勇一『戦国武将、虚像と実像』の書評で触れている)。しかし、著者のようなアプローチが有効であると最も強く感じるのは、「日本人の無宗教」に関する分析においてであると私は感じた。
本書の紹介から外れるので手短に述べるが、私は「なぜ日本人の大半は自身を無宗教と認識するようになったのか」ということを長い間考え続けており、本を読むだけでなく身近な人にも何人か問うたことがある(ちなみに日本人の大半が無宗教を自認していることは聞き取り調査で継続的な数値的データとして確認できる)。それに対する答えは様々で、例えば「アメリカ的物質至上主義」、「共産主義」、「多神教と宗教的混交で元から宗教的帰属意識が薄弱だった」などが挙げられる(ちなみに私は2004年にトルコでこの質問を受けた際、明治期の神仏分離と廃仏毀釈が宗教意識に大きな影響を与えた、という趣旨の答えをしている)。
では、これらは妥当な認識なのだろうかと考えてみるに、「アメリカ的物質至上主義」なら「じゃあアメリカは何であんなに宗教的な国のままなの?」という反論がすぐさま返されるし、「共産主義」なら「じゃあその総本山とも言うべきロシアでは正教が今も盛んで、宗教が抑圧されていたソ連時代でさえ密やかに信仰を守っていた人も少なくなかったのか?」という反論が出てくる。最後の「多神教と宗教的混交」についても、インドという反証を提示することは容易だろう(言い換えれば、それらを他国と比較検証すると、少なくとも十分条件ではないと気付けるのである)。
日本人の大半が無宗教を自認しているという定量的事実に対し、その理由に関する考察はデータや文献資料に基づかない思い付きだからこういうことが起こるわけだが、だからこそ逆に日本人の世界理解や自己認識を表すものとして興味深いとも言える。例えば「共産主義」に関して言えば、1960年代の学生運動のイメージが強固であることを示している、といった具合に(当時の大学進学率もあわせて考えると、そこへの参画は決してマジョリティなどではなく、「共産主義」の影響も限定的であったと言える。前に取り上げた小熊英二の『生きて帰ってきた男』をはじめすでに様々指摘があるが、そこへ関わった人々が知識階級として発信力があるため、一種の「ノイジーマイノリティー」としてその存在が強く印象付けられているという点に注意を喚起したい)。
あるいはそういった自己認識(自己評価)の中で欧米との比較(距離感)はしばしば問題とするのに、アジアとの比較はしばしば抜け落ちる現象が見られることを、私は「脱亜入欧的オリエンタリズム」と名付けた(例えば日本人の宗教意識を論じるの際に韓国の話が出てきたケースは管見の限り見たことがないが、宗教が混交した仏国寺の有様などが取り上げられないのは実に不思議なことである)。これも、評価はさておくとしてそういう傾向が見られることを認識しておくことは有益だろう。
というわけで、筆者のアプローチ方法はひとり民俗学的なものに限らず、様々な領域において有益であると再度強調しておきたい。
【悪い点】
では本書で問題を感じる部分について言及したい。本書は基本的に近代や近代化について警鐘を鳴らすという方向で書かれている。よって例えば近代の根幹をなす自然と人間の二項対立的捉え方を批判したり、人間理性を感情の上位に置くような捉え方に批判的な記述をしている。
そのようなスタンスは理解できるが、ゆえにこそいささか行き過ぎの危うさを感じさせる部分が散見される。例えば、「欲」や「自我」に流される人間に対し、自然とは「あるがまま」だと述べているが、それほど単純化できるものかは疑問である。後者は本能に駆動された自動的行為の集積で善悪の彼岸にあると捉えるのであれば、例えば猫がゴキブリの子供を遊びで殺すようなものは、防衛本能とも狩猟本能とも言い難いだろう。これはどのように評価するのか。また、それが止むに止まれぬものであるのかどうかは、イルカなど彼らの「言語」を解明できてないだけということはないのか(ちなみにイルカは賢いだけに止むに止まれぬと言えるか微妙な狡知さや残虐さも見せる点に注意を喚起して起きたい)?確かに、筆者は自然を人間が支配すべき下位の存在とはみなしていない。しかしながら、「自然とは~な存在である」というレッテルで一括りにして語っている点においては、結局二項志向からは抜け出せていないと思うのである(例えば先に書いたイルカの「狡知」や「残虐」という表現を人間の側の勝手な評価だとみるのは一理あるが、だとしたら生存本能に属さない人間の富への欲望を悪とみなすのもまた、手前勝手な評価ではないのだろうか?)。
また、今の話にも連動するが、理性や意識に基づいた「知性」重視を危険視し、「直観」や身体に刻み込まれた「感覚」の重要性を強調しているが、これもいささか危うさを感じる。もちろん、例えば「理性」>「感情」のような見方はあまりに一面的で短絡的すぎて話にならないとは思うが、一方で意識に関する記事でも触れたように、そもそも「人間というレセプターが万能ではないがゆえの必謬性」という視点が欠落したまま直観や感覚は過たないかのような書き方をするのは、単に近代的世界理解の逆張りに過ぎないと私は考える(ちなみにこういう手合いは「生ー権力」的な人間コントロールをしようとする人々にとっては実に都合のよい存在である)。一つだけ例を挙げておくなら、私たちは「重力」というものを実感できない。ならば、重力は存在しないのだろうか?そのような発想をするのならば、「重力はない→地球は丸いはずがない(落ちてしまうから)→よって地球は平たい」というフラットアーサー的思考につながることであろう(地球が平面だとすると、諸々の観察される事象との比較検証によって様々な矛盾が生じるがわかり、それとの整合性がどうなるのかという問題に行き当たる)。
以上を踏まえると、筆者のスタンスもまた、近代批判の興味深いパターンの一つとして批判的に論じられるべきものと言えるだろうと述べつつ、この稿を終えたい。

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます