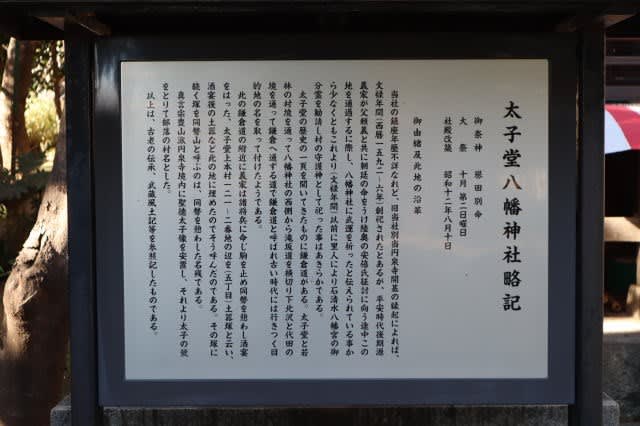数日前まで台風9号の雨予報だったのが、雨の心配がなくなり代わりに暑さの心配をしなければならないという日でした。。ウォーキングスタート10時の暑さ指数実績が30.6、11時は30.2でした。指数予報が31.0以上だと熱中症警戒情報が「危険」となり活動を中止しているのでぎりぎり活動ができるレベル。暑い中10人以上が集まってのウォーキングとなりました。

自由が丘駅前
スタートは自由が丘。現在駅前のビルが建て替え工事中です。

九品仏川緑道

緑道のユリ
自由が丘駅付近にはストレッチができる公園などがないのでいきなり緑道を歩き始めます。白いユリ、咲き始めといった感じ。

九品仏浄真寺東門

緑豊かで気温が少し下がった感じ

山門の仁王像

「おめんかぶり」で有名
山門の脇をお借りしストレッチ。備えていったのですが蚊に刺されました。山門を入り右側に世田谷区の花であるサギ草が見られる場所があります。今年はまだ早いのか数輪咲いているだけでした。

御本堂

上品堂(改修中)

下品堂
上品堂、中品堂、下品堂それぞれに三体ずつの阿弥陀如来座像が鎮座して合計九体。これが九品仏の由来です。現在九品佛大修繕事業が行われており九体すべてお揃いではありませんが、修繕が終わってピカピカの仏様とお会いすることができます。

大平ブドウ園
九品仏の後ねこじゃらし公園を通り西へ進むとブドウ園がありました。

玉川神社

椎の木根張り
目黒通りを横断すると玉川神社。こちらでストレッチをして等々力駅まで歩いてこの日のウォーキングは終了です。以前は等々力渓谷を歩き等々力八幡まで行っていたのですが、等々力渓谷が倒木で閉鎖されているので、駅で解散となりました。
12時の暑さ指数は33.4、13時は33.5、その時間帯にはすでに渋谷へ移動しライオンでおいしいビールをいただいていました。
すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。
まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。
sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。
すこやか歩こう会活動スケジュール
参加を希望される方はご一報ください。

自由が丘駅前
スタートは自由が丘。現在駅前のビルが建て替え工事中です。

九品仏川緑道

緑道のユリ
自由が丘駅付近にはストレッチができる公園などがないのでいきなり緑道を歩き始めます。白いユリ、咲き始めといった感じ。

九品仏浄真寺東門

緑豊かで気温が少し下がった感じ

山門の仁王像

「おめんかぶり」で有名
山門の脇をお借りしストレッチ。備えていったのですが蚊に刺されました。山門を入り右側に世田谷区の花であるサギ草が見られる場所があります。今年はまだ早いのか数輪咲いているだけでした。

御本堂

上品堂(改修中)

下品堂
上品堂、中品堂、下品堂それぞれに三体ずつの阿弥陀如来座像が鎮座して合計九体。これが九品仏の由来です。現在九品佛大修繕事業が行われており九体すべてお揃いではありませんが、修繕が終わってピカピカの仏様とお会いすることができます。

大平ブドウ園
九品仏の後ねこじゃらし公園を通り西へ進むとブドウ園がありました。

玉川神社

椎の木根張り
目黒通りを横断すると玉川神社。こちらでストレッチをして等々力駅まで歩いてこの日のウォーキングは終了です。以前は等々力渓谷を歩き等々力八幡まで行っていたのですが、等々力渓谷が倒木で閉鎖されているので、駅で解散となりました。
12時の暑さ指数は33.4、13時は33.5、その時間帯にはすでに渋谷へ移動しライオンでおいしいビールをいただいていました。
すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。
まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。
sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。
すこやか歩こう会活動スケジュール
参加を希望される方はご一報ください。