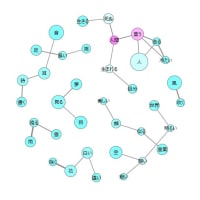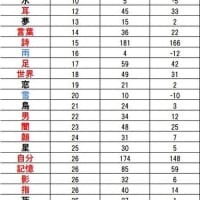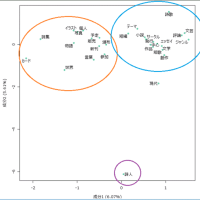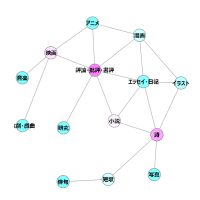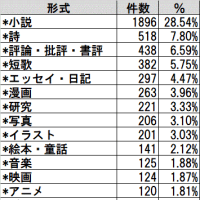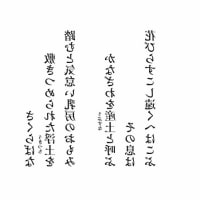八木重吉は、病床にあって、次のような詩句を記した。以前にも引用したが、生前の草稿にあった言葉である。
○
ナニ、あとで分かるさ――
ホホウ! 外はひどく寒む相だ
○
私は一人のヤソ教徒
それの外はなんでもない
なんにも無い――オーッ 寒ム
口語と、一括りで何かを語ろうとしているが、それは文語に対する、いわゆる「しゃべり言葉」と焦点を一旦絞ってみようとしたが、どうもそうすれば、今本稿を継続して記していることの意図が、かすんでしまうように思えてきた。
たとえばその枠取りを少し緩めて『口語的切実』といってみればどうだろう。八木の口語的な切実は、上に引いた詩句の場合「寒い」という実感吐露になっている。これは容易く読むことができる。しかし、この容易さという詩における結び目は、いざ解いていこうとすれば即座に、強い力で抵抗されることに気づく。なぜかというと、この「寒い」という実感は、まさにその時の、時間と気象、病態である八木の刹那を、高速にどんな喩えにも迂回することはなく、直情的に記録されているからだろう。しかも、それが喩えでないことにおいて、逆に、哀れさという切実がじんわりと滲み出してくるのである。その意味では、喩えではないと言っておきながら、ある種、潜まされた多層の感情が深く堆積され、その感情の束の尖端が、口語的切実として地表に晒されていると言うことができるのかもしれない。つまり、この口語もまた、ひとつの喩えであり、八木自身の身体から実際に絞り出た嘆息の「自家引用」と解すこともできるのである。
私は、本稿で口語的なものを探索することで、一体何を、あるいはどんな隘路という可能性を見つけ出そうとしているのか。ごく素朴に発言すれば、それは自由詩の「自由」をもう一度探し出したいということと、喩えに頼らない切実さの在り処を探りたいということだった。幼い発想かもしれないが、どうも単純に、最近書かれている詩にこの、自由と切実が欠けているのではないかと考えていたのは、確かだ。
詩を書き始めた頃より、あるいは詩を読み始めた頃より、ずっと大切にしている詩がある。高見順が、亡くなる直前に発表(1964年)した詩集『死の淵より』からの一篇。
電車の窓の外は
光りにみち
喜びにみち
いきいきといきづいている
この世ともうお別れかと思うと
見なれた景色が
急に新鮮に見えてきた
この世が
人間も自然も
幸福にみちみちている
だのに私は死なねばならぬ
だのにこの世は実にしあわせそうだ
それが私の心を悲しませないで
かえって私の悲しみを慰めてくれる
私の胸に感動があふれ
胸がつまって涙が出そうになる
団地のアパートのひとつひとつの窓に
ふりそそぐ暖い日ざし
楽しくさえずりながら
飛び交うスズメの群
光る風
喜ぶ川面(ルビかわも)
微笑のようなそのさざなみ
かなたの京浜工場地帯の
高い煙突から勢いよく立ちのぼるけむり
電車の窓から見えるこれらすべては
生命あるもののごとくに
生きている
力にみち
生命にかがやいて見える
線路脇の道を
足ばやに行く出勤の人たちよ
おはよう諸君
みんな元気で働いている
安心だ 君たちがいれば大丈夫だ
さようなら
あとを頼むぜ
じゃ元気で――
長々と引いたが、そうせざるを得ない。言葉がどこまでも途切れない。しかも一篇がまるごと迫ってくる。
「だのに私は死なねばならぬ/だのにこの世は実にしあわせそうだ」と高見は、書いている。書いているというよりも、呟いているといったほうがいいかもしれない。この「だのに」のリフレインに驚く。高見は、元々広く大衆にまで浸透した幾つもの小説を著している。詩は、特別であったかもしれない。ただ、晩年になって詩に戻った。熟練の作家が、一読して、軽々とした言葉の態で、「死なねばならぬ」という嘆息の前に、その嘆息を強調するかのように「だのに」と無防備に呟いている。
文庫版「死の淵より」の解説で鮎川信夫は、はからずも「小説表現の復讐」と書いているが、この軽々とした「だのに」の重なる呟きに、私は、高見にとっての、詩的な獲得、あるいは「復讐」などではなく、詩の奪還を感ずる。鮎川は、また、次のようにも書いている。
主観に徹して客観を踏みはずさず、対象を見詰めることが、とりもなおさず自己を凝視することにほかならないといえるのは、そこに「喩」が成立しているからであるが、ほとんど直観的に詩が成立するというこの発見は、高見順にとってけっして小さなものではなかったはずである。
このことは、高見の次の詩で、如実に語られている。
円空が仏像を刻(ルビきざ)んだように
詩をつくりたい
ヒラリアにかかったナナ(犬)が
くんくんと泣きつづけるように
わたしも詩で訴えたい
カタバミがいつの間にかいちめんに
黄色い花をつけているように
わたしもいっぱい詩を咲かせたい
飛ぶ鳥が空から小さな糞(ルビふん)を落とすように
無造作に詩を書きたい
時にはあの出航の銅鑼(ルビどら)のように
詩をわめき散らしたい
私は先に「潜まされた多層の感情が深く堆積され、その感情の束の尖端が、口語的切実として地表に晒されている」と書いた。これは、鮎川が言うように喩的な内実とも言えるかもしれないが、私にはそれが、喩として褶曲する以前に霧散した、感情の束と感じられる。
詩における喩法の由来をたどれば、そこに一旦は、像(イメージ)となった断片(紙切れ)が見える。象徴的な画と言ってもよい。それを言葉に変えていく。変えていくときに象徴の束は、横の平面に並べられるか、ただ縦に堆積される。口語的切実とは、この堆積されたものの、地表に出た突端なのだろう。これはもう、象徴性すらない。
「わめき散らされた」「訴え」であり、「糞」であり「銅鑼の音」なのだ。
そこに詩がないとは言えない。むしろそこに詩が抜け出していく隘路の態が私には見えてくる。
○
ナニ、あとで分かるさ――
ホホウ! 外はひどく寒む相だ
○
私は一人のヤソ教徒
それの外はなんでもない
なんにも無い――オーッ 寒ム
口語と、一括りで何かを語ろうとしているが、それは文語に対する、いわゆる「しゃべり言葉」と焦点を一旦絞ってみようとしたが、どうもそうすれば、今本稿を継続して記していることの意図が、かすんでしまうように思えてきた。
たとえばその枠取りを少し緩めて『口語的切実』といってみればどうだろう。八木の口語的な切実は、上に引いた詩句の場合「寒い」という実感吐露になっている。これは容易く読むことができる。しかし、この容易さという詩における結び目は、いざ解いていこうとすれば即座に、強い力で抵抗されることに気づく。なぜかというと、この「寒い」という実感は、まさにその時の、時間と気象、病態である八木の刹那を、高速にどんな喩えにも迂回することはなく、直情的に記録されているからだろう。しかも、それが喩えでないことにおいて、逆に、哀れさという切実がじんわりと滲み出してくるのである。その意味では、喩えではないと言っておきながら、ある種、潜まされた多層の感情が深く堆積され、その感情の束の尖端が、口語的切実として地表に晒されていると言うことができるのかもしれない。つまり、この口語もまた、ひとつの喩えであり、八木自身の身体から実際に絞り出た嘆息の「自家引用」と解すこともできるのである。
私は、本稿で口語的なものを探索することで、一体何を、あるいはどんな隘路という可能性を見つけ出そうとしているのか。ごく素朴に発言すれば、それは自由詩の「自由」をもう一度探し出したいということと、喩えに頼らない切実さの在り処を探りたいということだった。幼い発想かもしれないが、どうも単純に、最近書かれている詩にこの、自由と切実が欠けているのではないかと考えていたのは、確かだ。
詩を書き始めた頃より、あるいは詩を読み始めた頃より、ずっと大切にしている詩がある。高見順が、亡くなる直前に発表(1964年)した詩集『死の淵より』からの一篇。
電車の窓の外は
光りにみち
喜びにみち
いきいきといきづいている
この世ともうお別れかと思うと
見なれた景色が
急に新鮮に見えてきた
この世が
人間も自然も
幸福にみちみちている
だのに私は死なねばならぬ
だのにこの世は実にしあわせそうだ
それが私の心を悲しませないで
かえって私の悲しみを慰めてくれる
私の胸に感動があふれ
胸がつまって涙が出そうになる
団地のアパートのひとつひとつの窓に
ふりそそぐ暖い日ざし
楽しくさえずりながら
飛び交うスズメの群
光る風
喜ぶ川面(ルビかわも)
微笑のようなそのさざなみ
かなたの京浜工場地帯の
高い煙突から勢いよく立ちのぼるけむり
電車の窓から見えるこれらすべては
生命あるもののごとくに
生きている
力にみち
生命にかがやいて見える
線路脇の道を
足ばやに行く出勤の人たちよ
おはよう諸君
みんな元気で働いている
安心だ 君たちがいれば大丈夫だ
さようなら
あとを頼むぜ
じゃ元気で――
(「電車の窓の外には」全篇)
長々と引いたが、そうせざるを得ない。言葉がどこまでも途切れない。しかも一篇がまるごと迫ってくる。
「だのに私は死なねばならぬ/だのにこの世は実にしあわせそうだ」と高見は、書いている。書いているというよりも、呟いているといったほうがいいかもしれない。この「だのに」のリフレインに驚く。高見は、元々広く大衆にまで浸透した幾つもの小説を著している。詩は、特別であったかもしれない。ただ、晩年になって詩に戻った。熟練の作家が、一読して、軽々とした言葉の態で、「死なねばならぬ」という嘆息の前に、その嘆息を強調するかのように「だのに」と無防備に呟いている。
文庫版「死の淵より」の解説で鮎川信夫は、はからずも「小説表現の復讐」と書いているが、この軽々とした「だのに」の重なる呟きに、私は、高見にとっての、詩的な獲得、あるいは「復讐」などではなく、詩の奪還を感ずる。鮎川は、また、次のようにも書いている。
主観に徹して客観を踏みはずさず、対象を見詰めることが、とりもなおさず自己を凝視することにほかならないといえるのは、そこに「喩」が成立しているからであるが、ほとんど直観的に詩が成立するというこの発見は、高見順にとってけっして小さなものではなかったはずである。
このことは、高見の次の詩で、如実に語られている。
円空が仏像を刻(ルビきざ)んだように
詩をつくりたい
ヒラリアにかかったナナ(犬)が
くんくんと泣きつづけるように
わたしも詩で訴えたい
カタバミがいつの間にかいちめんに
黄色い花をつけているように
わたしもいっぱい詩を咲かせたい
飛ぶ鳥が空から小さな糞(ルビふん)を落とすように
無造作に詩を書きたい
時にはあの出航の銅鑼(ルビどら)のように
詩をわめき散らしたい
(「円空が仏像を刻んだように」全篇)
私は先に「潜まされた多層の感情が深く堆積され、その感情の束の尖端が、口語的切実として地表に晒されている」と書いた。これは、鮎川が言うように喩的な内実とも言えるかもしれないが、私にはそれが、喩として褶曲する以前に霧散した、感情の束と感じられる。
詩における喩法の由来をたどれば、そこに一旦は、像(イメージ)となった断片(紙切れ)が見える。象徴的な画と言ってもよい。それを言葉に変えていく。変えていくときに象徴の束は、横の平面に並べられるか、ただ縦に堆積される。口語的切実とは、この堆積されたものの、地表に出た突端なのだろう。これはもう、象徴性すらない。
「わめき散らされた」「訴え」であり、「糞」であり「銅鑼の音」なのだ。
そこに詩がないとは言えない。むしろそこに詩が抜け出していく隘路の態が私には見えてくる。
つづく