Ⅱ)組織ぐるみの女性差別犯罪と国鉄労働運動破壊の事実を隠蔽しては
ならない(続)
――破廉恥、あまりにも破廉恥なり‼ 革共同26全総(その2)
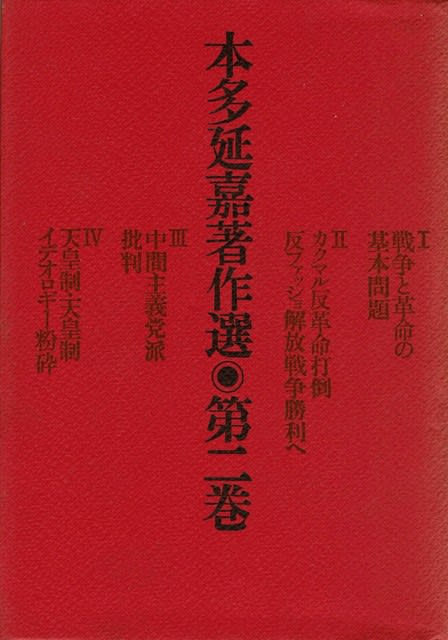
(承前)
●本多646号論文の地平を全否定した26全総決定
以上のことから、「党と労働組合の一体的建設」論において中野洋の軍門に下った清水丈夫の姿が浮き彫りになる。その清水が果たした犯罪的な役割を明らかにしなければ、この問題を解明、総括することにはならない。
26全総決定では、次の清水の文章を麗々しく引用している。
「3全総路線……これはまさに、今日の革共同の〈党と労働組合の一体的建設〉という路線の原型モデルともいうべきものであった。」(『革命的共産主義運動の50年/現代革命への挑戦〈上巻〉』序章=清水丈夫執筆、13年12月刊)
この清水の一文とそれを美化する26全総決定は、革共同の歴史的な到達地平をことごとく否定し、解体するものである。とりわけ本多の『前進』646号論文「革命闘争と革命党の事業の堅実で全面的な発展のために」に対立・敵対するものである。
周知のように、三全総は1966年第3回大会へと進化し、1967年10・8羽田闘争に始まる「激動の7カ月」、そこにおける1968年革命の高揚、1969年10・11月安保・沖縄決戦、1971年11月沖縄返還協定粉砕決戦という階級決戦に発展した。同時に反戦青年委員会運動(反戦派労働運動)や全国的な全共闘運動の内部に、三全総の実践が貫かれていった。いいかえれば、革命的統一戦線戦術をも打ちだした三全総は、ひとり革共同の路線であるにとどまらず、三派共闘、五派共闘、八派共闘という試みや全共闘運動および反戦青年会運動というラディカル左翼の運動全体に寄与する党的土台として発展していった。
もちろん、そこにおける革共同の主流派主義、セクト主義、大衆運動の利益の上に党派利害を置く誤りを一つひとつ自己批判的に総括しなければならないが、ここでは捨象させていただく。
理論的には、三全総は、第3回大会の三つの報告(第1報告=陶山健一、第2報告=清水丈夫、第3報告=本多延嘉)へと進化し、本多延嘉「70年安保闘争と革命的左翼の任務」(1969年4月、10月大幅加筆)、同「戦争と革命の基本問題」(1972年6月)、同「レーニン主義の継承か、レーニン主義の解体か」(1972年9月、1973年1月大幅加筆)、同「偉大な勝利の道」(1973年1月)、同「革命闘争と革命党の事業の堅実で全面的な発展のために(646号論文)」(1973年8月)、津久井良策(清水丈夫)「70年代中期におけるわれわれの政治的・組織的・軍事的任務」(1973年10月)として内的に発展していった。
それらはどれ一つ欠くことができない歴史的文献であるが、本多「継承か解体か」論文を引き継ぐ本多646号論文が革共同の理論と実践を総括し、革共同のプロレタリア革命論を集大成し、それを凝縮した理論という位置をもっている。この意味で、三全総は本多646号論文へと止揚されたといっていいだろう。
ちなみに、津久井(清水)「70年代中期」論文は、646号論文に学び、それを内容的にリフレインするものであるが、対カクマル戦激化論を補強するものでもあった。646号論文は、対カクマル戦の初期的劣勢の段階で執筆されたものであり、実際その後、対カクマル戦がますます激化していったという歴史的諸関係のもとでは、ただちに党の現実の方針とするには‘早すぎた提起’という限界をもっていた。そのため、本多自身が「646号論文をいったんお蔵入りさせる」と語っていたのだった。そして本多は、自ら最先頭に立ち、全身全霊をあげて二重対峙・対カクマル戦争を指導し、その渦中で反革命カクマルの1975年3・14反革命によって虐殺された。646号論文からの1年半は、まさに646号論文を蔵出しし本格的な軌道に乗せるための、本多の強い使命感に満ちた、血みどろのたたかいの日々だったのである。
「継承か解体か」論文と646号論文は、革共同書記長・本多延嘉が10年余にわたって練り上げ、かつ死をかけて守りぬいたプロレタリア革命の壮大な構想あるいは共産主義運動の理想型である。これは、時代的制約性と一定の限界をもちつつも、普遍的な歴史的意義をもつと、筆者らは考えている。このことを改めて明確にさせることによって初めて、本多を先頭とする革共同の地平を〈守り・破り・離れる〉たたかいが可能になるであろう。そのことを、21世紀革命とその一環である日本帝国主義打倒の日本革命の今日的な戦略的課題と重ね、相互に弁証法的に往還させることで、次の展望を切り開くことができるのではないだろうか。なお、論文「戦争と革命の基本問題」の思想史的意義については後述する。
その本多646号論文(『本多延嘉著作選』第2巻所収)には、次のような重要かつきわめて基礎的な規定がある。とくに下線に注目してほしい。
「(3)経済闘争とは、労働者階級の直接の経済的利益をまもり、改善するための集団的なたたかいであり、労働者階級と人民大衆の完全な解放をめざすたたかいの一翼をなすものである。
経済闘争の主要な形態をなすものは労働組合運動である。(中略)労働者階級の経済闘争は、真の革命党の指導を基礎とすることなしには、労働者の直接の経済的利益をまもり、改善するたたかいという面でも、労働者階級と人民大衆の完全な解放をめざすプロレタリア階級闘争の一翼としてたたかうという面でも、真の階級的な前進をかちとることはできないのである。
それゆえ、われわれは、一方では労働組合運動にたいし、党の独自活動をとおして共産主義の政治、侵略を内乱に転化しプロレタリア独裁をかちとることをめざす政治闘争を系統的にもちこむとともに、他方では、労働者階級の経済闘争をかちとる観点から現実の経済闘争を指導し、たたかいぬき、当面その総括点を労働戦線における党組織の建設の前進、それを基礎とした労働組合運動でのヘゲモニーの前進にまとめあげていかなくてはならないのである。また、経済闘争・権利闘争の対政府闘争、政治闘争としての発展にたいしては、政治闘争を経済闘争・権利闘争の継続としてだけ承認しようとする組合主義の政治や、革命に敵対する改良主義の政治の立場からではなく、侵略を内乱に転化し、プロレタリア独裁をかちとることをめざす政治闘争の立場から、その革命的、内乱的な発展をめざしてたたかうのである。
社会党支持か、政党支持の自由か、という反動的で反階級的な論争の現実にたいし、われわれは、労働戦線における党組織の建設の前進と、それを基礎とした労働運動の革命的、内乱的な推進をとおして、「党と労働組合のより緊密な接近」(シュツットガルト大会)の課題を実践的に解決していかなくてはならないのである。侵略の内乱への転化、プロレタリア独裁樹立をめざす真の革命党が、その主要な勢力として労働戦線における強大な党組織を建設し、それを基礎として労働運動の革命的、内乱的発展をかちとることなしには、党と労働組合の問題の解決は、けっしてありえないのである。」
「共産主義者の政治的結集体としての党は、職業上、産業上の一致を基礎とした労働組合組織、資本にたいする現実の関係の一致を基礎とした労働組合組織とは異なり、資本主義の打倒と共産主義的解放の達成、そのための当面する結節環をなすプロレタリア独裁の樹立、という共産主義的意識と共産主義的政治を唯一の共同の立脚点とする共産主義者の団結形態であり、ただ革命の勝利にのみ未来を見いだす革命家の団結形態である。だからこそ、党は現実の直接的利益の一致を基礎とした労働者の種々の組織にたいし、共産主義の意識、共産主義の政治を系統的にもちこむことができるのであり、また、労働者階級の全体の利益のいっかんした代表者として、労働者の個々のたたかいにたいし、真の援助と指導を与えることができるのである。」
ここに引用した646号論文の諸規定は、じつは三全総の立脚点を、その後の10年間の実践を通して改めて浮かび上がらせるものでもある。ここからは、「党と労働組合の一体的建設」などという、党と労働組合を並列させる初歩的な誤りが出てくるわけもない。党と労働組合をその区別と連関においてとらえることができないことは、階級闘争のイロハがわかっていないことを示している。「労働運動の力で革命を」「団結の拡大が革命である」などというかけ声も、同じレベルの誤りである。したがって、646号論文の地平に立てば、三全総の意図的な解釈替えなどが成り立つ余地もまったくないのである。
すなわち、26全総決定と清水は、三全総を右翼的経済主義的に解釈替えするとともに、本多646号論文の地平を全否定し、解体しようとするものである。それは、本多の無念を踏みにじり、本多を先頭にした革共同の理論的・実践的構築物を破壊する許しがたい裏切りなのである。
●ついに革共同になれなかった清水丈夫
先に引用した清水の文章――「3全総路線……これはまさに、今日の革共同の〈党と労働組合の一体的建設〉という路線の原型モデルともいうべきものであった」――には、日本の革命運動、社会運動において「歴史上の著名な人物」となっている清水丈夫という人が、1950年代半ば以降、さまざまな内的葛藤や研鑽をつみながらも、ついに革共同にはなれなかったという悲しい歴史的現実が投影されている。
清水は、なにゆえにこのようなデマというべき、でたらめな文章を書いたのだろうか。いや、なにゆえにこれほど愚劣かつ低水準な文章を書けるのだろうか。
清水は、第一に、1962年革共同三全総が内的に発展した歴史、とりわけ本多「継承か解体か」論文と646号論文に到達した地平を弁証法的につかみとることがまったくできていない。
第二に、中野の親分・子分の組織論の軍門に下り、「共産主義の政治」を投げ捨ててしまった。そのため7・7自己批判の立場をも投げ捨て、排外主義・差別主義・権威主義とのたたかいを追放してしまった。
第三に、中野のいいなりに、労働運動を経済主義・組合主義に押しとどめようとし、動労千葉のたたかいをも職能主義的組合主義に落とし込めようとした。そして、「労働運動の革命的、内乱的推進あるいは発展」(646号論文)に反対するという、きわめて反動的、反階級的な役割をしている。
第四に、革共同の党組織論およびその基礎にあるレーニン『なにをなすべきか』を主体的につかみとることに失敗し、自らの思想的・政治的なアイデンティティーを喪失している。
第四の点を敷衍すると、革共同を革共同たらしめてきた要素の一つ、あえていえば、革共同が他のラディカル左翼党派と区別される根拠は、レーニン『何をなすべきか』を基礎とする党組織論にある。革共同の反スターリン主義思想も、きわめて早い時期での自らの党組織論の確立とそれへの確信なしにはありえなかった。
それにたいして、清水はブント時代から、とくにプロレタリア通信派結成においても、また革共同加入時期においても、さらに黒田寛一の陰謀的分派フラクに加わったことを自己批判して本多派に合流したときにも、その都度、『何をなすべきか』の学習の重要性を強調してきた。その後も、レーニン党組織論のもっとも忠実な実践者であるかのように振る舞ってきた。しかし、じつは、彼は党組織論を部分的に語り執筆することはあっても、まとまった党組織論はなにもない。そのことは、筆者らが革共同に籍を置いていたとき、ずっと不思議に思ってきたのだった。
党組織論の分野では、清水は本多に依拠し、本多死後は木下尊晤(野島三郎)に依拠してきたのが、偽らざる実態だったのではないだろうか。
清水が「最大多数の最大幸福がオレのやり方なんだってことを、お前らは、どうしてわからなかったんだ」と語ったことを、筆者らは忘れない(『革共同政治局の敗北』第2章第3節参照)。このことばが示すように、清水の組織論は、しょせん組織運営の政治技術論でしかなく、党内力学相互作用論でしかない。だが、党組織論はそんなものではない。
党組織論は、一人ひとりの共産主義者の思想性を絶対的基礎にして初めて成り立つ。したがって党組織論は、目的意識的な運動である共産主義運動を実体的に保証するという位置にある。このことは反スターリン主義の原点なのである。
同時に次の問題も厳格に確認しておかなければならない。すなわち、共産主義者の党といえども、ひとたび帝国主義国家権力とのたたかいにたじろぎ、反革命との対決をネグレクトすることがあるならば、その党組織はたちまち支配と服従のシステムおよび論理によって党内外への抑圧者に転化してしまうのである。このことは世界革命運動の血の教訓であり、革共同の反スターリン主義は、このことへの組織論的な反省を内在化しようとしたのである。
つまり、清水は、本多を先頭に鍛え上げてきた革共同の反スターリン主義党組織論を、ついにつかむことができなかったというべきであろう(註5)。
清水を議長に押し戴くような組織には、何の党組織論もない。26全総決定がそのことを端的に示している。党組織論がない党派は、思想的・政治的なアイデンティティーをもたないがゆえに存立しえない。ただ液状化するのみである。
【註1】山梨=神奈川県委員会湘南支部の一員ではなくキャップという情報がある。中央WOBに選抜されたのだから、神奈川県委員会の指導的位置、支部キャップである可能性は高い。山梨は、1970年代の二重対峙・対カクマル戦から逃亡し、長らく関西にいて、2013年ごろに神奈川に舞い戻ってきたそうである。そしてすぐに中央WOBとなっていた。以前から天田と黒川のお気に入りだったと考えてもおかしくない。
【註2】中野洋崇拝を一挙に強めた中央派においては、マル青労同のメンバーたちが「安田親衛隊」を結成した。彼らは、06~08年には驚くべきことに、「安田 命」と刻んだストラップを特注して常に身に着け、大衆運動場面では、「安田 命」と染め抜いた鉢巻をして登場した。中国文化大革命で「毛沢東語録」を掲げた紅衛兵が組織され、暴威をふるったが、まさに「中野(安田)紅衛兵」が登場したのだった。
【註3】「グルジアのスターリン」=革命ロシアにおいて、ロシア帝国主義の大ロシア主義によって抑圧されてきた諸民族の帰属と分離をめぐってどのような民族政策をとるべきか、その理論はいかにあるべきかが現実的な問題となっていた。1921年~22年にグルジア問題が生起した際に、スターリンはグルジアの民族自決の要求を拒絶し、グルジアをソビエト連邦に強制的に併合する方針をとった。それは同時にグルジアの共産党指導部を政治的に弾圧する粛清として強行された。病床のレーニンがスターリンと決別し、民族自決の意義を訴え、大ロシア主義を強く批判し、スターリンの書記長解任を求めた。それは「レーニンの最後の闘争」となった。グルジア人であるスターリンが率先して大ロシア民族主義をもってグルジア民族を裏切り、グルジアの民族自決を絞殺したことは、スターリン主義成立の本質的な規定要因となった。そのようなスターリン主義に特有の卑劣な裏切りと暴力的な圧殺を「グルジアのスターリン」と呼ぶ。
【註4】社会ファシズム論=1920年代のドイツでヒトラー・ナチスが台頭したとき、当時のコミンテルンとドイツ共産党はそれを戦略的にも戦術的にも軽視した。ファシズムと社会民主主義を等置し、むしろ社民党SPDを主要打撃対象とした。トロツキーがそれを批判する社会ファシズム論批判を猛然と展開し、KPDとSPDがともにナチスと対決するドイツ労働者階級の統一戦線を訴えた。一方でのファシズムを戦略的打倒対象とせず、ナチスの台頭と政権掌握をもたらしたスターリン主義の致命的な誤りとその階級的犯罪性、他方でのトロツキーの悲痛かつ断固とした社会ファシズム論批判=革命的統一戦線論は、1930年代の国際階級闘争の普遍的な教訓である。
【註5】清水丈夫と『なにをなすべきか』=中核派は、1960年代以来、マルクス、エンゲルス、レーニンの著作から「中核派学習指定文献」を選定し、それらを集団的・個別的に学習してきた。その後、それら指定文献の解説書として『マルクス主義基本文献学習シリーズ』を企画・出版してきた。清水丈夫が監修者だった。筆者も加わっていた時期があるので、大いに責任があるが、これまでに7文献が取り上げられた。未出版は、『経哲草稿』、『家族・私有財産および国家の起源』、『なにをなすべきか』、『帝国主義と民族・植民地問題』などである。それら未出版4文献はどうやら、今後も企画・出版されそうにない。なかでも、反スターリン主義の思想的立脚点の形成に決定的だった『経哲草稿』と『なにをなすべきか』が欠けていることは、06年3・14Ⅱ以降の脱革共同というべき思想状況を象徴しているようである。清水が議長であり監修者であるかぎり、この2文献の解説書は出版されないと思われる。とりわけレーニン党組織論『なにをなすべきか』の学習は、「党と労働組合の一体的建設」論を唱えて革共同2019年問題を引き起こした清水たち中央派にとっては、タブーとなっていることであろう。
(つづく)
次回予告:
Ⅲ)共産主義からの逃走――革共同09年綱領の犯罪性
















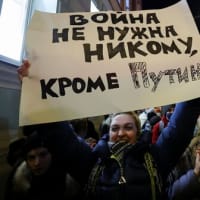


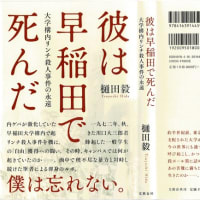
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます