<今までの投稿>
十八松平家・・・平成25年10月16日
竹谷松平家・・・平成25年10月26日
安祥松平家・・・平成25年11月16日
形原松平家・・・平成26年 1月 2日
大草松平家・・・平成26年 2月25日
五井松平家・・・平成26年 4月16日
深溝松平家・・・平成26年 9月30日
能見松平家・・・平成27年 7月 8日
長沢松平家・・・平成27年10月 2日
大給松平家・・・平成28年 3月29日
今日は、滝脇松平家(たきわきまつだいらけ)を紹介いたします。
脇松平家(たきわきまつだいらけ)は、松平親忠の九男・乗清を祖とする松平氏の庶流。三河国加茂郡滝脇(現在の愛知県豊田市)を領したことから滝脇松平家と称した。須原屋版武鑑などで世良田松平氏と表記される場合もある。



松平氏の分家であり、早くから松平宗家の家臣化していた。
乗清から5代目に当たる松平正勝は滝脇分家の麻生松平家の出だが滝脇本家を継いだとも伝えられている。正勝は徳川家康に旗本として仕え、慶長19年(1614年)の大坂冬の陣で功績を立てたが夏の陣の天王寺・岡山の戦いにて討死したため、徳川秀忠の命で形原松平家の松平家信の次男・重信が婿養子として家督を継承した。
重信は、正保2年(1645年)に従五位下丹後守に叙任、小姓組番頭、書院番頭、大番頭と役職を重ねて明暦2年(1656年)から駿府城代を務め、知行も1,200石から駿河国内5,000石まで増加した。
次代もまた形原松平家の丹波篠山藩主・松平典信の庶長子・信孝を養子を迎えた。信孝も累進を重ね、元禄2年(1689年)5月に若年寄となり、それまでの駿河6,000石に武蔵・上野の両国の所領4,000石を加増され、合計1万石で大名となった。有能で知られたが病弱だった信孝は翌元禄3年(1690年)10月18日に36歳で死去した。
次代の 松平信治は旗本の戸田重恒の次男であったが、信孝の外孫にあたり、養子入りして継承した。信治の時に武蔵・上野の所領を駿河国に移され、同国小島の地に陣屋を構えた。駿河小島藩1万石は幕末まで続いた。

滝脇松平氏の陣屋が置かれていた長松院付近現状 滝脇陣屋跡(豊田市滝脇町西洞)

小島陣屋跡(静岡県清水市小島本町)に残る石垣、小大名の居所と思えない構え
滝脇松平氏の別家にて 初代乗清から四代目正勝の系統が大名に列している。
(元禄十一年 1698)
乗清から正勝に至る系譜は三説あり 一定しないが、正勝が徳川家康に仕え千二百石の旗本となったことに始まる。正勝の跡は、形原松平家より養子に入った重信が継ぎ、二千俵の加増を受けた。重信の跡は兄の子信孝が継ぎ、将軍綱吉の側衆、若年寄を勤め一万石の諸侯に列した。
信孝の末期養子には、寄合戸田家から信治が迎えられ、所領を駿河国内に移されている。
宝永元年、駿河国庵原郡小島村に陣屋を構築し小島藩(一万石)を称した。

桜井陣屋(貝淵陣屋)(千葉県木更津市桜井)
明治元年、徳川宗家の駿河入封により 滝脇松平家は 駿河小島より上総桜井に封地替えとなった。桜井藩を称し廃藩を迎えた。
住宅地化され遺構はない。案内碑のみ。
十八松平家・・・平成25年10月16日
竹谷松平家・・・平成25年10月26日
安祥松平家・・・平成25年11月16日
形原松平家・・・平成26年 1月 2日
大草松平家・・・平成26年 2月25日
五井松平家・・・平成26年 4月16日
深溝松平家・・・平成26年 9月30日
能見松平家・・・平成27年 7月 8日
長沢松平家・・・平成27年10月 2日
大給松平家・・・平成28年 3月29日
今日は、滝脇松平家(たきわきまつだいらけ)を紹介いたします。
脇松平家(たきわきまつだいらけ)は、松平親忠の九男・乗清を祖とする松平氏の庶流。三河国加茂郡滝脇(現在の愛知県豊田市)を領したことから滝脇松平家と称した。須原屋版武鑑などで世良田松平氏と表記される場合もある。



松平氏の分家であり、早くから松平宗家の家臣化していた。
乗清から5代目に当たる松平正勝は滝脇分家の麻生松平家の出だが滝脇本家を継いだとも伝えられている。正勝は徳川家康に旗本として仕え、慶長19年(1614年)の大坂冬の陣で功績を立てたが夏の陣の天王寺・岡山の戦いにて討死したため、徳川秀忠の命で形原松平家の松平家信の次男・重信が婿養子として家督を継承した。
重信は、正保2年(1645年)に従五位下丹後守に叙任、小姓組番頭、書院番頭、大番頭と役職を重ねて明暦2年(1656年)から駿府城代を務め、知行も1,200石から駿河国内5,000石まで増加した。
次代もまた形原松平家の丹波篠山藩主・松平典信の庶長子・信孝を養子を迎えた。信孝も累進を重ね、元禄2年(1689年)5月に若年寄となり、それまでの駿河6,000石に武蔵・上野の両国の所領4,000石を加増され、合計1万石で大名となった。有能で知られたが病弱だった信孝は翌元禄3年(1690年)10月18日に36歳で死去した。
次代の 松平信治は旗本の戸田重恒の次男であったが、信孝の外孫にあたり、養子入りして継承した。信治の時に武蔵・上野の所領を駿河国に移され、同国小島の地に陣屋を構えた。駿河小島藩1万石は幕末まで続いた。

滝脇松平氏の陣屋が置かれていた長松院付近現状 滝脇陣屋跡(豊田市滝脇町西洞)

小島陣屋跡(静岡県清水市小島本町)に残る石垣、小大名の居所と思えない構え
滝脇松平氏の別家にて 初代乗清から四代目正勝の系統が大名に列している。
(元禄十一年 1698)
乗清から正勝に至る系譜は三説あり 一定しないが、正勝が徳川家康に仕え千二百石の旗本となったことに始まる。正勝の跡は、形原松平家より養子に入った重信が継ぎ、二千俵の加増を受けた。重信の跡は兄の子信孝が継ぎ、将軍綱吉の側衆、若年寄を勤め一万石の諸侯に列した。
信孝の末期養子には、寄合戸田家から信治が迎えられ、所領を駿河国内に移されている。
宝永元年、駿河国庵原郡小島村に陣屋を構築し小島藩(一万石)を称した。

桜井陣屋(貝淵陣屋)(千葉県木更津市桜井)
明治元年、徳川宗家の駿河入封により 滝脇松平家は 駿河小島より上総桜井に封地替えとなった。桜井藩を称し廃藩を迎えた。
住宅地化され遺構はない。案内碑のみ。

















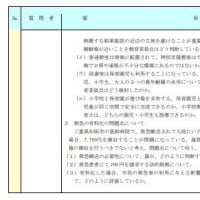









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます