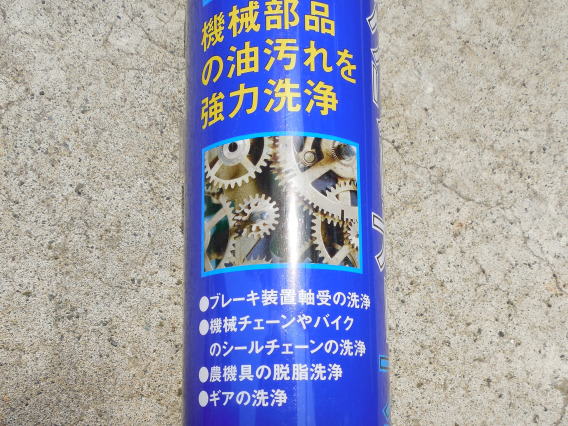土曜日にプラグとプラグキャップを交換したGPZ750R改
月曜日に早く帰れたのでちょっと近所を乗って調子を確かめました。
このGPZ750Rのエンジン、1000RXのエンジンをボアアップして
カムはフルパワー仕様の900用、キャブレターも900用をベースに
モデファイしたもので、中低回転域でも使えるエンジンに仕上げてあります。
だって、このクラスだとピークパワーが10馬力足らないからって言っても
何の問題も無いでしょ?
ベンチにかけて・・・の結果より、実際に乗って楽しいか?というのを
私は重視しています。
で、いつもの乗り方
4速 1500回転からの加速も 5000回転以上の加速も
本来の状態に戻りました。
そういえば、帰りの海老名駅

虹が見えてました。
この後、土砂降りの雨が降ったのですが
自宅の最寄り駅着いたときは、ぜんぜん雨が降った跡がありませんでした。
局地的な雨だったみたいで、まだ明るかったので その後GPZを出した訳です
16日からの東北ツーリング
私がFJ1200、女房がGPZ750R改で行けそうです。
月曜日に早く帰れたのでちょっと近所を乗って調子を確かめました。
このGPZ750Rのエンジン、1000RXのエンジンをボアアップして
カムはフルパワー仕様の900用、キャブレターも900用をベースに
モデファイしたもので、中低回転域でも使えるエンジンに仕上げてあります。
だって、このクラスだとピークパワーが10馬力足らないからって言っても
何の問題も無いでしょ?
ベンチにかけて・・・の結果より、実際に乗って楽しいか?というのを
私は重視しています。
で、いつもの乗り方
4速 1500回転からの加速も 5000回転以上の加速も
本来の状態に戻りました。
そういえば、帰りの海老名駅

虹が見えてました。
この後、土砂降りの雨が降ったのですが
自宅の最寄り駅着いたときは、ぜんぜん雨が降った跡がありませんでした。
局地的な雨だったみたいで、まだ明るかったので その後GPZを出した訳です
16日からの東北ツーリング
私がFJ1200、女房がGPZ750R改で行けそうです。