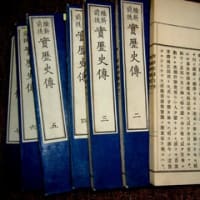田中河内介・その132
外史氏曰
【出島物語ー44】
 土佐の南学―6
土佐の南学―6
会津藩「家訓」十五ヶ条
保科正之は、寛文三年( 一六六三 )、五十三歳の冬から時々吐血し、白内障にも罹ってやがて盲目となる恐れが出て来た。 家老友松勘十郎はしきりにこれを案じ、且つ、会津藩の将来を慮って正之に、これからの藩主や家臣の政治にたずさわる者が永く守るべき家訓(かきん) を作ることを進言した。 保科正之はこの進言により、隠居する前年の 寛文八年( 一六六八 ) に会津藩の憲法ともいうべき、家訓十五ヶ条を制定、国許の御城代田中正玄(まさはる) を江戸に呼び寄せてこれを手渡した。 これが会津藩の教条として永く藩の上下を支配薫陶した 家訓十五ヶ条と言われるものである。
この 「 家訓 」 は、後に続く藩主を含め、家臣たちの心構えとして、会津藩の成り立ちを認識させ、精神面の昂揚と団結をはかり、心のよりどころとするため、藩政の基本を家臣たちに示したもので、この時からちょうど二百年後、会津藩が戊辰戦争に敗れて 滅藩の運命に到るまで、永く会津藩を指導した極めて重要な規範である。
この「 家訓 」 は、先ず山崎闇斎がその草案を作り、正之の意見によって修正を加え、更に又闇斎の意見を徴するなど、反覆論議を繰り返して出来上がったもので、その間に家老の友松勘十郎氏興が種々斡旋する所があったものであろう。 されば固より 正之の意見が主となったであろうが、闇斎は唯々として他の意見にのみ従う性格ではない、闇斎の考えも相当に織り込まれ、両者の一致点の上に出来上がったものと思われる。
現実の政治を行う立場にある正之の啓蒙的専制君主としての姿勢と、聖賢の道を明らかにして風俗を教化させようとする闇斎の理想、そして その為のキーポイントは、公共的な規範意識に支えられた為政者としての武士を創り出す事であるとする闇斎の捉え方とが 互いに共鳴、化合して この「 家訓 」 が出来上がった。
なお、家訓成立の第一の功労者である友松勘十郎氏興(うじおき) は、元豊臣家家臣の裔で、 寛永十一年( 一六三四 )八月に正之が上洛した際、見出されて十三歳にして、正之の小姓として仕えた。 若くから学問、武芸に秀れ、のちにその才能が認められ 寛文三年(一六六三)四十二歳の時、家老に抜擢された。
もとは漢文であるが、以下に、読み下し文でこの家訓十五ヶ条の全文を掲げる。
一、大君の儀、一心大切に忠勤を存ずべく、列国の例を以て自ら処(お) るべからず。
若(も)し二心を懐(いだ)かば、則(すなわ)ち我が子孫に非ず、面々決して従うべからず。
一、武備は怠るべからず。 士を選ぶを本(もと) とすべし。 上下の分を乱るべからず。
一、兄を敬い弟を愛すべし。
一、婦人女子の言、一切聞くべからず。
一、主を重んじ、法を畏(おそ) るべし。
一、家中は風儀を励むべし。
一、賄(まいない) を行ない、媚(こび) を求むべからず。
一、面々依怙贔屓(えこひいき) すべからず。
一、士を選ぶに便辟(べんぺき) 便佞(べんねい) の者(心のねじ曲った者)を取るべからず。
一、賞罰は、家老の外、これに参加すべからず。 若(も) し位を出ずる者あらば、
これを厳格にすべし。
一、近侍者をして、人の善悪を告げしむべからず。
一、政事は、利害を以て道理を枉(ま) ぐべからず。 僉議(せんぎ) は、私意を挟み
人言を拒(ふさ) ぐべからず。 思う所を蔵せず、以てこれを争うべし。
甚だ相争うと雖(いえど) も、我意を介すべからず。
一、法を犯す者は、宥(ゆる) すべからず。
一、社倉は民のためにこれを置く、永利のためのものなり。 歳(とし) 饑(う) えれば
則ち発出して、これを済(すく) うべし。 これを他用すべからず。
一、若しその志を失ない、遊楽を好み、驕奢を致し、士民をしてその所を失わしめば、
則ち何の面目あって封印を戴(いただ) き、土地を領せんや。 必らず上表蟄居(ちっきょ)すべし。
右十五件の旨堅くこれを相守り、以往(以後)、以て同職の者に申し伝うべきものなり。
寛文八年戌申四月十一日 会津中将
家老中
中でも、家訓第一条が最重要になる。 異母兄の三代将軍家光に見出されて信州高遠三万石の大名から会津二十三万石の大大名へと出世し、幕政にも参与して存分に能力を発揮した正之は、終生家光に感謝し続けていた。 託弧の遺命( 家光の遺命として十一歳の家綱の補佐を依頼される ) を忠実に守り、足掛け二十三年間も江戸に留まって四代将軍家綱を補佐し続けたのもそれ故であって、正之にとって会津藩立藩の精神は実にこの家訓第一条にこそ存したのである。
正之は、この家訓を非常に重要なものとして末代まで伝えようとその徹底に力を尽した。 正之は寛文十二年十二月十八日、江戸の藩邸にて六十二歳で死去するが、その年の八月、正之が会津に在る時、世嗣正経が江戸へ参覲のために出発の際に、会津若松城内三の丸の屋敷に於て、正之自ら家訓の趣旨を正経や家老達に懇切丁寧に説明している。 さらに死の三日前には、家訓について遺言し、それを稲葉丹後守を通じて一同に伝えさせている。 この時 友松勘十郎等 家老一同は、もし正之が逝去したならば、御家訓の旨固く相守りつつ 正経に仕えようと、各自血判して その誓紙を正之に差出した。 この後も藩主代替りの時には必ず家訓を守るべき旨を 誓詞に書き付けた。 これでどれ程家訓が重要性を持ったかが判る。 そして、正之薨去後に於ては、友松勘十郎が、家訓の普及徹底に努めている。
以後、毎年正月十一日、八月朔、など、年に二、三度、時を定めて城中で、家訓が読み上げられ、家臣一同がこれを拝聴することになった。
このように、会津藩に於ては家訓を金科玉条として、二百年来、上下共に之を常に心に留め、且つ之を丁重に取り扱ったので、これが藩士の精神上に及ぼした影響は計り知れない程大きい。 それはとりもなおさず、その草案を作った山崎闇斎が及ぼした影響が大きいということでもある。
前田恒治は その著 『 会津藩に於ける 山崎闇斎 』 の中で、次のように述べている。 『 この家訓の最大の特徴は、「 大君之儀・・・・ 」 という冒頭の第一条であろう。 これは、徳川幕府に対して、一心に忠勤を挺んで、二心を抱いてはならぬ誡めであって、徳川幕府至上主義を表明するもので、これが明治戊辰戦役の原因を為し、彼の悲壮なる会津籠城の死守も、これが為であると言う説がある。 果してそうであろうか。
この家訓は前述のように、山崎闇斎が草案を作り、正之が加筆したもので、二人の合作と言ってよいものである。 闇斎は言うまでもなく、有名なる尊皇論者である。 然らば、家訓の内容が、我が国体と一致しないようなものであるならば、闇斎が、これに同意を表する筈が無い。 又正之は 卜部(うらべ)神道家であるから、我が国体に相反するようなものを制定する意志でないことも確かである。 故に 「 二心を懐(いだ) かば、則(すなわ) ち我が子孫に非ず 」 との戒めは、徳川幕府に対するものであるが、同様の事は、皇室に対しても考えていたものに相異ない。 むしろ それは言うを要しない事としていたのであろう。 正之はむしろ不義に対しては従ってはならぬということに重点を置いたように思われる。
会津藩の皇室に対する真精神は、寧ろ、幕末に於ける藩主松平容保が京都守護職に任ぜられた時代に於て、最も能く発揮せられたと言うべきである。 容保は能く難局に當りて、その大任を尽し、孝明天皇の叡感斜ならざるものがあった。 その時容保の奏文中にも、藩祖正之が独り皇朝の道を好み、朝廷尊崇の意を尽し、以て子孫に伝え 「 曰臣今まで奏上候は正之の遺意に御座候 」 と述べている。 是に因って見れば、正之の家訓が幕府至上主義を表しているものであると解するのは決して妥当でなく、従ってそれが、又戊辰戦役の原因を為すものであると考える如きも尚適当でないと思う。 』 と、
確かに会津藩は、固より朝廷に敵対する気持ちはさらさらなかったに違いない。 しかし、会津藩が戊辰戦争を戦い、敗戦の憂き目に陥り、滅藩に陥った最大の要因は、やはり この家訓の冒頭の第一条にあることはまぎれもない事実であろう。 それは、幕府政治総裁職にあった 前越前福井藩主 松平慶永(よしなが)( 春嶽 ) が、京都守護職への就任要請を 再三断わり続ける松平容保に、執拗に拝命を迫る時に、持ち出したのは この家訓であり、また、藩内の反対意見を抑えて、松平容保が 京都守護職を拝命したのも、家訓を忠実に守った為と言われる。 首席家老 西郷頼母、家老 田中土佐らが 会津より江戸にとんで来て 「 今の時 この至難の局にあたるは、所謂薪を負うて火を救うにひとしく、恐らくは労多くして其の功なからん 」 ( 『 京都守護職始末 』 山川浩著 ) と、反対したが、藩主容保の最後のよりどころは、やはり この「 家訓 」であった。 容保が 「 ・・・・我家、宗家と盛衰存亡を倶に共にすべしとは、藩祖公の遺訓、加うるに数代隆恩に浴せるを、予不肖と雖も 豈一日も其報效を忘るべけんや 」 ( 同 ) と、容保がこの家訓の精神に殉じるとの覚悟を表明すれば、会津藩の家老たちとしても、もはや彼を諫言することは出来なかった。 「 この上は 義の重き所を執り、他日の如何を論ずべき秋(とき) にあらず、君臣 唯京師の地を以て 死所となすべきなりと、議遂に決す。」 ( 同 )
その結果、松平容保が、文久二年( 一八六二 )師走から、京都守護職として京に赴任し、会津兵約千人が駐屯し、京都見廻組や 新撰組の剣客集団までその配下に収め、尊攘派志士たちの取り締まりを行い、その為 多くの尊攘派志士が犠牲になり、倒幕派から強い怨みを買うことになった。 会津藩は、この家訓に集約されるような、徳川宗家の藩屏たる精神を 幕末まで頑なまでに 忘れなかったがために、自ら滅びの途(みち) を選択するという悲劇に見舞われてしまった。 これもまた、正之と 家訓の存在の大きさを 物語る事実であろう。
「 家訓 」十五ヶ条制定の翌年、寛文九年( 一六六九 )四月二十七日、保科正之は隠居を許され、四男正経が後を嗣いだ。 正之、五十九歳の時である。
寛文十一年( 一六七一 )十月には、山崎闇斎は、吉川惟足から垂加零社の号を与えられ、十一月には正之が、吉川惟足から神道の奥義 「 四重奥秘 」の伝と土津霊神の神号を受けている。
「 山崎家譜 」 によれば、闇斎が会津の地を訪れたのは、寛文十二年( 一六七二 ) と 同十三年( 一六七三 ) の二回である。 寛文十二年は、正之最後の領内巡視の時であり、翌年は、正之の葬儀の時であった。
正之の最後のお国入りとなった第五回目の会津入りは、寛文十二年五月三日であった。 そして八月二十一日には、自分の寿蔵の場所を見立てるため、猪苗代に行き、磐梯山麓の見祢山(みねやま) を寿蔵( 墓所 ) に定めている。 そして九月十三日、会津を出発して、南山路( 南会津郡会津街道 ) を経て、同十八日江戸に還った。 この還りの一行には闇斎も加わって、正之に同伴している。
『 この時の闇斎の会津往路の事や、会津に於ける行動については明瞭に分らない。 唯自筆の「 山崎家譜 」 に、
「 十二年( 寛文 ) 秋八月十七日巳未東遊、至会津。」
とあるのみである。 これから推考すると、闇斎は八月十七日京都を発して江戸に到り、正之は会津の封地に帰還中であったので、その蹤(あと) を追って会津に行き、会津には十日前後の間滞在して、九月十三日、正之の一行と共に、会津出発、江戸に還ったものであろう。 』 ( 『 会津藩に於ける 山崎闇斎 』 前田恒治著 )
保科正之は、寛永二十年( 一六四三 ) 会津藩主として会津に入国以来、兄である三代将軍家光のよき相談相手として、かつ、家光逝去後は、家光の遺命( 託弧の遺命 ) により、十一歳の幼君四代将軍家綱の輔弼役として幕閣にとどまり幕政に参与していたので、足掛け二十三年間も江戸に留まっており、国許に帰国したのは、その藩主時代はわずか三回にすぎなかった。
しかし、国詰めの城代家老をはじめ家臣たちを巧みに指揮し、貢税の軽減・産業の振興・文武両道の奨励等の善政を布いた結果、会津藩の基礎は確立し、藩は繁栄して民は富んだ。 また、幕閣にあっても将軍を補佐し、善政を敷いて数々の治績を遺し、名君の名をほしいままにしたが、その中でも家綱政権の 「 三大美事 」 は特に有名である。 この 「 三大美事 」 とは、末期(まつご) 養子の禁の緩和、殉死の禁止、大名証人制度の廃止をいう。( 証人とは、いわゆる人質のこと。 謀反防止策として、幕府が大名の正室や嫡男を国許ではなく江戸屋敷に住まわせていた。)
正之は、このように文治政治家として、幕府の要職に身を置きながらも、藩政の改革を図り会津松平藩の基礎を築いた。
特に儒教( 朱子学 )の思想を深く研究した正之は、政治体制の基本理念とか 根本となる思想を儒教に求め、諸学問にも通じた学者であった。 しかも、彼の学問は、幕政や藩政の中に取り入れられた 生きた実践的学問で、政治の中に人間の道徳性を常に要求した。
家中の殉死を禁止し、親孝行の者を賞し、高齢者への扶持米支給、参子養育の奨励、難儀旅人の救済等、数々の福祉厚生の政策を実行してきた。 特に会津藩の社倉制度は、他に誇ることの出来る社会福祉制度であった。 これらのことは、正之の儒学ならびに 奥秘に達していた神道の道の実現に他ならなかったのである。
このように名君の誉れ高い正之も、寛文十二年( 一六七二 )十二月十八日、病の床にあった三田屋敷で六十二歳の生涯を閉じた。 そして翌年三月二十七日には葬儀が執り行われ、猪苗代の見祢山(みねやま) 寿蔵(じゅぞう) に葬られ 「 土津霊神(はにつれいじん) 」 として祭られることになった。 正之は、「 神 」 となって会津の地を守ることになったのである。
つづく 次回
外史氏曰
【出島物語ー44】
 土佐の南学―6
土佐の南学―6会津藩「家訓」十五ヶ条
保科正之は、寛文三年( 一六六三 )、五十三歳の冬から時々吐血し、白内障にも罹ってやがて盲目となる恐れが出て来た。 家老友松勘十郎はしきりにこれを案じ、且つ、会津藩の将来を慮って正之に、これからの藩主や家臣の政治にたずさわる者が永く守るべき家訓(かきん) を作ることを進言した。 保科正之はこの進言により、隠居する前年の 寛文八年( 一六六八 ) に会津藩の憲法ともいうべき、家訓十五ヶ条を制定、国許の御城代田中正玄(まさはる) を江戸に呼び寄せてこれを手渡した。 これが会津藩の教条として永く藩の上下を支配薫陶した 家訓十五ヶ条と言われるものである。
この 「 家訓 」 は、後に続く藩主を含め、家臣たちの心構えとして、会津藩の成り立ちを認識させ、精神面の昂揚と団結をはかり、心のよりどころとするため、藩政の基本を家臣たちに示したもので、この時からちょうど二百年後、会津藩が戊辰戦争に敗れて 滅藩の運命に到るまで、永く会津藩を指導した極めて重要な規範である。
この「 家訓 」 は、先ず山崎闇斎がその草案を作り、正之の意見によって修正を加え、更に又闇斎の意見を徴するなど、反覆論議を繰り返して出来上がったもので、その間に家老の友松勘十郎氏興が種々斡旋する所があったものであろう。 されば固より 正之の意見が主となったであろうが、闇斎は唯々として他の意見にのみ従う性格ではない、闇斎の考えも相当に織り込まれ、両者の一致点の上に出来上がったものと思われる。
現実の政治を行う立場にある正之の啓蒙的専制君主としての姿勢と、聖賢の道を明らかにして風俗を教化させようとする闇斎の理想、そして その為のキーポイントは、公共的な規範意識に支えられた為政者としての武士を創り出す事であるとする闇斎の捉え方とが 互いに共鳴、化合して この「 家訓 」 が出来上がった。
なお、家訓成立の第一の功労者である友松勘十郎氏興(うじおき) は、元豊臣家家臣の裔で、 寛永十一年( 一六三四 )八月に正之が上洛した際、見出されて十三歳にして、正之の小姓として仕えた。 若くから学問、武芸に秀れ、のちにその才能が認められ 寛文三年(一六六三)四十二歳の時、家老に抜擢された。
もとは漢文であるが、以下に、読み下し文でこの家訓十五ヶ条の全文を掲げる。
一、大君の儀、一心大切に忠勤を存ずべく、列国の例を以て自ら処(お) るべからず。
若(も)し二心を懐(いだ)かば、則(すなわ)ち我が子孫に非ず、面々決して従うべからず。
一、武備は怠るべからず。 士を選ぶを本(もと) とすべし。 上下の分を乱るべからず。
一、兄を敬い弟を愛すべし。
一、婦人女子の言、一切聞くべからず。
一、主を重んじ、法を畏(おそ) るべし。
一、家中は風儀を励むべし。
一、賄(まいない) を行ない、媚(こび) を求むべからず。
一、面々依怙贔屓(えこひいき) すべからず。
一、士を選ぶに便辟(べんぺき) 便佞(べんねい) の者(心のねじ曲った者)を取るべからず。
一、賞罰は、家老の外、これに参加すべからず。 若(も) し位を出ずる者あらば、
これを厳格にすべし。
一、近侍者をして、人の善悪を告げしむべからず。
一、政事は、利害を以て道理を枉(ま) ぐべからず。 僉議(せんぎ) は、私意を挟み
人言を拒(ふさ) ぐべからず。 思う所を蔵せず、以てこれを争うべし。
甚だ相争うと雖(いえど) も、我意を介すべからず。
一、法を犯す者は、宥(ゆる) すべからず。
一、社倉は民のためにこれを置く、永利のためのものなり。 歳(とし) 饑(う) えれば
則ち発出して、これを済(すく) うべし。 これを他用すべからず。
一、若しその志を失ない、遊楽を好み、驕奢を致し、士民をしてその所を失わしめば、
則ち何の面目あって封印を戴(いただ) き、土地を領せんや。 必らず上表蟄居(ちっきょ)すべし。
右十五件の旨堅くこれを相守り、以往(以後)、以て同職の者に申し伝うべきものなり。
寛文八年戌申四月十一日 会津中将
家老中
中でも、家訓第一条が最重要になる。 異母兄の三代将軍家光に見出されて信州高遠三万石の大名から会津二十三万石の大大名へと出世し、幕政にも参与して存分に能力を発揮した正之は、終生家光に感謝し続けていた。 託弧の遺命( 家光の遺命として十一歳の家綱の補佐を依頼される ) を忠実に守り、足掛け二十三年間も江戸に留まって四代将軍家綱を補佐し続けたのもそれ故であって、正之にとって会津藩立藩の精神は実にこの家訓第一条にこそ存したのである。
正之は、この家訓を非常に重要なものとして末代まで伝えようとその徹底に力を尽した。 正之は寛文十二年十二月十八日、江戸の藩邸にて六十二歳で死去するが、その年の八月、正之が会津に在る時、世嗣正経が江戸へ参覲のために出発の際に、会津若松城内三の丸の屋敷に於て、正之自ら家訓の趣旨を正経や家老達に懇切丁寧に説明している。 さらに死の三日前には、家訓について遺言し、それを稲葉丹後守を通じて一同に伝えさせている。 この時 友松勘十郎等 家老一同は、もし正之が逝去したならば、御家訓の旨固く相守りつつ 正経に仕えようと、各自血判して その誓紙を正之に差出した。 この後も藩主代替りの時には必ず家訓を守るべき旨を 誓詞に書き付けた。 これでどれ程家訓が重要性を持ったかが判る。 そして、正之薨去後に於ては、友松勘十郎が、家訓の普及徹底に努めている。
以後、毎年正月十一日、八月朔、など、年に二、三度、時を定めて城中で、家訓が読み上げられ、家臣一同がこれを拝聴することになった。
このように、会津藩に於ては家訓を金科玉条として、二百年来、上下共に之を常に心に留め、且つ之を丁重に取り扱ったので、これが藩士の精神上に及ぼした影響は計り知れない程大きい。 それはとりもなおさず、その草案を作った山崎闇斎が及ぼした影響が大きいということでもある。
前田恒治は その著 『 会津藩に於ける 山崎闇斎 』 の中で、次のように述べている。 『 この家訓の最大の特徴は、「 大君之儀・・・・ 」 という冒頭の第一条であろう。 これは、徳川幕府に対して、一心に忠勤を挺んで、二心を抱いてはならぬ誡めであって、徳川幕府至上主義を表明するもので、これが明治戊辰戦役の原因を為し、彼の悲壮なる会津籠城の死守も、これが為であると言う説がある。 果してそうであろうか。
この家訓は前述のように、山崎闇斎が草案を作り、正之が加筆したもので、二人の合作と言ってよいものである。 闇斎は言うまでもなく、有名なる尊皇論者である。 然らば、家訓の内容が、我が国体と一致しないようなものであるならば、闇斎が、これに同意を表する筈が無い。 又正之は 卜部(うらべ)神道家であるから、我が国体に相反するようなものを制定する意志でないことも確かである。 故に 「 二心を懐(いだ) かば、則(すなわ) ち我が子孫に非ず 」 との戒めは、徳川幕府に対するものであるが、同様の事は、皇室に対しても考えていたものに相異ない。 むしろ それは言うを要しない事としていたのであろう。 正之はむしろ不義に対しては従ってはならぬということに重点を置いたように思われる。
会津藩の皇室に対する真精神は、寧ろ、幕末に於ける藩主松平容保が京都守護職に任ぜられた時代に於て、最も能く発揮せられたと言うべきである。 容保は能く難局に當りて、その大任を尽し、孝明天皇の叡感斜ならざるものがあった。 その時容保の奏文中にも、藩祖正之が独り皇朝の道を好み、朝廷尊崇の意を尽し、以て子孫に伝え 「 曰臣今まで奏上候は正之の遺意に御座候 」 と述べている。 是に因って見れば、正之の家訓が幕府至上主義を表しているものであると解するのは決して妥当でなく、従ってそれが、又戊辰戦役の原因を為すものであると考える如きも尚適当でないと思う。 』 と、
確かに会津藩は、固より朝廷に敵対する気持ちはさらさらなかったに違いない。 しかし、会津藩が戊辰戦争を戦い、敗戦の憂き目に陥り、滅藩に陥った最大の要因は、やはり この家訓の冒頭の第一条にあることはまぎれもない事実であろう。 それは、幕府政治総裁職にあった 前越前福井藩主 松平慶永(よしなが)( 春嶽 ) が、京都守護職への就任要請を 再三断わり続ける松平容保に、執拗に拝命を迫る時に、持ち出したのは この家訓であり、また、藩内の反対意見を抑えて、松平容保が 京都守護職を拝命したのも、家訓を忠実に守った為と言われる。 首席家老 西郷頼母、家老 田中土佐らが 会津より江戸にとんで来て 「 今の時 この至難の局にあたるは、所謂薪を負うて火を救うにひとしく、恐らくは労多くして其の功なからん 」 ( 『 京都守護職始末 』 山川浩著 ) と、反対したが、藩主容保の最後のよりどころは、やはり この「 家訓 」であった。 容保が 「 ・・・・我家、宗家と盛衰存亡を倶に共にすべしとは、藩祖公の遺訓、加うるに数代隆恩に浴せるを、予不肖と雖も 豈一日も其報效を忘るべけんや 」 ( 同 ) と、容保がこの家訓の精神に殉じるとの覚悟を表明すれば、会津藩の家老たちとしても、もはや彼を諫言することは出来なかった。 「 この上は 義の重き所を執り、他日の如何を論ずべき秋(とき) にあらず、君臣 唯京師の地を以て 死所となすべきなりと、議遂に決す。」 ( 同 )
その結果、松平容保が、文久二年( 一八六二 )師走から、京都守護職として京に赴任し、会津兵約千人が駐屯し、京都見廻組や 新撰組の剣客集団までその配下に収め、尊攘派志士たちの取り締まりを行い、その為 多くの尊攘派志士が犠牲になり、倒幕派から強い怨みを買うことになった。 会津藩は、この家訓に集約されるような、徳川宗家の藩屏たる精神を 幕末まで頑なまでに 忘れなかったがために、自ら滅びの途(みち) を選択するという悲劇に見舞われてしまった。 これもまた、正之と 家訓の存在の大きさを 物語る事実であろう。
「 家訓 」十五ヶ条制定の翌年、寛文九年( 一六六九 )四月二十七日、保科正之は隠居を許され、四男正経が後を嗣いだ。 正之、五十九歳の時である。
寛文十一年( 一六七一 )十月には、山崎闇斎は、吉川惟足から垂加零社の号を与えられ、十一月には正之が、吉川惟足から神道の奥義 「 四重奥秘 」の伝と土津霊神の神号を受けている。
「 山崎家譜 」 によれば、闇斎が会津の地を訪れたのは、寛文十二年( 一六七二 ) と 同十三年( 一六七三 ) の二回である。 寛文十二年は、正之最後の領内巡視の時であり、翌年は、正之の葬儀の時であった。
正之の最後のお国入りとなった第五回目の会津入りは、寛文十二年五月三日であった。 そして八月二十一日には、自分の寿蔵の場所を見立てるため、猪苗代に行き、磐梯山麓の見祢山(みねやま) を寿蔵( 墓所 ) に定めている。 そして九月十三日、会津を出発して、南山路( 南会津郡会津街道 ) を経て、同十八日江戸に還った。 この還りの一行には闇斎も加わって、正之に同伴している。
『 この時の闇斎の会津往路の事や、会津に於ける行動については明瞭に分らない。 唯自筆の「 山崎家譜 」 に、
「 十二年( 寛文 ) 秋八月十七日巳未東遊、至会津。」
とあるのみである。 これから推考すると、闇斎は八月十七日京都を発して江戸に到り、正之は会津の封地に帰還中であったので、その蹤(あと) を追って会津に行き、会津には十日前後の間滞在して、九月十三日、正之の一行と共に、会津出発、江戸に還ったものであろう。 』 ( 『 会津藩に於ける 山崎闇斎 』 前田恒治著 )
保科正之は、寛永二十年( 一六四三 ) 会津藩主として会津に入国以来、兄である三代将軍家光のよき相談相手として、かつ、家光逝去後は、家光の遺命( 託弧の遺命 ) により、十一歳の幼君四代将軍家綱の輔弼役として幕閣にとどまり幕政に参与していたので、足掛け二十三年間も江戸に留まっており、国許に帰国したのは、その藩主時代はわずか三回にすぎなかった。
しかし、国詰めの城代家老をはじめ家臣たちを巧みに指揮し、貢税の軽減・産業の振興・文武両道の奨励等の善政を布いた結果、会津藩の基礎は確立し、藩は繁栄して民は富んだ。 また、幕閣にあっても将軍を補佐し、善政を敷いて数々の治績を遺し、名君の名をほしいままにしたが、その中でも家綱政権の 「 三大美事 」 は特に有名である。 この 「 三大美事 」 とは、末期(まつご) 養子の禁の緩和、殉死の禁止、大名証人制度の廃止をいう。( 証人とは、いわゆる人質のこと。 謀反防止策として、幕府が大名の正室や嫡男を国許ではなく江戸屋敷に住まわせていた。)
正之は、このように文治政治家として、幕府の要職に身を置きながらも、藩政の改革を図り会津松平藩の基礎を築いた。
特に儒教( 朱子学 )の思想を深く研究した正之は、政治体制の基本理念とか 根本となる思想を儒教に求め、諸学問にも通じた学者であった。 しかも、彼の学問は、幕政や藩政の中に取り入れられた 生きた実践的学問で、政治の中に人間の道徳性を常に要求した。
家中の殉死を禁止し、親孝行の者を賞し、高齢者への扶持米支給、参子養育の奨励、難儀旅人の救済等、数々の福祉厚生の政策を実行してきた。 特に会津藩の社倉制度は、他に誇ることの出来る社会福祉制度であった。 これらのことは、正之の儒学ならびに 奥秘に達していた神道の道の実現に他ならなかったのである。
このように名君の誉れ高い正之も、寛文十二年( 一六七二 )十二月十八日、病の床にあった三田屋敷で六十二歳の生涯を閉じた。 そして翌年三月二十七日には葬儀が執り行われ、猪苗代の見祢山(みねやま) 寿蔵(じゅぞう) に葬られ 「 土津霊神(はにつれいじん) 」 として祭られることになった。 正之は、「 神 」 となって会津の地を守ることになったのである。
つづく 次回