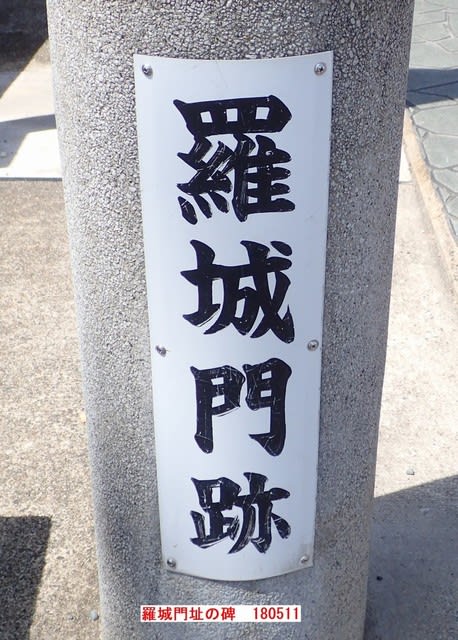18年桜紀行 03
3月30日 勧修寺・醍醐寺・伏見(宇治川派流)
3月31日 植藤・遍照寺・平安郷・大覚寺・亀山公園・西光院
3月30日。
桂川駅から山科に行き、地下鉄で小野まで。勧修寺を訪ねる。
山科にはあまり行かないので、春の勧修寺も4度目くらいと少ない。
地下鉄で小野駅下車して、かつて知ったる道を歩いて行くのだが、
数年ぶりだというのに道はかろうじて記憶にある。
勧修寺の境内のたたずまいも記憶にある通りであった。
気持ちが急くわけではなかったのだが、一通り見てから醍醐寺にと歩く。
さすがに勧修寺から醍醐寺までの道はスマホの地図アプリで確認する。
醍醐寺は桜の名所だけあって、どこからこんなに人が蝟集するのかと
思うほどに混雑している。
醍醐寺も3.4年ぶりなのだが、人の多さに多少は辟易して、そんなにじっくりと
撮影したわけではない。でも数葉は良さそうなものがありそうにも思う。
理性院は写すほどのこともないのだが、醍醐寺の別格寺院として有名なのだし、
山家集にも記述があるので、なんとなく親しみを感じる。
地下鉄醍醐駅に戻って六地蔵駅まで。下車して川を渡って京阪に
乗り換えて中書島下車。歩いて宇治川派流に向かう。
桜も盛りで30石船も運行していて良いには違いないのだが、なぜか
光りを味方につけられなかったようだ。写真は光がとても大事だというのに。
どこにレンズを向けても人が映り込むという感じで、それを避けたかったのだが、
数枚は人が写っている。仕方ない。気になるところだ。



翌日の3月尽(晦日)は自転車で嵐山方面。
植藤→遍照寺→平安郷→大覚寺→亀山公園→西光院→西芳寺川で撮影する。
平安郷は初めて入ってみた。いつもの季節は公開していない。
仁和寺の支院の何とかという施設のあった場所のはずだ。遍照寺山のふもと、
広沢の池の東隣の広大な土地に主に桜を植栽しており、春には公開するらしい。
家族連れも結構多かったのだが、飲食は禁止にした方が良いような気もする。
次いで大覚寺。大覚寺は紅葉の頃は毎年行くのだが、桜の頃はそんなに行かない。
昨年も行きはしたのだが、今年と同じく良い写真がない。むつかしい。
大覚寺から嵐山の亀山公園。
なんとか銀龍草がないかと探したのだが見つからない。遅すぎた。残念。
嵐山からは帰路である。拙宅までは5キロ弱。西の山沿いに自転車を走らせて西光院。
西行の伝承の伝わるお寺である。ここの桜が江戸時代には西行桜であった。
かくして、この二日間が終わった。





30日・31日の画像もひとまとめにして18年桜紀行に置いています。
興味がありましたらご覧願います。
18年桜紀行
言葉をそんなに吟味していず、小学生の日記みたいだが備忘録としてはこれでも良しとしたい。
あとは4月4日の撮影分があります。しかし、することがあり、すぐには手が付かない。
来週の初めころのアップ予定です。