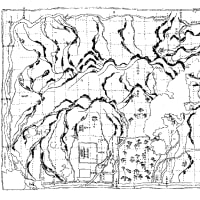先日、たまたま見ていたテレビ番組「欧州美食紀行」にニッツァモンフェッラートの名前が出てきてびっくりした。ピエモンテ州の町のひとつとして紹介された寒村は、白トリュフの産地として有名なのだそうで、その有名な白トリュフを使った料理として紹介されていたラビオリのようなもので更に驚いた。と言うのはそれがカルドンを使った料理でもあったことだからです。
以前書いたようにカルドンはバーニャカウーダに使われるということは一応知っていましたから、カルドンゴッボ ディ ニッツァ(という野菜)のニッツァがこのニッツァモンフェッラートのことだという推測は当たっていたことになります。バーニャカウーダに使うくらいだから地中海のニース(イタリア語だとニッツァ)とは当然違うだろうとは思っていましたが、巷にニースのカルドンなどと説明しているものがあったりしたのは、一般的な辞書を引いても当然ニースしか出てこず、コムーネの一つであるモンフェッラートが載ってる訳も無いためです。ズッキーニの一種にもニース産のニッツァが有ったり、カルドンやアーティチョークの原産が地中海周辺だという事もあってもやもやした感じを持っていましたが番組を見て確定しました。
かの地の名産の白トリュフがどんなものなのか、アルバ産の白トリュフは聞いたことがあるが口にした事が無い身としては想像に難いのですが、値の張り様は日本のマツタケに似ている。香りは全然別物らしくマツタケは世界中の温暖湿潤な林地で取れてもそれをありがたがるのは殆ど日本人だけらしいし、それをありがたがらない日本人もここにいる訳です。トリュフも実は日本の雑木林などに普通に自生というのか寄生して存在しているらしいので、古来それを利用しなかったのは知らなかったということでは無いはず、日本人の好みに合わないものだったのでしょうか?土を掘っているとごく稀に白っぽいゴムのようなものを見つけることがありますが、あれがもしかしたらトリュフなのかと考えますがそんな訳無いですよね。水辺や湿り気の多い土地のニレや菩提樹、ハシバミ等の根周りの土中15センチほどのところにあるらしいので、この辺りだと春日原始林が一番有りそうな感じです。イノシシなどは恐らくエサとして利用しているであろう事は、欧州のトリュフハンター達がかつて犬の代わりに豚を使っていたことから想像できます。
そういえば、イノシシに山の畑で出くわした経験は今でも忘れられません。冬の頃だったと思いますが、畑際の松林に緑色のレインコートを羽織って休憩して腰を下ろしていた時、遠くで犬の啼く声と鈴の音がしたので猟をしている事には気付いていました。しばらくしてガサガサという音がする方に目を向けると、向こうの林からドラム缶ほどは無いにしてそれに近い大きさの紡錘形をした黒い塊が恐ろしい速さでこちらに向かって来たかと思うと、目の前数メートルを駆け抜けて行ったという事がありました。
猟犬に追いかけられてイノシシはこちらには全く気付くことはありませんでしたが、あのスピードは尋常じゃ無く咄嗟の事に身動きも出来なかったのを覚えています。それ以来イノシシにはとても太刀打ちできないと悟りました。
ごぼうとカルドンの奇妙な関係について以前書いたもの
以前書いたようにカルドンはバーニャカウーダに使われるということは一応知っていましたから、カルドンゴッボ ディ ニッツァ(という野菜)のニッツァがこのニッツァモンフェッラートのことだという推測は当たっていたことになります。バーニャカウーダに使うくらいだから地中海のニース(イタリア語だとニッツァ)とは当然違うだろうとは思っていましたが、巷にニースのカルドンなどと説明しているものがあったりしたのは、一般的な辞書を引いても当然ニースしか出てこず、コムーネの一つであるモンフェッラートが載ってる訳も無いためです。ズッキーニの一種にもニース産のニッツァが有ったり、カルドンやアーティチョークの原産が地中海周辺だという事もあってもやもやした感じを持っていましたが番組を見て確定しました。
かの地の名産の白トリュフがどんなものなのか、アルバ産の白トリュフは聞いたことがあるが口にした事が無い身としては想像に難いのですが、値の張り様は日本のマツタケに似ている。香りは全然別物らしくマツタケは世界中の温暖湿潤な林地で取れてもそれをありがたがるのは殆ど日本人だけらしいし、それをありがたがらない日本人もここにいる訳です。トリュフも実は日本の雑木林などに普通に自生というのか寄生して存在しているらしいので、古来それを利用しなかったのは知らなかったということでは無いはず、日本人の好みに合わないものだったのでしょうか?土を掘っているとごく稀に白っぽいゴムのようなものを見つけることがありますが、あれがもしかしたらトリュフなのかと考えますがそんな訳無いですよね。水辺や湿り気の多い土地のニレや菩提樹、ハシバミ等の根周りの土中15センチほどのところにあるらしいので、この辺りだと春日原始林が一番有りそうな感じです。イノシシなどは恐らくエサとして利用しているであろう事は、欧州のトリュフハンター達がかつて犬の代わりに豚を使っていたことから想像できます。
そういえば、イノシシに山の畑で出くわした経験は今でも忘れられません。冬の頃だったと思いますが、畑際の松林に緑色のレインコートを羽織って休憩して腰を下ろしていた時、遠くで犬の啼く声と鈴の音がしたので猟をしている事には気付いていました。しばらくしてガサガサという音がする方に目を向けると、向こうの林からドラム缶ほどは無いにしてそれに近い大きさの紡錘形をした黒い塊が恐ろしい速さでこちらに向かって来たかと思うと、目の前数メートルを駆け抜けて行ったという事がありました。
猟犬に追いかけられてイノシシはこちらには全く気付くことはありませんでしたが、あのスピードは尋常じゃ無く咄嗟の事に身動きも出来なかったのを覚えています。それ以来イノシシにはとても太刀打ちできないと悟りました。
ごぼうとカルドンの奇妙な関係について以前書いたもの