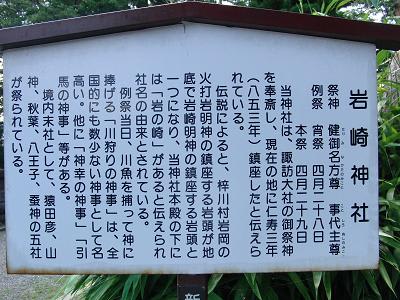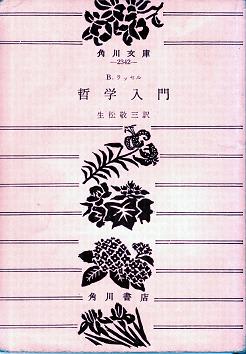●5月14日放送のNHK『その時歴史が動いた』を見た。
テーマは『日本人の心を守れ ~
岡倉天心・
廃仏毀釈からの復興~』であった。
■10数年前に地元の歴史探索会に参加した時に、廃仏毀釈の蛮行を知った。
もちろん授業で習ったことはあったが、その現状を初めて目の当たりにし貴重な仏像、寺社を失ったことを知った。
それからはこのテーマに関しては、かなり勉強してきたつもりだ。
そして長野県松本市での被害が大きかったことも知った。

【岡倉天心】
◆岡倉天心がこの復興に深く関わったことは知っていたが、その偉業を知り驚いた。
「神仏分離令」が廃仏毀釈の発端と言われているが、実際にはこの命令は無い。
慶応4年3月17日に布達された太政官布告により、身体を仏像としている神社は仏像を取り払い、仏具などを取り除くよう命じた。
興福寺の経典が商品の包み紙にされたり、仏像が薪として燃やされたり、貴重な財産が失われた。
興福寺の五重塔はなんと今の貨幣価値にして約2万円で売られた。
そんな中、天心は文部官僚として10年間に21万件もの仏像や文化財を調査、文化財保護の法律を訴えるなどしてその保護に力を尽くした。
★その中でも最も素晴らしい業績は『現状維持修理法』である。
「仏像は部分が欠けていると信仰の対象となりにくいが、かと言って闇雲な修理をすれば美術品としての価値を損なう」と言う考え方だ。
悩んだ末に、彼は両方の価値観を満足させる「現状維持修理」と言う方法に行き着くのである。
この方法は、遺されている姿をこれ以上損傷させないように保持することを目的とし、部分が欠けていて信仰の対象となりにくい時には取り外しできるパーツを作って仮留めで補修復元する方法である。

【東大寺法華堂】
この方法により、仏像は民衆の信仰の対象となり、さらに現代のすぐれた修復技術によって、より完璧に蘇ったのです。
天心の伝統美術を重要視した姿勢は洋画派から敵視され役職を追われるなどの不幸な時代もあった。
しかしそのような状況にも負けずに、ポリシーを曲げなかった天心に脱帽した。
来月は「手を失われた弥勒菩薩」を見に行く。基礎勉強を積んでおこう。