長編『守り人』シリーズを完結させた後に書かれた短編作品『ラフラ』は、次のようにはじまります。
夏の日が、暮れはじめていた。
開けはなしてある窓から吹きこんでくる風が、ひんやりと冷たくなっている。それでも、涼しさを感じられるのは窓に近づいたときだけで、酒場の内側には、昼間の暑さが、むっと、よどんでいた。
窓から見える空は、茜色がうすれ、ゆっくりと青紫へ変わりはじめている。
バルサは、ぼうっと、その空を見あげて、茜雲を縫うように飛んでいく黒い鳥の群れを目で追っていた。
今日は十日に一度の休業日で、酒場には客の姿はなく、奥の賭博場に一組、ススット(サイコロを使う賭博)をやっている客がいるだけだった。この酒場に泊まり込みで働いている給仕の娘たちは、昨夜のうちに、いそいそと家族のもとに帰っていき、今夜遅くにならないともどってこない。
バルサは、帰る家がある仲間たちのことを、なるべく考えまいとしていた。六つの年に故郷から逃げだして、七年。養父のジグロと共に、旅から旅へと流れ歩いてきた自分の暮らしを、他人の暮らしとくらべたいとは思わなかった。
それでも、夕空をひとりで見ていると、空ろなさびしさがこみあげてくる。
(父さん、早く帰ってこないかな……。)
(「ラフラ〈賭事師〉」、『流れ行く者』所収 上橋菜穂子 偕成社 2011年)
長編『守り人』シリーズからの読者であれば、バルサが幼くして父の親友ジグロとともに故郷を逃れ、流れ者の宿運を歩まざるを得なかった事情をわかっていますから、このバルサの見せる空ろな心象の描写に胸を打たれるものがあります。このとき、作者は長編『守り人』シリーズの物語世界に再び入り込んでおり、作者の派遣する語り手が少女時代のバルサのとある場面を物語の言葉として語りはじめます。
まず、季節と時の情景、風、酒場の中の空気、バルサが今佇む酒場の窓から視線を向けた空の様子、酒場が休業日であること、バルサも給仕のひとりで、給仕の娘たちが家に帰っていて今いないという事情、そしてバルサの内面に入り込んだ描写、と語り手の視線は目まぐるしく転換を繰り広げています。これは、今窓辺に立つバルサが酒場で肌合いで感じてきたこと、感じること、眺めることに沿って語り手は語っています。しかし、読者は異和感を持つことなく言葉をたどっていくことができます。そして、その場面の底には、作者の言葉を借りれば、「物語の底にいつも感じていた、大切な調べ」、つまり、「里に根づき、子どもや孫にかこまれて一生を終えるという人生から外れてしまった人びと―流れ行く者たち―の、人生の行く末……」という、作者のモチーフの流れが潜んでいます。 少女バルサが、追い込まれるように形作ってしまった流れ者としての自分の現在の有り様を普通の生活をしている人々と比べたいとは思わなかったと描写されています。比べてみてもどうすることもできないからです。しかし、「帰る家がある仲間たちのことを、なるべく考えまいとしていた」ともありますから、どうしても考えてしまうのでしょう。強いられた運命の中でじっと耐えている少女バルサがいます。「空ろなさびしさ」は、おそらくそういう心の場所から湧いてきています。
また、この場面の描写に、「ひんやりと冷たくなっている」や「それでも、涼しさを感じられるのは窓に近づいたときだけ」「昼間の暑さが、むっと、よどんでいた」などの肌合いの感覚的な描写がなされているのは、言葉が生み出す架空の場面に現実感を生み出す上でそれらは必須のものと考える作者固有の考えが実現されていると言えます。
ここで「ある事情で故郷を逃れ、土地に腰を下ろして普通の生活をすることがかなわない、流れ者とならざるを得なかった少女の心象」というモチーフで、他の表現とのちがいや共通性を考えてみます。小説の言葉による表現は当然別様にも描写できますが、そのひとつが引用のような表現になります。言葉による表現では、モチーフは言葉によって実現されます。読者は表現された言葉をていねいにたどることによって、その作者のモチーフに近づくことができます。同時に、そのモチーフを実現する作者の、言葉に込めた固有の選択や匂いや感受の流れをも味わっていることになります。
他の表現の考察に際して、わたしの手持ちは誰もが小中学生の間に体験する、美術や音楽や習字の体験という素人性しかありません。したがって、他の表現の根本の大枠を考えてみます。現在では、様々な形式の芸術表現として分化し、高度化してきてしまっていますが、遠い遠いそれらの初源にまでさかのぼれば、それらはおそらく一つの場に収束(着地)していきます。人間が何事かを外に放つ欲求を抱き、その欲求の果てしない積み重ねの歴史を経て、あるとき、岩に刻みつけたり、踊り出したり、歌ったり、語ったり、というように形あるものとしての表現を獲得してしまったという地点です。この人間にとっての表現というものの起源の性格は、現在のように芸術として各分野に別れ、高度な発達を遂げてきているように見えても、それらの深い部分に保存されていると思われます。
したがって、現在では芸術と呼ばれている表現が、起源の方から眺め渡せばわたしたち皆に開かれているはずです。しかし、芸術に限らず、あらゆる分野が複雑に専門化してきている中で、自分のいる分野とはちがった他の分野について考えたり、論じたりする場合には、それぞれの分野を実際にはじめからたどるのは不可能に近いですから、自分の分野から想像力を働かせるほかありません。それぞれの分野の表現の具体的な体験や手触りを持つ人が論じる方が誤差は少ないかもしれませんが、あくまで手持ちの素人性からそれぞれの表現の大枠に触れてみます。
絵画であればどうでしょう。まず、モチーフを実現する形式として具象画や抽象画があります。あるいは、従来の絵画という概念を解体した絵画というものもあるでしょう。選択した形式によって、いわば作者は半ば線や形や色となって画布などとの対話を繰り返しながら、言葉を繰り出すように空白の画布に線や形や色を動的にあるいは静的に、かたち成し、配置、構成していきます。作者の手は、積み重ねられきたこの国の絵画の歴史を、その達成を意識的にも無意識的にも踏まえながら、表現の時空に入り込み、モチーフにそってそれを現実化していきます。したがって、正確な模写でもない限り例えば江戸期の絵画にはなりません。(もちろん、模写でも微妙なところに現在は忍び込みます) 作品は正しく現在を呼吸する作者の現在性を帯びています。この過程は、表現というものがある幻を織り上げていくという意味では言葉の表現と共通しますが、ここでは言葉は線や形や色などの内臓感覚を含んだ感覚的な表現に変身しています。もちろん現在を生きる作者の思想性を表現することはできますが、絵画のある形式の選択にそれは現れたり、また、選択し構成された感覚的な表現のあわいに、あるいは底流に潜在してして存在します。モチーフの心象は、線や形や色など配置や関わり合う構成に溶けてしまっていて、そこから浮かび上がってくるものと思われます。
音楽の場合は、作者は半ば音になって (注)、音との対話を繰り返しながら、音に旋律やテンポを注ぎ込んで、音に生命を吹き込むように構成していきます。物理的には単なる音の組み合わせや速度の変化かもしれませんが、音を自在に操りながら人間的な音の表現になってきます。モチーフの心象は、その音の織りなしに溶けていて、楽譜はその音の表現や構成の再現可能な足跡であり、楽器によってそれが表現されると、その感覚的な表現から観客の内臓感覚を含んだ感覚的な味わいによって浮かび上がってきます。歌詞がある場合は、歌と音と仕草(踊り)が総合され、増幅された全身的な表現となることができます。詩や小説や絵画などを味わう場合より、歌謡曲を味わう方がわたしたち観客への内臓に響くような全身的な揺さぶりが強いのもこのためです。これは遠い遠い人間の初源の表現の形を保存しているからではないかと思われます。
映像であれば、作者(たち)は半ば映像となってある映像の場面を選択し、少女を登場させます。その少女の表現する表情や動作、背景の様子などを、映像の選択や動きによってモチーフの実現を図ります。こういう過程をいくつも踏んで作品としての構成を成し遂げていきます。これだけでは不十分ですから、その過程では別の登場人物を配し会話の場面を挿入したり、あるいはナレーションを入れたりして、モチーフの実現を強化します。
書。この場合、作者は半ば姿形(形象)となった言葉となって、そのような言葉との対話を繰り返しながら、手は筆と一体になって紙(白い空間)に、その空間と向き合いながら、言葉をかたち成していきます。このことは物理的には文字を書き付けていることになります。しかし、作者の内面では、白い空間を舞台としてモチーフの心象に沿った生産=消費の活動、つまり、流れたり、はねたり、休止したり、停滞したり、というその場面での内面的な運動を繰り広げています。「バルサ」という名でなくても何でもいいわけですが、例えば「バルサ」という言葉を書にしたら、そういう過程を経て生み出されたものと言えます。書を見る者は、白紙という時空において、その言葉へとかたち成す内面の運動をたどりながら、重い、軽い、静止、跳ぶなど主に内臓感覚的なもので受けとめてあるイメージを形作っていきます。ちなみに、『筆蝕の構造』(ちくま学芸文庫)として、書の内面的な表現の過程を初めて明らかにする試みを成したのは書家の石川九楊です。ここでの書のわたしなりの捉え方も彼の業績を参照しています。
書の題名はよくわかりませんが、言葉の表現でも絵画でも音楽でも現在では題名があります。万葉集以来、和歌には詞書(ことばがき)と呼ばれる、作歌の事情や場面がわかるものが歌の前に添えられているのがあります。人はそれぞれ十人十色でこちらが思わぬことを他人が考えることがあり得るように、芸術表現も題名を与えないと解釈の自由度が大きすぎてモチーフがよくわからないことがあります。題名は、モチーフが概念として凝縮されたものと見なすことができます。和歌の詞書が生まれた事情はわかりませんが、おそらく作者が作り上げた作品の世界に道に迷わないで入り込んでくれるよう導く、小さな道案内のようなものと思われます。
古今集や新古今集の時代でも専門歌人ではない貴族層が歌を詠んだり味わったりする困難はあったはずですが、現在でも、詩や物語や音楽や映画や絵画などを素人が味わうのは、難しいものがあります。上に、あるモチーフに沿ったいろんな芸術表現を例示してみました。しかし、現実には作品を深く味わうのはとても難しいという思いがあります。作品から受け取るものは、一人ひとり違います。一人ひとりの作品の受け取り方でいいじゃないかという考えもあり得ます。しかし、特に近代以降、作品に作者という個人が張り出してきましたから、作品へと表現した作者と出会うのは、作品を深く味わう上で大切なことになって来ています。
人間の芸術表現には、見る聴く触れる匂う味わうなどの感覚的な表現とともに人の多様な内臓感覚的な表現が伴います。単に何かを指し示すとか概念的なもの(考え)だけでは生き生きとした生命感を生み出したり、感じ取ったりすることはできません。芸術表現の形式によって、内臓感覚的な表現による度合いの大小のちがいもあります。絵画や音楽や書は、もちろんそれらの中でも各作品のその度合いのちがいはありますが、一般的には概念的なものは縮退し内臓感覚的な表現の度合いが高いと思われます。したがって、それらの作品は頭で見る、聴くではなくて、むしろからだ全体で見る、聴く、感じるものになっています。
ところで、芸術表現のある形式が生み出す過程は、各分野毎の歴史と独自性を持っています。各表現を実現する具体的な過程では、現在を呼吸する作者は現在の風を受けつつ、それぞれの形式の歴史性や独自性に則り、ということはその内部で一定の修練を積んで手慣れた手付きで、あるいはその歴史的な蓄積と格闘しながら、表現することになります。その面から眺めれば、各表現は互いに孤立して見えます。さらに現在では各表現は迷路のように複雑で緻密な世界に入り込んでいます。しかし、あらゆる芸術表現は、人間が絵画や音や映像や舞踊などを介して、心から精神に渡る世界を駆動させながら、幻を外に生み出すという点では太古以来共通しています。ただ、それぞれの形式によって表現が生み出されていく時、人間の心から精神に渡るスペクトル帯のような世界のどの領域を主要に駆動としているかの違いがあります。
ここで考えてきたことは、各芸術表現の大枠であり、入り口に過ぎません。読者(鑑賞者、観客)として単に作品の印象を語るのではなく、各芸術表現の具体的な作品を批評するには、それぞれの分野の歴史的に積み重ねられてきた表現の現在をたどりながら、そういった場から放たれた作者固有の作品といういうものをたどらなくてはなりません。これはとても大変なことです。もうひとつ、別の方法もあるように思われます。先に述べた各芸術表現の大枠で、「それぞれの形式によって表現が生み出されていく時、人間の心から精神に渡るスペクトル帯のような世界のどの領域を主要に駆動としているか」に着目し、その作者による現在的な駆動と表現の有り様をたどってみる方法です。これはまだやれるかどうかわからない、わたしの直感的なイメージに過ぎません。
(注)
本文中の「 音楽の場合は、作者は半ば音になって、」について
本文でこのようにさらりと述べていますが、各表現は、心から精神に渡る領域からなにものかを形あるものとして生み出すためには、表現の媒介(仲立ち)が必要となります。それは、人間が初源から積み重ねてきた言葉や音や形象や所作などが、美を生み出し美を感じ取ることができるものとなったという人間的な表現の歴史の現在として存在しており、各表現の作者たちは、そのことを無意識に踏まえて表現を生み出します。その表現の過程では、ちょうど巫女が神の言葉を語るとき、神(の言葉)と同調するように、音楽であれば音に語らせることになります。つまり、作者は意識の中では人間的な音になっていることになります。そうでないとうまく音を操れないと思われます。
ある作家が作品を制作しているときに、誰かが訪れてきたら気づいて手を休めるでしょう。「半ば」と書いたのは、遠い昔の巫女が短時間、神に全入して忘我の状態になり得るのとはちがって、一般に表現の過程にある作者たちにはその度合いの差はあっても醒めた現実的な部分も残っています。このようなことは各表現の作者たちが実感していることだと思います。
最新の画像[もっと見る]
-
 水詩(みずし) #5
1ヶ月前
水詩(みずし) #5
1ヶ月前
-
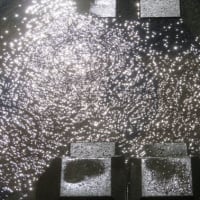 画像・詩シリーズ #14 はじまりの映像から
1ヶ月前
画像・詩シリーズ #14 はじまりの映像から
1ヶ月前
-
 農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
1ヶ月前
農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
1ヶ月前
-
 農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
1ヶ月前
農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
1ヶ月前
-
 農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
1ヶ月前
農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
1ヶ月前
-
 最近のツイートや覚書など2024年6月
2ヶ月前
最近のツイートや覚書など2024年6月
2ヶ月前
-
 最近のツイートや覚書など2024年6月
2ヶ月前
最近のツイートや覚書など2024年6月
2ヶ月前
-
 水詩(みずし) #4
2ヶ月前
水詩(みずし) #4
2ヶ月前
-
 農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26)
2ヶ月前
農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26)
2ヶ月前
-
 農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26)
2ヶ月前
農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26)
2ヶ月前










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます