農における感動 ②
もう五、六年くらい前になるか(念のためわたしのパソコンにファイル検索をかけたら「読書ノート2009年5月」に『柳田國男全集29』の読書メモがあったから、もう12年ほども前のことであった)、ちくま文庫の『柳田國男全集』を少しずつ読み進めているときに、〈農の感動〉というような言葉に出会った。農村や農民に対する上空からの視線はあっても、こういう農村や農民たちの内からの感受や心意に視線を向けた学者や思想家はほとんど見かけたことがないな、と思いながら読み進んだことがある。いままで何度かどこに書いてあったか調べようとしたが、かなわなかった。今回は、たぶん都市と農村問題や農政論などを収めた『柳田國男全集29』にあるかもしれないなと当てを付けて、少し流し読み風に読んでいたら、やっと出会えた。〈農の感動〉という言葉ではなかったが、それに相当する部分である。
農村の動揺にはもちろん遠い素因がある。近代はただこれを促した事情が、急にかつ露骨に現れたというまででもあろう。しかしこういう世の中に入って行く際に、もしあらかじめ農に衣食する者をして、少しでも自分の持つ力覚(さと)らしめる道があったら、事態は必ずしもこの形をもって発展しなかったかと私は思う。これが革新のなお希望多き理由である。
三つの貴重なる経験をもって、少なくとも田舎人は、かえって都市住民に教うべき資格を持っていた。その一つは勤労を快楽に化する術、すなわち豊熟の歓喜とも名づくべきもので、都市ではただわずかの芸能の士、学問文章に携わる者などが、個人的にこれを味わい得るのみであるが、村では常人の一生にも、何度となくその幸福を感じ得たのであった。ただ税と闘った百姓は努めてこれを包もうとし、一方無責任なる田園文学が、幾分かこれを誇張したために、今まは改めて考えてみようとする人が村の内にもなくなっただけである。第二には智慮ある消費の改善をもって、なお生存を安定にする道がいくらもあるということ。その反対の側面から言うならば、保守固陋(ころう)をもって目せられる田舎風の生活にも永い歳月の間には種々なる取捨選択が行われ、また往々にしてその失敗に悩まされていたということである。・・・中略・・・
第三の特に大切なる一点は、土地とその他の天然の恩沢を、人間の幸福と結び付ける方法、これも社会がすこしばかり複雑になると、はや濫用が始まり妨碍(ぼうがい)が起って、恥かしいほど我々の制度は拙劣であったが、狭い島国ではなくとも、人はこれよりほかに進んで物を豊かにする途を持たず、また田舎者以外には専門にこれを掌(つかさど)る者はないのであった。いかに巧妙なる交易をもってしても、結局は生産した以上の物を消費し得ないことは、家も村も国も世界も同じである。
(『柳田國男全集29』「都市と農村」P418-P419 ちくま文庫)
「勤労を快楽に化する術、すなわち豊熟の歓喜とも名づくべきもの」という部分が、〈農における感動〉に当たる部分である。しかし、柳田が「都市ではただわずかの芸能の士、学問文章に携わる者などが、個人的にこれを味わい得るのみであるが、村では常人の一生にも、何度となくその幸福を感じ得たのであった。」と書いているから、この〈農における感動〉は、収穫の秋の喜びなどの一年の内でも大きな区切りのような時の感動を指しているように見える。
この柳田の〈農における感動〉は、もう少し一般化されるべきだと思う。
もう五、六年くらい前になるか(念のためわたしのパソコンにファイル検索をかけたら「読書ノート2009年5月」に『柳田國男全集29』の読書メモがあったから、もう12年ほども前のことであった)、ちくま文庫の『柳田國男全集』を少しずつ読み進めているときに、〈農の感動〉というような言葉に出会った。農村や農民に対する上空からの視線はあっても、こういう農村や農民たちの内からの感受や心意に視線を向けた学者や思想家はほとんど見かけたことがないな、と思いながら読み進んだことがある。いままで何度かどこに書いてあったか調べようとしたが、かなわなかった。今回は、たぶん都市と農村問題や農政論などを収めた『柳田國男全集29』にあるかもしれないなと当てを付けて、少し流し読み風に読んでいたら、やっと出会えた。〈農の感動〉という言葉ではなかったが、それに相当する部分である。
農村の動揺にはもちろん遠い素因がある。近代はただこれを促した事情が、急にかつ露骨に現れたというまででもあろう。しかしこういう世の中に入って行く際に、もしあらかじめ農に衣食する者をして、少しでも自分の持つ力覚(さと)らしめる道があったら、事態は必ずしもこの形をもって発展しなかったかと私は思う。これが革新のなお希望多き理由である。
三つの貴重なる経験をもって、少なくとも田舎人は、かえって都市住民に教うべき資格を持っていた。その一つは勤労を快楽に化する術、すなわち豊熟の歓喜とも名づくべきもので、都市ではただわずかの芸能の士、学問文章に携わる者などが、個人的にこれを味わい得るのみであるが、村では常人の一生にも、何度となくその幸福を感じ得たのであった。ただ税と闘った百姓は努めてこれを包もうとし、一方無責任なる田園文学が、幾分かこれを誇張したために、今まは改めて考えてみようとする人が村の内にもなくなっただけである。第二には智慮ある消費の改善をもって、なお生存を安定にする道がいくらもあるということ。その反対の側面から言うならば、保守固陋(ころう)をもって目せられる田舎風の生活にも永い歳月の間には種々なる取捨選択が行われ、また往々にしてその失敗に悩まされていたということである。・・・中略・・・
第三の特に大切なる一点は、土地とその他の天然の恩沢を、人間の幸福と結び付ける方法、これも社会がすこしばかり複雑になると、はや濫用が始まり妨碍(ぼうがい)が起って、恥かしいほど我々の制度は拙劣であったが、狭い島国ではなくとも、人はこれよりほかに進んで物を豊かにする途を持たず、また田舎者以外には専門にこれを掌(つかさど)る者はないのであった。いかに巧妙なる交易をもってしても、結局は生産した以上の物を消費し得ないことは、家も村も国も世界も同じである。
(『柳田國男全集29』「都市と農村」P418-P419 ちくま文庫)
「勤労を快楽に化する術、すなわち豊熟の歓喜とも名づくべきもの」という部分が、〈農における感動〉に当たる部分である。しかし、柳田が「都市ではただわずかの芸能の士、学問文章に携わる者などが、個人的にこれを味わい得るのみであるが、村では常人の一生にも、何度となくその幸福を感じ得たのであった。」と書いているから、この〈農における感動〉は、収穫の秋の喜びなどの一年の内でも大きな区切りのような時の感動を指しているように見える。
この柳田の〈農における感動〉は、もう少し一般化されるべきだと思う。
柳田の時代には現在と違って、産業の構成において農業従事者の割合が会社員(サービス業)の割合を大きく凌いでいたから、産業の主な主体である農民に照明を当てたのである。現在ならば、産業の構成においてもっとも割合の多いサービス業従事者の内面に視線を向けるということになるだろう。
わたしたちの人間的な活動が、〈労働〉という抽象化された範疇で論じられる場合には、〈農における感動〉、現在でいえば労働をしている時の〈仕事の感動のようなもの〉は、一般に俎上(そじょう)に載せられることがないように思う。しかし、日々労働をしているわたしたちの内面にとっては、それはとても重要なことである。
------------------------------------------------------------------------------------------------------
※2014.7.26の文章
農における感動(とでも呼ぶべきもの) ①
農の中での感動(とでも呼ぶべきもの)は、パン屋さんが今日はパンが良くできたとか、家事で洗い物をしてきれいに片付いたとか、人のあらゆる労働や仕事における人間的な感動とそう違うわけではない。ただ、感動の湧き上がってくる対象が、農の場合は生きて活動している作物であるという違いがある。したがって、農事は子育てに似ているところがある。しかし、家庭菜園作りや「日曜農業」のようなものにわたしの場合も入るのだろうが、それらは仕事として農業をやっている場合と違って仕事における様々な配慮が取り払われた純粋な感動の舞台となっている。そういう点では、趣味と言えるかもしれない。作物を市場に出すこともないということは、社会性が絶ち切られているからである。
農政論や農民史を追究した柳田国男は、おそらくそれらの論考の中でだったと思うが、この農における感動(とでも呼ぶべきもの)に触れていた。おそらく普通の学者たちの言葉の視線は、そこまで届かないであろう。しかし、一昔前までの農民にとってそれは付随的なもので、作物がうまく育ってくれることは現在以上に切実に日々の生活と直結していたはずである。人々は猛威と慈愛の自然に囲まれ、さらに人間界の制度に絡まれ、長い長い間飢餓と労苦の不安に苛まれてきたからである。
遠い遠い昔、自生している植物を採集していた段階からそれらを栽培するということを始めたときの人間の感動はいかばかりであったか、想像するほかないが、感動を噛みしめたのではないだろうか。そこから幾多の試行錯誤や品種改良などを経て現在があるわけだが、その農における感動の質はそんなに変わらないように思われる。ただ現在においては、普通の生活者が趣味のように純化された形で、生活のための生産とは切り離されてその農における感動(とでも呼ぶべきもの)を手にすることができるようになった。長い長い農の歴史の底流に、日々の慌ただしい生活のあわいに湧き上がるものが秘められ続けてきたのではないだろうか。対自然でも、人間界の人が関わり合う世界でも、人という存在が巨きな何ものかに促されるようにしてこのような感動を表出するのは現在も受け継がれてきている。
上に作物のある場面を写真に撮ってみた。もちろん、それぞれの作物はわたしの見ていないところでそれぞれの生涯の曲線をたどっている。例えば、スーパーから買ったきゅうりやスイカと自分が育てたそれらとたいして違わないとしても、よその子と自分の子と違うように感受が違っている。その違いは自分が関わり合ってきているということから来るのは確からしく思われる。作物が育っているという感動のようなものとともにきゅうりやカボチャのみどりがまぶしく感じられてくる。
実を結び、いっときの盛りを過ぎたら枯れてゆく。この感動(とも呼ぶべきもの)の根源は、その機構が未だ不明であるとしても、この世界に、このようにわたしたちが生存しているということに、ある促しを波及させ続けている。
(2014.7.26)
















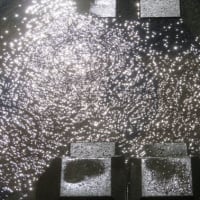



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます