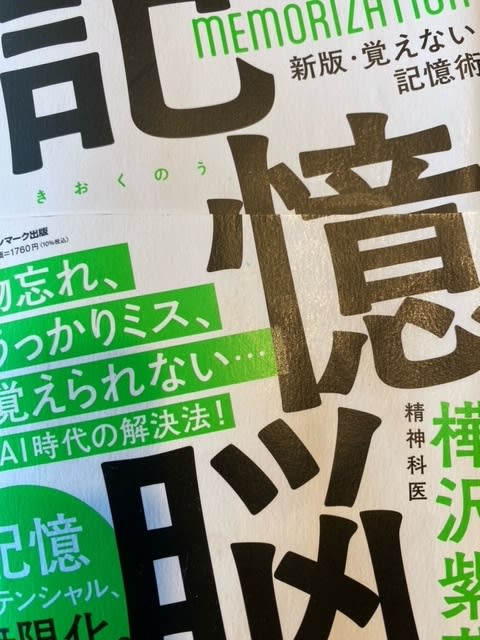
今日は皆さんに
「どうしたら、勉強がよくできるようになるか?」
ということについてお話をします。
樺沢紫苑という精神科医の先生が書いた本
「記憶脳」の中にその方法がたくさん書かれています。
今日はその中から、小学校2年生の皆さんに7つ教えますね。
① 五感を使って覚える。(「書く+声に出す」でさらに記憶に残す。)
いつも新しい漢字を練習するときに、机の上に人差し指で書く「指書き」をしているでしょう。
その時に
「一 二 三 しーい・・・」
と書き順を声に出して読んでいますね。
これは、「書く」ことに加えて「声に出して読む」ことでさらに記憶に残すという記憶術と同じです。
又、指書きは指先に机の刺激が伝わるのでさらに覚えやすいのです。爪の色が少し変わるくらい強めに書いていくと脳への刺激も強くなり忘れにくくなりますよ。
② アウトプットするなら「直後」がいい~「体験丸ごと記憶術」
算数などの授業のまとめの時間に振り返りをしますね。
「今日の学習で何を学んだのかを短い言葉でまとめてノートに書く」
学習をしています。学習内容は学んだ瞬間から忘れ始めます。
記憶の新しいうちにノートに書いておけば、後で見直した時にすぐに思い出せるというわけです。
ですから、振り返りのノートに
「今日は新しいことを覚えました。」
とか
「分数が楽しかったです。」
のようなことを書いてもほとんど意味がないのです。
「掛け算の3の段の答えは3ずつ増えていくことが分かりました。」
などのように学習した内容・分かったことを書いていかなければ記憶に残りません。
③ 記憶のゴールデンタイムは「寝る前」
さて、みなさんは宿題をいつやりますか?
家に帰ってすぐにやってしまうという人。いいですね。
やる時間を決めているのは宿題を忘れないためにとても良い習慣です。
しかし、記憶のゴールデンタイムの考え方からすると「寝る直前」がいいようですよ。
お風呂に入って、ご飯も食べて、歯みがきもして後は寝るだけになってから今日の復習の宿題をすると余計な情報が入らず、
寝ている間に脳に記憶されていきます。
しかし、家に帰ってからさっさと宿題を済ませて、その後ゲームなどをするとゲームの刺激で勉強した内容が消されてしまいます。
記憶に残すなら断然、「宿題は寝る前」です。
ただし、みなさんはまだ小学2年生ですね。寝る前にやろうとすると眠くて寝てしまい宿題を忘れてしまうかもしれません。
「宿題は寝る前」を実行するのはもう少し大きくなってからの方がいいかもしれませんね。
④ 緊張は「敵」ではない~「ほどよい緊張記憶術」
授業中に、お客さんのように話を聞いているだけだとすぐに忘れてしまうということはよくあるでしょう?
でも、自分の考えを友達に話すと忘れにくくなるね。
それも、みんなの前で話すともっとよく覚えているんじゃないかな?
「ただ聞いている」→「友達に話す」→「みんなの前で発表する」
の順番に少しずつ緊張感が高まるね。この位のちょうどいい緊張感で勉強をすると記憶に残りやすいようだね。
だから、学習の振り返りをノートに書いて、それをみんなの前で発表するというのは最強の勉強法なんだね。
恥ずかしがらずに、発表した人はお得ですよ。
でも、「強すぎる緊張」は逆効果。頭が真っ白になって、勉強したことも思い出さなくなってしまう。
「はじめて」とか「ほんのたまに」みんなの前で発表すると「緊張感が強すぎ」になってしまう。
だから、普段からみんなの前で発表することは大切なんだね。
⑤ 「制限時間記憶術」
制限時間を設定すると程よく緊張感が高まり、作業効率が上がります。
先生もよく授業中に「~について、自分の考えをノートに書きなさい。時間は2分です。」と言ってタイマーをかけていますね。
みんな2年生なのに驚くような集中力で自分の考えをノートに書いて先生のところに持って来てくれるでしょう。
タイマーをかけて制限時間を設けるとすごい力が出るんだね。あれを自分の家でも自分の勉強の時にやってみたらどうだろう。
「この計算は10分で終わらせるぞ!」なんてタイマーをかけて時間と闘ってみたらゲーム感覚で楽しく勉強できそうだね。
お家の人のスマホを借りてタイマーをかけてもいいし、百均で小さなタイマーを買ってもらってもいいよね。きっといい効果が出るよ。
⑥ 場所を移動するだけで活性化 「カフェ仕事記憶術」
みんな体育とか音楽とか大好きだよね。もちろん学習内容が楽しいっていうのもあるけど、体育と音楽は教室から移動して別の場所で活動する学習だね。なんと!脳は場所を移動するだけでいきいきと動き出すんだって。だから楽しく感じるんだね。
先生もよく国語の授業とかで「自分の考えを3人の友達に話してきなさい。」なんて指示を出すでしょう。
教室の中を歩き回って友達と話すと楽しいよね。気持ちもリフレッシュするね。
さらに記憶にも残るんだから一石二鳥だね。
「③の問題までできたらノートを持って来なさい。」という指示も少しだけど先生のところまで歩いてくるから効果がありそうだね。
これをもっと応用しようとするとどうなるかな?
例えば、「閲覧室と学習室と多目的室の黒板に問題が書いてあります。正解したら次の教室の問題を解きましょう。」なんてできるかもしれないね。
⑦ 机がきれいな人は仕事ができる
先生が出す指示で「漢字ドリルだけ 漢字ドリル だけ 出します。」っていうのがあるでしょう。
これ、脳科学的にも正しかったんだね。机の上が整理されている人は頭の中も整理されてるんだって。
そうすると覚えたことも必要な時に思い出せそうだね。
いつでもそういう習慣が身についていれば、自分の部屋も整理整頓できて勉強ができるようになるよ。
それに、机の上に他の物があると、それに気を取られてしまい集中できなくなることもあるよね。
そうすると勉強も・・・そうできなくなりそうだね。
「一時に一事」
「今、目の前のことに集中する。」
これが、勉強ができるようになるために大事なことの1つだよ。
今日は、皆さんに勉強ができるようになる方法を樺沢先生の「記憶脳」という本の中から7つお話ししました。
全員起立。まずどれからやってみたいですか?決めたら座って、その理由を考えなさい。発表してもらいます。
・・・という話を小学校2年生の児童にしてあげたいとこの本を読んで思いました。
ただ、7つは多いですね。1つずつ、7回に分けてお話ししようかな?
「どうしたら、勉強がよくできるようになるか?」
ということについてお話をします。
樺沢紫苑という精神科医の先生が書いた本
「記憶脳」の中にその方法がたくさん書かれています。
今日はその中から、小学校2年生の皆さんに7つ教えますね。
① 五感を使って覚える。(「書く+声に出す」でさらに記憶に残す。)
いつも新しい漢字を練習するときに、机の上に人差し指で書く「指書き」をしているでしょう。
その時に
「一 二 三 しーい・・・」
と書き順を声に出して読んでいますね。
これは、「書く」ことに加えて「声に出して読む」ことでさらに記憶に残すという記憶術と同じです。
又、指書きは指先に机の刺激が伝わるのでさらに覚えやすいのです。爪の色が少し変わるくらい強めに書いていくと脳への刺激も強くなり忘れにくくなりますよ。
② アウトプットするなら「直後」がいい~「体験丸ごと記憶術」
算数などの授業のまとめの時間に振り返りをしますね。
「今日の学習で何を学んだのかを短い言葉でまとめてノートに書く」
学習をしています。学習内容は学んだ瞬間から忘れ始めます。
記憶の新しいうちにノートに書いておけば、後で見直した時にすぐに思い出せるというわけです。
ですから、振り返りのノートに
「今日は新しいことを覚えました。」
とか
「分数が楽しかったです。」
のようなことを書いてもほとんど意味がないのです。
「掛け算の3の段の答えは3ずつ増えていくことが分かりました。」
などのように学習した内容・分かったことを書いていかなければ記憶に残りません。
③ 記憶のゴールデンタイムは「寝る前」
さて、みなさんは宿題をいつやりますか?
家に帰ってすぐにやってしまうという人。いいですね。
やる時間を決めているのは宿題を忘れないためにとても良い習慣です。
しかし、記憶のゴールデンタイムの考え方からすると「寝る直前」がいいようですよ。
お風呂に入って、ご飯も食べて、歯みがきもして後は寝るだけになってから今日の復習の宿題をすると余計な情報が入らず、
寝ている間に脳に記憶されていきます。
しかし、家に帰ってからさっさと宿題を済ませて、その後ゲームなどをするとゲームの刺激で勉強した内容が消されてしまいます。
記憶に残すなら断然、「宿題は寝る前」です。
ただし、みなさんはまだ小学2年生ですね。寝る前にやろうとすると眠くて寝てしまい宿題を忘れてしまうかもしれません。
「宿題は寝る前」を実行するのはもう少し大きくなってからの方がいいかもしれませんね。
④ 緊張は「敵」ではない~「ほどよい緊張記憶術」
授業中に、お客さんのように話を聞いているだけだとすぐに忘れてしまうということはよくあるでしょう?
でも、自分の考えを友達に話すと忘れにくくなるね。
それも、みんなの前で話すともっとよく覚えているんじゃないかな?
「ただ聞いている」→「友達に話す」→「みんなの前で発表する」
の順番に少しずつ緊張感が高まるね。この位のちょうどいい緊張感で勉強をすると記憶に残りやすいようだね。
だから、学習の振り返りをノートに書いて、それをみんなの前で発表するというのは最強の勉強法なんだね。
恥ずかしがらずに、発表した人はお得ですよ。
でも、「強すぎる緊張」は逆効果。頭が真っ白になって、勉強したことも思い出さなくなってしまう。
「はじめて」とか「ほんのたまに」みんなの前で発表すると「緊張感が強すぎ」になってしまう。
だから、普段からみんなの前で発表することは大切なんだね。
⑤ 「制限時間記憶術」
制限時間を設定すると程よく緊張感が高まり、作業効率が上がります。
先生もよく授業中に「~について、自分の考えをノートに書きなさい。時間は2分です。」と言ってタイマーをかけていますね。
みんな2年生なのに驚くような集中力で自分の考えをノートに書いて先生のところに持って来てくれるでしょう。
タイマーをかけて制限時間を設けるとすごい力が出るんだね。あれを自分の家でも自分の勉強の時にやってみたらどうだろう。
「この計算は10分で終わらせるぞ!」なんてタイマーをかけて時間と闘ってみたらゲーム感覚で楽しく勉強できそうだね。
お家の人のスマホを借りてタイマーをかけてもいいし、百均で小さなタイマーを買ってもらってもいいよね。きっといい効果が出るよ。
⑥ 場所を移動するだけで活性化 「カフェ仕事記憶術」
みんな体育とか音楽とか大好きだよね。もちろん学習内容が楽しいっていうのもあるけど、体育と音楽は教室から移動して別の場所で活動する学習だね。なんと!脳は場所を移動するだけでいきいきと動き出すんだって。だから楽しく感じるんだね。
先生もよく国語の授業とかで「自分の考えを3人の友達に話してきなさい。」なんて指示を出すでしょう。
教室の中を歩き回って友達と話すと楽しいよね。気持ちもリフレッシュするね。
さらに記憶にも残るんだから一石二鳥だね。
「③の問題までできたらノートを持って来なさい。」という指示も少しだけど先生のところまで歩いてくるから効果がありそうだね。
これをもっと応用しようとするとどうなるかな?
例えば、「閲覧室と学習室と多目的室の黒板に問題が書いてあります。正解したら次の教室の問題を解きましょう。」なんてできるかもしれないね。
⑦ 机がきれいな人は仕事ができる
先生が出す指示で「漢字ドリルだけ 漢字ドリル だけ 出します。」っていうのがあるでしょう。
これ、脳科学的にも正しかったんだね。机の上が整理されている人は頭の中も整理されてるんだって。
そうすると覚えたことも必要な時に思い出せそうだね。
いつでもそういう習慣が身についていれば、自分の部屋も整理整頓できて勉強ができるようになるよ。
それに、机の上に他の物があると、それに気を取られてしまい集中できなくなることもあるよね。
そうすると勉強も・・・そうできなくなりそうだね。
「一時に一事」
「今、目の前のことに集中する。」
これが、勉強ができるようになるために大事なことの1つだよ。
今日は、皆さんに勉強ができるようになる方法を樺沢先生の「記憶脳」という本の中から7つお話ししました。
全員起立。まずどれからやってみたいですか?決めたら座って、その理由を考えなさい。発表してもらいます。
・・・という話を小学校2年生の児童にしてあげたいとこの本を読んで思いました。
ただ、7つは多いですね。1つずつ、7回に分けてお話ししようかな?
























