光石富士朗監督のインタービュー
「彼らがかかえる悩みは、本質的には普通の人々と変わるところはない。たとえば、ちょっとしたこと、ニキビができて学校に行けなくなったとか、誰もが持っている悩みのバリエーションにすぎない。だから、特別な人々の変わった物語を描いているわけでは決してない。」
ということですが。
普通の家族といえるかどうか分からないですが、“未来の理想の家族形態”と思いました。
大人(親)、子供。個個に、在りそうなといえば在りそうだが、それでも、それぞれにかなりシビアーで屈折する複雑な問題を抱えながらも、落ち込むことなく、意固地になることなく、いがみ合うことなく、懸命に困難を乗り越え前向きに生きていこうとする、「今此処に一緒に暮らしている」というその一番大切な「トコロ」を個個が暗黙の了解の中で理解しあい、温かく「家族」を作っている。
そのおおらかさが何とも言えず見事で、その温もりが切なくホロリとさせられました。
それぞれの哀しみや苦悩や孤独は、それはそれとして包み込む温かい大きな大きな「眼差し」がソコには在りました。
上質の「眼差し」とはこういうことを言うのだと、またまた身に近づけてより深く理解しました。
「人生いろいろあるけれど、生きとったら、それでええやん」
「誰の子でもええやん」
「幸せってごっつうシンプルでナイスやで!」
お父ちゃんの49日もたたない内に自称おとうちゃんの弟という他人?が同居することになる。誰も疑問に思わず、スンナリそういうことを受け入れている。今までさまざまな普通でない経験をしてきたであろう、剣のない不器用なおっちゃん。
お母ちゃんは、屈託なく、おおらかで、昼は病院で老人介護をし、夜はカラオケバーで飲んだくれを相手にしている。お父ちゃんが亡くなっているのにお母ちゃんがいつしか妊娠している。
中学3年生の長男が年齢を偽って大学4年生の女性に恋してまい、「私のお父ちゃんになって」といわれる。そして戸惑いながらも真摯に彼女の心の闇に向き合いながら本当の大人の男に成長していく。
中学1年のヤンキーの次男が、死んだおとうちゃんにまったく似ていないことで出自に悩み、「ハムレット」を読み込んでいくうちに、人の心の奥の襞を感得してゆく。
小学生の三男が女の子になりたい願望を持っていて、他の学童からいじめられ、からかわれめげそうになるが、強く耐えて自分らしく生きてこうとする。
等等、どれをとっても、かなり深刻な出来事や悩みをそれぞれがそれぞれに見守りながら、拘らずサラリと交わし、暖かく包み込んでいる。
そういう個個の深刻さが、家族間に亀裂や波風を決して立てず、昨今の家庭崩壊に帰結せず、それどころかより一層の家族の温かい絆になっていく理想的で稀有な関係が「ソコ」にはあり、それがこの映画を観る人々の感動を誘うのだと思いました。
観終わった後、温かい涙が幾すじか頬を伝いました。
余韻の灯火を消さず、しばらくそこに座っていたい気持ちでした。
ですが、エンディングのテーマソングの「あいたくて...」が耳障りでした。
これは完全に“はずしているな”と思いました。
ポジティーブに人間賛歌、人生を謳歌する大きな大きな「愛」というのがこの映画の基底に流れているものだと思いますので、月並みな旋律で歌詞の、片思いソングでは、意味が違うと思いました。
このおかあちゃんとの幅が違い過ぎます。
決して、倉木麻衣の曲を貶しているのではありません。
人間賛歌や男女の愛を表現するには薄すぎます。
人生の、人間存在の深い哀しみと喜びが感じられません。
残念。
例えば、ルイ・アームストロングの "What a wonderful world" のような曲だったら、もっと幸せに感じたでしょうに。もっと幸せの深い涙があふれ出てきたことでしょう。(アメリカ社会にあって、黒人として虐げられ続けてきたジャズの大御所が晩年に歌うこの曲は、意味深で透明感のある哀しさがあります)
現実にこんな家族があるのかと思ってしまいますが、それがいい意味で映画なのだ。
ということだと思います。
深刻さもサラリと笑いに転化できる技量(機知)と自由さと温かさと粘り強さが「大阪」なのだと思いました。
ビバ、オオサカ!!
「彼らがかかえる悩みは、本質的には普通の人々と変わるところはない。たとえば、ちょっとしたこと、ニキビができて学校に行けなくなったとか、誰もが持っている悩みのバリエーションにすぎない。だから、特別な人々の変わった物語を描いているわけでは決してない。」
ということですが。
普通の家族といえるかどうか分からないですが、“未来の理想の家族形態”と思いました。
大人(親)、子供。個個に、在りそうなといえば在りそうだが、それでも、それぞれにかなりシビアーで屈折する複雑な問題を抱えながらも、落ち込むことなく、意固地になることなく、いがみ合うことなく、懸命に困難を乗り越え前向きに生きていこうとする、「今此処に一緒に暮らしている」というその一番大切な「トコロ」を個個が暗黙の了解の中で理解しあい、温かく「家族」を作っている。
そのおおらかさが何とも言えず見事で、その温もりが切なくホロリとさせられました。
それぞれの哀しみや苦悩や孤独は、それはそれとして包み込む温かい大きな大きな「眼差し」がソコには在りました。
上質の「眼差し」とはこういうことを言うのだと、またまた身に近づけてより深く理解しました。
「人生いろいろあるけれど、生きとったら、それでええやん」
「誰の子でもええやん」
「幸せってごっつうシンプルでナイスやで!」
お父ちゃんの49日もたたない内に自称おとうちゃんの弟という他人?が同居することになる。誰も疑問に思わず、スンナリそういうことを受け入れている。今までさまざまな普通でない経験をしてきたであろう、剣のない不器用なおっちゃん。
お母ちゃんは、屈託なく、おおらかで、昼は病院で老人介護をし、夜はカラオケバーで飲んだくれを相手にしている。お父ちゃんが亡くなっているのにお母ちゃんがいつしか妊娠している。
中学3年生の長男が年齢を偽って大学4年生の女性に恋してまい、「私のお父ちゃんになって」といわれる。そして戸惑いながらも真摯に彼女の心の闇に向き合いながら本当の大人の男に成長していく。
中学1年のヤンキーの次男が、死んだおとうちゃんにまったく似ていないことで出自に悩み、「ハムレット」を読み込んでいくうちに、人の心の奥の襞を感得してゆく。
小学生の三男が女の子になりたい願望を持っていて、他の学童からいじめられ、からかわれめげそうになるが、強く耐えて自分らしく生きてこうとする。
等等、どれをとっても、かなり深刻な出来事や悩みをそれぞれがそれぞれに見守りながら、拘らずサラリと交わし、暖かく包み込んでいる。
そういう個個の深刻さが、家族間に亀裂や波風を決して立てず、昨今の家庭崩壊に帰結せず、それどころかより一層の家族の温かい絆になっていく理想的で稀有な関係が「ソコ」にはあり、それがこの映画を観る人々の感動を誘うのだと思いました。
観終わった後、温かい涙が幾すじか頬を伝いました。
余韻の灯火を消さず、しばらくそこに座っていたい気持ちでした。
ですが、エンディングのテーマソングの「あいたくて...」が耳障りでした。
これは完全に“はずしているな”と思いました。
ポジティーブに人間賛歌、人生を謳歌する大きな大きな「愛」というのがこの映画の基底に流れているものだと思いますので、月並みな旋律で歌詞の、片思いソングでは、意味が違うと思いました。
このおかあちゃんとの幅が違い過ぎます。
決して、倉木麻衣の曲を貶しているのではありません。
人間賛歌や男女の愛を表現するには薄すぎます。
人生の、人間存在の深い哀しみと喜びが感じられません。
残念。
例えば、ルイ・アームストロングの "What a wonderful world" のような曲だったら、もっと幸せに感じたでしょうに。もっと幸せの深い涙があふれ出てきたことでしょう。(アメリカ社会にあって、黒人として虐げられ続けてきたジャズの大御所が晩年に歌うこの曲は、意味深で透明感のある哀しさがあります)
現実にこんな家族があるのかと思ってしまいますが、それがいい意味で映画なのだ。
ということだと思います。
深刻さもサラリと笑いに転化できる技量(機知)と自由さと温かさと粘り強さが「大阪」なのだと思いました。
ビバ、オオサカ!!


















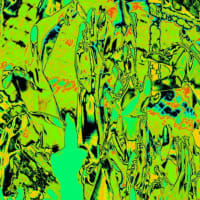
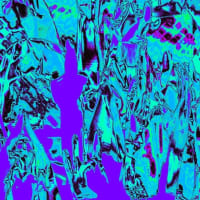
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます