あけましておめでとうございます。昨年12月から新たなブログ書き込みをすっかりご無沙汰して迎えた2020年、早やくも10日が過ぎて仕舞いましたが本年も亦、当ブログのお付き合いの程何卒よろしくお願い申し上げます。
想えば拙い本ブログを開設してから間もなく10年目を迎えます。本年からは、齢83歳を元気で迎えられるように更なる気力を絞って取り上げる話題をより広くカテゴリーシフトさせながら続行する所存で居り、引き続きのご拝読を重ねてお願い申し上げます。

―ストレスに定義無く 人それぞれに違う!-webimagesより
扨て、今年の冒頭の題名の 「健康長寿道の途に就く!」ですが、年頭話題に相応しいかどうか分かりませんが余生でも健康長寿道の妨げにもなる 「ストレス」の話、取り上げさせて頂きます。
先ず以って今日では 「ストレス」という言葉を知らない日本人は居ないと言えますが、一方で、その本質的な意味合いでの心身を護る上での大切さを、はっきり認識されている方は殆ど居ないように見受けられますが、如何でしょうか?
それで近隣の親しい方々に何気なく伺って見たのですが、殆どの方が加齢と共に自分の健康に何等かの不安を抱いて居られ、大方は少しでも身体に異常を感じたりすると、ストレスににならないよう先ずは医療のお世話になるのが一番と、その心配の払拭を第一義にされているようです。
大概は、誰にもやがては訪れる年齢と共に進む身体各部の衰えの老化現象なのでしょうが、それ故に健康不安はストレス((有害作用)になり易く、言うなれば高齢化社会は老いのもたらす加齢ストレス社会の縮図と言えそうです。
そうした心配からの解放を担っているのが今の増えている高齢者医療の役割であり、高齢化社会にあっての医療費増大に繋がっているのでいるでしょうが、其の決して好ましいとは言えない高齢者特有の加齢ストレス現象、無駄な医療費の支出の温床になってしまっては居ないでしょうか。
と申すも現代医療では その「ストレス」が原因と承知されて居ても、老人の訴えるそうした個々の症状の気休めの対症療法しかなく、老化防止本治療法等は何処にも無いからであります。

―セリエが研究した カナダのモントリオールのマギル大学-WebImagesより
其のストレスの中核を成している概念は、1930年代にカナダの生理学者 ハンス セリエが提唱した 「ストレス学説」であります。その発端は、セリエがプラハの医学生時代に受けた診断学の講義の事であり、担当教授が病気診断する時にどの病人にも見られる 「発熱」、「舌の荒れ」、「身体の痛み」や「胃腸障害」等、それら一般的な症状には全く関心が払われず、教授に依れば患者が目の前で示しているそうした症状は、どんな病気にも見られる極ありふれた非特異的な症候群であり、当時の病気とみなされた感染症の診断には全く役立たないとされたと言うのです。
しかし、セリエは当時の教授の講義に深い疑問を抱き、学位を取得後、ロックフェラー財団の奨学金を得てアメリカに留学し、其の後、カナダのモントリオールのマギル大学に移って研究生活を始めました。
セリエが所属した当時の研究室を指導していたのは、膵臓から糖尿病の特効成分のインシュリンの抽出に成功し、さらに脳下垂体から分泌するホルモンを次々に単離して、インスリンの糖尿病の臨床応用を最初に試みた生理学者でもあったコリップでした。
其処でのセリエの研究は、インシュリンのような新しいホルモンの発見に野心を燃やし、実験動物(ラット)を使っての多くの実験を行ったのですがことごとく失敗し、何らの成果を上げられなかったとあります。 だが彼は其の研究中に、患者が示す非特異的な症状と、実験動物が様々な実験操作さに対して同じように示す非特異的反応との間には、或る共通性がある事に気付き、其処に注目するようになったと言うのです。
そして研究を重ねた結果、遂に生体には外から加えられた有害な作用(ストレス)に対抗して、自身を防衛する自然の摂理を発見し、「ストレス学説」を打ち立てるに至ったと言うのです。
生体には自身を防衛する仕組みの免疫機能が備えられていますが、其の働きはもっぱら身体に侵入する細菌やウイルスに対して発揮される作用であり、セリエが発見した仕組みは、もっと広汎なあらゆる有害作用(ストレス)に対抗して働く生体の根幹的なシステムと言う事であります。
それでは生体は、そのストレス(有害作用)を継続して受けると、どのような反応を以って、わが身を守ろうとするのでしょうか?
先ずセリエが注目したのは、ストレスに対する生体反応には3つの変化であり、其れが 「副腎皮質の肥大」、「胸腺とリンパ節の萎縮」、「胃腸癖の潰瘍」でありました。
このようなストレスによって起こる臓器の変化は、ストレス(有害作用)の種類や性質には関係なく、一様に臓器に変化が起こる事が確かめられたのです。
人でのいろいろな病気で起こる、極ありふれた症状での 「舌の荒れ」、「発熱」、「胃腸障害」、「体の痛み」等は、ストレスによって起こる上記の変化に共通している 「非特異的症候群」として、生体の基本的機能と捉えられたのです。

―ハンス セリエの胸像-Wikipediaより
セリエは更に進めたストレス反応の研究から、其の反応を下記に示すような、警告反応期、抵抗期、疲憊期の時期に分け、それらの反応を起こす経路には、脳下垂体―副腎皮質の内分泌系に依る臓器組織の変容、自律神経系に依る変調の二通りが示されました。
警告反応期
有害作用に対し警報を発し、ストレスに耐えるための内部環境を急速に準備する緊急反応時期であり、自律神経のバランスが崩れ、筋弛緩・血圧低下・体温低下・血液濃度の上昇・副腎皮質の縮小などの現象が見られ外部環境への適応ができていない状態。この作用状態は、数分〜1日程度持続する。一方、抗作用状態では害作用の適応反応が本格的に発動される時期で、視床下部、下垂体、副腎皮質から分泌されるホルモンの働きにより、苦痛・不安・緊張の緩和、神経伝達活動の活性化、血圧・体温の上昇、筋緊張促進、血糖値の上昇・副腎皮質の肥大・胸腺リンパ節の萎縮現象が見られる。
抵抗期
生体の自己防御機制としての有害作用への適応反応が完成した時期で持続的な有害作用とその耐性が拮抗している安定した時期。この状態を維持するためにはエネルギーが必要であり、エネルギーを消費しすぎて枯渇すると次の疲憊期に突入。疲憊期に入る前に有害作用が弱まるか消えれば、生体は元へ戻り健康を取り戻す。
疲憊期
長期間にわたって継続する有害作用に生体が対抗できなくなり、段階的に抵抗力(ストレス耐性)が衰えてくる。疲憊期の初期には、心拍・血圧・血糖値・体温が低下する。さらに疲弊状態が長期にわたって継続し、有害作用が弱まることがなければ、生体はさらに衰弱してくる。
扨て、此処で問題として取り上げたいのは、「ストレス」の自律神経系に及ぼす有害作用であり、特に今日の文明社会に有って誰もが避け難い、多様化する社会から受ける、広汎な精神的ストレスの受難時代に遭遇している現状です。
今や現代人は、老若男女を問わず、一連の自律神経系の失調が原因となって発症に至る、文明病とも言える様々心身の疾患に苦しんで居り、今や如何にして原因となる精神的ストレスに、対処して行くべきかが問われているのです。
其の背景の縮図とも言える今日の社会構造の変容ぶりは、既存常識では益々理解し難い程に、新なる飛躍が望まれる時代要求に満ちて居り、その結果がもたらす、苛極な精神的ストレスをもたらす社会環境にに耐え、巧妙に生き延びられる、現代病罹患からの勝ち組だけが、謳歌・認容される時代の到来か?のように、今や83歳になる老人には見えてなりません。
此処で話は一寸飛躍しますが、実は古代中国に端を発した東洋医学には古の時代から、セリエの提唱したストレス学説と、その軌を一つとする、大自然の摂理に則った、生体疾病を発生させる要因を、内因、外因、病理的代謝産物の三つに分けた、ストレス(有害作用)が原因となる病の捉え方が、下記に示すように、既に明らかにされて居たのです。
内因では、体質的素因と精神的素因とに分けられ、体質的素因は更に先天的体質(遺伝・胎児期の種々の障害)と後天的体質(成長・発育・老化などの過程にあらわれた異常)とに分けられます。
次に精神的素因では、精神的・情緒的変動である (怒・喜・思・憂・悲・恐・驚)の七情が、或る限度を超えた場合に、精神的ストレス(有害作用)となって疾病の発生に繋がるとしています。
外因では、自然素因と生活素因とに分けられ、自然素因は、気候変化を六つに分け (風・寒・暑・湿・燥・火)の六気とし、それが或る程度の人体に障害となる身体的ストレス(有害作用)に達すると (風邪・寒邪・暑邪・湿邪・燥邪・火邪)の六淫になるとしています。
また、生活素因には、日常生活での暴飲暴食、過労、過度の情欲などが、疾病の発生につながるストレス(有害作用)になるとしています。
また、その生活素因や、東洋医学での生体エネルギー要素の気・血・水の停滞によって、生じた病理的代謝産物を、内因・外因に属さない不内外因としています。

―中国古代の養生奇書と言うーwebpageより
扨て、歳を経ても残されている天与の余生を無病息災で全うするには 「健康長寿街道の途に就く」、心構えが必要であり、その秘訣は何でしょうか。
実は、前述のセリエの提唱した「ストレス学説」と、その軌を一つにする東洋医学の大自然の摂理に則った生体疾病の、内因、外因、不内外因の病理的代謝産物の中に、そのヒントが隠されていたのです。
中国に現存する最古の医学教典、黄帝内経の『素問』の「上古天眞論」にある有名な 「恬淡虚無なれば、真気之に従い、精神内に守り、病いづくんぞ従い来たらん」の一行であります。
その意味ですが 「心静かして無欲の淡々たる境地に至れば、以って生命エネルギーが全身に漲り、我が身内より守られて、病気にはなりようが無い!」と言うことです。

―神経細胞の構造図―WebImagesより
この古代からの病理の捉え方を、現代生理学の知見に照らして解釈するならば、大脳皮質の神経活動のニューロン シナップスに生ずる精神的ストレスからの有害な神経活動電位(インパルス)を、自律神経系の中枢へ伝わる連絡路で、意識的、随意的に、人の意思の力を以って、断ち切れる事が出来たなら、生体活動を司る律神経系の神経活動電位(インパルス)の阻害要因が除かれ、生体の自律恒常性(ホメオスタシス)が正常化し、且つ免疫系、内分泌系システムがバランス良く作動して、生体の健全な生命活動の維持継続が図られると言う事であります。其の根本には東洋医学で謂う、精神と肉体は不可分とする 「心身一如」の思想が其の背景になっているのです。
生きとし生けるもののすべて及ぶ、其の存在の阻害要因となるストレスの有害作用、高度な文明を発達させた人類だけが、他の動物には無い、大脳皮質の作り出す、高次元の精神活動が、結果的にもたらす弊害の精神的ストレスに苦悶すると言う、混沌たる人間社会環境の展開に誰もが当面して内なる精神的難題を抱え込むと言う、事態に自ら陥って仕舞っているのです。
今や人生百年時代と言い、世界屈指の高寿者大国となった日本人の課題、何かと言えば内なる精神活動が作り出して自らを窮地に落とし込む、精神的ストレスの有害作用を、如何にして自ら克服して行くかであります。
それで今年83歳を迎える老人にも必要な「健康長寿街道の途に就く」余生の無病息災の心得に想いを寄せなら現代の「ストレス」の意味の一端を語らせて頂きました。
![]()



















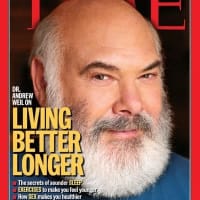


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます