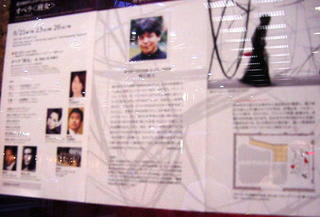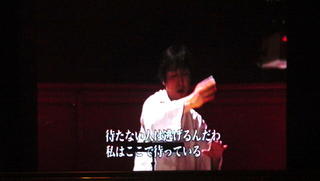松本・文化会館 2F・10-36・17,000円・
初見で聴き慣れてないので、前半の旋律感では、音楽に入り込めなかった、ただ合唱の歌わせ方等、作曲者の音楽創造の才を感じたかな、・・席に恵まれ、R側から、 SKF松本児童合唱団の賛美歌的?・・天使が、天国に導く・・美しい響きです
合唱も良く歌い込んでいて、美しい低音声域と高音声域に力強さを兼ね備えていたと感じました・・
大きなオケ編成は合唱付きとソプラノが主で、小編成では、テノール、バリトンのソロ歌唱・・対話が進む・・感じが、
小オケは室内楽編成的で弦楽五重奏+ホルン、ファゴット、クラリネット、オーボエ、フルートにハープ、パーカッションが奏で、其れに歌唱が入る・・
私は、後半、時間にして25分ほど・・音楽に惹きこまれました、小編成と歌唱のアンサンブルに長け、聴き応え十分でした・・矢部さんのソロとテノールの声質の美しさに痺れました
コンマスは豊嶋さん(新日フィル・コンマス)、小編成に矢部さん(都響コンマス)とお馴染みの顔ぶれです・・
サイトウキネンを聴くのも何年振りかな・・・顔ぶれが大分変ってますが、奏者若手の育成も目的ですね
25日 戦争レクイエム
ソプラノ: クリスティン・ゴーキー
テノール : アンソニー・ディーン・グリフィー
バリトン : ジェイムズ・ウェストマン
合唱 : SKF松本合唱団
東京オペラシンガーズ 栗友会合唱団
児童合唱 : SKF松本児童合唱団
演奏 : サイトウ・キネン・オーケストラ
指揮 : 小澤征爾 サイトウキネン結成当初の動画 19時開演
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今年は生々しい反戦の音楽=サイトウ・キネンで小沢征爾総監督-長野・松本〔地域〕8月18日14時6分配信 時事通信
18日開幕のサイトウ・キネン・フェスティバル・松本を前に17日午後、総監督を務める指揮者の小沢征爾さん(73)が長野県松本市入りし、今年2月に県内で公募した児童合唱団などと合唱のリハーサルを行った。
小沢さんは今回上演する「戦争レクイエム」について、「今年はほんとに反戦の、平和主義とかじゃなくて、生々しい反戦の音楽を僕たちは選びました」と記者団に語った。
「戦争レクイエム」はイギリスの作曲家ブリテンの代表的な声楽作品。テノールとバリトンがそれぞれイギリス兵とドイツ兵を演じ、敵対する兵士のやりとりを通じて、第2次大戦を生々しく歌いあげ、戦争の悲惨さを訴える。小沢さんが日本で「戦争レクイエム」を指揮するのは、終戦40年の1985年に広島などで公演して以来初めて。
今年で18回目を迎えるサイトウ・キネン・フェスティバル・松本は、9月9日まで長野県松本市などで開かれる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
戦争レクイエム』(せんそうレクイエム、War Requiem)は、ベンジャミン・ブリテンの作曲したレクイエム(死者のためのミサ曲)である。ブリテンの代表作として筆頭に上げられる。彼の集大成とも言えるこの作品は、単に第二次世界大戦の犠牲者の為のレクイエムではなく、だからと言って通常の教会音楽でもない。
ブリテンはこの曲のスコア冒頭に次のような、詩人ウィルフレッド・オーウェンの一節を書き記している。
私の主題は戦争であり、戦争の悲しみである。詩はその悲しみの中にある。詩人の為しうる全てとは、警告を与えることにある。
この文は「戦争レクイエム」の持つ性格を端的に現しているだけでなく、戦争を二度と繰り返さない為の作者の深い祈りがこもっている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
戦争レクイエム この曲は名目上、1962年5月に英国ウォリックシャーのコヴェントリーにある聖マイケル教会に新たに建立された大聖堂の献堂式を行うために、この教会の委嘱によって書かれた。この教会自体も第二次世界大戦中の1940年、ドイツ空軍の大空爆によって破壊されたのであった。この空爆はその後「空爆で破壊する」という意味を持つ conventraize という新しい動詞を生み出すほどの有名なもので、いわばイギリス国民にとって第二次世界大戦を象徴すると言っても過言ではないほど悲惨な体験の一つであった。これは日本が1945年3月の東京大空襲を受け、「空襲」といえばこれを指す事に通じるものがあるだろう。ブリテンは1960年後半から、作曲中であった他作品を中止してこの作品に取り組み、1961年12月に完成させた。そして予定通り1962年5月30日の献堂式に初演された。
初演
ブリテンはこの大作の初演のソリストを、ソ連のソプラノ、ガリーナ・ヴィシネフスカヤ、イギリスのテノール、ピーター・ピアーズ、ドイツのバリトン、ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウとすることを初めから考慮して作曲したといわれる。第二次世界大戦ヨーロッパ戦線の中心的交戦国であり、戦争の恐怖と被害を身に沁みて体験したこれら三国の最も優秀な歌手を一堂に集めることで、真の和解を確認して平和への誓いを固めたいという願いからだった。折りしも1962年といえば冷戦の真っ只中であり、そうした時代に初演を迎えるからこそ意義のあった作品である。
しかしガリーナ・ヴィシネフスカヤは、夫であり作曲者の友人でもあったムスティスラフ・ロストロポーヴィチの急病とソ連当局の出国停止命令により渡英不可能となり、コヴェントリー聖マイケル教会における実際の初演(1962年5月30日)は次のメンバーで行われた。
初見で聴き慣れてないので、前半の旋律感では、音楽に入り込めなかった、ただ合唱の歌わせ方等、作曲者の音楽創造の才を感じたかな、・・席に恵まれ、R側から、 SKF松本児童合唱団の賛美歌的?・・天使が、天国に導く・・美しい響きです
合唱も良く歌い込んでいて、美しい低音声域と高音声域に力強さを兼ね備えていたと感じました・・
大きなオケ編成は合唱付きとソプラノが主で、小編成では、テノール、バリトンのソロ歌唱・・対話が進む・・感じが、
小オケは室内楽編成的で弦楽五重奏+ホルン、ファゴット、クラリネット、オーボエ、フルートにハープ、パーカッションが奏で、其れに歌唱が入る・・
私は、後半、時間にして25分ほど・・音楽に惹きこまれました、小編成と歌唱のアンサンブルに長け、聴き応え十分でした・・矢部さんのソロとテノールの声質の美しさに痺れました
コンマスは豊嶋さん(新日フィル・コンマス)、小編成に矢部さん(都響コンマス)とお馴染みの顔ぶれです・・
サイトウキネンを聴くのも何年振りかな・・・顔ぶれが大分変ってますが、奏者若手の育成も目的ですね
25日 戦争レクイエム
ソプラノ: クリスティン・ゴーキー
テノール : アンソニー・ディーン・グリフィー
バリトン : ジェイムズ・ウェストマン
合唱 : SKF松本合唱団
東京オペラシンガーズ 栗友会合唱団
児童合唱 : SKF松本児童合唱団
演奏 : サイトウ・キネン・オーケストラ
指揮 : 小澤征爾 サイトウキネン結成当初の動画 19時開演
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今年は生々しい反戦の音楽=サイトウ・キネンで小沢征爾総監督-長野・松本〔地域〕8月18日14時6分配信 時事通信
18日開幕のサイトウ・キネン・フェスティバル・松本を前に17日午後、総監督を務める指揮者の小沢征爾さん(73)が長野県松本市入りし、今年2月に県内で公募した児童合唱団などと合唱のリハーサルを行った。
小沢さんは今回上演する「戦争レクイエム」について、「今年はほんとに反戦の、平和主義とかじゃなくて、生々しい反戦の音楽を僕たちは選びました」と記者団に語った。
「戦争レクイエム」はイギリスの作曲家ブリテンの代表的な声楽作品。テノールとバリトンがそれぞれイギリス兵とドイツ兵を演じ、敵対する兵士のやりとりを通じて、第2次大戦を生々しく歌いあげ、戦争の悲惨さを訴える。小沢さんが日本で「戦争レクイエム」を指揮するのは、終戦40年の1985年に広島などで公演して以来初めて。
今年で18回目を迎えるサイトウ・キネン・フェスティバル・松本は、9月9日まで長野県松本市などで開かれる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
戦争レクイエム』(せんそうレクイエム、War Requiem)は、ベンジャミン・ブリテンの作曲したレクイエム(死者のためのミサ曲)である。ブリテンの代表作として筆頭に上げられる。彼の集大成とも言えるこの作品は、単に第二次世界大戦の犠牲者の為のレクイエムではなく、だからと言って通常の教会音楽でもない。
ブリテンはこの曲のスコア冒頭に次のような、詩人ウィルフレッド・オーウェンの一節を書き記している。
私の主題は戦争であり、戦争の悲しみである。詩はその悲しみの中にある。詩人の為しうる全てとは、警告を与えることにある。
この文は「戦争レクイエム」の持つ性格を端的に現しているだけでなく、戦争を二度と繰り返さない為の作者の深い祈りがこもっている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
戦争レクイエム この曲は名目上、1962年5月に英国ウォリックシャーのコヴェントリーにある聖マイケル教会に新たに建立された大聖堂の献堂式を行うために、この教会の委嘱によって書かれた。この教会自体も第二次世界大戦中の1940年、ドイツ空軍の大空爆によって破壊されたのであった。この空爆はその後「空爆で破壊する」という意味を持つ conventraize という新しい動詞を生み出すほどの有名なもので、いわばイギリス国民にとって第二次世界大戦を象徴すると言っても過言ではないほど悲惨な体験の一つであった。これは日本が1945年3月の東京大空襲を受け、「空襲」といえばこれを指す事に通じるものがあるだろう。ブリテンは1960年後半から、作曲中であった他作品を中止してこの作品に取り組み、1961年12月に完成させた。そして予定通り1962年5月30日の献堂式に初演された。
初演
ブリテンはこの大作の初演のソリストを、ソ連のソプラノ、ガリーナ・ヴィシネフスカヤ、イギリスのテノール、ピーター・ピアーズ、ドイツのバリトン、ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウとすることを初めから考慮して作曲したといわれる。第二次世界大戦ヨーロッパ戦線の中心的交戦国であり、戦争の恐怖と被害を身に沁みて体験したこれら三国の最も優秀な歌手を一堂に集めることで、真の和解を確認して平和への誓いを固めたいという願いからだった。折りしも1962年といえば冷戦の真っ只中であり、そうした時代に初演を迎えるからこそ意義のあった作品である。
しかしガリーナ・ヴィシネフスカヤは、夫であり作曲者の友人でもあったムスティスラフ・ロストロポーヴィチの急病とソ連当局の出国停止命令により渡英不可能となり、コヴェントリー聖マイケル教会における実際の初演(1962年5月30日)は次のメンバーで行われた。