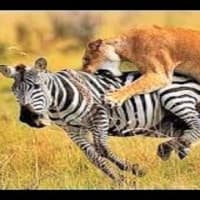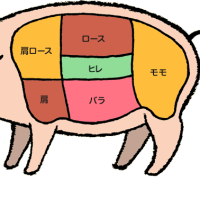中世ヨーロッパでは、和声(心地よいハモり)としては4度と5度(ドファとドソ)しか認められていなかった。3度(ドミ)はまだ不協和音だった。だが、じきにドミソが和声として認められるようになった。(いまやフォークソングは3度のハモりが定番である。)
ベートーベンなどのロマン派音楽になると、7th が和声として入ってきた。(ドミソシ♭のような和音。これを7th コードという。フォークソングやポップスには普通に使用されるが、演歌にはめったに使われない。)
ところが、モダンジャズになると9th , 11th , 13th が和声として使用されるようになり、和声の定義が格段に広がった。これらをあえてテンジョンノート(緊張の音)と呼ぶ。テンジョンノートやそれを使用したテンジョンコードはモダンジャズのサウンドをモダンジャズらしくする決定的な発明だった。
それらとは別に、suspension4 (宙ぶらりんコード、ドファシ♭)というのが出てきた。このコードが和声学的にどう位置付けられているのかは知らない。sus4 はドファラに解決する。むかし「青い三角定規」というフォークグループの「太陽がくれた季節」という歌が大ヒットしたが、その歌の前奏に使われている(前奏の4小節で「sus4→解決」を2回繰り返す)。当時、しゃれているなと思った。
参考:「太陽がくれた季節」Youtube より。
ベートーベンなどのロマン派音楽になると、7th が和声として入ってきた。(ドミソシ♭のような和音。これを7th コードという。フォークソングやポップスには普通に使用されるが、演歌にはめったに使われない。)
ところが、モダンジャズになると9th , 11th , 13th が和声として使用されるようになり、和声の定義が格段に広がった。これらをあえてテンジョンノート(緊張の音)と呼ぶ。テンジョンノートやそれを使用したテンジョンコードはモダンジャズのサウンドをモダンジャズらしくする決定的な発明だった。
それらとは別に、suspension4 (宙ぶらりんコード、ドファシ♭)というのが出てきた。このコードが和声学的にどう位置付けられているのかは知らない。sus4 はドファラに解決する。むかし「青い三角定規」というフォークグループの「太陽がくれた季節」という歌が大ヒットしたが、その歌の前奏に使われている(前奏の4小節で「sus4→解決」を2回繰り返す)。当時、しゃれているなと思った。
参考:「太陽がくれた季節」Youtube より。