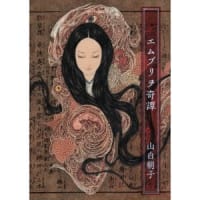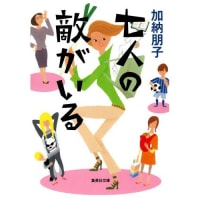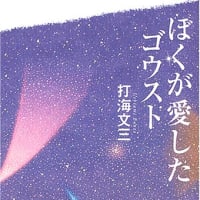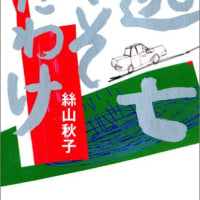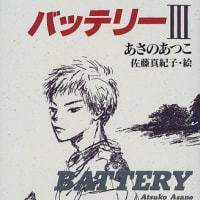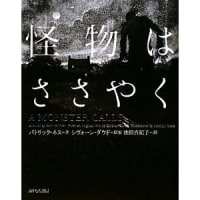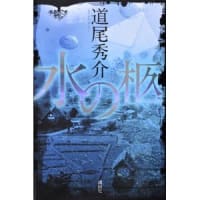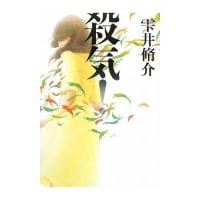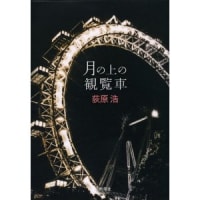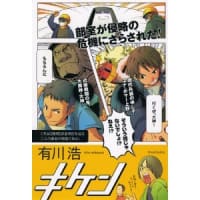抜粋
古書店アルバイトの大学生・菅生芳光は、
報酬に惹かれてある依頼を請け負う。
依頼人・北里可南子は、亡くなった父が生前に書いた、
結末の伏せられた五つの小説を探していた。
調査を続けるうち芳光は、未解決のままに終わった事件
“アントワープの銃声”の存在を知る。
二十二年前のその夜何があったのか?
幾重にも隠された真相は?
米澤穂信が初めて「青春去りし後の人間」を描く最新長編。
感想文書くにあたってまずは某所から画像を引っ張ってくるんだけど。
そこでついでに出版社からの紹介文をいつも抜粋しているわけだけど。
>米澤穂信が初めて「青春去りし後の人間」を描く最新長編。
ここにひっかかる。
今回の主人公は男性。
大学を一身上の都合で休学している二十歳前後の男の子。
その子をもってして「青春去りし後の人間」とは。
なんかひっかかるんだけど、わたしだけ?
甘酸っぱさがなきゃ青春じゃないっていいたしのかしらん。
さよなら妖精や小市民シリーズ、古典部シリーズは
たしかに瑞々しい十代の男女がなんやかやしてるけど。
ボトルネックは青春だった?
インシテミルは?
犬はどこだは?
“初めて”に語弊があるんだと気づく。
青春が去ったなんて誰が決めるんだー
どうでもいいことに反応して長い冒頭になった。
一身上の都合というのは、彼の家庭の事情である。
大学で学ぶこと、または通うための費用の捻出が
不可能になった男の子が、それでも東京から離れたくなくて
伯父を頼り、彼の経営する古書店の手伝いをするかわりに
居候をしながら次の手を鬱々と考えている、
基本的には素直な青年が主人公。
時代背景としては、バブル後。
今の時代もこんな話はそこらへんに転がっている。
お金がなくて休学しているっていう同級生の話。
そしてその休学の期限が今年いっぱいだとか。
学費と生活費は親が出してくれていて、
奨学金は自分のこづかいにあてていた、とか。
今、その奨学金をちゃくちゃくと返しているよ。
全部返し終わったら30過ぎてるよー、なんて。
そんな話をきいたからにはわたしも親に感謝の念が沸いてくる。
何不自由なく高校行って、なんとなくで決めた専門学校に
いかせてくれて、最終的に今はその仕事はしていないときた。
たしかに数年間勤めたけども。
なんだかなぁ、と思ってるのはもはやお互い様かもしれない。
話を元に戻す。
居候の身で、実家に電話をかけるのにも気を使っていた主人公は
突然舞い込んできた儲け話につい興味を引かれた。
探してほしい本があるという依頼を受けた彼は、
彼の伯父に話を通さずに自分ひとりでその依頼を引き受けることに。
たまたまその場に居合わせたバイトの女子も、
わたしも一口かませてくれてということで、報酬の2割を約束させて
仲間になることに。
このあらすじを読んでるぶんにはまだ主人公のひととなりは
わからないんじゃないかと思う。
主人公はお調子者でもなく、生真面目でもなく、
まして熱血タイプでもなく、やや冷めた普通の元・大学生だ。
だからここまでのなりゆきはコミカルな会話なんかじゃなく、
たんたんと話が進んでいった。
感情を抑えるというか、いつもどこか引け目を感じているような
罪悪感を抱えて生きているみたいな影のある人だった。
依頼主は女性で、彼女の今は亡き父が私的に書いていた短編小説を
探してほしいとのこと。全部でおそらく5つある。
一編みつけるごとに10万のお礼を払うという。
それだけ大金をはたくということで、どこかいぶかしむ主人公。
当然なんかあるからそんな大金をかけるんだろうな
とわたしでもわかる。
小説を見つけるごとに、踏み込んではいけないようなところまで
踏み込んでいく主人公。
小説を探すために彼女の父親の過去まで知ることになっていく。
なぜ五つある、とわかるのか。
彼女の元に残された小説の結末が五つ用意されていたから。
父が書いたショートストーリーはリドルストーリーだった。
この言葉は始めて知った。
そのものは知っているけれど。
いわゆる芥川龍之介の「藪の中」のようなものを指す。
結末を読者に委ねて書いていない小説。
次々と見つかっていく断章。
なぜ、父はリドルストーリーとして完成品としたのか。
なぜ、父はリドルストーリーなのに結末を用意したのか。
その答えは。
小説が見つかる度に彼女へコピーを送れば、
返事と共に、用意されていた結末が送られてくる。
読まないままがよかったと思うような結末だったり。
そうだったのかと思うような結末だったり。
結局真相は、悲しいものだったけれど。
おもしろかった。
途中で挟まれる彼女の父が残したショートストーリー。
それぞれが深かった。
よく、小説の中に登場する、小説があったりする。
小説というよりも、逸話であったり、例え話だったりするのだけど。
ふと思い出したのは、掌の中の小鳥。
賢者の手の中の小鳥は、生きているか、死んでいるか。
それから、スパルタという国の狐を盗んだ少年の話とか。
三月は深き紅の淵をだって、その本を巡る話だったりする。
そして、今思い出したけど“猿の手”のストーリーを知ったのも
恩田陸のまひるの月を追いかけて、だったのだ。
洞穴の穴の蝋燭の話には胸が詰った。
そんな風に、小説そのものよりも
そっちの方が印象に強く残ったりするものだ。
今回はそれだった。
怖い話をきいているような。
知らないままでいられたらよかったのに。
そんなこと世の中にたくさんあるのに。
知らないままでいられなかったひとたちの話。
追想五断章
断章の意味がわからなくて調べた。
詩や文章の断片。
五つの断章を思い出して偲ぶこと。
これがタイトルなのだから、きっとこれから二人は、
あるいは彼女はそうするつもりだったんだろう。
途中、主人公が「花は嫌いだ」といった。
不思議に思った。
あるだけでなんだか気分がよくなったり、癒されるのに。
その花が嫌いなのかと思ったらそうじゃなく、花が嫌いといった。
梅が咲けば、去年の梅が咲いてから一年が経ったことを思い知らされる。
桜が咲けば、去年の桜が咲いてから一年が経ったことを思い知らされる。
そんな風に感じる人もいるんだ、って思った。
思い出される、じゃなくて。
思い知らされる、とある。
彼は時が経ったことを焦りとか苛立ちに感じるんだろう。
だから思い知らされると感じる。
花を見て、いい匂いだとか綺麗だと感じる前に、
見たくもないって思う人がいるなんて。
花を見てそう感じる人がいるということに軽く驚いた。
そう感じる男の子が主人公なお話。
余談
本の表紙
本の中に少女が眠っている
閉じ込められたわけじゃないんだろうけど
これでメトロポリタンミュージアムを連想したのはわたしだけだろうか
2010.02.26
古書店アルバイトの大学生・菅生芳光は、
報酬に惹かれてある依頼を請け負う。
依頼人・北里可南子は、亡くなった父が生前に書いた、
結末の伏せられた五つの小説を探していた。
調査を続けるうち芳光は、未解決のままに終わった事件
“アントワープの銃声”の存在を知る。
二十二年前のその夜何があったのか?
幾重にも隠された真相は?
米澤穂信が初めて「青春去りし後の人間」を描く最新長編。
感想文書くにあたってまずは某所から画像を引っ張ってくるんだけど。
そこでついでに出版社からの紹介文をいつも抜粋しているわけだけど。
>米澤穂信が初めて「青春去りし後の人間」を描く最新長編。
ここにひっかかる。
今回の主人公は男性。
大学を一身上の都合で休学している二十歳前後の男の子。
その子をもってして「青春去りし後の人間」とは。
なんかひっかかるんだけど、わたしだけ?
甘酸っぱさがなきゃ青春じゃないっていいたしのかしらん。
さよなら妖精や小市民シリーズ、古典部シリーズは
たしかに瑞々しい十代の男女がなんやかやしてるけど。
ボトルネックは青春だった?
インシテミルは?
犬はどこだは?
“初めて”に語弊があるんだと気づく。
青春が去ったなんて誰が決めるんだー
どうでもいいことに反応して長い冒頭になった。
一身上の都合というのは、彼の家庭の事情である。
大学で学ぶこと、または通うための費用の捻出が
不可能になった男の子が、それでも東京から離れたくなくて
伯父を頼り、彼の経営する古書店の手伝いをするかわりに
居候をしながら次の手を鬱々と考えている、
基本的には素直な青年が主人公。
時代背景としては、バブル後。
今の時代もこんな話はそこらへんに転がっている。
お金がなくて休学しているっていう同級生の話。
そしてその休学の期限が今年いっぱいだとか。
学費と生活費は親が出してくれていて、
奨学金は自分のこづかいにあてていた、とか。
今、その奨学金をちゃくちゃくと返しているよ。
全部返し終わったら30過ぎてるよー、なんて。
そんな話をきいたからにはわたしも親に感謝の念が沸いてくる。
何不自由なく高校行って、なんとなくで決めた専門学校に
いかせてくれて、最終的に今はその仕事はしていないときた。
たしかに数年間勤めたけども。
なんだかなぁ、と思ってるのはもはやお互い様かもしれない。
話を元に戻す。
居候の身で、実家に電話をかけるのにも気を使っていた主人公は
突然舞い込んできた儲け話につい興味を引かれた。
探してほしい本があるという依頼を受けた彼は、
彼の伯父に話を通さずに自分ひとりでその依頼を引き受けることに。
たまたまその場に居合わせたバイトの女子も、
わたしも一口かませてくれてということで、報酬の2割を約束させて
仲間になることに。
このあらすじを読んでるぶんにはまだ主人公のひととなりは
わからないんじゃないかと思う。
主人公はお調子者でもなく、生真面目でもなく、
まして熱血タイプでもなく、やや冷めた普通の元・大学生だ。
だからここまでのなりゆきはコミカルな会話なんかじゃなく、
たんたんと話が進んでいった。
感情を抑えるというか、いつもどこか引け目を感じているような
罪悪感を抱えて生きているみたいな影のある人だった。
依頼主は女性で、彼女の今は亡き父が私的に書いていた短編小説を
探してほしいとのこと。全部でおそらく5つある。
一編みつけるごとに10万のお礼を払うという。
それだけ大金をはたくということで、どこかいぶかしむ主人公。
当然なんかあるからそんな大金をかけるんだろうな
とわたしでもわかる。
小説を見つけるごとに、踏み込んではいけないようなところまで
踏み込んでいく主人公。
小説を探すために彼女の父親の過去まで知ることになっていく。
なぜ五つある、とわかるのか。
彼女の元に残された小説の結末が五つ用意されていたから。
父が書いたショートストーリーはリドルストーリーだった。
この言葉は始めて知った。
そのものは知っているけれど。
いわゆる芥川龍之介の「藪の中」のようなものを指す。
結末を読者に委ねて書いていない小説。
次々と見つかっていく断章。
なぜ、父はリドルストーリーとして完成品としたのか。
なぜ、父はリドルストーリーなのに結末を用意したのか。
その答えは。
小説が見つかる度に彼女へコピーを送れば、
返事と共に、用意されていた結末が送られてくる。
読まないままがよかったと思うような結末だったり。
そうだったのかと思うような結末だったり。
結局真相は、悲しいものだったけれど。
おもしろかった。
途中で挟まれる彼女の父が残したショートストーリー。
それぞれが深かった。
よく、小説の中に登場する、小説があったりする。
小説というよりも、逸話であったり、例え話だったりするのだけど。
ふと思い出したのは、掌の中の小鳥。
賢者の手の中の小鳥は、生きているか、死んでいるか。
それから、スパルタという国の狐を盗んだ少年の話とか。
三月は深き紅の淵をだって、その本を巡る話だったりする。
そして、今思い出したけど“猿の手”のストーリーを知ったのも
恩田陸のまひるの月を追いかけて、だったのだ。
洞穴の穴の蝋燭の話には胸が詰った。
そんな風に、小説そのものよりも
そっちの方が印象に強く残ったりするものだ。
今回はそれだった。
怖い話をきいているような。
知らないままでいられたらよかったのに。
そんなこと世の中にたくさんあるのに。
知らないままでいられなかったひとたちの話。
追想五断章
断章の意味がわからなくて調べた。
詩や文章の断片。
五つの断章を思い出して偲ぶこと。
これがタイトルなのだから、きっとこれから二人は、
あるいは彼女はそうするつもりだったんだろう。
途中、主人公が「花は嫌いだ」といった。
不思議に思った。
あるだけでなんだか気分がよくなったり、癒されるのに。
その花が嫌いなのかと思ったらそうじゃなく、花が嫌いといった。
梅が咲けば、去年の梅が咲いてから一年が経ったことを思い知らされる。
桜が咲けば、去年の桜が咲いてから一年が経ったことを思い知らされる。
そんな風に感じる人もいるんだ、って思った。
思い出される、じゃなくて。
思い知らされる、とある。
彼は時が経ったことを焦りとか苛立ちに感じるんだろう。
だから思い知らされると感じる。
花を見て、いい匂いだとか綺麗だと感じる前に、
見たくもないって思う人がいるなんて。
花を見てそう感じる人がいるということに軽く驚いた。
そう感じる男の子が主人公なお話。
余談
本の表紙
本の中に少女が眠っている
閉じ込められたわけじゃないんだろうけど
これでメトロポリタンミュージアムを連想したのはわたしだけだろうか
2010.02.26