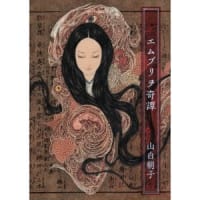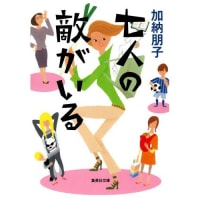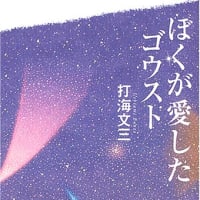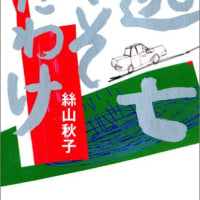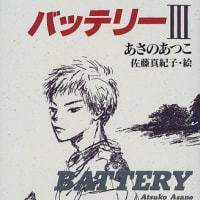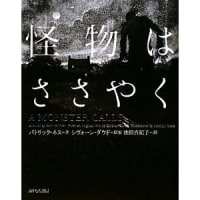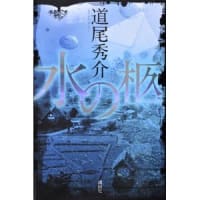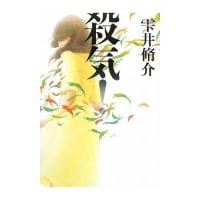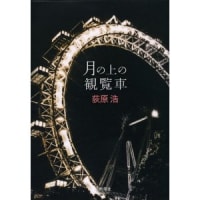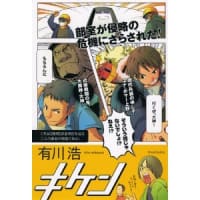抜粋
ある夜、怪物が少年とその母親の住む家に現れた。
怪物はその少年に言う。
「わたしが三つの物語を語り終えたら、 四つめの物語をわたしに話すのだ」と。
そして怪物は付け加えた、その物語は少年が心に秘めた真実の物語であり、
その物語を語り聞かせるために少年が怪物を呼んだのだ、と。
少年が語るべき真実とはなにか?
少年がそれを語り終えるとき、この物語も同時に結末を迎える。
その大きな喪失感をもたらす結末は読む者すべてにそれぞれの 感動をもたらすことだろう。
13歳の少年は”それ”を受け入れ、飼い慣らし、乗り越えていくことができるのか…。
”Chos Walking Trilogy”シリーズ第3作でカーネギー賞を受賞した
全英ベストセラー作家が描く喪失と浄化の物語。
『物語は暴れん坊だ。・・・・まさに油断のならない生き物だ』
―池田真紀子 本書訳者あとがきより
図書館で、貸し出し更新してからふと児童書コーナーを眺めていて。
怪物はささやく・・・
魔術はささやく、をなんとなく思い出した。
全然違うのだけれど、とりあえず手にとって見た。
印象的なのは描き殴ったような荒々しいタッチの中にも
繊細さを感じ取れるような独特の画。
まず挿画が目に飛び込んできた。
白黒で描かれる真っ黒なシルエット。
表情は見えないのに、絶望が伝わってくるようだった。
あらすじを読んで惹かれるものがあり、借りてみた。
怪物の話す物語とはなんなのか。
真夜中に怪物の訪問を受け入れる少年。
少年は怪物を怖いとは思わなかった・・・
なぜならこの世にはもっと恐ろしいものがあるから。
終始陰鬱で、怪物との会話の方が人間的だった。
怪物の話す物語はどれもがバットエンドといってもいいような内容で
今にもプレッシャーに押しつぶされそうになりながらも必死にもがいている少年に
追い討ちをかけるかのように辛辣だった。
最後は自分との戦い。
少年は認めることで、自らを許すことができたのだろうか。
わたしが身近な人の死に直面したのは小学生の頃だった。
最初に父方の祖母が亡くなった。
この時はまだ死体が怖かった。
身近な人の死ではあったけど、柩に花をつめる時にしか涙はでなかった。
父方の祖父の余命を告げられたのは中学生の時だったかもしれない。
それを知った夜は泣いた。
そして、父方も母方もどちらも兄と姉が唐突に亡くなった。
あまりに唐突だったので、実際に亡骸を見るまで悲しいという感情は浮かばなかった。
この時、初めて気が付いたら涙が出ていたというのを体験した。
悲しいより先に涙がでることがあるんだなって知った。
祖母はこの頃記憶が曖昧なことが多くて、何か騒がしいなと思っていたと思う。
親より先に逝ってはならない、とこの時強く思った。
父方の祖父は末期ガンで、余命が宣告されている中での息子の葬式だった。
葬式の続いた年だった。
立て続けに肉親を失った両親の落ち込みようは激しく
実際に姉や兄が亡くなった年を追い越すまで感慨は続いた。
死にまつわる記憶。
そんなことを呼び起こされた本だった。
少年の母親は多分ガンで、少年がまだ中学生ぐらいの年からいっても
40代ぐらいなんだろうと思う。
ガン細胞も若い人の場合は元気がいいときいたことがある。
だから進行が早いって。
モルヒネを打って記憶がごちゃごちゃになった祖父を思いだした。
いたるところから管が伸びていて、風呂に入れないので少し匂う。
中学生だっわたしは、親戚がそろった病室で
手を握って声をかけてといわれても、涙を堪えるのに必死で
親戚の背中越しに無言でげっそりと肉の落ちた祖父を見るので精一杯だった。
沢山の管に繋がれて意識が朦朧としている祖父が痛々しくて
笑って挨拶なんてとてもじゃないけどできなかった。
そっけないわたしを両親や親戚は思春期だから、と思っただろうか。
わけもわからず出てくる涙を止められなくてトイレで少し泣いた。
わたしはずっと身近でそれを見てきたわけじゃないから
少年に共感できるとはいえないのだけど、
身近で見てきた彼だからこそ想像するものがあるんだろうと思う。
ベットに横たわる母親を何度も、何度も見てきた少年だからこそ
思うものがあったんだろう、と思う。
この先、身近な人の死に直面するのは
願わくば、もっとずっと、ずっと先であって欲しい。
『ボグ・チャイルド』のシヴォーン・ダウドの原案を
“Monsters of Men: Chaos Walking: Book Three”でカーネギー賞を獲得した
パトリック・ネスが小説化したもの。
その方を知らないのですが、本人が書けなかったということは
もうこの世の人ではないということで。
故人が喜ぶような出来になっているといいな、と思った。
2013.01.10
ある夜、怪物が少年とその母親の住む家に現れた。
怪物はその少年に言う。
「わたしが三つの物語を語り終えたら、 四つめの物語をわたしに話すのだ」と。
そして怪物は付け加えた、その物語は少年が心に秘めた真実の物語であり、
その物語を語り聞かせるために少年が怪物を呼んだのだ、と。
少年が語るべき真実とはなにか?
少年がそれを語り終えるとき、この物語も同時に結末を迎える。
その大きな喪失感をもたらす結末は読む者すべてにそれぞれの 感動をもたらすことだろう。
13歳の少年は”それ”を受け入れ、飼い慣らし、乗り越えていくことができるのか…。
”Chos Walking Trilogy”シリーズ第3作でカーネギー賞を受賞した
全英ベストセラー作家が描く喪失と浄化の物語。
『物語は暴れん坊だ。・・・・まさに油断のならない生き物だ』
―池田真紀子 本書訳者あとがきより
図書館で、貸し出し更新してからふと児童書コーナーを眺めていて。
怪物はささやく・・・
魔術はささやく、をなんとなく思い出した。
全然違うのだけれど、とりあえず手にとって見た。
印象的なのは描き殴ったような荒々しいタッチの中にも
繊細さを感じ取れるような独特の画。
まず挿画が目に飛び込んできた。
白黒で描かれる真っ黒なシルエット。
表情は見えないのに、絶望が伝わってくるようだった。
あらすじを読んで惹かれるものがあり、借りてみた。
怪物の話す物語とはなんなのか。
真夜中に怪物の訪問を受け入れる少年。
少年は怪物を怖いとは思わなかった・・・
なぜならこの世にはもっと恐ろしいものがあるから。
終始陰鬱で、怪物との会話の方が人間的だった。
怪物の話す物語はどれもがバットエンドといってもいいような内容で
今にもプレッシャーに押しつぶされそうになりながらも必死にもがいている少年に
追い討ちをかけるかのように辛辣だった。
最後は自分との戦い。
少年は認めることで、自らを許すことができたのだろうか。
わたしが身近な人の死に直面したのは小学生の頃だった。
最初に父方の祖母が亡くなった。
この時はまだ死体が怖かった。
身近な人の死ではあったけど、柩に花をつめる時にしか涙はでなかった。
父方の祖父の余命を告げられたのは中学生の時だったかもしれない。
それを知った夜は泣いた。
そして、父方も母方もどちらも兄と姉が唐突に亡くなった。
あまりに唐突だったので、実際に亡骸を見るまで悲しいという感情は浮かばなかった。
この時、初めて気が付いたら涙が出ていたというのを体験した。
悲しいより先に涙がでることがあるんだなって知った。
祖母はこの頃記憶が曖昧なことが多くて、何か騒がしいなと思っていたと思う。
親より先に逝ってはならない、とこの時強く思った。
父方の祖父は末期ガンで、余命が宣告されている中での息子の葬式だった。
葬式の続いた年だった。
立て続けに肉親を失った両親の落ち込みようは激しく
実際に姉や兄が亡くなった年を追い越すまで感慨は続いた。
死にまつわる記憶。
そんなことを呼び起こされた本だった。
少年の母親は多分ガンで、少年がまだ中学生ぐらいの年からいっても
40代ぐらいなんだろうと思う。
ガン細胞も若い人の場合は元気がいいときいたことがある。
だから進行が早いって。
モルヒネを打って記憶がごちゃごちゃになった祖父を思いだした。
いたるところから管が伸びていて、風呂に入れないので少し匂う。
中学生だっわたしは、親戚がそろった病室で
手を握って声をかけてといわれても、涙を堪えるのに必死で
親戚の背中越しに無言でげっそりと肉の落ちた祖父を見るので精一杯だった。
沢山の管に繋がれて意識が朦朧としている祖父が痛々しくて
笑って挨拶なんてとてもじゃないけどできなかった。
そっけないわたしを両親や親戚は思春期だから、と思っただろうか。
わけもわからず出てくる涙を止められなくてトイレで少し泣いた。
わたしはずっと身近でそれを見てきたわけじゃないから
少年に共感できるとはいえないのだけど、
身近で見てきた彼だからこそ想像するものがあるんだろうと思う。
ベットに横たわる母親を何度も、何度も見てきた少年だからこそ
思うものがあったんだろう、と思う。
この先、身近な人の死に直面するのは
願わくば、もっとずっと、ずっと先であって欲しい。
『ボグ・チャイルド』のシヴォーン・ダウドの原案を
“Monsters of Men: Chaos Walking: Book Three”でカーネギー賞を獲得した
パトリック・ネスが小説化したもの。
その方を知らないのですが、本人が書けなかったということは
もうこの世の人ではないということで。
故人が喜ぶような出来になっているといいな、と思った。
2013.01.10