今年は、10月23日(土)
秋晴れの天候に恵まれて
フアインプラザでの室内学習会(1時間)


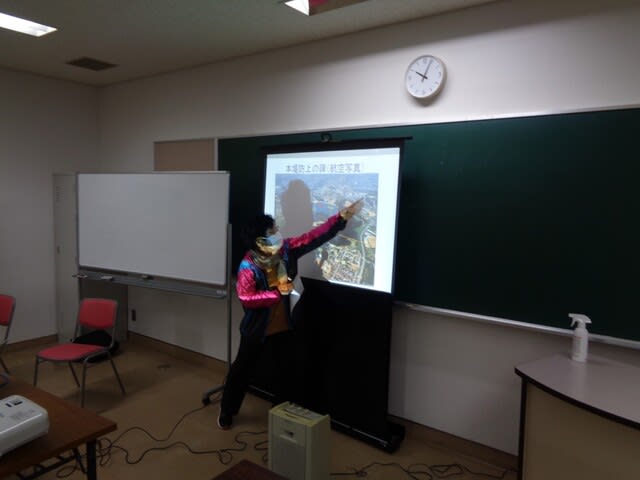

フイールドワーク(本堤防、光明池守護神社、本堤防の石碑、朝鮮人労働者犠牲者慰霊碑)も快適に実施できました。


<




2006年に建立した説明版
1年間かかって碑文が出来上がりました
皆さんの協力の賜物です。

光明池工事の証言をしてくださった方々がほとんど他界されました。
最近は21年間調査に付き合ってくださった
朴南出さんの息子さんも6月に急逝され、寂しさをかみしめています。
小学校6年間、光明池工事を見てきた井上実さん(18年前に逝去)は、朴南出さんの息子さんと友達で
一緒に光明池歴史調査に同行して説明してくださいました。
二人に思いを馳せて『みのるじいさんから聴いた話」を今年度中に冊子としてまとめることにしました。
学習会参加の方々に聞いていただきました。
慰霊碑前では、在日の方々によってチェサが行われましたが、コロナ下で昼食交流会は今年も中止でした。
秋晴れの天候に恵まれて
フアインプラザでの室内学習会(1時間)


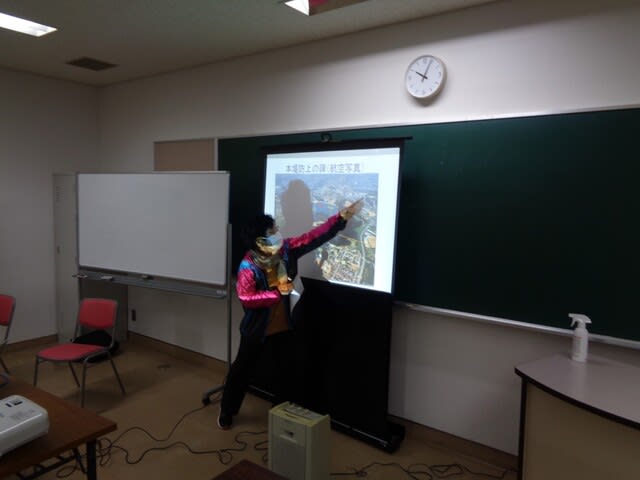

フイールドワーク(本堤防、光明池守護神社、本堤防の石碑、朝鮮人労働者犠牲者慰霊碑)も快適に実施できました。


<




2006年に建立した説明版
1年間かかって碑文が出来上がりました
皆さんの協力の賜物です。

光明池工事の証言をしてくださった方々がほとんど他界されました。
最近は21年間調査に付き合ってくださった
朴南出さんの息子さんも6月に急逝され、寂しさをかみしめています。
小学校6年間、光明池工事を見てきた井上実さん(18年前に逝去)は、朴南出さんの息子さんと友達で
一緒に光明池歴史調査に同行して説明してくださいました。
二人に思いを馳せて『みのるじいさんから聴いた話」を今年度中に冊子としてまとめることにしました。
学習会参加の方々に聞いていただきました。
慰霊碑前では、在日の方々によってチェサが行われましたが、コロナ下で昼食交流会は今年も中止でした。

































