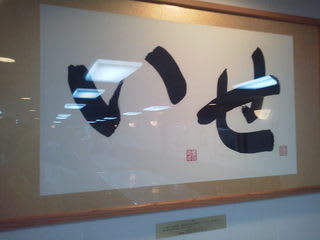自衛隊の海外派遣に関する議論で、国会は揺れておりますが、
そういう今だからこそ、ぜひとも読んでほしい一冊の本があります。
「ペルシャ湾の軍艦旗」

一度、FM番組内で取り上げましたが、
実は、ブログできちんと記事にしたいとずっと思っており、
今回、ようやく書くことができました。
この本は、自衛隊が初の海外派遣を行った、湾岸戦争後の機雷除去の任務にあたった、
海上自衛隊機雷掃海部隊の詳細なドキュメンタリーです。
1991年4月26日、部隊は出港の日を迎えた。派遣の大義名分は戦争ではなく、平穏な海を取り戻すための
平和目的―しかし、掃海の任務につくものからすれば、いささか違う。依然として恐るべき破壊力を持った
機雷と戦う掃海屋にとっては、戦場に赴くも同然であり、当然被害を想定しなければならなかった。
(本書裏表紙より)
久しぶりに、読んでよかったと思った本に出会いました。
この本は、今でも付き合いのある、中学生時代の社会科の先生から頂きました。
自衛隊に興味をもたれた先生は、自衛隊の事をもっと知りたいと思い、
この本を手に取られ、読み、
「自分がいかに自衛隊について知らないできたか」
ということに、改めて思いを致されたとのことで、
ぜひ、私に読んでほしいとのことで、手渡してくださったのです。
湾岸戦争において、日本は国際評価を著しく下げることになりました。
「お金出して、命を出さない」
と、諸外国から大きな非難を受けたのです。
また、中東に駐在していた企業は、戦争が始まるや否や、ただちに従業員を帰国させ、
日本人だけが中東からいなくなったのだそうです。
「日本は、憲法で戦争に加担しないと決まっているので、戦争に加わりません」
と、言ったところで、単に無責任で自分勝手だと思われるのは、当然です。
日本企業は、国家ごと大きく信用を失ないました。
かつてイラン・イラク戦争の時、自衛隊に代わって、ペルシャ湾を航行する日本のタンカーを、
米海軍やNATOの海軍が護衛してくれたのですが、
その時の彼らの心中は、実際に掃海部隊の海上自衛官に向けられました。
「自国のエネルギー源の70%を中東に依存している日本のタンカーを守るため、
なぜ、アメリカやその他の国の若者が危険に身をさらさねばさならないのか」
腹に据えかねた、司令の落合一佐が
「日本人は130億ドル、国民一人当たり1万円払って国際貢献している」
と反論したところ、
「国民一人当たり1万円か。ニアリ―イコール100ドル。100ドル払えばペルシャ湾に来なくてすむのなら、
今ここで100ドル払ってやるよ」
と切り返され、言葉に詰まる場面が出てきます。
また、現地に駐在していた企業の民間人は、
「なぜ日本の海軍はこないのか?」
とアラブ人から聞かれて、忸怩たる思いを抱えていたのですが、
初めて海上自衛隊の掃海艇と、艦尾にはためく「軍艦旗」を見た時の感激はいかばかりだったでしょう。
ここで書くまでもありませんが、自衛隊が自ら意志で、海外に行かなかったわけではないし、
海外のみならず、現在、小笠原などの離島に派遣できないのも、自衛隊が離島を見捨てたのではありません。
海外派遣であれ、国防であれ、充分に高い水準で任務を完遂する能力と意思を持っているにも拘らず、
あらゆる行動の制限の中で、手足を縛られたような状態で様々な任務についていらっしゃる現状を知ると、
中国を利するためのエセ平和主義論を声高に主張する、左野党に憤りを禁じ得ません。
そんな中でも、粛々と自分たちに与えられた任務を完遂され、
国際的に地に落ちた日本の信用を回復しただけでなく、世界で最も高い評価にまで上げてくれた自衛隊には、
感謝と尊敬の念しかありません。
その、国際貢献の第一歩が、このペルシャ湾における機雷除去なのです。
通常、掃海部隊は三隻で掃海作業を行いますが、数か月(終わりが未定)ということから、
長期に渡って作業可能なように4隻の編成で行われました。
「ひこしま」「ゆりしま」「あわしま」「さくしま」
掃海母艦「はやせ」補給艦「ときわ」が選ばれました。
小さな掃海艇でペルシャ湾には行って帰ってくるだけでも、相当困難なことです。
また、当時は、潜水艦「なだしお」事故の海難審判の一審が終わろうとしていた時だったので、
特に自衛隊に対する風当たりがひどく強かった時代でしたから、当時の広報官も相当な苦労をされていたようです。
…派遣部隊の人選が決まり、出港するまでの件は、平成の話とは思えない、
大東亜戦争時代の出兵と同じような緊迫感がありました。
なにをどう取り繕おうと、この派遣部隊は当事者にとっては「出兵」と何ら変わりがなかったことが分かります。
「二度と帰ってこれないかもしれない」
という思いを抱いていた方が、少なくなかったのです。
派遣の大義名分は戦争ではなく、平穏な海を取り戻すための平和目的
―しかし、掃海の任務につくものからすれば、いささか違う
その理由は、ミサイルはもう飛んでこないし、人間も銃を撃ってはこないという点で、戦争は終結しているが、
海中の「機雷は戦争を止めていない」ので、
掃海部隊にとっては、戦争は終わっていないので、戦地に赴くのと何ら変わりがなかったのです。
また、こんな話もありました。
灼熱の太陽の下、航海における最も過酷な任務は艦首見張りで、かつ、万が一触雷でもした場合、
最も命の危険がある配置なのだそうで、この勤務を、国内では当直に立つことのない先任海曹たちが、
進んで引き受けられたのだそうす。
「若い者は、我々より長く生きる権利がある。そんな彼らを先に死なせるわけにはいかない。
だから、危険な艦首見張りは我々が引き受けよう」
帝国海軍魂が、平成の時代まで途絶えずに脈々と受け継がれていることを感じました。
ここで、海外派遣における自衛隊の武装について書きます。
海上自衛隊の元々の部隊編成プランでは、掃海艇は6隻、護衛艦を2隻つけるものだったそうですが、
「戦闘艦の派遣は不可という、国内の世論によって削られた」
のだそうです。
ほぼ丸腰と言ってもいい掃海艇の頼みの綱は、掃海母艦「はやせ」の3インチ砲のみとなりました。
「護衛艦がダメなら、せめて補給艦「ときわ」にヘリコプターを搭載してほしい」
と頼んでも、却下されたのだそうです。
理由はただ一つ、派遣部隊に軍事色が強すぎる印象を与えかねないという、決めて非論理的なものです。
無知で感情論だけの主張が、いかに自衛隊を危険にさらすものであるか、お分かり頂けると思います。
これよりあと、陸上自衛隊のPKO派遣が決まってからも、
「一人につき、銃を1丁だけ持たせるか」が、2丁まで持たせるかが議論になっていましたが、
甚だバカげた議論だと言わざるを得ません。
そして、こういうバカげた考えを持ちだしかねない内局の支配下に、
自衛隊を置かない事ことが、自衛隊を危険にさらさない手段を撮り得る最善の策だと考えます。
「私服組と制服組」を並列に置く意義は、まさしくここにあると考えます。
左に傾いた野党連中は、
「危険だから、派遣しなければいい」
という思考ですが、先も申し上げたように、国際社会から孤立するわけにはいかない以上、
もはや、自衛隊を派遣しない、という選択肢はないのですから、
危険な場所で、自分たちを、きちんと守れるための準備が不可欠です。
また、このペルシャ湾であれ、南スーダンやカンボジアであれ、
非武装地帯だからと、安全と言いきれる場所などないことは、まともな推察力を持っていれば分かることで、
だからこそ、必要な法整備をした上で、必要な武器を持たせて、送り出さねば危険なのではないでしょうか?
そう考えると、勘違いした平和主義で軽武装で危険な場所に赴かされることが、
どれほど危険なことか、想像するに難くないでしょう。
そもそも、海外の、正規軍であれ民兵であれ、民間人であれ、
「自衛隊は軍隊ではない」
と認識している外国人って、どれほどいるのでしょうか?
上記に挙げたように、諸外国から見たら、
海上自衛隊ではなく「日本海軍」という認識であり、そしてそれは、決して忌避されるものではないのです。
現地の新聞には「日本海軍来たる」という見出しが出て、港で、艦尾に翻る旭日旗を見た時に、
「これでやっと国際社会の仲間に入れた」
と、肩身の狭い思いをしていた現地日本人に勇気を与えたのです。
これが、国際社会の現実です。
イギリス人やインド人の友人も一緒になって、
「よかったな
 日本海軍が来るんだな
日本海軍が来るんだな 」
」と喜んでくれたそうなので、国際社会における「日本の軍隊に対するアレルギー」とやらが、
いかに幻想で、それが特定アジアの日本を抑え込む戦略でしかないかということを、
いい加減、日本人は推して知るべきではないでしょうか。
結局、護衛に関しては、米海軍に頼ることになり、ヘリが必要な時も、
ヘリを搭載していないので米軍のヘリを借りるほかになく、それは、
「同じNavyの指揮官として、いささか落合一佐のプライドを損なうものであった」
ことは、「いささか」どころではないかと思います。
現在、集団的自衛権にかんする議論で、掃海部隊の派遣が挙げられていますが、
実際派遣されるようなことがある場合、よもや、このようなことはないだろうと思いたいものです。
この本を手に取った時、
海上自衛隊のことについて書いてあるにも関わらず、
「軍艦旗」
と書いてあることが疑問だったのですが、
帝国海軍時代と同じ旭日旗である自衛艦旗は、軍艦旗であるに違いなく、
海上自衛隊は、海外においては海軍と認識されるのは自然なことであろうと思います。
呼称がどうであれ、海上自衛官の中に、自分たちは帝国海軍の末裔なのだという誇りが受け継がれていること、
それが理屈抜きであることを、毎朝の自衛艦旗掲揚時に垣間見る思いです。
今回あまり触れませんでしたが、
ペルシャ湾で行われた機雷除去の様子は必見です。
「事実は小説より奇なり」
全てが事実であり、脚色が一切行われていない話であることに、驚くばかりです。
そしてこの本は、自衛隊の海外派遣の重要性を認識することができ、
海外派遣における法整備と武装の必要性について認識することができ、
日本の機雷掃海技術の高さを知ることがでる、素晴らしい一冊です。
自衛隊の問題に国内が揺れている今、ぜひ、読んでみられてはいかがでしょうか?