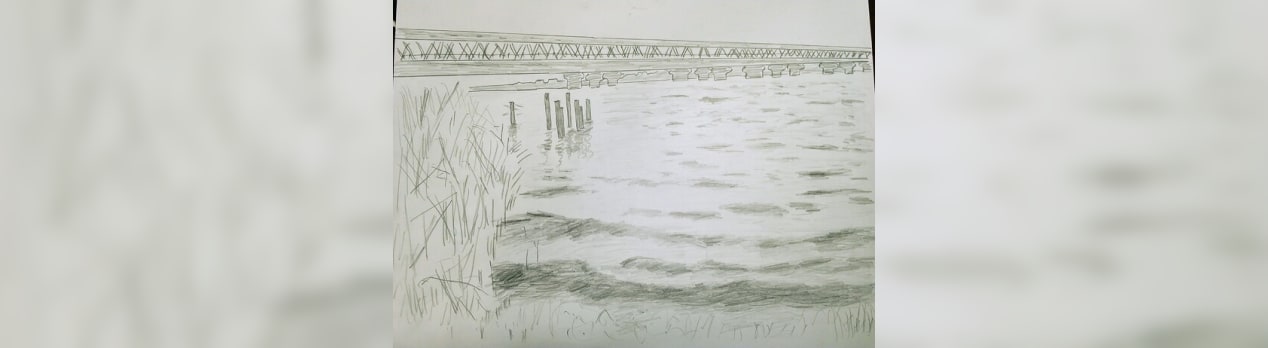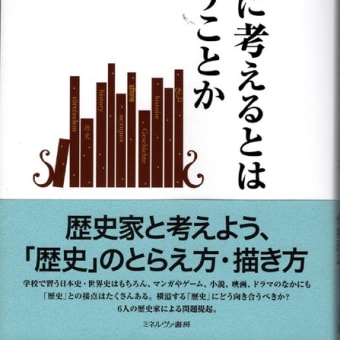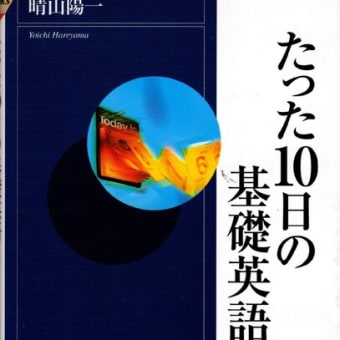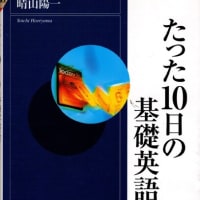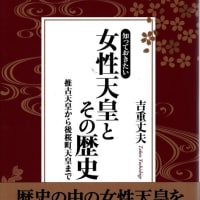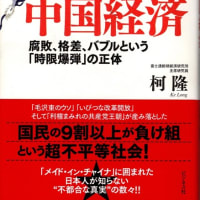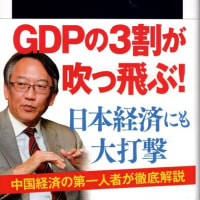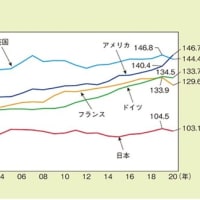一般に日本画は「写生」→「草稿」→「本画」という手順を踏む。その写生の部分を写真に置き換えてはいけないとされる。なぜ「写真を見て絵を描いてはいけない」のか。その意味がようやく分かった。
そもそも絵画とは、対象の再現を目的とするものではなく、その必要もない(上村淳之)。写生は現実の世界、作品は想像の世界である。写生はいわば基礎知識であり、草稿は計算用紙、そして本画は解答である(上村淳之)。
日本画の代表的ジャンルである花鳥画は、自分が抱いている美しい世界があり、それを鳥に託して描こうとするのものである。水や風、岩石などの無機物は魂を持たないとされる。しかし日本では、水の神、風の神など自然信仰が縄文時代以来脈々と受け継がれている。花鳥画は単に美しい景色を写し取ることではなく、山川草木に「いのちの素を吹き込む」ことである。「写生」はこの「いのちの素」を訪ねることである。だから現場に身を置き、まっすぐに見つめ、根気よく向き合うことが必要である。
それを「草稿」の段階で実空間から虚空間へ変換する。このとき写生したものをそのまま本画にしてはならない。それはたとえ膠や岩絵具を使っていたとしても日本画とは言えない。「日本画もどき」の絵である。
日本画を描くには徹底写生が必要である。確かに言われてみれば、一流の画家はみんな徹底写生を行っている。例えば東山魁夷画伯。彼は皇居の壁画や唐招提寺障壁画を描くにあたって、全国の海のスケッチをしている。

平山郁夫画伯もシルクロードを描くために百数十回にわたって現地を訪れている。

人を感動させる絵には描く側の「強い思い」が必要である。そのためには徹底した写生(デッサン)が欠かせないのだ。
理屈はわかるが、うーん、難しい!