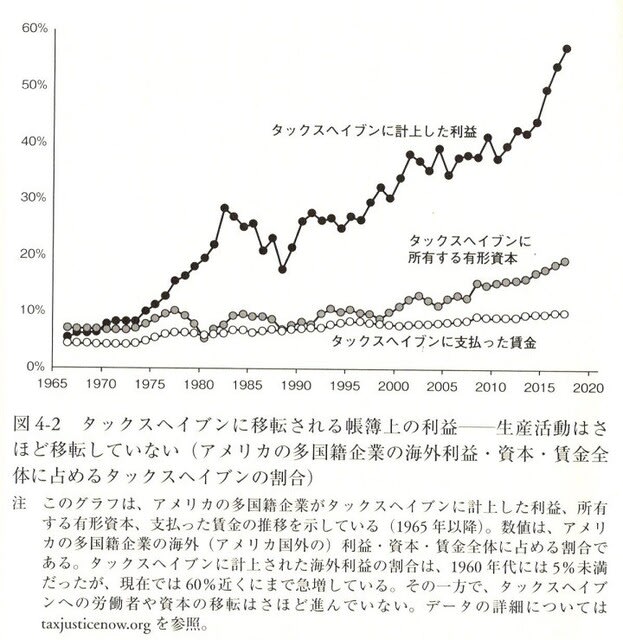コロナ対策のために政府の財政支援の増額を求める声が高まっています。政府の借金は増えるばかりです。今や国債の発行残高は約900兆円、地方政府の借金である地方債の発行残高は約200兆円、国と地方を合わせるとその総額は約1100兆円に達します。この借金を将来どうするのか?
この問題について少し考えてみたいと思います。
1.返済の方法
まず第一に、政府の借金は返す必要があるのかないのか。
答えはもちろん返す必要があります。
では、だれが返すのか?
① 政府が政府紙幣を発行して返済に充てる。
② 国民が「政府にお金を貸している国民」に税金で返す。
③ ハイパーインフレを起こし借金をチャラにする。
①の考え方はまやかしです。
物事は極端に考えると本質が見えてきます。もし、政府が紙幣を発行して返済に充てることが許されるなら、いま税金をゼロにしてすべての歳入を政府の発行する紙幣で賄ってもいいはずです。しかし、世界には税金ゼロの国など存在しません。だから、①の考え方は長い目で見ると間違いです。
②の考え方は一番常識的な考え方です。
いま個人が銀行からお金を借りたとします。貸してくれたのは銀行にお金を預けている国民です。この場合、お金を借りた個人は、お金を貸してくれた個人に銀行を通してお金を返済することになります。
銀行を政府に置き換えると、現在の日本の財政状況になります。国債発行はたとえそれが日本国内で消化されていたとしても、将来世代の負担になります。
では、将来的に国民は1100兆円もの借金を返済できるのか?
もちろん「できません」。民主主義の下では国民は減税には賛成しても増税には反対します。だから政治家は増税を公約に掲げることができないのです。
ではどうするのか?
答えは③のハイパーインフレを起こすことしかありません。財務省も本音のところではそう思っているはずです。もはや日本の借金総額は返済できるレベルをはるかに超えています。借金で首が回らなくなったら最後はハイパーインフレを起こす。これは世界共通の公式みたいなものです。
ハイパーインフレで政府の借金がチャラになるなら、それも「有り」だと思うかもしれません。でも、ハイパーインフレが起きると「銀行にお金を預けていた人」は損をし、逆に「お金を借りていた人」は得をします。すなわち、国民が大損をし、政府が大もうけをします。ハイパーインフレで政府の借金をチャラにするといっても、結局その借金を払わされているのは国民なのです。
もうお分かりですね。増税もハイパーインフレも、国民が負担するという点では同じなのです。これを「インフレ税」と言います。民主的な方法で借金の返済ができないなら、最後はハイパーインフレを起こし「暴力的に」「有無を言わさず」チャラにするしかありません。もうだれにも止められない気がします。民主主義の限界ともいえます。
2.財政破綻はありうるか?
結論から言えば、通貨発行権を持つ政府・日銀は、紙幣をいくらでも印刷できますから、形式的には財政破綻はあり得ません。その代わりハイパーインフレが起きます。
現在のところ財務省の綱渡り的な国債管理政策により、何とか国債の国内消化が実現しています。しかし、政府の借金が限界を超えてくると国債を買う人がいなくなります。そうなると公務員の給料も払えなくなってしまいます。
それでは困るので、政府は財政法第5条で禁止されている「日銀引き受けの国債発行」に踏み切らざるを得なくなります。法改正が行われ、お札がジャンジャン印刷され、ハイパーインフレが発生します。
物価が100倍になれば100円の大根1本が1万円、タクシーの初乗り料金が6万円、40万円の月給が4000万円になり、為替レートは1ドル1万円になります。そうして政府の1000兆円の借金は実質10兆円になり、国民が銀行に預けていた1000万円の預金は10万円に目減りしてしまいます。
そんなことは起こりえないと思われるかもしれませんが、日本では1947年から1949年にかけて日銀引き受けの国債(復金債)が発行され、物価が戦前の240倍になったという事実があります。そして過去の借金をいったんリセットし、その後の経済発展につなげたのです。
確かに形式的には財政破綻は生じません。また、ハイパーインフレが起きたとしても日本がなくなるわけではありません。しかし、そんな事態にならないようにするのが政治というものではないでしょうか。最近は100年先のことを考える政治家が少なくなってきたように思います。もっとも100年先のことを訴えても当選できないから仕方がないのかもしれませんが。
この問題について少し考えてみたいと思います。
1.返済の方法
まず第一に、政府の借金は返す必要があるのかないのか。
答えはもちろん返す必要があります。
では、だれが返すのか?
① 政府が政府紙幣を発行して返済に充てる。
② 国民が「政府にお金を貸している国民」に税金で返す。
③ ハイパーインフレを起こし借金をチャラにする。
①の考え方はまやかしです。
物事は極端に考えると本質が見えてきます。もし、政府が紙幣を発行して返済に充てることが許されるなら、いま税金をゼロにしてすべての歳入を政府の発行する紙幣で賄ってもいいはずです。しかし、世界には税金ゼロの国など存在しません。だから、①の考え方は長い目で見ると間違いです。
②の考え方は一番常識的な考え方です。
いま個人が銀行からお金を借りたとします。貸してくれたのは銀行にお金を預けている国民です。この場合、お金を借りた個人は、お金を貸してくれた個人に銀行を通してお金を返済することになります。
銀行を政府に置き換えると、現在の日本の財政状況になります。国債発行はたとえそれが日本国内で消化されていたとしても、将来世代の負担になります。
では、将来的に国民は1100兆円もの借金を返済できるのか?
もちろん「できません」。民主主義の下では国民は減税には賛成しても増税には反対します。だから政治家は増税を公約に掲げることができないのです。
ではどうするのか?
答えは③のハイパーインフレを起こすことしかありません。財務省も本音のところではそう思っているはずです。もはや日本の借金総額は返済できるレベルをはるかに超えています。借金で首が回らなくなったら最後はハイパーインフレを起こす。これは世界共通の公式みたいなものです。
ハイパーインフレで政府の借金がチャラになるなら、それも「有り」だと思うかもしれません。でも、ハイパーインフレが起きると「銀行にお金を預けていた人」は損をし、逆に「お金を借りていた人」は得をします。すなわち、国民が大損をし、政府が大もうけをします。ハイパーインフレで政府の借金をチャラにするといっても、結局その借金を払わされているのは国民なのです。
もうお分かりですね。増税もハイパーインフレも、国民が負担するという点では同じなのです。これを「インフレ税」と言います。民主的な方法で借金の返済ができないなら、最後はハイパーインフレを起こし「暴力的に」「有無を言わさず」チャラにするしかありません。もうだれにも止められない気がします。民主主義の限界ともいえます。
2.財政破綻はありうるか?
結論から言えば、通貨発行権を持つ政府・日銀は、紙幣をいくらでも印刷できますから、形式的には財政破綻はあり得ません。その代わりハイパーインフレが起きます。
現在のところ財務省の綱渡り的な国債管理政策により、何とか国債の国内消化が実現しています。しかし、政府の借金が限界を超えてくると国債を買う人がいなくなります。そうなると公務員の給料も払えなくなってしまいます。
それでは困るので、政府は財政法第5条で禁止されている「日銀引き受けの国債発行」に踏み切らざるを得なくなります。法改正が行われ、お札がジャンジャン印刷され、ハイパーインフレが発生します。
物価が100倍になれば100円の大根1本が1万円、タクシーの初乗り料金が6万円、40万円の月給が4000万円になり、為替レートは1ドル1万円になります。そうして政府の1000兆円の借金は実質10兆円になり、国民が銀行に預けていた1000万円の預金は10万円に目減りしてしまいます。
そんなことは起こりえないと思われるかもしれませんが、日本では1947年から1949年にかけて日銀引き受けの国債(復金債)が発行され、物価が戦前の240倍になったという事実があります。そして過去の借金をいったんリセットし、その後の経済発展につなげたのです。
確かに形式的には財政破綻は生じません。また、ハイパーインフレが起きたとしても日本がなくなるわけではありません。しかし、そんな事態にならないようにするのが政治というものではないでしょうか。最近は100年先のことを考える政治家が少なくなってきたように思います。もっとも100年先のことを訴えても当選できないから仕方がないのかもしれませんが。
(追記 この文章はある議員さんに向けて書いたメッセージです)