芸術の秋
絵はやっぱり日本画が好きだ。中でも東山魁夷はとりわけ好きだ。絵を見ていると心があらわれる。「白い朝」「緑響く」「静唱」「白夜光」なども展示されており、画集では伝わらない圧倒的な迫力を身近に感じることができた。
もちろん、唐招提寺の襖絵もあった。
以前、京都の高島屋で唐招提寺襖絵を見たときは、ものすごい人波で、「押さないでください」「止まらないでください」という中での駆け足鑑賞だった。しかし、今回は平日だったこともあり、広い展示室でゆっくり見ることができた。いい1日だった。






木曜日の夜「グッド・ドクター」というテレビドラマをやっている。自閉症で且つサヴァン症候群の主人公が小児科医として活躍するドラマである。
発達障害と呼ばれるものには自閉症のほか、ADHD(注意欠陥多動性障害)、学習障害、読字障害(例:トム・クルーズ)などがある。長い間教員をしてきたが、これまで自閉症の生徒と直接接したことがなかった。だから、自閉症というものがどういうものなのかいまひとつピンとこなかった。そこで、このテレビドラマをきっかけにもっとよく知りたいと思うようになり、数冊の本を買ったという次第である。
自閉症は、自分以外の他者や外の世界をすべて排除しているかのような患者の状態をいう。自閉症が論文に最初に現れたのは1943年にさかのぼる。具体的な症状としては
① 社会性の異常(コミュニケーションの障害)
(例)・人と目を合わさない
・まるで耳が聞こえないように名前を呼んでも返事をしない
・他人の立場でものを考えることができない(=相手の心を読むことができない)
・相手の表情や声色から感情を読み取ることができない
・共感能力の欠如
・話題の流れにあわない発言をしてしまう
・オウム返しの返事をする
・言葉の遅れ
② 常同行動をする
(例)同じおもちゃでずっと遊び続ける(趣味の限定)
また、自閉症患者は感覚が過敏であったり、反対に鈍感であったりもする。たとえば、音に敏感だと、普通の人が無意識に遮断している小さな音まですべて耳に届いてしまうため、ちょっとした音にも耳を手で覆ってパニック状態になったり、あるいは教室の外の雑音が先生の声と同じレベルで聞こえてしまい、人の声が聞き取れなかったりする。人の声が聞き取りにくいと、自閉症特有の「言葉の遅れ」にもつながる。
しかし、こうした感覚異常は、ある分野で驚異的な天才性を発揮する場合があり、サヴァン症候群と呼ばれる。
(例)
・一度本を読んだだけですべての内容が頭の中に入る。たとえば映画「レインマン」のモデルとなったキム・ピークという人は、読んだ9000冊の本の内容をすべて記憶していた。「グッド・ドクター」に出てくる主人公もそういう設定になっている。
・一度聞いた音楽はすべて正確に再現し、暗譜できる。
・一度見た風景を瞬時にスキャンして、1年後に絵に描くことができる。(山下清画伯)。
・風景を3Dとして見ることができる。(スピルバーグ)
・過去および未来のカレンダーの曜日を言い当てることができる。
・並外れた暗算力を持つ
・数字が風景のように見える。
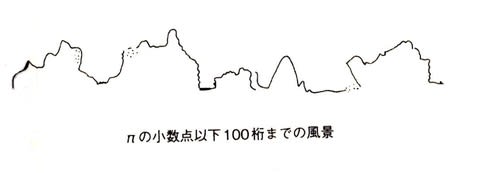
最近有名なアスペルガー症候群も、自閉症の一つである。ただし、アスペルガー症候群は、他者とのコミュニケーションに障害があったりはするが、知能は高い。それで、アスペルガー症候群の人は「高機能自閉症」と呼ばれたりもする。自閉症は重い症状から軽い症状まで幅が広いことから「自閉症スペクトラム障害」(連続体)と呼ばれ、一番程度の軽い自閉症と健常者との間には明確な境界線はないとされる。
だから、わずかな自閉傾向を持つ人は身近にも存在する。とくに偏差値の高い理系の大学には、比較的多くの自閉傾向の学生がみられるという。
古くはニュートン、アインシュタイン、モーツァルト、ベートーベン、『不思議の国のアリス』を書いたルイス・キャロルなどのほか、現代ではビル・ゲイツなどもそうした傾向があるといわれる。
もし、江戸時代だったら読字障害や学習障害などはほとんど問題にならなかった。みんな字が読めなかったからである。また、コミュニケーション能力に障害があったとしても、人とのかかわりが少ない職人として生きる道がたくさんあった。ところが、学校教育が進み、人とかかわる3次産業が発展した結果「普通であること」が求められるようになり、「普通」からはみ出してしまった人たちにとっては生きにくい時代になってしまった。
以前、ピアノで演奏された曲を聞いた直後に全く同じように弾くことができ、しかもこれまで聞いた10万曲を全部暗譜しているという人をテレビで見たことがある。「すごい、天才だ」と言ったら、娘が「お父さん、あれも障害だよ」と言われてはっとしたことを思い出した。
一度聞いたり見たりしたことをすぐ記憶できるというのは、うらやましいようにも思う。しかし、いやなこともずっと記憶から消すことができないのだから、これほど不幸なことはないともいえる。忘れることができるというのは、神が人間に与えた素晴らしい能力の一つなのかもしれない。