2011年1月9日:日曜日。
大相撲初場所が東京・両国国技館で開催される。
2010年は大相撲にとって激震の一年として記憶された。
横綱:朝青龍関の度重なる素行(不祥事)は自身を引退に追い込み、
暴力団が関与する賭博行為に現役力士・親方など多人数が手を染め、
TV放送の中止、スポンサー企業の協力辞退、観客動員の伸び悩みなど、
かつてない存亡の危機に陥った。
疑惑と不信が渦巻く存亡の中で一人敢然と立ち向かったのが、
横綱:白鵬であることに誰も疑いを持たない。
日本人不在と言われてしまいそうな上位陣にあってモンゴル勢力の台頭は、
オールド・ファンにとって嘆きたい気持ちでいっぱいであろう。
ハワイ力士に続く脅威となったモンゴル力士の代表格が元横綱:朝青龍だった。
朝青龍の相撲は憎憎しいまでに強く土俵上でのパフォーマンスは豪快で面白かった。
ただし、
横綱の品位を汚していると言われ続けても“ふてぶてしさ”は変わらず、
激しい世間の批判にさらされ必要以上のパッシングを受けたことも事実だ。
~現役時代の朝青龍が日本人であったとしたら同じパッシングを受けたのだろうか?
では批判した人達が求める横綱の品位(品格)とは何であり、
横綱に求められる強さとは何であのるか?
その答えを求め本書『白鵬翔著・相撲よ!』を手に取った。
そして、
日本人以上に日本人の心を持つとされる大横綱:白鵬翔の心技体に感服。
少しだけ著書の中身を紹介し白鵬関の真実を考察する事にした。
【心を鍛える:吾未木鶏為得】
双葉山関が得意とした立ち合い、
“後の先(このせん)”について
双葉山著『相撲求道緑』に記された
幼少の頃の目の怪我でほぼ視力を失い、
“目に頼らず身体で相手の動きを感じ取り隙を見抜く修練”
を重ねて得た立ち合いの技術ではないかと白鵬関の分析。
~後の先の立会いは横綱相撲の代名詞として現在にも語り継がれる。
双葉山関は勝ちに行く相撲をとらなかった。
私(白鵬)の経験からも心が動くと負けるはずのない相手に負けることがある。
苦労しなくても良い相手だから簡単に勝ちたい、早く勝ちたいと思うと、
“勝ちに行く相撲”となって足元をすくわれる事がある
つまり勝つだけの相撲をとると相撲が荒れるのだ。
双葉山関の言葉として、
「自分と相手との千差万別の体勢に応じて“かねて身に付けたもの(=稽古)”が、
いつでも出てこなければならず“そのためには無意識の内に技が出る”必要がある。」
つまり土俵上での理想的な取り組みとは“無心”になる事であって、
作戦を考えるのではなく“相撲に流れに応じて身体が自然に反応”できれば良し。
相撲は気持ちや技といった部分にこだわりがちであるが部分にこだわると相撲はとれない。
それよりも無意識(勝つという邪念を捨てる)に相撲をとることが大事であり、
私(白鵬)は座禅を組む事によって瞑想(無の境地)の感触を掴める様になってきた。
双葉山関の69連勝が止まった時、
親交のある思想家:安岡正篤氏に宛てた電報の言葉、
“いまだ木鶏たりえず(吾未木鶏為得)”
は最も印象深い言葉だ。
中国の古典にある闘鶏使いの名人が、
王から預かった鶏の調教を依頼され、
訓練を終え王に返す時の言葉が
「如何なる敵にも無心です。
傍で他の鶏が鳴いても平然とし、
恰も木で作った鶏のように動じず、
徳は充実しまさに天下無敵です。」
この無心こそが理想であり、
双葉山関の“泰然自若”に通ずる。
双葉山関の名言、
「よく稽古する者に怪我はなく、
稽古は本場所の如く、
本場所は稽古の如く」
昨年の暮れにNHKで放送された、
『NHKスペシャル:横綱 白鵬 ~最強への挑戦~』
でも核となっていた、
“後の先”と“われ、いまだ木鶏たりえず”。
横綱:白鵬関が双葉山関の不滅の記録に挑んだ2010年11月。
稀勢の里関の闘志の前に吾を忘れて勝ちを焦ったとの後日談。
一発張られたことでカッとなったとも語る横綱:白鵬の空回り。
TVでは前の取り組みでの熱戦に心が動いた事実もレポート。
白鵬関の“不動心”とは花道を入場する前の所作から既にはじまっている。
技・体ともに充実している白鵬関の心のわずかな揺れは、
所作(型=一連の動作)に狂いを生じさせ、
白鵬関にとって思いもよらぬ負けを経験。
稀勢の里関に敗れた白鵬関の口からでた、
“これが、負けか”
私は白鵬関が敗れた翌日の夜に文字にした、
→ http://blog.goo.ne.jp/mimifuku_act08/d/20101115
70連勝を阻まれた双葉山は知人に電報で、
「ワレ イマダモツケイ(木鶏)タリエズ」と告げた。
“我、今だ木鶏(もっけい)たりえず。”
無我の境地への挑戦。
意味を中国の故事に求める記事を目にしたが、
私は禅に通じる無我に意味を求めたい。
欲を捨て無心で稽古した動作を繰り返す。
自身の型を極めれば勝ちは自ずとやってくる。
迷いは感情の中から生じるものである。
勝負の中の一瞬の迷い。
“我、今だ木鶏たりえず”
常人には得がたい心境ながら、
肝に銘じたい言葉である。
に概ね誤りはなかったように思う。
勿論この心境に至るには誰にも負けない強さを有した者にこそ有効で、
所作(=稽古により体得した型)を極めていない者には無用である。
弱いものが敵わない者に挑戦するときは策が必要な事は言うまでもないが、
頂点を極めた者にとって“欲”が敵になることは、
好敵手:朝青龍や大関・把瑠都関の相撲を見れば理解しやすい。
“つまり勝つだけの相撲をとると相撲が荒れるのだ”
の言葉の意味は美しく勝つことや思いやりの心など、
伝統的な日本文化の真髄を極める事にも通ずる。
その意味を次の項目【横綱の品格】で確かめて欲しい。
【横綱の品格】
大相撲は“神事”である。
大相撲に於ける神とは八百万(やおよろず)の神であり、
土俵のしつらえや力士の行う所作の一つ一つには神との関わりがある。
例を挙げれば俵(たわら)で丸く囲う土俵は“神の下りる場所”であり、
土俵の上に吊るされる4色の房は春夏秋冬や四神相応(しじんそうおう)を表わす。
大相撲場所前日には相撲の神様を土俵にお招きするための土俵祭りを行う。
また、
千秋楽の後には土俵の上で新弟子が行司を胴上げするしきたりがあり、
15日間見守ってくださった神様に感謝する“神送りの儀”が行われる。
15日間の土俵は“神の庭”とされ、
力士達の所作(しょさ)ひとつにも深い意味がある。
四股(しこ)は土の中にいる魔物を踏みつぶすとされ、
水をつけるのは身体を清める意味を持ち、
塩をまくのは土俵に穢(けが)れをいれないためとされ、
蹲踞(そんきょ)の姿勢は相手を敬う意味を持つ。
立合いで両手をつけることは悪霊を追い払う所作であり、
懸賞金を受け取る手刀は勝負の三神に感謝を示す所作である。
横綱だけに許された土俵入りの意味は、
拍手(かしわで)を打ち四股を踏むことで、
神を鎮め地面の下の悪霊を封じ込め、
五穀豊穣(ごこくほうじょう)を願う。
横綱とは、
許された力士だけが“腰に締める綱”の名称であるが、
横綱とは御幣(ごへい)の下がった注連縄(しめなわ)であり、
それは、
神社の鳥居・本殿や各家の神棚などに飾られる神聖な綱であって、
横綱を締める者は相撲界に於いて現人神(あらひとがみ)とされている。
こうした立場の力士(横綱)に品格が求められる事は言うまでもない。
知らない事が次々と分かってきた。
古来相撲の最高位は大関であり、
横綱は名誉職であったと聞いたことがあるが、
横綱の地位として象徴的な、
“降格を許されない立場”は、
現人神としての証明なのか?
相撲とは白鵬関が述べた言葉としての、
“神事と芸能と競技が渾然一体となった伝統文化”
であるため“作法”を欠いては成立せず、
守り継がれた作法が一部の親方達の指導方針で瓦解し、
商業的側面や興行的側面が歓迎され、
大衆に迎合したプロ格闘技としての傾向が大衆認知された事は、
伝達する側のメディアにも問題があったのかも知れないし、
学ぼうとしなかった私達に問題があることも事実だろう。
日本人が知らない日本の伝統文化を学ぼうと、
懸命な白鵬関の姿勢に頭が下がるばかりだ。
【武士道に通じる相撲道】
相撲には“美しさ”が求められる。
それは勝者が敗者をいたわる姿のことだ。
相撲道は武士道の流れをくんでおり、
武士道には、
“敗者の痛みを勝者が思いやる心構え”
が説かれている。
そのことを理解していれば、
土俵の上でガッツ・ポーズをすることなどできるはずがない。
土俵のルールにも相撲道を表現していると考えられる、
「かばい手」「生き体」「死に体」等は土俵の上で、
相手に怪我をさせないための取り決めであり、
日本人独特(固有)の思いやりの表れである。
双葉山関と交流のあった、
思想家:安岡正篤氏(前出)の力士規七則には、
「人にして礼節なくは禽獣にひとし。
力士は古来礼節を持って聞ゆ。
謹んでその道の美徳を失うことなかれ。」
と記されている。
横綱である私(白鵬)は、
そうしたことも積極的に伝えていかねばと思っている。
横綱:白鵬関の著作の節々に表現される、
伝統的な日本文化の真髄。
“禅、稽古、神事、所作、作法、武士道、礼節”
63連勝の後に1敗をはさんで13連勝。
勝負に“もしも”はタブーに違いないが、
もしも…。
歴史上最も偉大な力士を、
私達は目の前にしているのかも知れない。
勝つだけが強さではなく、
勝つ事は結果に過ぎない。
“礼節をわきまえ思いやりを持ち美しくなければ相撲ではない”
そんな事を思いながら相撲をとる力士がどれだけいるのだろう。
そんな事を思いながら相撲を観戦するファンがどれだけいるのだろう。
~心情としては嬉しさの表現としてのガッツポーズを否定しきれないが。
本書で紹介されている微笑ましい話として、
会話に長けた白鵬関も読むのは苦手か、
多くの過去の相撲の資料や著作物を、
奥さんに読んで聞かせてもらうのだそうだ。
また、
白鵬関は他人の言葉に耳を傾ける才能にも優れており、
親方や両親は勿論、
モンゴルの親戚や先輩力士や後援会の人達の言葉も、
“教えてもらった”と逐一著述している。
さらに、
NHKスペシャルで映し出された映像で知る熱心な相撲の研究。
新時代の横綱はあらゆる手段を使って相撲を学び相撲道を学ぶ。
学ぶ心=向上心。
“勝って尚、手綱をゆるめず”
“勝って尚、天狗にならず”
横綱の品格とは何かと問われれば、
私は迷わず、
この本を読まれてみれば!
とお薦めする。
 |
相撲よ! 白鵬 翔 角川書店(角川グループパブリッシング) このアイテムの詳細を見る |
~下記NHKホームページより記事転載。
NHKスペシャル/横綱 白鵬 ~“最強”への挑戦~
九州場所で双葉山の連勝記録69の更新を目指した横綱白鵬。
惜しくも連勝は63で止まったが、
大鵬、千代の富士を上回る歴代二位の記録は燦然と輝いている。
白鵬はなぜ強いのか?
NHKは大相撲の歴史の中で初めて科学の眼で横綱の秘密に迫った。
超ハイスピードカメラなど最新の撮影技術によって明らかになったのは、
相手の攻撃を受け止める不思議な吸収力のメカニズムや、
横綱相撲の神髄と言われる「後の先」の奥義だった。
さらに、
独特の質感を持つ単焦点レンズのカメラで白鵬の日常に密着。
高まるプレッシャーの中、自らの心の弱さと向き合う25歳の横綱の内面に迫った。
その映像には、ンタル面をサポートする専門家のアドバイスを受けながら、
「平常心」を維持しようとする白鵬の知られざる闘いが記録されている。
相次ぐ不祥事に揺れた大相撲を一人横綱として支え続けた白鵬。
連勝が途切れたショックを乗り越え再び記録の更新にむけて歩み始めた、
白鵬の心技体に迫る。










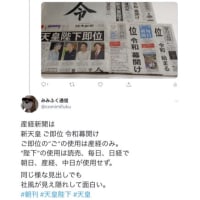

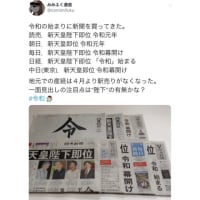

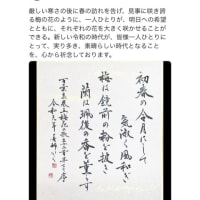
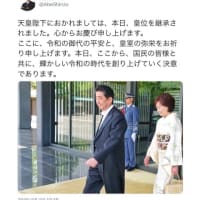



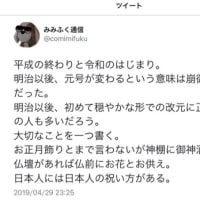





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます