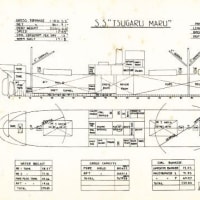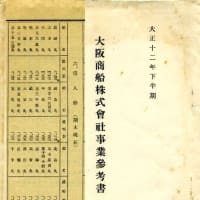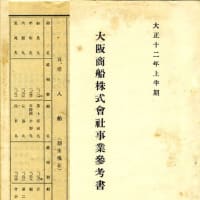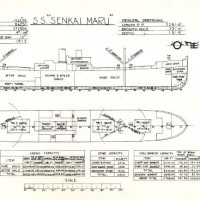「萬幸丸」という蒸気船を追いかけていた。当初は、工部省兵庫工作分局において建造された船らしい‥としか
理解していなかった。この船名は船名録から見い出せない。
造船工長を記す船名録はM26版からであり、M20-25版までは製造地名のみとなっている。汽船表に記録された
情報も貴重であるが、全船を網羅していない。
明治初期に建造された汽船には、製造者不明船が多い。特に創業期の大坂商船会社在籍船は、造船工長の記載
されるM26船名録(M25.12.31)までに廃船となった船も多く、謎に満ちている。
工部省沿革史リストをもとに、兵庫造船局建造船26隻組(蒸気船23隻、帆船3隻)のその後を検証してみた。覚え
として作成した表を抜書きしたため、見づらいものとなっている。
No 船名 長 登簿噸 製造年月 M20船名録 長 登簿噸 製造年月 *=M15 M18汽船表 製造年月 製造地名 船主 M26船名録 造船工長
01 萬幸丸 87.0 104 M11.05 138 / HCBK 太安丸* M10.09 兵庫川崎新田 大坂商船会社 -
02 平運丸 102.2 126 M11.09 188 / HBMF 平運丸 108 70 M11.01 M11.01 兵庫工作分局 大坂商船会社 -
03 福傳丸 142.0 291 M11.11 165 / HCDS 静凌丸* M11.11 兵庫工作分局 大坂商船会社 -
17 徳島丸 90.0 126 M11.11 <記載無し> <記載無し> -
04 凌波丸 80.0 109 M11.12 41 / HBQN 凌波丸 85 84 M11.12 <記載無し> 鈴木吉蔵
05 龍丸 90.0 127 M12.04 190 / HCGD 龍丸 96 91 M12.05 M12.05 兵庫新田 大坂商船会社 兵庫工作分局
18 巳卯丸 98.0 138 M12.12 83 / HBTC 巳卯丸 104 88 M12.11 M12.11 兵庫工作分局 大坂商船会社 -
06 平穏丸 108.0 214 M12.12 216 / HCJK 平穏丸 116 123 M12.12 M12.12 神戸川崎町 大坂商船会社 兵庫工作分局
07 鵬勢丸 99.0 148 M13.02 93 / HBTG 鵬勢丸 104 94 M12.12 M12.12 兵庫工作分局 大坂商船会社 -
09 筑紫丸 150.0 415 M13.02 222 / HCJQ 筑紫丸 155 208 M13.03 M13.03 兵庫工作分局 大坂商船会社 -
10 廣島丸 96.0 136 M13.06 700 / HFBD 第二広島丸 100 88 M13.05 M13.05 兵庫 大坂商船会社 兵庫工作分局
08 謙受丸 131.0 366 M13.04 271 / HCMK 謙受丸 129 210 M13.06 M13.06 兵庫工作分局 鴻益社 -
11 明運丸 99.8 141 M13.12 426 / HDBK 明運丸* <記載無し> -
13 高田丸 99.8 141 M14.01 590 / HDNT 高田丸 97 84 M14.02 M14.02 兵庫工作分局 越佐海運会社 -
12 大龍丸 135.0 274 M14.04 544 / HDKS 大龍丸 138 187 M14.03 M14.03 兵庫工作分局 大坂商船会社 ゼームス、ハンナ
14 北洋丸 124.0 211 M14.08 702 / HFBJ 第一北洋丸 110 98 M14.08 M14.08 兵庫工作分局 北洋会社 -
15 游龍丸 90.0 74 M15.05 不登簿 游龍丸 86 56 M15.03 M15.03 大津 太湖汽船会社 不登簿○
16 三光丸 154.0 288 M15.05 695 / HDWR 三光丸 158 207 M15.04 M15.04 兵庫工作分局 大坂商船会社 ゼームス、ハンナ
19 第一小野田丸38.7 8.01 M16.09 不登簿 第一小野田丸 39 3 M16.06 M16.06 兵庫造船局 セメント製造会社 不登簿○
20 志摩丸 153.5 373.3 M16.06 805 / HFMC 志摩丸 141 237 M16.09 M16.09 兵庫工作分局 共同運輸会社 -
21 第二小野田丸46.9 10.87 M17.04 不登簿 第二小野田丸 49 7 M16.12 M17.03 兵庫造船局 セメント製造会社 不登簿○
22 金龍丸 168.0 494.81 M17.05 836 / HFPD 金龍丸 172 329 M17.04 M17.04 兵庫川崎 大坂商船会社 川崎造船所・ゼームス、ハンナ
23 第二徳山丸 96.2 102 M18.05 890 / HFSR 第二徳山丸 98 77 M18.05 <記載無し> 佐山芳太郎
① (帆)太平丸 119.0 335 M11.08 434 / HDBR 太平丸 122 279 M11.08 - -
② (帆)太陽丸 127.5 446 M11.12 435 / HDBS 太陽丸 135 368 M11.12 - 鈴木吉造(ママ)
③ (帆)新田丸 127.5 446 M12.12 <記載無し>神路丸か? - -
一列目は工部省沿革史リストに記された長さ、登簿噸、製造年月を記した。Noは元々の掲載順序とし、M20船名録
の製造年月順に行を並べ替えた。
二列目はM20船名録から長さと登簿噸数、製造年月を記した。M20船名録に掲載されない船でM15船名録に掲載さ
れる船に「*」を付した。
三列目はM18汽船表から製造地名と船主を記した。
四列目はM26船名録から造船工長を記した。
意外にも、改名された船は少ない。「廣島丸」「北洋丸」に、当初から「第二」「第一」が付されていたか判らない。
長さの数値は微妙に異なり、登簿噸数は別船と思える程の違いを見せる。同一地の建造にかかわらず、製造地名
の表記の違いも興味深い。
1868(慶応4).01兵庫開港。
1869(M02)バルカン鉄工所設立(東川崎)。金沢藩兵庫製鉄所設立。
1870(M03).12工部省設置(製鉄等を民部省より移管)。
1872(M05).02工部省は兵庫製鉄所を買収。製作寮兵庫製作所と改称。
1873(M06).04工部省はバルカン鉄工所を買収。兵庫製作所と統合。
1875(M08).04兵庫製作所修理船架完成。
1877(M10).01工部省製作寮は工作局、兵庫製作所を兵庫工作分局と改称。
〃 .07一等技手佐畑信之着任。
1881(M14).03川崎正蔵は川崎兵庫造船所開設(兵庫東出町)。
1883(M16).09工部省は工作局を廃止。兵庫工作分局を兵庫造船局と改称。
1885(M18).01兵庫造船局に輸入の鉄船製造設備竣工。
〃 .05兵庫造船局は船台3基建設に着工。
〃 .09兵庫造船局は引揚重量2000トンの大船架竣工。
〃 .12工部省廃止に伴い農商務省工務局に移管、兵庫造船所と改称。
1886(M19).05兵庫造船所を川崎正蔵に貸与。川崎兵庫造船所と合併、川崎造船所と改称。
〃 .10川崎造船所にて大坂商船「吉野川丸」竣工。
1887(M20).07兵庫造船所を川崎正蔵に払下げ。
兵庫造船局最後の建造船は既出の「第二徳山丸」。共栄社の発注により建造され、帝国商船、吉田義方(小田原)
を経て東京湾汽船の所有船となった。


「第二徳山丸」の画像は、小田原海岸停泊中に加え、新たに航行中も見つかった。恐らく、同日の記録と思わ
れる。こちらにキャプションは無く、少々ピンは甘い。船名は停泊中画像より取り込んだ。
以降、建造船26隻のうち蒸気船23隻に限って記したい。
M20船名録に見あたらない船名は「萬幸丸」「福傳丸」「徳島丸」「明運丸」の4隻。
「福傳丸」は汽船表から「静凌丸」へ改名されたと判る。
「徳島丸」は全く追いかけられない。この船については項を改めて記したい。
「明運丸」はM18船名録から抹消されている。明治期の木造汽船は、損傷程度にもよろうが、沈没しても浮揚修復
されている。「明運丸」はどうなったのか。
「萬幸丸」の後身を「太安丸」とするには、疑問は二点ある。
①工部省リストと船名録は、製造年月が異なる。
②工部省リストと徳島県統計表は、登簿噸数が異なる。
廃藩置県以来、今の徳島県の地域は複雑な経緯を経ている。徳島県統計表は、幸いにもM13-M14二カ年間に船名
を記載している。
【M13統計表】
船名 噸数 所有者 定繋港 購入・新造年月
鵬翔丸 488 井上三千太 小松島 12.03.28購入
太安丸 20 撫養会社 撫養 13.10購入
末廣丸 56.22 船場会社 津田 13.11新造
巳卯丸 84.16 船場会社 津田 12.11新造
鵬勢丸 57.3 船場会社 津田 12.12新造
【M14統計表】
船名 噸数 馬力 造船年月 所有者 定繋港
鵬勢丸 57.3 16 13.01建造 船場会社 津田
末廣丸 30 46 13.10建造 船場会社 津田
巳卯丸 84.16 16 12.01建造 船場会社 津田
長久丸 84.08 33.8 14.10建造 船場会社 津田
太陽丸 78 25 14.07建造 太陽会社 古川
朝陽丸 72 25 14.07建造 太陽会社 古川
太安丸 20 15 10.09建造 撫養会社 撫養
撫養丸 19 12 14.08建造 撫養会社 撫養
常磐丸 1 3 14.04建造 安川長平 撫養
ここから「太安丸」について読み取れるのは次のとおり。
撫養会社「太安丸」(20噸・12馬力)は撫養港を定繋港とし、M10.09に建造された船を、同社はM13.10に購入
した――。
記載事項は異なるものの、工部省リスト、船名録及び汽船表をのデータを並べると次のとおり。
工部省 萬幸丸 87尺 104噸 20馬力 M11.05
M14版 太安丸 138 20噸 15馬力 撫養会社
M15版 太安丸 138 / HCBK 20噸 15馬力 撫養会社
M18版 太安丸 138 / HCBK 63.91噸 20馬力 大坂商船会社
汽船表 太安丸 94尺 62.78噸 20馬力 M10.09兵庫川崎新田 大坂商船会社
M20版 太安丸 138 / HCBK 94尺 63噸 20馬力 M10.09摂津国兵庫 大坂商船会社
徳島県統計表やM14-15船名録に記された登簿噸数20噸は錯誤だったのか。何時の時点か20馬力の「20」の数
値が、登簿噸数に取り違えられたのではあるまいか。工部省リストは登簿噸数104噸。M18船名録は63.91噸になっ
ている。仮に、船舶原簿に登簿噸数20噸と記されていたなら、それは正しいと云えるのか? 建造後3年目の誤
記載(?)は真実に思えてくる。登簿噸数の異なるM15船名録とM18船名録の「太安丸」を結びつけるのは、船舶番
号と信号符字。
明治大正期の船舶を追いかける際、トン数や長(Lr)は重要な手掛かりとなるが、尺(曲尺)と呎(feet)の混同や、用
語定義の誤認は避けたい。
船名録に「川崎造船所」とある「金龍丸」は、兵庫造船所の川崎正蔵への貸与が1886(M19).05であることから、
船名録若しくは船舶原簿の誤記と思われる。「ゼームス、ハンナ」と記される造船工長は1名ではなく、お雇い外国人
の造船師「ハンナ」(英)と機械師「ゼームス、ラング」(英)であり、この2名は「13.05傭入、17.06解傭」と、同一期
間の在籍となっている。船名録の記載は2名の名を重ねてしまっていると見られる。船名録にありがちな記載の
省略である。
「萬幸丸」の製造年月の錯誤は工部省リストにあると見られる。このことを裏付ける史料を挙げておきたい。



『萬幸丸史料』には、共立定約証、市中御賀帳、領収書等を含んでいる。支払は一括ではなく、機器や船体な
ど、出来高のようだ。領収書には工部省の技手佐畑信之の名がある。工部省沿革史によると営業したらしい。
萬幸丸の建造は、海運が活況を呈した南西戦争の時期にあたる。市中御賀帳には「銘酒」「窓幕」「将棋盤」等
が見え、船用備品となったことを考えると、非常に興味深い。

船場会社の活動した明治10年代は、近代海運史における神話時代のような感覚を持っていた。この史料により、
歴史の延長線上に姿を現してくれた感がある。
史料には船場会社の社長辞令も含まれる。社長に就任した湊喜八は、斎津村の初代村長となり、人望厚い人物
と記録される湊多平の関係者と思われる。湊多平は、共立定約証第壱条に氏名のある湊太平と同一人か。湊家
は、津田浦において代々回漕業を営んできた。
萬幸丸の建造時期や共立契約書の存在などから、津田浦の有力者の共立により1877(M10)蒸気船「萬幸丸」を建
造し、「船場会社」は翌年に組織されたと見られる。西南戦争の前後、各地に勃興した海運会社の成立過程を知
る上において興味深い。
昨年暮れ、大阪のT氏より、ご自身の栽培された香り高い種無し柚子が届いた。勿体なくて、冬至のお風呂に使
うのは数個に止め、凍結させて摺り下ろし、薬味にした。徳島繁栄組汽船部の宣伝看板を探しに出掛けた際、神
社の前で困り果てていたボクに、声をかけて下さったのがT氏だった。参拝した神社のお引き合わせか、T氏に巡
り会ったことにより、元教師の老婦人から看板の位置をご教示いただき、念願の対面を果たした。T氏は、最初に
大阪へ出た時は船で渡ったが、今は自家用車で大阪のご自宅と徳島の農園を行き来しているという。ご自身の生
活と、重ね合わせて語って下さった船や航路への思いは、喜びと共に胸に染みた。
今回は「萬幸丸」と「太安丸」の関係に止めたい。この『萬幸丸史料』は、徳島県にて保存活用されるべき郷土
史料と考えている。
理解していなかった。この船名は船名録から見い出せない。
造船工長を記す船名録はM26版からであり、M20-25版までは製造地名のみとなっている。汽船表に記録された
情報も貴重であるが、全船を網羅していない。
明治初期に建造された汽船には、製造者不明船が多い。特に創業期の大坂商船会社在籍船は、造船工長の記載
されるM26船名録(M25.12.31)までに廃船となった船も多く、謎に満ちている。
工部省沿革史リストをもとに、兵庫造船局建造船26隻組(蒸気船23隻、帆船3隻)のその後を検証してみた。覚え
として作成した表を抜書きしたため、見づらいものとなっている。
No 船名 長 登簿噸 製造年月 M20船名録 長 登簿噸 製造年月 *=M15 M18汽船表 製造年月 製造地名 船主 M26船名録 造船工長
01 萬幸丸 87.0 104 M11.05 138 / HCBK 太安丸* M10.09 兵庫川崎新田 大坂商船会社 -
02 平運丸 102.2 126 M11.09 188 / HBMF 平運丸 108 70 M11.01 M11.01 兵庫工作分局 大坂商船会社 -
03 福傳丸 142.0 291 M11.11 165 / HCDS 静凌丸* M11.11 兵庫工作分局 大坂商船会社 -
17 徳島丸 90.0 126 M11.11 <記載無し> <記載無し> -
04 凌波丸 80.0 109 M11.12 41 / HBQN 凌波丸 85 84 M11.12 <記載無し> 鈴木吉蔵
05 龍丸 90.0 127 M12.04 190 / HCGD 龍丸 96 91 M12.05 M12.05 兵庫新田 大坂商船会社 兵庫工作分局
18 巳卯丸 98.0 138 M12.12 83 / HBTC 巳卯丸 104 88 M12.11 M12.11 兵庫工作分局 大坂商船会社 -
06 平穏丸 108.0 214 M12.12 216 / HCJK 平穏丸 116 123 M12.12 M12.12 神戸川崎町 大坂商船会社 兵庫工作分局
07 鵬勢丸 99.0 148 M13.02 93 / HBTG 鵬勢丸 104 94 M12.12 M12.12 兵庫工作分局 大坂商船会社 -
09 筑紫丸 150.0 415 M13.02 222 / HCJQ 筑紫丸 155 208 M13.03 M13.03 兵庫工作分局 大坂商船会社 -
10 廣島丸 96.0 136 M13.06 700 / HFBD 第二広島丸 100 88 M13.05 M13.05 兵庫 大坂商船会社 兵庫工作分局
08 謙受丸 131.0 366 M13.04 271 / HCMK 謙受丸 129 210 M13.06 M13.06 兵庫工作分局 鴻益社 -
11 明運丸 99.8 141 M13.12 426 / HDBK 明運丸* <記載無し> -
13 高田丸 99.8 141 M14.01 590 / HDNT 高田丸 97 84 M14.02 M14.02 兵庫工作分局 越佐海運会社 -
12 大龍丸 135.0 274 M14.04 544 / HDKS 大龍丸 138 187 M14.03 M14.03 兵庫工作分局 大坂商船会社 ゼームス、ハンナ
14 北洋丸 124.0 211 M14.08 702 / HFBJ 第一北洋丸 110 98 M14.08 M14.08 兵庫工作分局 北洋会社 -
15 游龍丸 90.0 74 M15.05 不登簿 游龍丸 86 56 M15.03 M15.03 大津 太湖汽船会社 不登簿○
16 三光丸 154.0 288 M15.05 695 / HDWR 三光丸 158 207 M15.04 M15.04 兵庫工作分局 大坂商船会社 ゼームス、ハンナ
19 第一小野田丸38.7 8.01 M16.09 不登簿 第一小野田丸 39 3 M16.06 M16.06 兵庫造船局 セメント製造会社 不登簿○
20 志摩丸 153.5 373.3 M16.06 805 / HFMC 志摩丸 141 237 M16.09 M16.09 兵庫工作分局 共同運輸会社 -
21 第二小野田丸46.9 10.87 M17.04 不登簿 第二小野田丸 49 7 M16.12 M17.03 兵庫造船局 セメント製造会社 不登簿○
22 金龍丸 168.0 494.81 M17.05 836 / HFPD 金龍丸 172 329 M17.04 M17.04 兵庫川崎 大坂商船会社 川崎造船所・ゼームス、ハンナ
23 第二徳山丸 96.2 102 M18.05 890 / HFSR 第二徳山丸 98 77 M18.05 <記載無し> 佐山芳太郎
① (帆)太平丸 119.0 335 M11.08 434 / HDBR 太平丸 122 279 M11.08 - -
② (帆)太陽丸 127.5 446 M11.12 435 / HDBS 太陽丸 135 368 M11.12 - 鈴木吉造(ママ)
③ (帆)新田丸 127.5 446 M12.12 <記載無し>神路丸か? - -
一列目は工部省沿革史リストに記された長さ、登簿噸、製造年月を記した。Noは元々の掲載順序とし、M20船名録
の製造年月順に行を並べ替えた。
二列目はM20船名録から長さと登簿噸数、製造年月を記した。M20船名録に掲載されない船でM15船名録に掲載さ
れる船に「*」を付した。
三列目はM18汽船表から製造地名と船主を記した。
四列目はM26船名録から造船工長を記した。
意外にも、改名された船は少ない。「廣島丸」「北洋丸」に、当初から「第二」「第一」が付されていたか判らない。
長さの数値は微妙に異なり、登簿噸数は別船と思える程の違いを見せる。同一地の建造にかかわらず、製造地名
の表記の違いも興味深い。
1868(慶応4).01兵庫開港。
1869(M02)バルカン鉄工所設立(東川崎)。金沢藩兵庫製鉄所設立。
1870(M03).12工部省設置(製鉄等を民部省より移管)。
1872(M05).02工部省は兵庫製鉄所を買収。製作寮兵庫製作所と改称。
1873(M06).04工部省はバルカン鉄工所を買収。兵庫製作所と統合。
1875(M08).04兵庫製作所修理船架完成。
1877(M10).01工部省製作寮は工作局、兵庫製作所を兵庫工作分局と改称。
〃 .07一等技手佐畑信之着任。
1881(M14).03川崎正蔵は川崎兵庫造船所開設(兵庫東出町)。
1883(M16).09工部省は工作局を廃止。兵庫工作分局を兵庫造船局と改称。
1885(M18).01兵庫造船局に輸入の鉄船製造設備竣工。
〃 .05兵庫造船局は船台3基建設に着工。
〃 .09兵庫造船局は引揚重量2000トンの大船架竣工。
〃 .12工部省廃止に伴い農商務省工務局に移管、兵庫造船所と改称。
1886(M19).05兵庫造船所を川崎正蔵に貸与。川崎兵庫造船所と合併、川崎造船所と改称。
〃 .10川崎造船所にて大坂商船「吉野川丸」竣工。
1887(M20).07兵庫造船所を川崎正蔵に払下げ。
兵庫造船局最後の建造船は既出の「第二徳山丸」。共栄社の発注により建造され、帝国商船、吉田義方(小田原)
を経て東京湾汽船の所有船となった。


「第二徳山丸」の画像は、小田原海岸停泊中に加え、新たに航行中も見つかった。恐らく、同日の記録と思わ
れる。こちらにキャプションは無く、少々ピンは甘い。船名は停泊中画像より取り込んだ。
以降、建造船26隻のうち蒸気船23隻に限って記したい。
M20船名録に見あたらない船名は「萬幸丸」「福傳丸」「徳島丸」「明運丸」の4隻。
「福傳丸」は汽船表から「静凌丸」へ改名されたと判る。
「徳島丸」は全く追いかけられない。この船については項を改めて記したい。
「明運丸」はM18船名録から抹消されている。明治期の木造汽船は、損傷程度にもよろうが、沈没しても浮揚修復
されている。「明運丸」はどうなったのか。
「萬幸丸」の後身を「太安丸」とするには、疑問は二点ある。
①工部省リストと船名録は、製造年月が異なる。
②工部省リストと徳島県統計表は、登簿噸数が異なる。
廃藩置県以来、今の徳島県の地域は複雑な経緯を経ている。徳島県統計表は、幸いにもM13-M14二カ年間に船名
を記載している。
【M13統計表】
船名 噸数 所有者 定繋港 購入・新造年月
鵬翔丸 488 井上三千太 小松島 12.03.28購入
太安丸 20 撫養会社 撫養 13.10購入
末廣丸 56.22 船場会社 津田 13.11新造
巳卯丸 84.16 船場会社 津田 12.11新造
鵬勢丸 57.3 船場会社 津田 12.12新造
【M14統計表】
船名 噸数 馬力 造船年月 所有者 定繋港
鵬勢丸 57.3 16 13.01建造 船場会社 津田
末廣丸 30 46 13.10建造 船場会社 津田
巳卯丸 84.16 16 12.01建造 船場会社 津田
長久丸 84.08 33.8 14.10建造 船場会社 津田
太陽丸 78 25 14.07建造 太陽会社 古川
朝陽丸 72 25 14.07建造 太陽会社 古川
太安丸 20 15 10.09建造 撫養会社 撫養
撫養丸 19 12 14.08建造 撫養会社 撫養
常磐丸 1 3 14.04建造 安川長平 撫養
ここから「太安丸」について読み取れるのは次のとおり。
撫養会社「太安丸」(20噸・12馬力)は撫養港を定繋港とし、M10.09に建造された船を、同社はM13.10に購入
した――。
記載事項は異なるものの、工部省リスト、船名録及び汽船表をのデータを並べると次のとおり。
工部省 萬幸丸 87尺 104噸 20馬力 M11.05
M14版 太安丸 138 20噸 15馬力 撫養会社
M15版 太安丸 138 / HCBK 20噸 15馬力 撫養会社
M18版 太安丸 138 / HCBK 63.91噸 20馬力 大坂商船会社
汽船表 太安丸 94尺 62.78噸 20馬力 M10.09兵庫川崎新田 大坂商船会社
M20版 太安丸 138 / HCBK 94尺 63噸 20馬力 M10.09摂津国兵庫 大坂商船会社
徳島県統計表やM14-15船名録に記された登簿噸数20噸は錯誤だったのか。何時の時点か20馬力の「20」の数
値が、登簿噸数に取り違えられたのではあるまいか。工部省リストは登簿噸数104噸。M18船名録は63.91噸になっ
ている。仮に、船舶原簿に登簿噸数20噸と記されていたなら、それは正しいと云えるのか? 建造後3年目の誤
記載(?)は真実に思えてくる。登簿噸数の異なるM15船名録とM18船名録の「太安丸」を結びつけるのは、船舶番
号と信号符字。
明治大正期の船舶を追いかける際、トン数や長(Lr)は重要な手掛かりとなるが、尺(曲尺)と呎(feet)の混同や、用
語定義の誤認は避けたい。
船名録に「川崎造船所」とある「金龍丸」は、兵庫造船所の川崎正蔵への貸与が1886(M19).05であることから、
船名録若しくは船舶原簿の誤記と思われる。「ゼームス、ハンナ」と記される造船工長は1名ではなく、お雇い外国人
の造船師「ハンナ」(英)と機械師「ゼームス、ラング」(英)であり、この2名は「13.05傭入、17.06解傭」と、同一期
間の在籍となっている。船名録の記載は2名の名を重ねてしまっていると見られる。船名録にありがちな記載の
省略である。
「萬幸丸」の製造年月の錯誤は工部省リストにあると見られる。このことを裏付ける史料を挙げておきたい。



『萬幸丸史料』には、共立定約証、市中御賀帳、領収書等を含んでいる。支払は一括ではなく、機器や船体な
ど、出来高のようだ。領収書には工部省の技手佐畑信之の名がある。工部省沿革史によると営業したらしい。
萬幸丸の建造は、海運が活況を呈した南西戦争の時期にあたる。市中御賀帳には「銘酒」「窓幕」「将棋盤」等
が見え、船用備品となったことを考えると、非常に興味深い。

船場会社の活動した明治10年代は、近代海運史における神話時代のような感覚を持っていた。この史料により、
歴史の延長線上に姿を現してくれた感がある。
史料には船場会社の社長辞令も含まれる。社長に就任した湊喜八は、斎津村の初代村長となり、人望厚い人物
と記録される湊多平の関係者と思われる。湊多平は、共立定約証第壱条に氏名のある湊太平と同一人か。湊家
は、津田浦において代々回漕業を営んできた。
萬幸丸の建造時期や共立契約書の存在などから、津田浦の有力者の共立により1877(M10)蒸気船「萬幸丸」を建
造し、「船場会社」は翌年に組織されたと見られる。西南戦争の前後、各地に勃興した海運会社の成立過程を知
る上において興味深い。
昨年暮れ、大阪のT氏より、ご自身の栽培された香り高い種無し柚子が届いた。勿体なくて、冬至のお風呂に使
うのは数個に止め、凍結させて摺り下ろし、薬味にした。徳島繁栄組汽船部の宣伝看板を探しに出掛けた際、神
社の前で困り果てていたボクに、声をかけて下さったのがT氏だった。参拝した神社のお引き合わせか、T氏に巡
り会ったことにより、元教師の老婦人から看板の位置をご教示いただき、念願の対面を果たした。T氏は、最初に
大阪へ出た時は船で渡ったが、今は自家用車で大阪のご自宅と徳島の農園を行き来しているという。ご自身の生
活と、重ね合わせて語って下さった船や航路への思いは、喜びと共に胸に染みた。
今回は「萬幸丸」と「太安丸」の関係に止めたい。この『萬幸丸史料』は、徳島県にて保存活用されるべき郷土
史料と考えている。