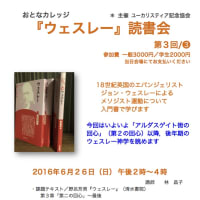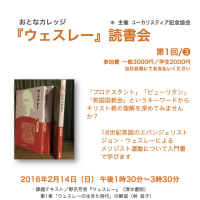ポストモダンという言葉は、様々な状況のもとであまりにも様々な意味において用いられている。このように、何がポストモダンなのか錯綜する中において、私が注目しなければならないテーゼのひとつに、ポストモダン運動の端緒ともいうべき「神の死」とは何だったのか、という問題がある。
実は、「放置されたままにされている近代の残した様々な課題」について、児童福祉という観点から書かれた白頭庵さんのエントリに刺激されて、こちらのカフェでもちょっと触れてみたくなったのである。
神学上、神の死が扱われた例としては1960-70年ごろ、トマス・アルタイザーらによる弁証法的方法論を用いて展開された、いわゆる「神の死の神学」があったが、この運動も、他の「~の神学」と名づけられた緒運動と同様、いっときの流行に終わってしまった感がある。今ここで私の言う神の死に関する運動は、この狭義の神学運動のことではなく、19世紀後半から20世紀前半にわたって広範囲の分野で共感され歓迎された、一連の、神を亡きものにしようとの試みおよび無神論に立つ思索活動である。
結論を先に言ってしまうと、神をなきものにしようというその試みは、失敗であったと思う。否、それは失敗というより、いわゆる刑法でいわれる客体の錯誤による殺人ならぬ殺神、と言った方がより適当である。客体の錯誤による殺人とはつまり、Aに殺意を抱いてピストルを発射したところ、実際はその脇にいたBに弾が当たり、実際に死亡したのはBであってAではないという錯誤をいう。その、刑法で扱われるような錯誤による殺人と、ポストモダン運動の端緒としての、いわゆる殺神の試みが、私には重なるように思える。ピストルでAなる神を撃った人たちは、どうやらAを殺害したと、未だ思い込んでいるらしいのだ。
神なき時代といわれるポストモダン(ただし、神学におけるポストモダンの扱いは、他の分野とは、ちと事情が違うから厄介だ)において扱われる神の死、あるいは神の不在、それらは実のところ、神には死んでくれた方が都合がよいと考える現代の偶像たちが、観念上の操作をして神を亡きものと看做したに過ぎない。実際に死んだのは脇にいたBであって、神は死ななかったAだということが分かっていながら、彼らはそれを敢えて無視して、観念上の遊びに興じている。極端な例をひとつ挙げれば、たとえばF・ニーチェによる超人思想や永遠回帰の思想がそれに当てはまる。
白頭庵さんの言葉を借りれば、「哲学が、社会思想とリンクしないままそれぞれ勝手にタコ壺的な専門化を推し進めているという、近代世界の負の遺産」は、こうした遊びによってもたらされているのではないだろうか。しかし仮に、いまだにAが本当に死んだと思い込んでいる哲学者がいるとすれば、「随分ナイーブだね」とその人とたちに私は言うだろう。
つまり、殺した、あるいは死んでくれたと思われた神は、実は死んではいない。にもかかわらず、恣意的に死んだとみなしているにせよ、本当に死んだと勘違いしているにせよ、どちらにしても神がいないことを前提とするポストモダン運動は、出発点においてすでに実態を見誤っていることになる。前提となる真理が揺らいだまま、その不安定な土台の上に構築されるその運動に、私たちはどれだけの説得力を見出すことができるのであろうか。ポストモダンを標榜する活動から生まれるそれぞれの成果はまるで、膨らんでは弾ける無数の小さなバブルのようでもあり、それらは実際社会と乖離したところで浮遊し続けている。
ここで忘れてはならないのは、Aがいまだ健在だとしても、確かに死んだBがいた、ということである。では、Bとはいったい何だったのか、そして依然として生きて私たちの世界に関与するAとは何であり、それがなぜ神だといえるのか、という疑問が生じてくるだろう。
その問題に対しては、かつて私は、パウル・ティリヒの存在論が答を与えてくれる強力な助っ人になると考えていた。ただし、存在論それ自体に付随する問題点をティリヒの存在論は包含しているし、それに対する批判を克服していかなければならないという課題は残る。しかし存在の多重性という概念を、キリスト教の世界観にとどまりつつも提供してくれる点で、ティリヒの存在論は確かに有効であると思う。しかし今の私には、ティリヒの存在論だけではかなり不十分であり、それを採用するとしても、さらに古代・中世をとおして検証され続けてきた、いわば歴史に裏打ちされてきた神に関する諸概念を、ここに改めて見直す必要があると思う。
つまりカトリック教会中心に、あるいはプロテスタント緒教会によって支えられてきた、いわゆる正統と看做されてきた偏狭な神概念の流れのみではなく、近年の歴史研究によって明らかにされつつある、かつては正統的権力によってベールを被われてきた神概念を改めて見直し、それらを現代神学の根底に据え置くという厚みが、もっと必要なのである。
ここに神論を展開することは、とてもではないができない。しかし、これだけではあまりにも具体性に欠けた話で終ってしまうので、殺されたBとはいったい何であったのかということを、ひとつのたとえで表現しておこう。Bとは――Aの皮膚を覆う垢のようなもの(ううっ、なんて汚いたとえ)、Aと全く無関係ではないけれども、こすり落とされて(つまり殺されて)当然であるような、経年の結果溜まってしまった垢である。その垢は、すでに聖書の、あるいは福音書の時代からキリスト教内で溜まり始めたものである。こすり落とすのに随分と難儀な垢であった。いまでもその垢は完全に落とされきっていない(完全に落とすことはできないし、その必要もない)が、本当のところ、その垢そのものが神であると、今なお排他的に固執する相当数の「同朋」たちこそが一番厄介な存在であるといえるのだが。
垢には垢なりの役割があるかもしれないが、垢があまり重要なものでないことは確かである。私たちはそろそろ、Aについて誠実に取り組む時期にきているのではないだろうか。まあ、神概念およびそれと深く関わる世界観の研究は、ポストモダン運動の陰で細々と(でもないか)行われている。それに自分が関わっていられることを、ありがたく思う。
ところで今まで述べてきたことを裏返せば、たとえば「神は死んだ」という場合の神とはどのような概念に基づく神であるのか、という問いに答えようとするときにも、同じような過程を辿って説明されなければならないということでもある。つまり、神は死んだ、というとき、ポストモダンの立場からすると、どのような意味でどの神を殺した、ということになるのか、という問題である。しかし、私は未だこれについて、説得力のある説明に出会ったことは、ない。
実は、「放置されたままにされている近代の残した様々な課題」について、児童福祉という観点から書かれた白頭庵さんのエントリに刺激されて、こちらのカフェでもちょっと触れてみたくなったのである。
神学上、神の死が扱われた例としては1960-70年ごろ、トマス・アルタイザーらによる弁証法的方法論を用いて展開された、いわゆる「神の死の神学」があったが、この運動も、他の「~の神学」と名づけられた緒運動と同様、いっときの流行に終わってしまった感がある。今ここで私の言う神の死に関する運動は、この狭義の神学運動のことではなく、19世紀後半から20世紀前半にわたって広範囲の分野で共感され歓迎された、一連の、神を亡きものにしようとの試みおよび無神論に立つ思索活動である。
結論を先に言ってしまうと、神をなきものにしようというその試みは、失敗であったと思う。否、それは失敗というより、いわゆる刑法でいわれる客体の錯誤による殺人ならぬ殺神、と言った方がより適当である。客体の錯誤による殺人とはつまり、Aに殺意を抱いてピストルを発射したところ、実際はその脇にいたBに弾が当たり、実際に死亡したのはBであってAではないという錯誤をいう。その、刑法で扱われるような錯誤による殺人と、ポストモダン運動の端緒としての、いわゆる殺神の試みが、私には重なるように思える。ピストルでAなる神を撃った人たちは、どうやらAを殺害したと、未だ思い込んでいるらしいのだ。
神なき時代といわれるポストモダン(ただし、神学におけるポストモダンの扱いは、他の分野とは、ちと事情が違うから厄介だ)において扱われる神の死、あるいは神の不在、それらは実のところ、神には死んでくれた方が都合がよいと考える現代の偶像たちが、観念上の操作をして神を亡きものと看做したに過ぎない。実際に死んだのは脇にいたBであって、神は死ななかったAだということが分かっていながら、彼らはそれを敢えて無視して、観念上の遊びに興じている。極端な例をひとつ挙げれば、たとえばF・ニーチェによる超人思想や永遠回帰の思想がそれに当てはまる。
白頭庵さんの言葉を借りれば、「哲学が、社会思想とリンクしないままそれぞれ勝手にタコ壺的な専門化を推し進めているという、近代世界の負の遺産」は、こうした遊びによってもたらされているのではないだろうか。しかし仮に、いまだにAが本当に死んだと思い込んでいる哲学者がいるとすれば、「随分ナイーブだね」とその人とたちに私は言うだろう。
つまり、殺した、あるいは死んでくれたと思われた神は、実は死んではいない。にもかかわらず、恣意的に死んだとみなしているにせよ、本当に死んだと勘違いしているにせよ、どちらにしても神がいないことを前提とするポストモダン運動は、出発点においてすでに実態を見誤っていることになる。前提となる真理が揺らいだまま、その不安定な土台の上に構築されるその運動に、私たちはどれだけの説得力を見出すことができるのであろうか。ポストモダンを標榜する活動から生まれるそれぞれの成果はまるで、膨らんでは弾ける無数の小さなバブルのようでもあり、それらは実際社会と乖離したところで浮遊し続けている。
ここで忘れてはならないのは、Aがいまだ健在だとしても、確かに死んだBがいた、ということである。では、Bとはいったい何だったのか、そして依然として生きて私たちの世界に関与するAとは何であり、それがなぜ神だといえるのか、という疑問が生じてくるだろう。
その問題に対しては、かつて私は、パウル・ティリヒの存在論が答を与えてくれる強力な助っ人になると考えていた。ただし、存在論それ自体に付随する問題点をティリヒの存在論は包含しているし、それに対する批判を克服していかなければならないという課題は残る。しかし存在の多重性という概念を、キリスト教の世界観にとどまりつつも提供してくれる点で、ティリヒの存在論は確かに有効であると思う。しかし今の私には、ティリヒの存在論だけではかなり不十分であり、それを採用するとしても、さらに古代・中世をとおして検証され続けてきた、いわば歴史に裏打ちされてきた神に関する諸概念を、ここに改めて見直す必要があると思う。
つまりカトリック教会中心に、あるいはプロテスタント緒教会によって支えられてきた、いわゆる正統と看做されてきた偏狭な神概念の流れのみではなく、近年の歴史研究によって明らかにされつつある、かつては正統的権力によってベールを被われてきた神概念を改めて見直し、それらを現代神学の根底に据え置くという厚みが、もっと必要なのである。
ここに神論を展開することは、とてもではないができない。しかし、これだけではあまりにも具体性に欠けた話で終ってしまうので、殺されたBとはいったい何であったのかということを、ひとつのたとえで表現しておこう。Bとは――Aの皮膚を覆う垢のようなもの(ううっ、なんて汚いたとえ)、Aと全く無関係ではないけれども、こすり落とされて(つまり殺されて)当然であるような、経年の結果溜まってしまった垢である。その垢は、すでに聖書の、あるいは福音書の時代からキリスト教内で溜まり始めたものである。こすり落とすのに随分と難儀な垢であった。いまでもその垢は完全に落とされきっていない(完全に落とすことはできないし、その必要もない)が、本当のところ、その垢そのものが神であると、今なお排他的に固執する相当数の「同朋」たちこそが一番厄介な存在であるといえるのだが。
垢には垢なりの役割があるかもしれないが、垢があまり重要なものでないことは確かである。私たちはそろそろ、Aについて誠実に取り組む時期にきているのではないだろうか。まあ、神概念およびそれと深く関わる世界観の研究は、ポストモダン運動の陰で細々と(でもないか)行われている。それに自分が関わっていられることを、ありがたく思う。
ところで今まで述べてきたことを裏返せば、たとえば「神は死んだ」という場合の神とはどのような概念に基づく神であるのか、という問いに答えようとするときにも、同じような過程を辿って説明されなければならないということでもある。つまり、神は死んだ、というとき、ポストモダンの立場からすると、どのような意味でどの神を殺した、ということになるのか、という問題である。しかし、私は未だこれについて、説得力のある説明に出会ったことは、ない。